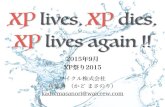はじめに 目次 取扱説明書の使いかた - Roland...
Transcript of はじめに 目次 取扱説明書の使いかた - Roland...
-
はじめにこのたびはローランド・ミュージック・ワークステーションXP-50をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。XP-50は、JV-1080を受け継いだ多彩な音色を発音するシンセサイザー音源と、抜群の操作性を誇る強力なシーケンサーを内蔵したミュージック・ワークステーションです。この1台でライブ・ステージでのパフォーマンスからデスクトップ・ミュージックまで幅広く対応することができます。
取扱説明書の使いかた優れた機能を十分にご理解いただき、末長くご愛用いただくために、本書および、取扱説明書をよくお読みください。
XP-50の取扱説明書は「ガイドブック」、「取扱説明書」の2冊構成になっています。
ガイドブックはじめてミュージック・ワークステーションをお使いになる方でも簡単に楽しんでいただけるように解説してあります。XP-50には豊富な機能が備わっていますので、より詳しい説明が必要な場合は、一度この本をお読みになってから、取扱説明書を併せてお読みください。
取扱説明書1章と2章ではXP-50の概要や基本操作方法を説明していますので、必ずお読みください。その他の章では、パラメーターや機能の説明、XP-50の使いかたの応用、資料などについて説明していますので、必要に応じてお読みください。
目次ご使用上の注意...............................................................................3XP-50の特長...................................................................................5各部の名称と働き...........................................................................6接続しましょう...............................................................................9電源を入れましょう....................................................................10いろいろな音を鳴らしてみましょう.......................................11パッチを切り換えて鳴らしましょう鍵盤で打楽器を演奏しましょう演奏機能を確認しましょう.....................................................12デモ・ディスクを使ってみましょう.......................................13デモ・ソングを聴いてみましょうソングに合わせてRPS機能を使ってみましょうRPS機能を使っていろいろなパターンを演奏してみましょう..................14
ソングを作ってみましょう........................................................15録音を始める前に打楽器をリアルタイム・レコーディングしましょう......................16演奏データを見てみましょう.................................................18ベースをステップ・レコーディングしましょう......................19メロディーをリアルタイム・レコーディングしましょう....................21ソングを保存(セーブ)しましょう.......................................22ディスクをフォーマットしましょうソングをディスクにセーブしましょう................................23ソングにあったパフォーマンスを作りましょう..................24メロディーのパッチに入れ換えてみましょうパフォーマンスに新しい名前をつけましょうパフォーマンスを保存しましょう.........................................25プロフィール ................................................................................26
1995 ローランド本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを
禁じます。
-
2
この製品の取り扱いについては、次の基本的な安全事項に、ご注意ください。 ●次のような場所でのご使用や保存は、故障の原因となりますので、ご注意ください。 ○温度が極端に高い場所(直射日光の当たる場所、暖房機器の近く、発熱する機器の上など) ○水気の近く(風呂場、洗面台、濡れた床など)や湿度の高い場所 ○ホコリの多い場所 ○振動の多い場所 ●電源プラグは、必ずAC100Vの電源コンセントに差し込んでください。 ●電源コードの上に重いものをのせたり、踏みつけたりして傷をつけないでください。 ●電源プラグをコンセントから抜く場合は、電源コードの断線やショートによる危険防止のため、必ず電源プラグを持ってください。 ●長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●本機には、異物(硬貨や針金など)や液体(水やジュースなど)が入らないように注意してください。 ●感電や故障の原因になりますので、本機の内部に手を入れたり、改造しないでください。
●本機に異常や故障が生じた場合は、直ちに使用を中止し、お買い上げ店またはローランド・サービスにご連絡ください。
安全にお使いいただくために
-
ご使用上の注意
3
2ページに記載されている安全事項以外に、次のことにご注意ください。
■電源について
●他の機器と接続する際は、誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の電源をオフにしてください。
●雑音を発生する装置(モーター、調光器など)や消費電力の大きな機器とは、別のコンセントをご使用ください。
■設置について
●本機の近くにパワー・アンプなどの大型トランスを持つ機器がある場合、ハム(うなり)を誘導することがあります。その場合は、本機との間隔や方向を変えてください。
●テレビやラジオの近くで本機を動作させると、テレビ画面に色ムラが出たり、ラジオから雑音が出ることがあります。このような場合は、本機を遠ざけてご使用ください。
●本機はディスク・ドライブが搭載されていますので、次の点にご注意ください。詳細は、本文の“ディスクをお使いになる前に”をご覧ください。○スピーカーなどの強い磁界の発生する場所には近づけない
○本機を極端に傾けない○ディスク・ドライブ動作中は、振動を与えたり移動したりしない
■お手入れについて
●通常のお手入れは、柔らかい布で空拭きするか、堅く絞った布で汚れを拭き取ってください。汚れが激しいときは、中性洗剤で汚れを拭き取ってから、必ず柔らかい布で空拭きしてください。
●変色や変形の原因となるベンジン,シンナー及びアルコール類は、絶対にご使用にならないでください。
■メモリー・バックアップについて
●本体内には、電源オフ後も記憶した内容を保持するための電池を装備しています。5年を目安に交換してください(電池の寿命は使用条件によって異なります)。交換の際は、必ずローランド・サービスにご相談ください。
●電池が消耗してくると、ディスプレイに次のように表示されます。電池が消耗してしまうと記憶した内容が失われますので、早めに交換してください。
“Battery Low”
●修理に出される場合や万一異常な動作をしたときには、記憶した内容が失われることがあります。大切なデータは、フロッピー・ディスクに保存するか、データをメモしておいてください。修理の際のデータ保存には細心の注意を払っておりますが、メモリー部の故障などでデータが復元できない場合はご容赦ください。
■ディスクをお使いになる前に
※ディスクの失われた記録内容の修復に関しましては、補償を含めご容赦願います。
本機の取り扱い
●外部からの振動を受けないしっかりした水平な場所に設置してください。極端に傾けると、ディスク・ドライブの動作に悪影響を与えることがあります(許容角度:上方向5度、下方向35度)。
●極端に湿度の違う場所に移動すると、ディスク・ドライブに水滴がつくことがあります。このまま使用すると故障の原因になりますので、数時間放置してからご使用ください。
●ディスクを挿入する際には、確実に奥まで入れてください。ディスクを取り出す際は、イジェクト・ボタンを奥まで押してください。万一ディスクが引掛かった場合は、無理に取り出さないでください。
●ディスク・ドライブの動作中(ディスク・ドライブのインジケーターが明るく点灯)は、ディスクを取り出さないでください。ディスクの磁性面に傷がつき、使用できなくなります。
●電源をオン/オフする際は、ディスクをディスク・ドライブから抜いてください。
-
4
ディスクの取り扱い
●ディスクは磁性体を塗布したフィルム状の記憶媒体です。磁性面には非常に高密度でデータが記憶されますので、取り扱いについては次の点にご注意ください。○磁性面に触れない○ホコリの多い場所で使用しない○直射日光の当たる場所や締め切った自動車の中などに放置しない(保存温度:10~50℃)
○スピーカーなどの強い磁界を発生する場所やものに近づけない
●ディスクには、書き込んだデータを誤って消さないように保護するプロテクト・タブがあります。書き込み操作を行なうとき以外は、プロテクト・タブをプロテクトの位置にしておいてください。
●万一にそなえて、大切なデータは複数のディスクにコピーしておいてください
●ディスクのラベルは、しっかりと貼り付けてください。ディスク・ドライブの中ではがれると、ディスクが取り出せなくなります。
●ディスクはケースに入れて保管してください。
■その他の注意について
●本機に強い衝撃を与えないでください。
●ディスプレイを強く押したり、叩いたりしないでください。
●本機は多少発熱することがありますが、故障ではありません。
●外国でご使用になる場合は、前もって最寄りのローランド・サービスにご相談ください。
●ディスプレイから多少音がすることがありますが、故障ではありません。
...............................................................................................................本文中の表記についてこの取扱説明書では、操作方法を簡潔にするために、次のように表記しています。・ ボタン/ ボタン、INCボタン/DECボタンなどは、どちらかのボタンを押すことを表しています。
・「SHIFTボタン+PERFORMボタン」は、SHIFTボタンを押しながら、PERFORMボタンを押すことを表わしています。
・文章の頭に※マークがついているものは注意文を表しています。
・文中の(P.**)は参照ページを示しています。・各パラメーターの説明では、[○画面中の略称(正式名称)の順で記しています。【例】○Rat(コーラス・レイト)○Typ(フィルター・タイプ)
※ XP-50には数多くのパラメーター(設定項目)があります。これらのパラメーターは、操作モード/画面グループ/画面という階層で整理されています。取扱説明書では、これらのパラメーターを示す場合、例えばCutパラメーター(PATCH:TVF:FILTER)というように表記します。これは、Cutというパラメーターが、PATCHの操作モードにおけるTVFグループのFILTER画面に含まれていることを示しています。また、画面を示すときも同様に表記します。
画面について取扱説明書に記載されているディスプレイ図の内容は、お買い上げ時の設定と異なることがありますので、ご了承ください。...............................................................................................................
-
XP-50の特長
5
優れた拡張性
● 4枚のウェーブ・エクスパンション・ボードを同時
装着ウェーブ・エクスパンション・ボードを4枚まで同時装着することができます。これにより大量の波形データを元にした音作りが可能です。
● SMFに対応市販のSMF(スタンダードMIDIファイル)の豊富なミュージック・データやSUPER-MRCで作成したソング・データを利用することができます。
すばやく、簡単、そしてシンプルな操作系各機能に対応したボタンを備えることで操作性が向上しました。ディスプレイ下のファンクション・ボタンにより直感的なエディット操作ができます。
JV-1080を受け継いだ高性能なシンセサイザ
ー音源部
● 64音ポリフォニック+16パート・マルチ・ティンバーXP-50は最大同時発音数64音の16パートのマルチ・ティンバー音源です。内蔵シーケンサーや外部のコンピューターと組み合わせて、自由な曲作りや演奏ができます。
●充実のエフェクター高性能DSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)により多彩なエフェクト効果を得ることができます。40種類のエフェクト・タイプを持つマルチ・エフェクター(EFX)をはじめ、音に広がりや奥行きをつけるコーラス、残響をつけるリバーブの合計3系統のエフェクターを搭載しています。
●豊富なストラクチャー音色要素の組み合わせかたを変えるストラクチャーを10種類用意しました。さらにリング・モジュレーターや新機能のブースターにより大幅な音の加工が可能です。
● GMシステムに対応パソコンで音楽を自由に操るDTM(デスクトップ・ミュージック)で共通語となったGMシステムに適合したモードを備えています。これにより、GMシステム対応のソング・データも再生することができます。
GMシステムGM(General MIDI)システムとは、音源のMIDI機能の仕様を、メーカーや機種を越えて標準化することを目的とした推奨規定です。GMシステムに適合した音源や曲データにはGMマーク( )がついており、GMマーク付きの音源であればどれでも同じように再生することができます。
高機能で使いやすいシーケンサー
●すぐにソングを再生できるクイック・プレイフロッピー・ディスクに記録されたソングは本体に読み込まなくても、直接再生することができます。
●ライブで威力を発揮するRPS(リアルタイム・フレ
ーズ・シーケンス)機能RPS機能は、あらかじめ作っておいたパターンを鍵盤を押さえて再生する機能です。ソングと同時に再生することもできます。
●いくつものソングを連続してプレイできるチェー
ン・プレイフロッピー・ディスクに記録されたソングを指定した順番にクイック・プレイできます。ステージなどでライブ用のシーケンサーとして使うとき、効果を発揮します。
●演奏のノリを変えるシャッフル・クォンタイズとグ
ルーブ・クォンタイズXP-50には、音のタイミングを補正する従来のクォンタイズ(グリッド・クォンタイズ)の他に、シャッフル・クォンタイズとグルーブ・クォンタイズの機能を持っています。シャッフル・クォンタイズは録音した演奏にスイング感を作り出します。グルーブ・クォンタイズは打楽器の演奏に効果があるものです。90種類のテンプレートの中から好みのものを選ぶだけで指定の演奏のノリが得られます。
-
6
各部の名称と働き■フロント・パネル
ENTER
YZ!VWXSTU
PQRMNOJKL
GHIDEFABC
SPACE0
1 2 3
4 5 6
7 8 91 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
COMMON EFFECTS MIDI PART INFOCOMMON EFFECTS CONTROL WAVE LFO PITCH TVF TVATRK EDIT NAME TRACK LOOP RPS SEQ UTILITY (ERASE)CREATE ERASE MOVE COPY PLACE VIEWINSERT DELETE CLR ALLSETUP CONTROL INFO
(REST)(TIE)
REC
BWD FWD
LOOP
STOP PLAYII
DEC INC
I
MIDI SEQUENCER TUNE PGM CHNG
PERFORMPATCH RHYTHM
SEQUENCERM.SCOPE
CHAIN PLAYSYSTEM
- OCT + OCT
9 -161 - 8
COMPAREUNDO
EXIT
PALETTE TX RXLOCAL
LOCATE TEMPO BEATTRACK
PATTERNI
PERFORM
SEQUENCER
SYSTEM
PATCH
CHAIN PLAY
UTILITY
RHYTHM
M.SCOPE
EDIT
I
EFFECTS
PART
ON OFFI
QUANTIZE
TRACK
DISK I
CONTRAST
GM
HELP E F G
B C D
A
3
3
3METRONOME
PANIC
SHIFT
EXP DEXP C
EXP BEXP AGM
USER
+ -I DIGIT HOLD
PRESET CPRESET BPRESET A
RESET SKIP
RPS
A
B
C
D E F
G
H
A操作モードを切り換えます。選んでいる操作モードのボタンのインジケーターが点灯します。ファンクション・ボタンの働きは選んだ操作モードによって変わります。
B● DISK/UTILITYボタンパッチのライト、コピー、ディスクのフォーマット、データのセーブなどの操作をするときに押します。
● EFFECTS ON/OFFボタン/METRONOMEボタンEFFECTS:内蔵されている各エフェクター(EFX、コーラス、リバーブ)についてオン/オフを切り換えるときに押します。METRONOME:メトロノームを鳴らすときは、SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押します。メトロノームを止めるときは、もう一度SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押します。
● RPSボタンRPS機能をオン/オフします。
● ―OUTボタン、+OUTボタン鍵盤の音域をオクターブ単位で移動します。
C● ファンクション・ボタン選んでいる操作モードと、EDITボタンのインジケーターの状態によって働きが変わります。
● EDITボタンいろいろな設定を変更するときに押します。変更するパラメーターの画面グループはファンクション・ボタンで選びます。
● 1-8/9-16ボタンファンクション・ボタンでパート/フレーズ・トラックを切り換えるときの、対象となるグループ(1~8/9~16)を選びます。
● UNDOボタン/COMPAREボタン/HELPボタン操作によって機能が変わります。UNDO:変更した値を元に戻すときに押します。COMPARE:パッチの設定を保存する際、書き込み先のパッチの音を確認するときに押します。HELP:指定しているパラメーターのフル・ネームや設定範囲を確認するヘルプ画面を表示させるときは、SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押します。
● PALETTEボタン/LOCATEボタンPALETTE:パレット画面を使ってパッチやパフォーマンスの設定を変更するときに押します。LOCATE:シーケンサーのポジション(小節-拍-クロック)を設定したり、移動したりするときに押します。
● TXボタン、RXボタンパフォーマンス・モードの演奏時は、ファンクション・ボタンで切り換えられるパートの機能を選びます。ローカル・コントロールのオン/オフを切り換えるときは、TXボタンとRXボタンの両方を押します。TX:MIDIメッセージの送信のオン/オフRX:MIDIメッセージの受信のオン/オフLOCAL:ローカル・コントロールのオン・オフ
● TEMPO/BEAT TRACKボタンシーケンサーの操作をしている場合は、テンポ・トラックまたはビート・トラックを選択するときに押します。テンポを一時的に変更してからソングの初期テンポに戻したいときは、SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押します。
-
7
● PATTERN TRACKボタンパターン・トラックに記録されているパターンを選ぶときに押します。
● EXITボタン/PANICボタンEXIT:操作モードのプレイ画面に戻すときや、実行操作を取り消すときなどに押します。PANIC:何らかの操作で、音が鳴り止まなかったり、音が鳴らなくなったりしたときは、SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押して対応します。
D● RECボタン演奏データを録音(レコーディング)するときに押します。
● BWDボタン、FWDボタンソングを巻き戻し/早送りします。SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押すと、ソングの先頭/最後になります。
● STOP/PLAYボタンソングを再生または停止します。
● LOOPボタンループ演奏のオン/オフを切り換えます。
E
● カーソル・ボタン( 、 )カーソル(下線)を変更したい値に移動します。
● ページ・ボタン( 、 )画面左側に↑/↓の表示がある場合は、このボタンを押すと他のパラメーターの設定画面(ページ)に切り換わります。
● INCボタン、DECボタン値を変更します。片方のボタンを押しながら、もう片方のボタンを押すと値が速く変わります。また、SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押すと、値の変化が大きくなります。
F● テン・キー値を変更します。数字の他にアルファベット、音符なども入力することができます。
● SHIFTボタンこのボタンは他のボタンと組み合わせて使います。パネル上のボタンの中には茶色の文字で記されているものがあります。これは、SHIFTボタンを押したときのボタンの機能名を示しています。
● ENTERボタン/DIGIT HOLDボタンENTER:値の確定や操作の実行に使います。DIGIT HOLD:SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押すとデジット・ホールド機能がオンになります。デジット・ホールド機能をオンにしておくと、テン・キーでパッチを指定するときにパッチの100の位と10の位のナンバーが固定され、1の位のナンバーだけが切り換わります。つまり、1の位のナンバーだけを切り換えるときは、ENTERボタンを押さなくてもすぐに切り換えられます。デジット・ホールド機能をオフにするときは、もう一度SHIFTボタンを押しながらこのボタンを押してください。パフォーマンスやリズム・セットを選ぶときも同様です。
G● αダイヤル値を変更します。SHIFTボタンを押しながらαダイヤルを回すと、値が大きく変わります。
H● ディスプレイ操作に応じていろいろな情報を表示します。
■サイド・パネル
● マスター・ボリューム・スライダーリア・パネルのOUTPUTジャックとPHONESジャックから出力する全体の音量を調節します。
● C1スライダー、C2スライダーさまざまなパラメーターや機能を割り当て、演奏中に音源部の発音のしかたを変化させることができます。
VOLUME
MAX
MIN
C2
MAX
MIN
C 1
MAX
MIN
-
8
● ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバーピッチ(音の高さ)を変化させたり、ビブラートをかけたりします。設定によっては特定のパラメーターをコントロールすることもできます。
● フロッピー・ディスク・ドライブ3.5インチの2DD/2HDのフロッピー・ディスク(以降はディスクと略します)を使用できます。ディスクを取り出すときは、ディスク挿入口の右下にあるイジェクト・スイッチを押してください。
■リア・パネル
● 電源スイッチ電源をオン/オフするときに押します。
● ACインレット付属の電源コードの差し込み口です。
● PEDAL 1ジャック、PEDAL 2ジャック別売りのペダル・スイッチ(DP-2/DP-6)やエクスプレッション・ペダル(EV-5/EV-10)を接続するジャックです。接続したペダルに特定の機能を割り当てることで音をホールドさせたり、音色を変化させるなど、様々なコントロールができます。
● HOLD PEDALジャックこのジャックに別売りのペダル・スイッチ(FS-1/DP-2)を接続して、ホールド・ペダルとして使います。
● MIDIコネクター他のMIDI機器とMIDIメッセージの送受信をするときに接続する端子です。
● OUTPUT Rジャック、OUTPUT L(MONO)ジャ
ックアンプやミキサーに音声信号をステレオ(L/R)で出力します。モノで出力するときはL側に接続してください。
● PHONESジャックヘッドホン(RH-20/80/120など)を接続するジャックです。お手持ちのヘッドホンを使う場合はインピーダンスが8~150Ωのものをお使いください。AC
POWER
OUTTHRU INMIDI
2PEDAL
1 PEDALHOLD
R L(MONO)OUTPUT
PHONES
-
9
接続しましょうXP-50にはアンプやスピーカーは内蔵されていません。音を出すためにはキーボード・アンプやオーディオ・セットまたはヘッドホンなどをご用意ください。下図を参考にしてXP-50と外部機器を接続してください。
※オーディオ接続ケーブル(PJ-1Mなど)は付属していません。別途販売店にてお買い求めください。
1. 接続をする前に、すべての機器の電源がオフになっていることを確認します。
※電源がオンのまま接続をすると、スピーカーの破損などトラブルの原因になります。
2. 付属のACコードを本体につなぎ、電源コンセントに差し込みます。
3. 図のようにオーディオ・ケーブル、MIDIケーブルを接続します。ヘッドホンを使う場合はPHONESジャックにプラグを差し込んでください。また必要に応じてペダル・スイッチ、エクスプレッション・ペダルも接続します。
※XP-50の性能を最大限に生かすためにもステレオでの使用をおすすめしますが、モノで使用されるときは
OUTPUTジャックのL(MONO)に接続してください。
※PEDAL 1ジャック/PEDAL 2ジャックにはペダル・スイッチも接続できます。
AC
POWER
OUTTHRU INMIDI
2PEDAL
1 PEDALHOLD
R L(MONO)OUTPUT
PHONES
Roland
Roland
-
10
電源を入れましょう1. 電源を入れる前に次のことを確認します。・周辺機器と正しく接続されている。・本体、および接続しているアンプやミキサーのボリュームが最小になっている。・ディスク・ドライブにディスクが入っていない。
2. XP-50のリア・パネルにある電源スイッチをオンにします。
※内部の回路を保護するため、電源を入れた直後はしばらく音が鳴りません。
3. 接続しているアンプ類の電源を入れます。
4. XP-50の音を出しながら、本体、および接続しているアンプやミキサーのボリュームを適当な音量に調節します。
※本体のマスター・ボリューム・スライダーを上げすぎないように注意してください。
● 電源を切るとき
1. 電源を切る前に次のことを確認します。・ XP-50とアンプ類のボリュームが最小になっている。・ディスク・ドライブにディスクが入っていない。・必要なデータはディスクなどに保存(セーブ)している(P.22)。
2. 接続しているアンプやミキサーの電源をオフにします。
3. XP-50の電源をオフにします。
POWER
VOLUME
MAX
MIN
-
11
いろいろな音を鳴らしてみましょう■パッチを切り換えて演奏しましょう
XP-50にはあらかじめ多くの音色が内蔵されています。XP-50では、通常の演奏に使う音色をパッチと呼んでいます。ここでは、パッチを切り換えながら、XP-50の多彩な音を聴いてみましょう。
1. PATCHボタンを押してパッチ・モードのプレイ画面に切り換えます。ディスプレイには、今選ばれているパッチのグループ、ナンバー、ネームが表示されます。
2. 鍵盤を弾くと音が鳴ります。
3. αダイヤルを回すか、INCボタン/DECボタンを押して、他のパッチを選んでみましょう。
素早く切り換えるには‥αダイヤルの場合.........................SHIFTを押しながら回すINC/DECボタンの場合.............SHIFTボタンを押しながらボタンを押す。または片方のボタンを押しながら
もう片方のボタンを押す
■鍵盤で打楽器を演奏しましょうXP-50にはさまざまな打楽器や特殊効果音を集めたリズム・セットがあります。リズム・セットを使って打楽器の演奏をしてみましょう。
1. RHYTHMボタンを押してリズム・セット・モードのプレイ画面に切り換えます。ディスプレイには、今選ばれているリズム・セットのグループ、ナンバー、ネームが表示されます。
2. 押さえる鍵によっていろいろな打楽器音が鳴ります。ディスプレイには、最後に押さえた鍵(ノート・ネーム)と、その鍵の打楽器音(ウェーブ・ネーム)が表示されます。
※各鍵でどのような打楽器が鳴るかは、選んでいるリズム・セットによって異なります。詳しくは取扱説明
書の「12章 お買い上げ時の設定」をご覧ください。
3. 他のリズム・セットに切り換えるときは、αダイヤルを回すか、INCボタン/DECボタンを押します。
PATCH PR-A:001 64voicePianoPLAY center=C 4
DEC INC
RHYTHM PR-A:001 PopDrumSet 1PLAY C 4(Cga Mute Hi )center=C 4
-
12
■演奏機能を確認しましょうXP-50は鳴らしている音に変化を与えるコントローラーを備えています。鍵盤を弾きながら、それぞれの効果を確認してみましょう。
※コントローラーを使って得られる効果は、選んでいるパッチなどの設定によって異なります。効果が分か
りにくいときは他のパッチを選んでください。
● ベロシティー/アフタータッチ鍵盤を弾く強さ(ベロシティー)によって音量や音の鳴りかたが変化します。また、鍵盤を弾いた後、さらに鍵を強く押さえる(アフタータッチ)と音の鳴りかたが変化します。
● ピッチ・ベンド/モジュレーション・レバー鍵盤を弾きながら、レバーを左に倒すとピッチが下がり、右に倒すとピッチが上がります。これをピッチ・ベンド効果といいます。また、レバーを向こう側に倒すとビブラートがかかります。これをモジュレーション効果といいます。レバーを左または右に倒しながら向こう側に倒したときは、両方の効果が同時に得られます。
● C1スライダー/C2スライダー鍵盤を弾きながらスライダーを上下に動かすと、音量や音色が変化します。
● ホールド・ペダルペダル・スイッチ(DP-2/DP-6:別売)をリア・パネルのHOLD PEDALジャックに接続すると、ペダルを踏んでいる間は鍵を離しても音を持続させる(ホールド)ことができます。ただし、鍵を離さなくても自然に音が消えてしまうパッチを選んでいるときは、ペダルを踏んでいても音が消えてしまうことがあります。
● エクスプレッション・ペダルエクスプレッション・ペダル(EV-5/EV-10:別売)をリア・パネルのPEDAL 1ジャック/PEDAL 2ジャックに接続すると、ペダルを使って音量や音色を変化させることができます。
-
13
デモ・ディスクを使ってみましょう■デモ・ソングを聴いてみましょう
付属ディスクにはデモ・ソングが7曲収録されています。デモ・ソングを聴いてXP-50の優れた音色やエフェクトをお楽しみください。
ソング・ナンバー:ファイル・ネーム(ソング・ネーム) 作曲者01:DEMO_001.SVQ (Phaser-Dance) Mitsuru Sakaue Copyright 1995 Roland Corporation02:DEMO_002.SVQ (Meaning Of Life) Masashi Hirashita, Kazuko Hirashita
Copyright 1995 Roland Corporation03:DEMO_003.SVQ (RPS City) Naoki Matsuura Copyright 1995 Roland Corporation04:DEMO_004.SVQ (Secrets) Chong Lim Copyright 1995 BMG Publishing05:DEMO_005.SVQ (Flying Chicken) S. Nakamura Copyright 1995 Roland Corporation06:DEMO_006.SVQ (Hard Day) Naoki Matsuura Copyright 1995 Roland Corporation07:DEMO_007.SVQ (Prince Of Peace) Eric Persing Copyright 1995 Big Green Music
※これらのソングを個人で楽しむ以外に権利者の許諾なく使用することは法律で禁じられています。
1. 付属ディスクをディスク挿入口に入れます。ディスクのラベル面を上にし、矢印が記されている方向に差し込んでください。正しくセットされると、カチッという音がして、挿入口右下にあるイジェクト・ボタンが飛び出します。
2. PERFORMボタンを押した後、SEQUENCERボタンを押してソングのプレイ画面に切り換えます。
3. ソング・ナンバーにカーソル(下線)があることを確認します。
4. αダイヤルを回すか、INCボタン/DECボタンまたはテン・キーを押して再生するデモ・ソングを選びます。
5. ENTERボタンを押してソングを確定させた後、STOP/PLAYボタンを押してデモ・ソングの再生を始めます。再生が終わると自動的に停止します。再生を中断したいときはもう一度STOP/PLAYボタンを押します。
※ENTERボタンを押さずにSTOP/PLAYボタンを押しても再生が始められます。
※再生を中断したりした場合、表示の小節ナンバー(M=)に“+”がつくことがあります。これは小節の
途中で停止していることを示しています。
※ソングの再生後に鍵盤を演奏して、音が鳴らなかったり、ピッチがずれたりする場合は、SHIFTボタンを
押しながらEXITボタンを数秒間押してください(パニック機能)。
■ソングに合わせてRPS機能を使ってみましょうRPS(リアルタイム・フレーズ・シーケンス)機能は、ソングのパターン・トラックに記録されているパターン(1つの演奏フレーズの単位)を特定の鍵を押さえて再生させる機能です。RPS機能はソングごとに設定できます。押さえる鍵によっていろいろなフレーズが再生できるので、ライブ演奏などで利用すると効果的です。付属ディスクにはRPS機能が使えるデモ・ソングが1曲収録されています。それでは実際に試してみましょう。
ソング・ナンバー:ファイル・ネーム(ソング・ネーム) 作曲者08:RPS_DEMO.SVQ (Try RPS) Tatsuya Senoh Copyright 1995 Roland Corporation
※このソングを個人で楽しむ以外に権利者の許諾なく使用することは法律で禁じられています。
1. カーソルがソング・ナンバーの位置にあることを確認した後、αダイヤル、INCボタン/DECボタン、またはテン・キーを使って“08:RPS_DEMO.SVQ (Try RPS) ”を選びます。
2. ENTERボタンを押してソングを確定させます。ソングを確定させると、RPSボタンとLOOPボタンのインジケーターが点灯します。
SONG 00:InternalSong( )[STOP] M= 1 | =120|B= 4/ 4|
-
14
3. STOP/PLAYボタンを押してソングの再生を始めます。1小節目にはどのパッチを使ってどのように演奏させるかなどを設定するセットアップ・データが記録され、2~8小節に演奏が記録されています。また、何度も繰り返して再生されるように設定されています。
4. ソングを聴きながらF2~C#3の鍵を適当に押してパターンを再生してみましょう。
※パターンの再生を途中で止めたいときはC2鍵を押してください。
5. STOP/PLAYボタンを押してソングの再生を終わります。
■RPS機能を使っていろいろなパターンを演奏してみましょう先ほどはソングを再生しながらRPS機能を使ってパターンを再生してみました。付属ディスクにはこの他に、RPS機能を使ってパターンを再生するだけのソングが11種類用意されています。これらのソングはSTOP/PLAYボタンを押しても再生されませんが、いろいろな演奏に利用できるパターンが数多く記録されています。ここでは、これらのパターンの再生のしかたを説明します。オリジナルのソングを作られるときなどにご利用ください。
ソング・ナンバー:ファイル・ネーム(ソング・ネーム) 制作者09:SAMPLE01.SVQ (Acid Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation10:SAMPLE02.SVQ (Acid Swing Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation11:SAMPLE03.SVQ (Dancehall Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation12:SAMPLE04.SVQ (Euro Beat Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation13:SAMPLE05.SVQ (Funk Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation14:SAMPLE06.SVQ (Ground Beat Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation15:SAMPLE07.SVQ (Hip Hop Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation16:SAMPLE08.SVQ (House Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation17:SAMPLE09.SVQ (Jazz Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation18:SAMPLE10.SVQ (Lovers Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation19:SAMPLE11.SVQ (Trance Set) Mitsuru Sakaue, Kiyotaka Takiyama Copyright 1995 Roland Corporation
※これらのパターンのフレーズの著作権は当社が保有しています。お客様が新たな作品の制作でこれらのフ
レーズを使用されることに関しては、当社の許諾を必要としません。ただし、作成された作品が第三者の
著作権を侵害しても当社は一切の責任を負いません。
※デモ・ソングの“RPS City”は“Trance Set”のパターンを使って作成されています。
※それぞれのパターンはパフォーマンスの基本設定を元にして作られています(パフォーマンスについては
次ページ参照)。そのため、現在選ばれているパフォーマンスの設定によっては音量バランスやエフェク
ターのかかりかたなどが変わってしまいます。パフォーマンスを基本設定にしたいときは、パフォーマン
スのイニシャライズの操作を行ってください(取扱説明書参照)。
1. PERFORMボタンのインジケーターが点灯していることを確認します。
2. 使いたい音楽ジャンルのソングを選んでからENTERボタンを押します。RPSボタンとLOOPボタンのインジケーターが点灯します。
3. STOP/PLAYボタンを押します。ソングは再生されませんが、パターンの演奏で使うパッチが選ばれます。また、ソングを再生状態にしておくことで、それぞれのパターンの再生を始めるタイミング(小節)を同期させることができます。
4. F2~C#3の鍵を適当に押してパターンを再生します。
※パターンの再生を途中で止めるときはC2鍵を押してください。
5. 操作を終えたらSTOP/PLAYボタンを押して停止させます。
-
15
XP-50を使って簡単なソングを作ってみましょう。XP-50では、1曲分の演奏データをソングと呼んでいます。ここでは以下のサンプル曲を録音して基本操作を覚えましょう。
■録音を始める前に
● 録音の方法録音にはリアルタイム・レコーディングとステップ・レコーディングの2つの方法があります。それぞれの特徴を生かしてレコーディング方法を決めます。
リアルタイム・レコーディングリアルタイム・レコーディングは鍵盤で弾いた演奏をそのまま録音する方法です。自分の演奏したニュアンスを残したいときはこの方法で録音するとよいでしょう。
ステップ・レコーディングステップ・レコーディングは、1音ずつ音符を指定していく録音方法です。しっかりとした譜割で演奏しなければならないパートの録音に向いています。また、自分で演奏するのが難しいフレーズを録音するときにも向いています。
● 録音の順番複数の楽器の演奏を録音するときは多重録音をします。多重録音は他のフレーズ・トラックに録音した演奏を聴きながら録音をする方法です。一般に多重録音をする場合は、“ドラム→ベース→伴奏→メロディー”の順に録音していきます。このように録音していけば、ドラムやベースの演奏を聴きながら伴奏やメロディーの録音ができるので、リズムを合わせやすくなります。
● パフォーマンスを選びましょう複数のパッチを使って演奏するときはパフォーマンス・モードに切り換えます。パフォーマンス・モードではパッチやリズム・セットをパートという箱に割り当てます。パートは16個あります。各パートにどのパッチやリズム・セットを割り当てるかなどはパフォーマンスという単位で設定します。これらの関係をまとめると、パートが演奏者、パッチやリズム・セットが楽器、パフォーマンスがバンド編成を決めるものということになります。パフォーマンスにはレイヤーとシングルの2つのタイプがあります。レイヤーのパフォーマンスでは複数のパートを同時に鳴らすことができます。シングルのパフォーマンスでは指定のパートだけを鳴らすことができます。アンサンブル演奏を録音するときはシングルのパフォーマンスを選びます。サンプル曲を録音するに当たっては、メロディー・パートにパート1、ベース・パートにパート2、リズム・パートにパート10を使います。また、パフォーマンスは“PR-A:12 Pop Set 1”使います。それでは、以下の操作でパフォーマンス・モードに切り換え、指定のパフォーマンスを選びましょう。
ソングを作ってみましょう
-
16
1. PERFORMボタンを押してパフォーマンス・モードのプレイ画面に切り換えます。ディスプレイには、今選ばれているパフォーマンスのグループ、ナンバー、ネームが表示されます。
2. αダイヤルを回すかINCボタン/DECボタンを押して、“PR-A:12 Pop Set 1”のパフォーマンスを選びます。
※パフォーマンスはテン・キーで選ぶこともできます。この場合は、SHIFTを押しながらテン・キーの1を押
します。これでパフォーマンスのグループPR-Aが選ばれました。次にテン・キーを1→2の順に押した後、
ENTERボタンを押します。これで“PR-A:12 Pop Set 1”のパフォーマンスが選ばれました。
■打楽器をリアルタイム・レコーディングしましょう複数の打楽器をリアルタイム・レコーディングの方法で一度に録音することは大変です。そこで、指定範囲を何度も繰り返して録音させるループ機能を使います。また、録音モードは音を重ねて録音する“MIX”を選びます。演奏はフレーズ・トラックと呼ばれる場所に録音します。フレーズ・トラックは16個(1~16)あります。ここでは、使用するパートと同じナンバーのフレーズ・トラック10に録音していきます。ドラム・セットはパフォーマンスに設定されている“PR-A:2 PopDrumSet1”を使います。
1. SEQUENCERボタンを押してソングのプレイ画面に切り換えます。
2. 録音先にインターナル・メモリーを選びます。ソング・ナンバーの位置にカーソルがあることを確認した後、αダイヤルを左に回すかDECボタンを押して“00:InternalSong”を選んでください。
※ソングを録音する場合、一旦インターナル・メモリーと呼ばれるところに記録します。ディスクに直接録
音することはできません。
3. RECボタンを押してスタンバイ画面に切り換えます。
※録音を中止するときはEXITボタンまたはRECボタンを押します。
4. 録音先のフレーズ・トラック10を選びます。1-8/9-16ボタンを押してボタンのインジケーターを点灯させた後、TRACKボタン10を押してください。TRACK 10ボタンのインジケーターが点滅します。フレーズ・トラック10を選ぶと、録音で使うパートとして同じナンバーのパート10が選ばれます。
5. 録音モードが“MIX”に設定されていることを確認します。
6. 繰返し録音する小節数(4小節)を設定します。 ボタンを押して“Loop”にカーソルを移動した後、αダイヤルを右に回すかINCボタンを押して“4”を選んでください。小節数を指定するとLOOPボタンのインジケーターが点灯します。
PERFORM PR-A: 12 Pop Set 1 part= 1PLAY center=C 4
TRACK 10 Mode= MIX|Loop= 4 part=10[STBY] M= 1 | =120|B= 4/ 4|Wait Note
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
I9 -161 - 8
EDIT
-
17
7. 録音を始める小節位置を確認します。ここでは最初の小節から録音を始めるので小節ナンバーは1です。
8. テンポを設定します。ここではとりあえず70に設定します。 ボタンを押して“ =”にカーソルを移動し、αダイヤルを左に回すかDECボタンを押して“70”に設定してください。
※最初に録音するときに設定したテンポはテンポ・トラックに記録されます。つまり、ソングを始めから再
生するときは、最初に設定したテンポで常に再生することができます。
9. 録音開始方法を選びます。ここでは鍵を押さえると録音が始まる方法を選びます。 ボタンを押してカーソルを右下端に移動し、αダイヤルを右に回すかINCボタンを押して“Wait Note”を選んでください。
10. メトロノームを鳴らして演奏のタイミングを合わせたいときは、SHIFTボタンを押しながらMETRONOMEボタンを押してください。
※メトロノーム音を消したいときは、もう一度SHIFTボタンを押しながらMETRONOMEボタンを押します。
これで録音の準備ができました。それでは次に演奏を録音してみましょう。
11. 最初はC2(ド)の鍵を押してバス・ドラム(Hybrid Kick1)を録音します。C2鍵を押すと同時に録音が始まります。
12. 4小節目までの録音が終わるとソングは1小節目に戻り、今録音したバス・ドラムの演奏が再生されます。この演奏に合わせてD2鍵のスネア・ドラム(Natural SN2)を録音してください。
※録音中、どの鍵にどの打楽器が割り当てられているかを確認したいときは、RECボタンを押しながら鍵を
押さえてください。この場合、押さえた鍵の打楽器が鳴りますが録音はされません。
13. 同じように、G2鍵(Verb Tom Hi)、F2鍵(Verb Tom Lo)、F#2鍵(Cl HiHat1)と順番に録音していきます。
ENTER
GHIDEFABC
SPACE0
1 2 3
- OCT + OCT
SYSTEM UTILITYEFFECTSON OFFI
DISK I
B C D
A
3METRONOME
SHIFT USER
+ -I DIGIT HOLD
PRESET CPRESET BPRESET A
RPS
-
18
.......................................................................................................................................................................................................<リアルタイム・イレース>思ったように録音できなかった場合は、リアルタイム・イレース機能を使って打楽器音を消します。リアルタイム・イレース機能を使うときは、録音状態でEDITボタンを押した後、(ERASE)ボタンを押します。ボタンを押すとリアルタイム・イレース画面に切り換わります。
消したい打楽器音の鍵を押すと、鍵を押している間の音が消えます。すべての打楽器の演奏を消したいときはRECボタンを押してください。RECボタンを押している間の演奏が消えます。消し終えたらEXITボタンを押して元の画面に戻します。.......................................................................................................................................................................................................
14. すべての打楽器の演奏を録音したらSTOP/PLAYボタンを押して終了します。
15. 今録音した演奏をもう一度聴いてみましょう。SHIFTボタンを押しながらBWDボタンを押して1小節目の頭に戻した後、STOP/PLAYボタンを押してください。
※録音した演奏のタイミングがばらついているときは、クォンタイズ機能を使って揃えることができます。
詳しくは取扱説明書をご覧ください。
■演奏データを見てみましょうシーケンサーで録音した演奏はMIDIメッセージとして記録されています。先程録音したトラック10のMIDIメッセージをマイクロスコープ画面で確認してみましょう。
1. SHIFTボタンを押しながらBWDボタンを押してソングの1小節目の頭に戻します。
2. M.SCOPEボタンを押してマイクロスコープ画面に切り換えます。
3. ボタン/ ボタンを押して記録されているMIDIメッセージを確認します。 ボタンを押すと次のMIDIメッセージが、 ボタンを押すと直前のMIDIメッセージが確認できます。
※MIDIメッセージのパラメーターが画面に表示しきれないときは、画面の右上に マークが表示されます。
その場合は、 ボタンを押して確認することができます。
※MIDIメッセージの左側に“*”マークが表示されたときは、同じ位置に複数のMIDIメッセージが記録され
ていることを示しています。
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
TRK EDIT NAME TRACK LOOP RPS SEQ UTILITY (ERASE)
I
PERFORMPATCH RHYTHM
SEQUENCERM.SCOPE
CHAIN PLAYSYSTEM
9 -161 - 8
EDIT
IQUANTIZE
TRACK 10|Real Time Erase [REC]:All Data[ERASE] |M= 1 | =120|
TRACK 10|*Note(C 2)|Ch|Note|OnVel|GateM.SCOPE 1-01-000|10| 36| 127| 96
-
19
■ベースをステップ・レコーディングしましょうベースの演奏はパート2に割り当てられている“Finger Bass”のパッチを使い、フレーズ・トラック2にステップ・レコーディングします。
1. PERFORMボタンを押してパフォーマンス・モードのプレイ画面に切り換えます。
2. ボタンを押して、鍵盤で演奏するパート2を選びます。
3. M.SCOPEボタンを押してマイクロスコープ画面に切り換えます。
4. ソングを1小節目の頭(1-01-000)に戻します。SHIFTボタンを押しながらBWDボタンを押してください。
5. 録音先のトラック2を選びます。EDITボタンのインジケーターの消灯を確認してから1-8/9-16ボタンを押すと、フレーズ・トラック2が選ばれます。
6. RECボタンを押してステップ・レコーディング画面に切り換えます。
7. 最初の音符のステップ・タイム(音符の長さ)を選びます。最初の音符は4分音符です。“Step”に が表示されていることを確認してください。
※ステップ・タイムはテン・キーでも入力できます。テン・キーの右下に記されている音符記号が入力でき
るステップ・タイムです。ここでは4分音符を入力するのでテン・キー8( )を押します。
8. 最初の音のG2(ソ)鍵を押します。
鍵を離すと値は確定され、次の音符が入力できる状態になります。
※入力を訂正するときは、BWDボタンを押して直前に入力した音を削除してからもう一度入力します。
PERFORM PR-A: 12 Pop Set 1 part= 2PLAY center=C 4
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
I9 -161 - 8
EDIT
TRACK 2| Note|Step|Gate| Velocity[S.REC] | 1-01-000| | 80%| REAL
TRACK 2| 2| 43:G 2|Step|Gate| Velocity[S.REC] | 1-01-000| | 80%| REAL
TRACK 2| Note|Step|Gate| Velocity[S.REC] | 1-02-000| | 80%| REAL
-
20
9. 次に8分休符を入力します。ステップ・タイムに8分音符を選んでから(REST)ボタンを押してください。
10. 次に16分音符を2回入力します。ステップ・タイムに16分音符を選んでからG2(ソ)鍵を2回押してください。
11. 次に2分休符を入力します。ステップ・タイムに2分音符を選んでから(REST)ボタンを押してください。
12. これで1小節目が入力できました。同じ要領で2小節目以降を入力してください。
13. 録音が終わったらSTOP/PLAYボタンを押します。
14. 録音した演奏を聴いてみましょう。SHIFTボタンを押しながらBWDボタンを押して1小節目の頭に戻します。SEQUENCERボタンを押した後、STOP/PLAYボタンを押して再生します。
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
CREATE ERASE MOVE COPY PLACE VIEW (REST)(TIE)
I
PERFORMPATCH RHYTHM
SEQUENCERM.SCOPE
CHAIN PLAYSYSTEM
9 -161 - 8
EDIT
I
TRACK 2| Note|Step|Gate| Velocity[S.REC] | 1-02-048| | 80%| REAL
TRACK 2| Note|Step|Gate| Velocity[S.REC] | 1-03-000| | 80%| REAL
TRACK 2| Note|Step|Gate| Velocity[S.REC] | 2-01-000| | 80%| REAL
-
21
■メロディーをリアルタイム・レコーディングしましょうメロディーの演奏はパート1に割り当てられている“64voicePiano”のパッチを使い、フレーズ・トラック1にリアルタイム・レコーディングします。打楽器の録音ではループ機能を使いましたが、ここでは1つの楽器のフレーズを録音するだけなのでループ機能は使いません。また、重ねて録音することもないので録音モードは“REPLACE”を選びます。単に演奏を録音するときは“REPLACE”を選びます。この場合、録音先のトラックに演奏が記憶されているときは、その演奏を消しながら書き換えていくことになります。その他、ここでは録音の開始方法として、メトロノームで1小節のカウントを入れる“Count In=1”を選びます。
1. SEQUENCERボタンを押してソングのプレイ画面に切り換えます。
2. RECボタンを押してスタンバイ画面に切り換えます。
3. 録音先のトラック1を選びます。1-8/9-16ボタンのインジケーターが消灯していることを確認した後、TRACKボタン1を押してください。
このとき、TRACK1ボタンとRECボタンのインジケーターが点滅し、TRACK2/10ボタンが点灯します。点灯しているトラックには演奏が記録されていることを示しています。今は1-8/9-16ボタンが消灯しているので、トラック2に演奏が記録されていることを示しています。また、フレーズ・トラック1を選ぶと、録音で使うパートとして同じナンバーのパート1が選ばれます。
4. 録音モードを“REPLACE”にします。 ボタンを押して“Mode”にカーソルを移動した後、αダイヤルを左に回すかDECボタンを押して“REPLACE”を選びます。
5. 打楽器の録音で使っていたループ機能をオフにします。 ボタンを押して“Loop”にカーソルを移動した後、αダイヤルを左に回すかDECボタンを押して“OFF”を選びます。“OFF”にするとLOOPボタンのインジケーターが消灯します。
6. 録音を始める小節ナンバー1を設定します。 ボタンを押して“M=”にカーソルを移動した後、αダイヤルを回すかINCボタン/DECボタンを押して“1”を選んでください。
7. 録音開始方法に“Count In=1”を選びます。 ボタンを押してカーソルを右端に移動した後、αダイヤルを左に回すかDECボタンを押して選んでください。
8. SHIFTボタンを押しながらMETRONONEボタンを押してメトロノームを鳴らします。
9. STOP/STARTボタンを押して録音を始めます。メトロノームで1小節のカウントの後、鍵盤を演奏してください。先ほど録音した打楽器とベースの演奏に合わせてメロディーを録音してください。
10. 録音が終了したらSTOP/PLAYボタンを押します。
11. SHIFTボタンを押しながらMETRONOMEボタンを押してメトロノームを止めます。
以上でサンプル曲の録音が終了しました。SHIFTボタンを押しながらBWDボタンを押してソングを1小節目に戻した後、STOP/PLAYボタンを押してソングを聴いてみましょう。
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
I9 -161 - 8
EDIT
-
22
ソングを保存(セーブ)しましょう作成したソングは、電源をオフにすると消えてなくなってしまいます。電源をオフにした後もソングを残しておきたいときは、ディスクに保存(セーブ)します。
■ディスクをフォーマットしましょう新品や他の機器で使用したディスクには、そのままソングをセーブできません。セーブをする前にXP-50でディスクを使用できるように準備(フォーマット)します。
1. ディスクを確認します。XP-50で使用できるディスクは3.5インチ2DD/2HDタイプのものです。また、フォーマットをすると、ディスクに記録されていたデータはすべて消えてしまいます。他の機器で使用していたディスクを使われるときは、データを消してもよいかどうかをあらかじめ確認してください。
2. ディスクのプロテクト・タブを解除(ライト側)します。
3. ディスクをディスク挿入口に入れます。
4. DISK/UTILITYボタンを押します。操作の選択画面が表示されます。
5. ボタンを押して“5:DISK”を点滅させた後、ENTERボタンを押します。ディスクに関係する操作の選択画面が表示されます。
6. “1:FORMAT”が点滅していることを確認した後、ENTERボタンを押します。フォーマットの実行画面が表示されます。
7. ENTERボタンを押してフォーマットを実行します。フォーマット中は“Formatting”と表示され、フォーマットが終了すると“Complete”と表示されます。
8. 引き続きソングのセーブ操作をするときは、EXITボタンを2回押して操作4のUTIL画面に戻します。ソングのプレイ画面に戻したいときはEXITボタンを3回押します。
UTIL|1:WRITE 2:LOAD 3:SAVE 4:SOUND |5:DISK
UTIL|1:FORMAT 2:BACKUP 3:VERIFY 4:VOLUMEDISK|5:DELETE 6:RENAME 7:INFO
DISK |[ ] [ENTER]FORMAT | [SHIFT]
-
23
■ソングをディスクにセーブしましょう先ほどフォーマットしたディスクにソングをセーブしましょう。
1. ボタンを押してUTIL画面の“3:SAVE”を点滅させた後、ENTERボタンを押します。保存するデータの選択画面が表示されます。
2. “1:SONG”が点滅していることを確認した後、ENTERボタンを押します。セーブの実行画面が表示されます。
3. ファイル・ネームをつけます(8文字以内)。 ボタン/ ボタンを押して文字を入力する位置にカーソルを移動し、αダイヤルを回すかINC/DECボタンを押して文字を選びます。
※ファイル・ネームの最後には“.SVQ”という記号がついています。これはファイルの種類を区別するため
の記号(拡張子)です。この記号は修正したり、削除したりすることはできません。
※ファイル・ネームはソングを区別するための名前なので必ずつける必要があります。ソング・ネームはつ
けなくてもかまいません。例えば、ファイル・ネームでソングを分類する名前をつけ、ソング・ネームで
タイトルをつけるといったように、両方の名前を使い分けるとソングを整理するときに便利です。ただし、
ソング・ネームはこの画面ではつけられません。ソング・ネームのつけかたは取扱説明書をご覧ください。
4. 名前をつけ終えたらENTERボタンを押してセーブを実行します。セーブ中は“Saving”と表示されます。セーブが終了すると“COMPLETE”と一瞬表示されてから操作2の画面に戻ります。
これでソングが保存できました。EXITボタンを3回押してソングのプレイ画面に戻してください。それでは最後にこのソングに合ったパフォーマンスを作ってみましょう。
UTIL|1:SONG 2:SMF-0 3:SMF-1 4:SOUND SAVE|
SAVE |[SONG_000 ].SVQ [ENTER]SONG |( ) [SHIFT]
-
24
サンプル曲の録音では、あらかじめ記憶されているパフォーマンスをとりあえずそのまま使いました。しかし、そのパフォーマンスで選ばれている設定が最適とは限りません。そこで、サンプル曲に合ったパフォーマンスに作りなおしてみましょう。パフォーマンスには数多くの設定がありますが、ここではメロディーで使っているパッチを他のものに入れ換えてみましょう。そして、作ったパフォーマンスの名前を書き換えてその設定を保存しましょう。
■メロディーのパッチを入れ換えてみましょう1. PERFORMボタンを押してパフォーマンス・モードのプレイ画面に切り換えます。
2. ボタンを押してパート1を選びます。
3. EDITボタンを押してボタンのインジケーターを点灯させます。EDITボタンのインジケーターを点灯させると、ファンクション・ボタンの機能がボタン下に記されている画面グループの切り換えになります。今はパフォーマンス・モードが選ばれているので、PERFORM列の画面グループの切り換えになります。
4. ファンクション・ボタンの中のPARTボタンを押してボタンのインジケーターを点滅させます。
パート1のPATCH画面が表示されます。この画面が表示されないときは ボタンを押して表示させてください。
5. 鍵盤を押さえて実際に音を鳴らしながら好みのパッチを選びます。この画面ではグループとナンバーを別々に選びます。 ボタン/ ボタンを押してどちらかを選び、αダイヤルを回すかINCボタン/DECボタンを押してそれぞれの値を変更してください。
6. 変更を終えたらEXITボタンを押します。表示のパフォーマンス・グループの右には「*」マークがついています。これはパフォーマンスの設定が変更されていることを示しています。
7. 実際にソングを再生して確認してみましょう。STOP/STARTボタンを押してください。
■パフォーマンスに新しい名前をつけましょうそれでは引き続き、パフォーマンスの名前をつけましょう。それぞれのパフォーマンスにはあらかじめ名前がつけられていますので、今ついている名前を変更することになります。
1. ファンクション・ボタンの中のCOMMONボタンを押してボタンのインジケーターを点滅させます。
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
COMMON EFFECTS MIDI PART INFO
I
PERFORMPATCH RHYTHM
SEQUENCERM.SCOPE
CHAIN PLAYSYSTEM
EDIT
I
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
COMMON EFFECTS MIDI PART INFO
I
PERFORMPATCH RHYTHM
SEQUENCERM.SCOPE
CHAIN PLAYSYSTEM
EDIT
I
PART 1| Group|NumberPATCH USER|001( )
ソングにあったパフォーマンスを作りましょう
-
25
PERFORM NAME画面が表示されます。この画面が表示されないときは ボタン/ ボタンを押して表示させてください。
2. ボタン/ ボタンを押して文字を変更する位置にカーソルを移動し、αダイヤルを回すかINC/DECボタンを押して文字を選びます。
3. 名前をつけ終えたらEXITボタンを押します。
■パフォーマンスを保存しましょう変更したパフォーマンスの設定は一時的なものです。電源を切ったり、他のパフォーマンスに切り換えたりすると失われます。変更したパフォーマンスの設定を残しておくときは、ユーザー・メモリーのパフォーマンスの設定を書き換えます。
※設定を書き換えてもイニシャライズの操作でお買い上げ時の設定に戻すことができます。操作については
取扱説明書をご覧ください。
1. パフォーマンス・モードでDISK/UTILITYボタンを押してUTIL画面に切り換えます。
2. ボタンを押して“1:WRITE”を点滅させた後、ENTERボタンを押します。パフォーマンスの設定を書き換える画面に切り換えます。
3. αダイヤルを回すかINC/DECボタンを押して書き込み先のパフォーマンス・ナンバーを選びます。ここでは適当なパフォーマンス・ナンバーを選んでください。
4. ENTERボタンを押して書き込みを実行します。ディスプレイには以下の画面が表示されます。この画面はインターナル・ライト・プロテクトがオンになっていることを知らせています。インターナル・ライト・プロテクトは、XP-50に記憶されているユーザー・メモリーの設定を誤って書き換えてしまわないように保護するためのものです。
5. αダイヤルを左に回すかDECボタンを押してインターナル・ライト・プロテクトをOFFにした後、ENTERボタンを押して確定します。そして、もう一度ENTERボタンを押して書き込みを実行します。
※インターナル・ライト・プロテクトの設定は電源を切るまでOFFになっています。インターナル・プロテ
クトがOFFになっている状態で同様の操作をしたときは、操作4で書き込みが実行されます。
これで、サンプル曲にあったパフォーマンスが保存できました。サンプル曲を再生するときは、このパフォーマンスを選ぶようにしてください
1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16I I I I I I I ITRACK PART
43214321TONE SWITCH TONE SELECT
COMMON EFFECTS MIDI PART INFO
I
PERFORMPATCH RHYTHM
SEQUENCERM.SCOPE
CHAIN PLAYSYSTEM
EDIT
I
PERFORM |[Pop Set 1 ]NAME [SHIFT]
PERFORM |Number [ENTER]WRITE |USER: 12(Ochestral)
WRITE | Internal Write Protect= ONPROTECT |
-
プロフィール付属ディスクに記録されているデモ・ソングとパターンの作成者のプロフィールです。
Chong Lim(チョン・リム)オーストラリアのメルボルンやシドニーを本拠地として活躍するセッション・ミュージシャン(キーボード)で、作曲、編曲、音楽プロデュースもこなす。ジャーメイン・ジャクソン(Jermaine Jackson)、リトル・リバー・バンド(LittleRiver Band)、ザ・ユーログライダーズ(The Eurogliders)などの著名アーティストとも共演している。最近では、映画やテレビのサウンドトラック・ミュージックの作曲も数多くてがけている。
Eric Persing(エリック・パーシング)現在、セッション・ミュージシャン/プログラマーとして、ロサンゼルスで最も売れっ子のアーティストの一人である。マイケル・ジャクソン(Michael Jackson)、チャカ・カーン(Chaka Khan)、ラリー・カールトン(Larry Carlton)、マーカス・ミラー(Marcus Miller)、ボン・ジョビ(Bon Jovi)など、数多くの有名アーチストと共演している。アメリカのTVショーやコマーシャルの音楽も数多く手掛けている。映画音楽の分野でもその才能を高く評価され、ミッシェル・コロムビエ(Michel Columbier)、ダニー・エルフマン(Danny Elfman)、ビル・コンティ(Bill Conti)などの著名な作曲家の作品にも参加している。また、ローランドのプロダクト・スペシャリストとして、新製品の開発や音作りに携わっている。
坂上暢(Mitsuru Sakaue)大学在学中より、キーボード・プレーヤー、アレンジャーとして数々のスタジオ・ワークやCM等の音楽制作にたずさわり、現在はコンポーザー、アレンジャー、キーボード・プレーヤー、コンピューター・ミュージックのエキスパートとして、TV、ラジオ等のCM音楽制作、音楽専門誌への執筆とあらゆるメディアで活躍中。ジャンルを問わない幅広い音楽性は高い評価を受けている。音楽クリエーター集団(株)アイデックスのチーフ・ディレクター。
滝山清貴(Kiyotaka Takiyama)1964年、東京生まれ。1986年にボストンのバークリー音楽大学に入学し、理論、アレンジ、ドラムを専攻する。在学中よりレコーディングやライブなどで数多くのミュージシャンと共演する。帰国後も数多くのアーティストのレコーディングに参加する一方でTVコマーシャルなども手掛け、ライブ&レコーディング・ミュージシャンとして活躍中である。
平下政志(Masashi Hirashita)
平下和子(Kazuko Hirashita)政志氏は、幼少からクラッシック・ピアノを学び、学生時代には作曲を専攻すると共に、キーボーディスト兼作曲家としての活動を始める。ジャズ、フュージョン、ポップスなど様々なジャンルのスタジオ・セッションや、サポート・ミュージシャンとして活動する。また、そのかたわらCM、アニメーションビデオ、ミュージカル、TVやFM番組などの音楽を手掛ける。現在は夫人の和子氏と共に作曲、演奏活動を行ない、ローランドからSMF Music Dataをリリースするなど、コンピューターを駆使した音楽制作に幅広く活躍中である。
松浦直樹(Naoki Matsuura)10年間の渡米中に本格的なプロベーシストとしての活動を開始。ボストンを中心にライブやスタジオなどの演奏活動を行う。フリーランスの活動が多く、パキート・デ・リヴェラ、クラウディオ・ロディッティ、トミー・キャンベル、スティーブ・ハント(アラン・ホールズワースのキーボード奏者)などと共演する他、タイガー大越(JVCアーティスト)率いるTiger's Bakuにも参加する。1991年には日本に帰国してローランド社員となり、ミュージック・データやデモ・データの開発を手掛けている。
妹尾達也(Tatsuya Senoh)ローランドのエンジニアで、XP-50開発チームの一員。音楽的造詣も深い。今回は自ら開発したRPS機能を紹介するためのデモ・ソングを作る。
S. Nakamuraローランドのエンジニア。数々の音源開発を担当する一方で、U-20、D-70、JV-80、JD-990等のデモ・ソングや音色データも数多く手掛けている。
-
・・・・・・・・・・・・・最寄りの営業所までご相談ください。
札幌営業所 〒060 札幌市中央区大通西6-2-6
三井生命札幌大通ビル7F TEL (011) 281-0708 仙台営業所 〒980 仙台市青葉区本町2-10-33
第2日本オフィスビル1F TEL (022) 225-6221 大宮営業所 〒331 大宮市桜木町1-441
GINZA YAMATO3 6F TEL (048) 648-8977 東京営業所 〒101 東京都千代田区神田須田町2-7
タームスビル7F TEL 代表(03) 3251-5595 横浜営業所 〒221 横浜市神奈川区鶴屋町2-11-3
KMビル5F TEL (045) 313-3841
名古屋営業所 〒460 名古屋市中区栄2-11-7
伏見大島ビル2F TEL (052) 202-1881 大阪営業所 〒530 大阪市北区堂島浜1-4-16
大和堂島ビル5F TEL代表 (06) 345-9521 広島営業所 〒730 広島市中区紙屋町1-1-17
広島MIDビル4F TEL (082) 247-2731 福岡営業所 〒812 福岡市博多区店屋町1-31
東京生命福岡ビル7F TEL (092) 282-4190
修理に関するお問い合わせは
東京サービス・ステーション 〒101 東京都千代田区神田須田町2-7
タームスビル7F TEL (03) 3251-1391 名古屋サービス・ステーション 〒460 名古屋市中区栄2-11-7
伏見大島ビル 2F TEL (052) 202-1881 大阪サービス・ステーション 〒559 大阪市住之江区新北島3-8-53
TEL (06) 681-5321 福岡サービス・ステーション 〒812 福岡市博多区店屋町1-31
東京生命福岡ビル 7F TEL (092) 282-4190
函館サービス・スポット〈(有)ドルビィ〉
〒042 函館市柏木町35-25 TEL (0138) 53-6249 秋田サービス・スポット〈(有)音響サービス〉 〒010 秋田市南通亀の町12-16
TEL (0188) 33-3465 新潟サービス・スポット〈サウンド・リペア北越〉
〒940 長岡市荻野1-7-16 TEL (0258) 29-2732 金沢サービス・スポット〈オリバー電子(有)〉
〒921 金沢市額谷1-32 TEL (0762) 98-8309 姫路サービス・スポット〈ギター ワークショップ PEG〉
〒670 姫路市総社本町214 TEL (0792) 82-6529
あるいはサービス・スポットまでご相談ください。 なお、保証期間内の場合は保証書を添えてご依頼ください。
商品と修理に関するお問い合わせは
サービスの窓口
・・・商品をお求めの販売店か上記営業所、または下記のサービス・ステーション
'95 2. 16 現在
商品のお取り扱いに関するお問い合わせは
お客様相談センター 受付時間:午前10時~午後5時(土、日曜、祝日を除く) ■東京 TEL (03) 3251-6150 〒101 東京都千代田区神田須田町2-7 タームスビル7F
■大阪 TEL (06) 345-9500 〒530 大阪市北区堂島浜1-4-16 大和堂島ビル5F
・・・ お客様相談センターまでご相談ください。
*上記窓口の名称、所在地、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。
-
00781790 '95-02-A3-11D