™… O瘻ムgbX1Title … O瘻ムgbX1 Created Date 2/23/2009 9:10:41 PM
Transcript of ™… O瘻ムgbX1Title … O瘻ムgbX1 Created Date 2/23/2009 9:10:41 PM

ISSN1346-9479
Shinkin Central Bank Monthly Review
第8巻 第3号(通巻435号) 2009. 3
バーナンキFRB議長の政策対応
米国経済の中期展望-家計の過剰債務調整の長期化で、景気底入れ後も回復テンポは緩慢-
恒久化後も取組み進む信用金庫の地域密着型金融-経営改善支援には事業への助言を、一部個別取組項目は制度の改善を-
全国に広がる「バイオマスタウン」構築への取組み-林地残材などの木質バイオマスと食品廃棄物の利活用が当面の焦点に-
中国山東省の投資環境について-青島市の現況-
平尾光司総合研究所長が専修大学で最終講義を行う
日本中小企業学会全国大会国際交流セッション講演抄録
東京都北区商業活性化支援事業調印式の開催について
和倉温泉活性化への提言キックオフミーティング開催について
統計

○対象分野は、当研究所の研究分野でもある「地域」「中小企業」「協同組織」に関連する金融・
経済分野とし、これら分野の研究の奨励を通じて、研究者の育成を図り、もって我が国におけ
る当該分野の学術研究振興に寄与することを目的としています。
○かかる目的を効果的に実現するため、本論文募集は、①懸賞論文と異なり、募集期限を設けな
い随時募集として息の長い取り組みを目指していること、②要改善点を指摘し、加筆修正後の
再応募を認める場合があること、を特徴としています。
○信金中金月報への応募論文の掲載可否は、編集委員会が委嘱する審査員の審査結果に基づき、
編集委員会が決定するという、いわゆるレフェリー制を採用しており、本月報に掲載された論
文は当研究所ホームページにも掲載することで、広く一般に公表する機会を設けております。
詳しくは、当研究所ホームページ(http://www.scbri.jp/)に掲載されている募集要項等をご
参照ください。
編集委員会(敬称略、順不同)
委 員 長 清水啓典 一橋大学大学院 商学研究科教授
副委員長 藤野次雄 横浜市立大学 国際総合科学部教授
委 員 川波洋一 九州大学大学院 経済学研究院教授
委 員 鹿野嘉昭 同志社大学 経済学部教授
委 員 首藤 惠 早稲田大学大学院 ファイナンス研究科教授
問い合わせ先
信金中央金庫総合研究所「信金中金月報掲載論文」募集事務局(担当:寺尾、照沼)
Tel : 03(5202)7671/Fax : 03(3278)7048
「信金中金月報掲載論文」募集のお知らせ

S h i n k i nC e n t r a lB a n kMon t h l yR e v i e w
個人名による掲載文のうち意見にわたる部分は執筆者個人の見解です。投資・施策実施等についてはご自身の判断によってください。
バーナンキFRB議長の政策対応 2信金中金月報掲載論文 編集委員長 清水啓典
(一橋大学大学院商学研究科教授)
研 究 米国経済の中期展望 角田 匠 4 -家計の過剰債務調整の長期化で、景気底入れ後も回復テンポは緩慢-
恒久化後も取組み進む信用金庫の地域密着型金融 間下 聡 23 -経営改善支援には事業への助言を、一部個別取組項目は制度の改善を-
全国に広がる「バイオマスタウン」構築への取組み 澤山 弘 41 -林地残材などの木質バイオマスと食品廃棄物の利活用が当面の焦点に-
調 査 中国山東省の投資環境について 篠崎幸弘 63 -青島市の現況-
信金中金だより 平尾光司総合研究所長が専修大学で最終講義を行う 総合研究所 73
日本中小企業学会全国大会国際交流セッション講演抄録 総合研究所 74
東京都北区商業活性化支援事業調印式の開催について 総合研究所 82
和倉温泉活性化への提言 総合研究所 83 キックオフミーティング開催について
信金中央金庫総合研究所活動状況(1月) 84
統 計 信用金庫統計、金融機関業態別統計 85
2009
3
2009年 3月号 目次

2 信金中金月報 2009.3
バーナンキ F R B議長の政策対応信金中金月報掲載論文 編集委員長
清水 啓典(一橋大学大学院商学研究科教授)
世界的金融危機は益々深刻化しているが、解決への鍵は震源地である米国の政策対応であり、
その中心人物は米国連邦準備理事会(FRB)のバーナンキ議長である。彼は2002年にFRB理事
となる前はプリンストン大学経済学部長として教鞭を執る研究者で、1930年代の米国大恐慌研
究の第一人者として知られていた。100年に一度と言われる世界的金融危機の際に彼がFRB議
長として采配を振る立場に居合わせるとは、本人も予想だにしていなかったであろうが、米国
は結果的にこれ以上ない最適な人選をしていたことになる(注)1。
彼は2000年の全米経済学会における日本の金融危機に関するセッションで、私を含む日米4
人の論文提出者の1人として論文を発表し、その内容は日米両国で出版されている(注)2。そこで
彼は、長期間デフレから脱却できない日本の金融政策を批判して、ゼロ金利下でも可能なより
大胆で積極的な政策の採用を促している。
また彼は、FRB理事となった翌年の2003年5月に初来日し、日本金融学会創立60周年記念大
会で就任直後の福井日銀総裁と共に、「日本の金融政策に関するいくつかの論考」と題する講演
を行った(注)3。そこで彼は、ゼロ金利政策に言及しつつ、デフレ脱却のためにインフレ目標政策
を更に一歩進めた物価水準目標の導入、並びに、日銀と財務省の明示的な政策協力を提唱した。
中央銀行はインフレ期に政府に対して「ノー」と言う役割を持つが、デフレ期には両者の協力
こそが必要であるとして具体的協調方法にまで立ち入った提案をしている。
更にその前日一橋大学において、彼は最も得意とする「米国1930年代の大恐慌の原因と教訓」
という、現時点で振り返ってみれば極めて示唆に富む内容の講演を行っている。そのポイント
は、大恐慌の本質は通貨供給量の激減による大規模なデフレであるとして、米国政府はその解
決のためにFRBと一体となって、FRBによる大規模な国債の買い上げや金平価の切り下げ更に
は金本位制からの離脱など、大胆な金融の量的緩和による一連の物価引き上げ政策を実施して
大恐慌を克服した、という点にある。当時、デフレ対策としての金融の量的緩和には強い制約
と抵抗感があり、このような政策運営上の誤りが大恐慌からの早期脱却を遅らせたのである。
彼は、米国のデフレが金本位制を通じて全世界に波及したメカニズムを丁寧に説明した上で、
(注)1.清水啓典「米連邦準備制度理事会バーナンキ新議長就任に寄せて」『金融』全国銀行協会 第708号 pp.3-8(2006年3月)2 .三木谷良一・アダム・ポーゼン編、清水啓典監訳、『日本の金融危機-米国の経験と日本への教訓-』東洋経済新報社(2001年8月)3.http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2003/20030531/default.htm

3
世界各国がデフレに苦しむ中、時の大蔵大臣として金本位制離脱による金融緩和などによる果
敢な物価引き上げ政策を実施し、早期のデフレ脱却と経済の健全化を実現した高橋是清が、「日
本の賢人」として当時世界的に知られていたエピソードを紹介している。
現在FRBが実施している対策は、以上の講演で彼が述べた内容をそのまま現在の環境に置き
直したものである。これまでFRBは、異例のスピードでの金利引き下げを続けて、現在はゼロ
金利政策を実施し、更に量的緩和に留まらないそれ以上の「信用緩和」と呼ばれる大胆な金融
緩和政策を実施している。金融機関に対する信用供給のみならず、政府機関債や住宅ローン担
保証券(MBS)や民間部門への信用供給のためコマーシャルペーパー、長期国債、更には世界
の中央銀行とのスワップ協定による大量のドル資金供給など、伝統的金融政策や量的緩和をも
大きく越えるあらゆる手段を動員して、伝統的金融政策の枠に囚われない大胆な政策に踏み込
んでいる。また、金融機関から不良債権を買い取って集中的に管理する「バッドバンク」を創
ることで金融機関の健全性を回復させ、金融システムの安定性を強化する構想も発表している。
その際に彼が強調しているのは、民間の期待に影響を与える政策コミュニケーションである。
政策が何を目指してどのように運営されるのか、将来どのような経済環境になるのかを民間が
理解し、経済の先行きに正しい展望を持って望むことこそ不況からの回復を早める道である。
彼はそのための情報提供に努めることを言明しており、事実あらゆる手段を動員して世界経済
悪化を防止する決意と具体策を次々に発表している。
この点に関して彼は、上記日本金融学会での講演においても、「人は旅に出かける前に、その
目的地を知っておく必要があります…その目的を如何に達成するかはその後の話です」と述べて
いる。目的は世界経済悪化の防止と早期の景気回復であり、そのためにFRBは米国政府と協力
してあらゆる手段を動員するので、世界は信頼して行動して欲しいとのメッセージである。世界
各国の中央銀行も基本的にはこの路線に従った政策運営を行うことになるであろう。事実日銀も
コマーシャルペーパーの買い取りを始めて、一般企業への直接信用供与に踏み切っている。
米国の景気後退は1930年代以来最悪になるのは避けれらないが、25%もの失業率が10間も続
いた大恐慌当時のような状態にはなり得ない。現在では、1930年代の大恐慌に関する膨大な研
究の蓄積があり、しかもその分野の第一人者がFRB議長として現実の政策運営を担っているか
らである。特に日本に関しては、64年前には敗戦で経済は灰燼に帰した上に、高度成長後も石
油ショック、バブル崩壊、金融危機、アジア金融危機、等々、いくつもの不況を経験しており、
今回は100年に一度という程の規模ではない。事実、円は他の全通貨に対して高騰しており、世
界は日本への影響が最も軽いと見ていることを示している。
ショックへの対応力こそ成長の源泉である。不況時こそ新たな発想が生まれることも多い。
長い目で見ると、市場は行き過ぎに対してはバランスのとれた評価を下す。暗い情報が溢れる
中で困難かもしれないが、日本経済の基盤である中小企業がマスコミの報道しない明るい面を
も正しく評価し、冷静に将来を見通す目を持って自らの強みを強化する努力を続けることこそ、
日本経済の早期回復と一層の成長には不可欠である。

4 信金中金月報 2009.3
(キーワード) 金融危機、サブプライムローン、住宅バブル、過剰債務問題、逆資産効果
(視 点) 住宅バブルの崩壊をきっかけとした金融危機が、米国の実体経済に深刻な影響を及ぼしている。金融安定化法の下で、公的資金による金融機関への資本注入が実施されているものの、信用収縮には歯止めがかからず、貸し渋りによる景気の一段の悪化によって金融機関の損失がさらに膨らむ悪循環に陥っている。米国の状況は、土地バブルの崩壊で90年代後半に金融危機に見舞われた日本と同じ構図であり、今後は過剰債務の調整によって景気の低迷が長期化することが懸念されている。もっとも、過剰債務のセクター別の状況や経済構造など、日米で異なる点も少なくない。内需の自律回復力が脆弱な日本経済にとっても、米国経済の先行きが最大の注目点であり、米国経済の中期的な動向を展望することは重要である。本稿では、日本の90年代後半以降の状況との比較を交えて、米国経済の現状と課題を分析する。
(要 旨)● 08年10~12月の経済活動は歴史的な悪化を示したが、これは、今回の金融危機が市場型で連鎖のスピードが速く、グローバルな信用収縮にも発展したことが背景にある。
● 不動産バブルの崩壊後に残るのが過剰債務問題であり、90年代後半以降の日本経済も過剰債務の調整に苦しめられた。ただ、米国の場合、過剰債務を抱えたセクターは住宅ブームの過熱を主導した家計であり、企業部門の財務状態は当時の日本とは異なり健全である。
● 日米の金融危機は不動産バブルの崩壊をきっかけとした点で類似しているが、米国の人口動態や物価情勢、財政事情など経済基盤は当時の日本と比べて優位であると考えられる。
● 金融危機の震源となった住宅価格の下落が続いている。ただ、価格調整は着実に進捗しており、現状の下落ペースが続けば09年8月頃に適正水準に達すると試算される。
● 企業の過剰債務は、大規模な資産売却やリストラで削減を加速するといった選択肢があるが、家計の過剰債務の調整は消費を控え、時間をかけて削減していく以外に方法はない。過剰債務が家計に集中している米国の場合、その調整期間が長期化する恐れがある。
● 金融危機による実体経済の悪化に対して、事実上の量的緩和、大規模な財政政策が打ち出されているが、これを前提にしても家計の過剰債務調整が続くため、当面は従来の回復力を取り戻すことは難しい。今後5年間の年平均実質成長率は1.4%にとどまると予測した。
研 究
米国経済の中期展望-家計の過剰債務調整の長期化で、景気底入れ後も回復テンポは緩慢-
信金中央金庫 総合研究所上席主任研究員
角田 匠
(注)本稿は2009年1月30日時点のデータに基づき記述されている。

研 究 5
1 .金融危機の波及で実体経済は急速に悪化
(1)非農業雇用者数は08年9月から減少が加速
米国経済は07年12月をピークに景気後退
局面に入っているが、金融危機が深刻化した
08年9月以降は、景気の落込みに拍車がか
かっている。
月次統計のなかでも注目度の高い雇用統計
は、足元で大幅な悪化を示している。非農業
雇用者数は08年1月から前月比マイナスに転
じたが、夏頃までは通常の景気後退期並みの
前月比10~20万人程度の減少で推移してい
た(図表1)。しかし、金融危機が拡大した
08年9月以降は減少幅が急拡大した。11月に
は、前月比58.4万人減と単月の減少数では74
年12月(60.2万人減)以来の大幅な減少とな
り、12月も52.4万人減と大幅な減少が続いて
いる。四半期ベースでみると、08年10~12
月の月平均増減数は、51.0万人減と終戦直後
の45年7~9月以来の減少幅を記録した。ま
た、08年12月の失業率は7.2%と93年1月以来
の高い水準となった。
(2 )雇用情勢の悪化と信用収縮で個人消費
は大幅減
雇用情勢の急速な悪化に加え、金融危機に
伴う株価急落、貸し渋りの深刻化などで個人
消費も大きく落ち込んでいる。年末商戦で
は、小売各社が大幅な値引き販売などを実施
したものの、家計の消費抑制傾向は一段と強
まり、08年12月の小売売上高は、前月比2.7%
減と6か月連続で前月の水準を下回った。
特に、金融危機に伴う信用収縮が個人消費
を一段と押し下げる構図が鮮明となってお
り、自動車ローンの借入れ難などから、自動
車販売は大きく落ち込んでいる。月次ベース
の自動車販売は、07年頃まで年率1,600万台
程度で推移していたが、ガソリン価格が高騰
した08年前半には年率1,400万台を割り込ん
だ。さらに、金融危機が拡大した秋以降は
一段と減少し、08年11月は1,014万台、12月
は1,027万台と82年頃の水準に落ち込んだ
(図表2)。
(備考)米労働省資料より作成
図表1 非農業雇用者数の前月比増減と失業率の推移
(年)88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
6050403020100-10-20-30-40-50-60
8.07.06.05.04.0
(万人) (%)
失業率(右目盛)
非農業雇用者数(四半期、月平均)(左目盛)

6 信金中金月報 2009.3
今回の景気後退と金融危機の震源である住
宅市場の悪化にも歯止めがかからない。08
年12月の住宅着工件数は、前月比15.5%減の
年率55.0万件と1959年の調査開始以来の最低
を更新し、08年合計では90.4万件と年間では
初めて100万件の大台を割り込んだ。
(3)企業部門も落込みが鮮明
生産活動も本格的な調整局面に入ってい
る。08年12月の鉱工業生産は前月比2.0%減
と2か月連続のマイナス、前年比で7.8%減と
大きく落ち込んでいる。自動車販売の不振が
影響していることに加え、底堅く推移してき
た輸出も世界景気の悪化でピークアウトして
いるためである。実質輸出㈶は、08年8月を
ピークに減少傾向に転じ、08年11月は前月
比3.3%減と3か月連続でマイナスとなった
(図表3)。
こうした需要面での大幅な落込みに加え、
金融危機の深刻化が企業の投資行動に波及
している。金融機関の貸し渋りや資本市場
からの資金調達難などで企業の資金繰りに
悪影響が出ており、設備投資を抑制する動
きが広がっている。設備投資の先行指標であ
るコア資本財受注をみると、08年11月に前
月比1.7%増と4か月ぶりに増加したが、12月
は再び2.8%減と落ち込み、08年10~12月は
前期比9.4%減と現行基準で最大のマイナス
となった。Fed(連邦準備制度)は企業の資
金繰りの支援策として、CP(コマーシャル
ペーパー)の買取り制度を創設したが、金
融機関は貸出基準を一段と厳格化しており、
企業の資金繰りはなお厳しい状態が続いて
いる(図表4)。
(4 )金融危機の広がりと速さは90年代後半
の日本の金融危機を上回る
08年10~12月の経済指標は相次いで過去
最大の悪化を示すなど、住宅バブルの崩壊
をきっかけとした金融危機の拡大が景気後
退をより深刻化させている。これは、土地
バブルの崩壊から始まった資産デフレで、
(備考)1.シャドー部分は景気後退期。3か月移動平均2.米商務省資料より作成
図表2 米国の自動車販売台数の推移
(年)
(百万台:年率)
70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
19181716151413121110987

研 究 7
金融機関の破綻が相次いだ90年代後半の日
本の金融危機と同じ構図である。もっとも、
今回の金融危機は、サブプライムローンとい
う信用力の低い個人向け住宅ローンを組み込
んだ証券化商品を世界中の金融機関が保有し
ていた結果、同ローンの焦付きに伴う損失が
世界各国に広がり、グローバルな信用収縮
が世界同時不況に発展するなど規模が大き
かった。資産デフレと不良債権問題が国内
の金融機関に集中していた日本の金融危機
に比べると、世界不況で外需や海外の資本に
も依存できないといった点で、今回の金融危
機による米国経済への悪影響はより深刻と
いえる。
また、今回は証券化商品の市場価格の急
落という形で表面化した市場型であったた
め、危機の広がるスピードが極めて速かった
という特徴がある。日本の場合、97年11月
の三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券の破
綻を起点にすると、日本長期信用銀行など大
手行が破綻(98年10月)するまでに約1年、
大手行に本格的な資本注入が実施(99年3
月)されるまで約1年半を要した。大手生命
保険会社である千代田生命が更生特例法を
申請(00年10月)したのは約3年後にあたる
(図表5)。
一方、米国では08年3月のベアー・スター
ンズの実質破綻(JPモルガン銀行による救済
的な買収)を起点にしても、同年9月のリーマ
ン・ブラザーズ破綻、米保険最大手AIGの救
済、S&L最大手のワシントン・ミューチュア
ル破綻と続き、10月には金融安定化法が成
立(同月末から資本注入開始)、11月には米
銀大手シティの救済と約8か月の間に大手金
融機関の破綻と救済、公的資金の投入が集中
している。リーマン・ブラザーズの破綻を基
点とすれば、金融危機はほぼ2か月間に凝縮
されている。こうした金融危機の広がりの速
さが、歴史的な株価急落や実体経済の急激な
悪化に波及したと考えられる。
(備考)FRB資料などより作成
図表3 実質輸出と鉱工業生産
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
110
100
90
80
70
60
50
40
115
110
105
100
95
90
85
80
75
70
(10億ドル) (02年=100)
(年)
鉱工業生産指数(右目盛)
実質輸出(財)(左目盛)
(備考)1 .融資基準を厳しくした銀行の比率から、緩くした銀行の比率を差し引いた数値2.FRB資料より作成
図表4 米銀の貸出基準判断
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
100
80
60
40
20
0
-20
-40
(%)
(年)
厳格化
緩和化

8 信金中金月報 2009.3
2 .不動産バブルの崩壊と金融危機後の懸念は過剰債務問題
(1 )住宅ブーム過熱の背景はサブプライム
ローンと低金利
日米の金融危機は、広がりの大きさや速さ
といった点に違いがあるものの、資産バブル
の崩壊が大手金融機関の相次ぐ破綻をもたら
し、その影響による貸し渋りや借り手側のバ
ランスシート調整といった形で実体経済に負
の影響を及ぼす点には変わりはない。特に、
不動産バブルの崩壊後に残る過剰債務は容易
に解消できる問題ではなく、金融危機後の日
本経済は、いわゆる「3つの過剰」の調整に
よって04~05年頃まで下押し圧力の強い状況
が続いた。米国経済も、過剰債務の調整過程
で経済活動が制約され、景気下押し圧力が長
期間にわたって続く可能性が指摘されている。
そこで、米国の家計と企業の債務の状態
を、金融危機に見舞われた当時の日本と比較
しながら確認しておきたい。
一般に、不動産の取得には資金の大部分
を借入金で調達する必要があり、高いレバ
レッジをかけた投資ということになる。こ
のため、不動産バブルが発生する過程では、
投資主体の債務残高が急拡大していく。日
図表5 日米の金融危機における主な金融機関の破綻と対応策日本 米国
92年 地価が下落に転じる。 ↓不良債権が増加
06年 住宅価格が下落に転じる。12月 サブプライム中心の中堅住宅ローン会社「オ
ウンイット・モーゲージ・ソリューション」が新規の融資業務を停止
94年 12月 東京協和、安全信組が破綻 07年 2月 バーナンキFBR議長、「サブプライム住宅ローン市場の健全性に懸念がある」と発言
95年 8月 兵庫銀行、木津信組が破綻 6月 米証券大手ベアー・スターンズ傘下のヘッジファンドがサブプライムに絡む運用に失敗
96年 6月 住専処理に公的資金を投入(住専法制定) 8月 BNPパリバ、傘下の3つのファンドを凍結ゴールドマン・サックス傘下のヘッジファンド2社が多額の損失を計上97年 11月 三洋証券、北海道拓殖銀行、山一証券が破綻
98年 2月 預金保護と資本注入に公的資金枠(30兆円) 08年 3月 ベアー・スターンズ実質破綻(JPモルガンが買収)
3月 21行に1.8兆円の資本注入(金融安定化法) 7月 連邦住宅抵当公社(ファニーメイ)、連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)の経営危機
10月 公的資金枠を60兆円に増額(早期健全化法) 9月 米住宅公社2社を政府管理下に置くと発表米証券大手リーマン・ブラザーズ破綻バンク・オブ・アメリカがメリルリンチを救済合併米保険最大手AIGの救済策を発表S&L最大手、ワシントン・ミューチュアルが破綻
10月 長銀が破綻(特別公的管理)12月 日債銀が破綻(特別公的管理)
99年 3月 15行に7.5兆円の資本注入(早期健全化法)
8月 一勧・富士・興銀が統合を発表
10月 住友・さくらが合併を発表 10月 金融安定化法(最大7,000億ドルの公的資金による不良債権の買取など)成立金融安定化法に基づく7,000億ドルの公的資金のうち最大2,500億ドルの資本注入を決定
00年 10月 千代田生命が更生特例法を申請
01年 3月 日銀、量的緩和政策を導入 11月 公的資金による米銀大手シティの救済策を発表FRB、住宅ローン市場、消費者ローン市場への資金供給に最大8,000億ドルの資金枠を設定02年 9月 日銀、銀行保有株の買取を決定
03年 5月 繰延べ税金資産の査定厳格化りそなHD実質国有化
12月 FFレートの誘導目標を0~0.25%へ引き下げ(事実上のゼロ金利政策)
(備考 )新聞報道などより作成

研 究 9
本で発生した土地バブルは、「地価は必ず上
がる」といわれた土地神話を背景に、金融
機関が土地を担保にして過剰な融資を実行し
たことが背景にある。家計も企業も借入れを
増やしていったが、とりわけ、企業の資金調
達意欲が高く、調達した資金は過剰な設備投
資や投機的な不動産取得に投じられた。し
かし、その後の地価下落で、レバレッジを
高めた不動産投資は行き詰まり、企業には
過剰債務、金融機関には不良債権が積み上
がった。
一方、米国の不動産バブルは、主に家計の
住宅取得熱の高まりによって発生した。例え
ば、米国の持家比率(全世帯数に占める持家
世帯の比率)をみると、80年代から90年代
半ば頃まで64%前後で安定していたが、その
後は住宅取得ブームを映した形で大きく上昇
した(図表6)。90年代後半は米国経済の生
産性上昇とともに実質賃金が上昇するなど、
米国経済の繁栄を享受する形で持家比率が上
昇したとの説明もできるが、2000年代の上
昇は住宅取得ブームの過熱によるものであっ
たと考えられる。経済的に住宅取得が困難な
低所得層までもが住宅購入に踏み切ったとい
うことである。
こうした住宅取得ブームの広がりを可能に
したのが、サブプライムローンといわれる低
所得者向けの住宅融資である。サブプライム
ローンは、他の優良な住宅ローンなどととも
にまとめて証券化されることで、リスクが分
散される仕組みであったうえ、住宅価格の持
続的な上昇によってデフォルトが発生しても
債権の回収が容易に行えたため、住宅ローン
会社による積極的な融資が実行された。IT
ブーム後の景気後退が終わった01年11月
(景気の底)以降も金融緩和が続き、住宅
ローン金利が低下傾向で推移したことも住宅
ブームを後押しした(図表7)。また、一部
の高収入世帯では、値上がりを目的とした投
機的な住宅取得も行われた。
(備考)米商務省資料より作成
図表6 米国家計の持家比率
82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06
70
69
68
67
66
65
64
63
62
(%)
(年)
(備考)1 .シャドー部分は景気後退期2.抵当貸付銀行協会(MBA)資料より作成
図表7 住宅ローン金利(30年固定)
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 0807
9
8
7
6
5
4
(%)
(年)

10 信金中金月報 2009.3
(2 )米国家計の過剰債務は日本のバブル時
を上回る
住宅取得の拡大に伴って、住宅ローン残高
も増大していった。住宅ローン残高の前年比
増加率をみると、90年代は可処分所得とほ
ぼ同じペースで推移していたが、00年代に
入ると、可処分所得の伸びを大幅に上回るよ
うになった。01年9月末から06年12月までは
前年比2ケタの増加が続き、07年3月末の残
高は10兆ドルを上回った(図表8)。
消費者ローンなどを含めた家計債務残高の
可処分所得倍率は、2000年から07年末まで
の8年間、急激な上昇を示した(図表9)。80
年代後半に土地バブルに沸いた日本でも、家
計債務残高の可処分所得比は上昇したが、急
激な上昇は86年から90年央までの約4年半と
米国に比べて短かった。この間の上昇幅は、
日本の0.35年(85年末~90年9月末)に対し、
米国は0.40年(99年末~07年末)と大きい。
また、債務残高の可処分所得倍率のピーク
は、米国が1.34年(07年末)と日本の1.19年
(90年9月末)を大きく上回る水準へ上昇し
た。足元では借入れの抑制で1.30年(08年9
月末)と上昇が止まっているが、過去の水準
やバブル時の日本との比較からみて、米国の
家計は明らかに過剰債務の状態にある。
(3)米国企業の債務残高は健全な水準を維持
住宅ブームの過熱を背景に、米国の家計は
巨額な過剰債務を抱えてしまったが、企業部
門の債務はなお健全な水準にある。日本の土
地バブルは、不動産開発会社、建設会社、住
宅メーカー、小売業や商社、さらに一部の
メーカーなど多くの企業がレバレッジを高
め、土地開発や不動産への投資を増やしたこ
とに原因があり、その後のバブル崩壊で企業
部門は過剰債務問題に苦しめられた。
日本企業は80年代後半から90年代前半にか
けて借入れを増やした。80年代後半こそ収益
の急拡大で、有利子負債キャッシュフロー倍
率に大きな変化はみられなかったが、収益の
伸びが鈍化した90年代前半には大きく上昇
(備考)FRB資料などより作成
図表8 住宅ローン残高と可処分所得の前年比
92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 05 06 07 0804
16
14
12
10
8
6
4
2
0
住宅ローン残高の前年比
可処分所得の前年比
(%)
(年)
(備考)1 .家計債務は消費者ローンなども加えた債務合計2.FRB、日銀資料などより作成
図表9 日米の家計債務残高の可処分所得倍率
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 06 0804
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
(年)
日本 米国
(年)

研 究 11
し、有利子負債残高は93年9月末にキャッ
シュフローの12.5年分に達した(図表10)。
90年代半ば頃から企業は過剰債務の調整に取
り組んだが、本格的な調整は、金融危機に
よって金融機関による抜本的な不良債権処理
が避けられなくなった90年代後半以降へズレ
込んだ。企業は設備投資の抑制と人員削減な
どのリストラ、保有資産の大規模売却などで
返済資金を捻出する必要に迫られた。企業の
過剰債務の調整は経済全体を大きく下押し
し、日本経済は厳しいデフレに見舞われた。
一方、米国企業の有利子負債キャッシュフ
ロー倍率は、07年にやや上昇したものの、
その水準はピークとなった01年末の5.6年を
上回るには至らなかった。住宅バブルが盛り
上がった00年代前半はむしろ低下傾向で推
移した。直近の08年9月末でも4.6年と過去の
平均的なレベルにある。
有利子負債の金額も適正な水準にあると考
えられる。米国企業のバランスシートをみる
と、08年9月末の有利子負債残高は7.0兆ドル
と過去最高ではあるが、企業規模の拡大に伴
う適切な増加である。簿価ベースの負債比率
(資産価格上昇の影響を除去した簿価ベース
の純資産に対する債務残高の比率)は、
2000年頃から70%を下回る水準で安定してい
る(図表11)。事業の拡大の範囲内で借入金
を積み増してきただけということである。バ
ブル期の日本企業のように、資産価格の上昇
分を担保にしてレバレッジを高めるような動
きはみられなかった。
貯蓄・投資バランスからみても、米国の企
業部門が健全な財務戦略を続けてきた姿がみ
てとれる(図表12)。米国企業は、90年代後
半からITブームが過熱した2000年頃にかけ
て、外部から資金を調達し、キャッシュフ
ローを上回る高水準の設備投資を実施した。
しかし、ITバブル後の景気後退を経て、企
(備考)1.有利子負債キャッシュフロー倍率= 有利子負債残高÷キャッシュフロー(年率)
2 .キャッシュフローは、税引き後利益(米国)、経常利益×0.5(日本)に減価償却費を加えた金額3.FRB、財務省『法人企業統計季報』などより作成
図表10 日米企業の有利子負債キャッシュフロー倍率
86 88 90 92 94 96 98 00 02 06 0804
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
(年)
米国
日本
(年)
(備考)1 .企業部門は非農業・非金融法人2.FRB資料より作成
図表11 米国企業部門の有利子負債残高と負債比率
88 90 92 94 96 98 00 02 06 0804
16
14
12
10
8
6
4
2
0
100
90
80
70
60
(兆ドル) (%)負債比率(簿価ベース)
①÷②(右目盛)
純資産(時価)(左目盛)
①有利子負債(左目盛)
②純資産(簿価)(左目盛)
(年)

12 信金中金月報 2009.3
業は財務体質の健全化に着手した。02年以
降の景気回復局面では企業収益は大幅に回復
したが、企業の投資はキャッシュフローの範
囲内に抑制された。企業部門の貯蓄・投資バ
ランスは、02年以降、大幅な貯蓄超過状態
が続いた。91~93年にも貯蓄超過となって
いるが、この時期は景気の後退局面から回復
初期にあたる。本格的な景気回復局面で企業
部門が大幅な貯蓄超過となったのは初めての
ことであり、この間、企業はキャッシュフ
ローを手元資金の積増しや借入金の返済など
に振り向け、財務体質の強化を進めたと考え
られる。企業部門の財務の健全性は、今後予
想される家計部門の過剰債務の調整による景
気下押し圧力を和らげる要因であり、日本の
バブル崩壊後と大きく異なる点でもある。
(4 )人口動態など経済基盤は当時の日本に
比べて優位
日米の金融危機は、不動産バブルの崩壊を
きっかけに大手金融機関の破綻が相次ぎ、過
剰債務問題が当面の景気を下押しするといっ
図表13 金融危機前後における経済・金融情勢の日米比較 (単位:%)日本 米国96年度 97年度 98年度 06年 07年 08年
実質成長率前年度比 2.9 △0.0 △1.5 前年比 2.8 2.0 1.3最終四半期の前年比 3.9 △2.6 △0.3 最終四半期の前年比 2.4 2.3 △0.2
名目成長率 前年度比 2.4 1.0 △1.9 前年比 6.1 4.8 3.4GDPデフレーター 前年度比 △0.5 (注)11.0 △0.5 前年比 3.2 2.7 2.2消費者物価上昇率 食料・エネルギーを除く 0.5 (注)12.0 0.2 食料・エネルギーを除く 2.5 2.3 2.3
地価(ピーク比)(注)2公示地価(91年比) △23.2 △24.8 △26.2 FHFA住宅価格指数(年末ピーク比)
(注)3上昇 △2.5 △10.5
住宅価格(ピーク比) 首都圏マンション坪単価(90年比) △34.2 △32.8 △36.4 ケースシラー住宅価格(注)4(年末ピーク比) △1.7 △11.3 △26.6
株価変動率日経平均株価(前年度末比) △15.9 △8.2 △4.2 NYダウ平均株価
(前年末比) 16.3 6.4 △33.8(注)5(ピーク比) △53.7 △57.5 △59.3 (注)5(ピーク比) △ △6.4 △38.0
家計の金融資産に占める株式・投資の比率 年度末 8.5 8.9 9.2 (注)6年末 48.0 47.6 45.6
財政収支のGDP比 (注)7暦年(OECD) △6.9 △5.8 △7.2 (注)7暦年(OECD) △3.7 △4.3 △6.7政府債務残高のGDP比 暦年(OECD) 94.0 100.5 113.2 暦年(OECD) 61.7 62.9 73.2人口増加率 10月 0.2 0.2 0.3 7月 1.0 1.0 0.9(注)8生産年齢人口増加率 10月 △0.1 △0.1 △0.1 7月 1.2 1.0 0.8
(注)1.97年度は消費税率引上げ(3→5%)の影響を含む。2.日本の地価は公示地価(全国住宅地)の91年からの累積変化率3.FHFAのピークは07年4月、08年末は11月の指数で算出4.ケースシラー住宅価格(10都市)のピークは06年6月、08年末は11月の指数で算出5.日経平均のピークは89年12月末、NYダウのピークは07年10月末とした。6.08年の米国の比率は9月末7.財政収支は社会保障基金を除く一般政府8.生産年齢人口は15~64歳人口
(備考)米商務省など日米の各種統計より作成
(備考)1 .貯蓄は固定資本減耗を含めたSNAベースの総貯蓄2.FRB資料などより作成
図表12 企業部門の貯蓄・投資のGDP比
80 82 84 86 88 90 92 94 98 00 02 04 06 0896
15
14
13
12
11
10
9
(%)
(年)
貯蓄
投資投資超過(資金不足)
貯蓄超過(資金余剰)

研 究 13
た点で類似性がみられるが、前述したように
家計と企業に分けてみると過剰債務問題の状
況はやや異なる。また、そのほかにも異なる
点がある。
日本は金融危機後に厳しいデフレに見舞わ
れた。デフレは過剰債務を抱えた企業の実質
債務負担を増加させ、設備投資の抑制や資産
売却によってデフレ圧力が一段と強まる悪循
環に陥った。いわゆるデフレスパイラルであ
る。もっとも、日本経済は90年前半のバブ
ル崩壊以降の需要低迷で、金融危機に見舞わ
れる前からデフレの危機にあった。国内需給
の影響を反映する食料・エネルギーを除く消
費者物価の前年比上昇率は、94年度以降1%
を下回る小幅な上昇となり、96年度は0.5%、
97年度は消費税率が2%引き上げられた影響
で2.0%となったが、98年度には0.2%まで鈍
化した。
一方、米国の消費者物価(食料・エネルギー
を除く)は、03年(1.5%)と04年(1.8%)に
1%台の上昇へ鈍化したが、05年以降は再び
2%台の上昇を続けた。足元では、厳しい景
気の後退で、自動車などの耐久財を中心に値
下げ圧力が強まっているが、08年12月は前
年比1.8%の上昇となった。今後、一段とデ
フレ圧力が強まる可能性もあるが、当時の日
本ほど危機的な状況に追い込まれているわけ
ではない。
金融危機に対して、米国政府は財政面から
の景気対策を打ち出しており、財政収支は大
きく悪化している。この点は当時の日本と同
じ状況といえる。OECDによると、米国の財
政収支(社会保障基金を除く一般政府)の
GDP比は、08年時点で6.9%の赤字と当時の
日本並みに悪化している。ただ、債務残高の
GDP比は、当時の日本が100%超だったのに
対し、米国は08年で73.2%にとどまってい
る。日本とは異なり、経常赤字国である米国
は国内の貯蓄で財政赤字をファイナンスでき
ないといったマイナス面があるが、一方で基
軸通貨国といった強みもある。米国の財政状
況は、当時の日本に比べるとやや余裕がある
と考えられる。
経済活動のベースである人口動態も日米で
大きく異なる。90年代後半の日本は、小幅
ながら人口の増加が続いていたものの、経済
活動の中心を担う生産年齢人口(15~64歳
人口)は、95年をピークに減少に転じてい
た。生産年齢人口の減少は、耐久財や住宅な
どの需要減となり、構造調整に伴う日本経済
をより下押しした可能性がある。一方、米国
は総人口、生産年齢人口とも1%程度の増加
を続けている。特に、生産年齢人口の増加
は、労働供給と需要を着実に拡大させる要因
であり、構造調整が続く米国経済を下支えす
る重要な要素になると考えられる。
3 .家計部門の過剰債務問題は景気回復に向けた最大のハードル
(1)住宅価格の下落が続く
金融危機後の懸念材料は、家計の過剰債務
問題であると考えられるが、その問題が解消
に向かうためには、まず住宅価格の下落に歯
止めがかかる必要がある。住宅価格の値下が

14 信金中金月報 2009.3
りが続けば、家計部門のバランスシートが一
段と悪化するだけでなく、金融機関には追加
損失が発生し、その結果、信用収縮によるデ
フレ圧力がさらに強まる恐れもある。
代表的な住宅価格指数であるS&Pケース
シラー住宅価格指数(10都市)は、06年6月
をピークに下落に転じた。04年半ばに前年
比で20%を超える上昇率を記録した後、
徐々に上昇ペースが鈍化し、07年1月には前
年比マイナスとなった(図表14)。直近の08
年11月には19.1%の下落とマイナス幅の拡大
傾向が続いている。ニューヨークやロサン
ゼルスといった住宅価格が高騰・急落した
地域の影響が大きいとはいえ、他の住宅価
格指数もほぼ同様な動きを示している。S&
Pケースシラーに比べ対象地域が広いFHFA
(連邦住宅金融庁)住宅価格指数の前年比
は、07年10月にマイナスに転じ、08年11月
は8.7%の下落とマイナス幅の拡大が続いて
いる。
(2)住宅価格の底入れは09年後半と試算
住宅価格指数のピークから08年11月まで
の下落率(前掲図表13)は、S&Pケースシ
ラー(10都市)が26.6%、FHFA住宅指数は
10.5%と価格調整が進んでいるものの、な
お、適正水準を上回っていると考えられる。
そこで、米国全体の住宅価格を把握するうえ
で適当と考えられるFHFAの住宅価格指数に
ついて適正水準を求め、その水準へ調整が進
む時期を試算してみた。
住宅価格の上昇は、物価や賃金の動きに応
じた範囲であれば、適正と考えられる。実
際、90年代の住宅価格指数の上昇は、年収
(1人当たり雇用者所得)の上昇と同程度で
あった。新築住宅販売の中間価格も、90年代
は年収(1人当たり雇用者所得)の5倍前後で
安定しており、90年代の住宅価格は適正水準
にあったと考えられる。この状況を踏まえ、
持家比率(前掲図表6)も安定していた95年
を基準として、そこからの年収倍率が一定に
維持される水準、すなわち年収の伸びを住宅
価格の適正上昇率と仮定した。
この方法で算出した適正住宅価格に対する
実際の住宅価格のかい離率をみると、06年6
月には適正価格を29.5%上回る水準まで上昇し
た(図表15)。その後、07年4月をピークに住
宅価格が下落に転じたため、かい離率は縮小
傾向にあるが、08年11月時点の価格は適正値
を7.6%上回っている。ただ、適正価格までの
調整はすでに3分の2程度まで進捗している。
今後、過去1年半と同じペース(月平均0.6%の
下落)で住宅価格の下落が続けば、年収が横(備考)米連邦住宅金融庁(FHFA)資料などより作成
図表14 各種住宅価格の前年比
(年)
(%)
01 02 03 04 05 06 07 08
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
-20
S&P10都市FHFA新築住宅販売価格(中央値、3か月移動平均)

研 究 15
ばいで推移すると仮定した場合、09年8月には
適正価格まで調整が進む計算になる。現状の
価格レベルからさらに7%程度の下落幅は小さ
くないが、住宅価格の底入れが視野に入って
くれば、物件の流動性が高まるなど住宅取引
が持ち直す可能性があり、金融機関の不良債
権の拡大にも歯止めがかかると考えられる。
(3 )家計の過剰住宅ローン残高は可処分所
得の35%
住宅価格は適正水準に向けて調整が進んで
いるものの、家計の住宅ローン残高は高止ま
りしている。特に、ホーム・エクイティ・
ローン(注)1などの利用で住宅の時価上昇にあ
わせて債務を増やしてきた結果、99年末に
4.4兆ドルだった住宅ローン残高は、07年3月
末に10兆ドルを突破した。住宅市場の調整
に伴って住宅ローン残高は、08年4~6月か
らネット(借入れ-返済)でみて返済超に転
じているが、08年9月末時点でも10.57兆ドル
と高い水準にある。
ちなみに、所得や人口、持家率などから住
宅資産の適正水準を算出し、適正住宅資産に
見合うローン残高を住宅ローンの適正値とし
た場合、足元の住宅ローン残高は3.7兆ドル
の過剰と試算(注)2される(図表16)。過剰住
宅ローン残高は、足元の可処分所得の35.1%
に相当する額である。
もっとも、家計の過剰債務の圧縮は簡単には
進まない。住宅ローンは数十年かけて返済する
長期契約であり、住宅価格の下落に応じて過剰
債務を圧縮するわけではない。家計は、消費者
(注)1 .ホーム・エクイティ・ローンとは、不動産の時価から住宅ローンを差し引いた住宅の純資産(Home Equity)を担保とした借入れ。住宅価格が上昇すれば、ホーム・エクイティの担保価値が上がり、借入れ可能額は増える。住宅を担保としているため、消費者ローンに比べて金利が低く、調達した資金は主に耐久財や教育費などの消費支出に振り向けられた。08年9月末時点で、ホーム・エクイティ・ローン残高は1.1兆ドル、住宅ローン残高(10.6兆ドル)の約1割を占める。2 .95年を基準に人口増加率と持家比率の上昇に見合う実質住宅資産を算出する。ただし、持家比率は、上昇テンポが加速しているため、適正値の算出に当たっては、緩やかに上昇した90年代前半の上昇ペースを延長して算出した。次に、この方法で求めた適正実質住宅資産に、図表15で試算した適正住宅価格を乗じて適正住宅資産を算出する。最後に、住宅資産に対する住宅ローンの比率(安定していた90年代後半の平均)を乗じて、適正住宅ローン残高を試算した。
(備考)1.住宅価格の上昇率や年収倍率、持家比率が安定していた95年を100とした。2.95年を基準に年収倍率が一定となる水準を適正住宅価格とした。3.先行きは、住宅価格が過去1年半の下落ペース、適正住宅価格は横ばいと仮定した。4.米連邦住宅金融庁(FHFA)、商務省資料などより作成
図表15 住宅価格の推移と適正価格の試算
住宅価格指数
09年8月(適正水準)
適正住宅価格
(年)95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09
(95年=100)21020019018017016015014013012011010090
試算

16 信金中金月報 2009.3
ローンやホーム・エクイティ・ローンなどの新
規の借入れを抑制するとともに、長期の契約
に従って返済を続け、時間をかけて住宅ロー
ン残高の圧縮を進めていくことになろう。
なお、米国の住宅ローンはノンリコース
ローン(注)3であり、住宅価格に対して債務残
高が超過すれば借り手は債務不履行を選択
し、結果として家計全体の債務残高が減少す
ることも考えられる。住宅価格の下落が続け
ば、債務不履行の拡大によって債務残高の減
少が加速する可能性もある。
(4)住宅バブルの崩壊で逆資産効果が顕在化
ホーム・エクイティ・ローンなどによる資
金調達は、2000年代の個人消費を押し上げる
要因になった。同ローンの借入れ(ネット)
は、02年頃から増勢が加速し、04年後半には
年率で2,200億ドル、可処分所得の2.6%へ拡大
した(図表17)。その後も06年まで常時1,000
億ドル(年率)を上回る借入れが続いた。米
国の家計は住宅価格の上昇をホーム・エクイ
ティ・ローンという形で益出しすることで消
費支出を増やしていった。
実際、こうした資産効果による個人消費の
押上げ効果は小さくなかった。住宅価格に加
え、株式など金融資産を含めた値上がりによ
る実質個人消費への影響を推計(注)4すると、
04年には株価上昇で0.3%、住宅価格の上昇で
0.5%(資産効果合計で0.8%)、05年には株価上
昇で0.2%、住宅価格の上昇で0.7%(合計0.9%)
の押上げ効果があった。もっとも、08年(1~
9月)は一転して逆資産効果となり、実質個人
消費は、株価の下落で0.3%、住宅価格の下落
で0.4%押し下げられている(図表18)。
(注)3 .非遡及型融資。住宅ローンの場合、住宅資産に対して貸し付ける方法で、借り手はローンが返済できなくなっても、担保資産以外の返済義務は負わない。また、返済の範囲を担保資産に限定していることから、原則として保証人を必要としない。4 .資産効果は以下の推計式から算出した。Ln(個人消費)=-0.414+0.965Ln(可処分所得)+0.023Ln(家計の株式資産)+0.079Ln(住宅価格)推計期間=93.1Q~08.3Q。変数はすべて消費デフレーターで実質化。t値はすべて有意。決定係数0.998。DW比=1.629推計式の係数は、所得や資産が1%変化したときに、消費が何パーセント変化するかを示す。仮に、住宅価格が10%上昇すると、個人消費は0.79%押し上げられる。
(備考)1.試算の方法は脚注2のとおり。2.過剰債務の試算は住宅ローンに限定した。3.FRB資料などより試算
図表16 住宅ローン残高と過剰債務の試算
適正住宅資産に見合う住宅ローン残高
実際の住宅ローン残高過剰債務3.7兆ドル
(年)
(兆ドル)
93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2

研 究 17
(5 )過剰債務の調整圧力は強く、中期的な
個人消費の回復力は鈍い
前述したように、住宅価格は09年中に下
げ止まるとみられるうえ、株価もこの水準か
ら大きく下落する可能性は小さく、10年以降
はこうした逆資産効果による押下げ効果は一
巡すると予想される。しかし、過剰債務の調
整にはなお時間を要するとみられ、家計は、
債務残高圧縮のために、貯蓄率を高めていか
ざるを得ない。金融危機後の日本経済が、金
融機関の不良債権処理と借り手の過剰債務の
削減によって厳しい調整を強いられたよう
に、米国経済も過剰債務の調整圧力に苦しめ
られることになろう。
ただ、過剰債務問題の中心セクターは、日
本の場合が企業部門、米国の場合が家計部門
といった点で違いがある。過剰債務を削減し
ていくためには、企業の場合、大規模な資産
売却やリストラなどで過剰債務の削減を加速
するといった選択肢があるが、家計部門は、
従来に比べて消費を控えて返済原資を着実に
確保し、時間をかけて削減していく以外に方
法はない。このため、家計による過剰債務の
調整は、企業の調整に比べて経済全体に与え
る短期的なデフレ圧力は小さいとみられるが、
反面、調整期間が長期に及ぶ恐れがある。
過剰債務を削減していくためには、返済原
資としての貯蓄を増やす必要があり、その過
程において消費支出の抑制は避けられない。
そこで、過剰債務の圧縮が続いた場合の個人
消費の中期的な伸びを試算してみた(図表
19)。これは、住宅ローンを含めた債務残高
を直近のペースで削減していくための必要貯
蓄額を算出し、可処分所得の平均増加率の違
いによる個人消費の伸びを計算したものであ
る。今後5年間で必要となる貯蓄額は年平均
で5,800億ドル程度となり、可処分所得の伸
びを年平均2~6%と5つのケースとしたいず
れの場合も、貯蓄率を90年代平均(4.9%)
の水準前後まで引き上げることが必要とな
る。仮に、可処分所得の年平均増加率が直近
の08年を下回る4%(ケース③)となった場
(備考)FRB資料より作成
図表17 ホーム・エクイティ・ローンの前期比増減額(年率)
(年)
(億ドル)
95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500(備考)1 .推計方法は脚注4を参照
2.米商務省資料などより作成
図表18 実質個人消費の前年比と資産効果
(年)
(%)
94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
実質個人消費の前年比
資産効果を除いた実質個人消費の前年比

18 信金中金月報 2009.3
合、名目個人消費の平均増加率は3.2%、物
価上昇率を2%程度とした場合、実質個人消
費は1%台前半の低い伸びを余儀なくされる。
また、ケース③の場合、5年後の債務残高の
可処分所得比は1.02年と、可処分所得を上回
る状態が続くことになる。過剰債務の調整
は、長期にわたって家計部門の回復を阻害す
る恐れがある。
4 .過剰債務の調整長期化で、景気底入れ後も回復テンポは緩やか
(1)09年の住宅市場は底入れを探る展開
住宅着工件数(図表20)や販売件数が過
去最低水準まで落ち込むなど、住宅市場の悪
化に歯止めがかからない状態だが、足元の水
準(08年12月は年率55万件)からさらに大
きく落ち込むとも考えにくい。金融機関の貸
出スタンスの厳格化などで、住宅市場は引き
続き低調な動きが予想されるが、09年中に
は大底を確認すると予想される。
新築住宅の販売在庫は、06年7月に57.2万
件まで増加したが、08年12月には35.7万件ま
で減少し、過去の平均的な水準付近まで調整
が進んでいる(図表21)。新築住宅の販売不
振が続いているため、なお在庫の過剰感が残
るが、在庫調整は最終局面にある。また、金
図表19 債務残高の圧縮を前提とした今後5年間の個人消費の平均増加率可処分所得
(5年平均伸び)名目個人消費
(5年平均伸び率)平均貯蓄率(5年平均)
5年後の債務残高可処分所得比(年)
ケース① 2.0 1.0 5.2 1.13ケース② 3.0 2.1 5.0 1.07ケース③ 4.0 3.2 4.9 1.02ケース④ 5.0 4.3 4.7 0.98ケース⑤ 6.0 5.4 4.6 0.93参考(実績)08年 4.6 3.6 1.7 1.3090-99年 5.2 5.7 4.9 0.8900-04年 5.3 5.5 2.1 1.10
(備考 )1.08年の債務残高の可処分所得比は08年9月末2.米商務省資料などより信金中金総合研究所が試算
(備考)1 .シャドー部分は景気後退期2.米商務省資料より作成
図表20 住宅着工件数の推移
(年)
(万件)
76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
230
210
190
170
150
130
110
90
70
50
(備考)1 .シャドー部分は景気後退期2.米商務省資料より作成
図表21 新築住宅販売在庫の推移
(年)
(万件)
76 78
60
55
50
45
40
35
30
25
2080 82 84 86 88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08

研 究 19
融面では、Fedによる住宅ローン担保証券
(MBS)の買取り(注)5が09年1月から開始され
た。6月末までの半年間で最大5,000億ドルを
購入し、金融機関の資金繰りを支援すること
で、住宅ローン市場を下支えする狙いがあ
る。FedがMBS購入の方針を発表した11月下
旬以降、住宅ローン金利は低下傾向にあり、
住宅ローンの申請件数は増加に転じている。
住宅価格は依然として下落が続いているが、
前述したとおり、09年後半には下落に歯止
めがかかる可能性がある。住宅部門は、着工
ベースで09年半ばまでに下げ止まるとみら
れる。もっとも、進捗ベースで計上される
GDPベースの住宅投資は09年中も前期比
ベースでマイナスが続き、プラスに転じるの
は10年にズレ込むと予想される。
(2 )健全なバランスシートを武器に企業部
門が回復のけん引役に
個人消費と並ぶ民需の柱である設備投資も
減少が続く公算が大きい。企業収益の落込み
が続いているうえ、資金面では、融資基準の
厳格化が設備投資の下押し要因になっている
(図表22)。ただ、事実上の量的金融緩和政
策や公的資金の資本注入に加え、政府が金融
機関の不良債権を買い取る専門銀行(バッド
バンク)の設立の検討に入るなど、金融安定
化策を次々に打ち出している。設備投資の押
下げ要因の一つである金融システムの機能不
全は、徐々に緩和に向かうとみられる。
第2章で指摘したように、企業部門は住宅
バブルの発生・崩壊の過程でレバレッジを高
めず、しかも、投資をキャッシュフローの範囲
内に抑制して、健全なバランスシートを維持
してきた。実際、07年12月までの景気拡大期
中、設備投資の名目GDP比は緩やかな上昇に
とどまり、直近のピークとなった08年4~6月
は11.0%、直近実績の10~12月は10.6%と70
年代以降の平均水準(11.2%)を下回ってい
る(図表23)。足元では、景気の急速な悪化
で設備過剰感が強まっているが、通常の経済
活動を基準とすれば、過剰設備が懸念される
ような状況ではない。
景気対策の効果などから景気の悪化に歯止
めがかかれば、企業マインドは回復に向かう
と予想される。家計部門が過剰債務の調整で
回復が遅れるのとは対照的に、健全なバラン
スシートを武器に企業部門の回復が先行しよ
う。設備投資は次の回復局面のリード役とし
て期待される。
(3 )金融・財政による景気刺激策が景気の
落込みを緩和
米国の08年10~12月の実質成長率は、前
期比年率3.8%減(事前推定値)と大幅に落
ち込み、09年4~6月までマイナス成長が続
くとみられる。ただ、事実上の量的緩和政策
や政府による大規模な財政政策などの実施を
(注)5 .08年11月25日にFRBが発表した最大8,000億ドル規模の金融対策の概要は以下のとおり。①連邦住宅抵当公社(ファニーメイ)と連邦住宅貸付抵当公社(フレディマック)、連邦政府抵当金庫(ジニーメイ)が発行・保証した住宅ローン担保証券(MBS)を総額5,000億ドルを上限に買い入れる、②ファニーメイとフレディマック、米連邦住宅貸付銀行(FHLB)12行が発行する債券を総額1,000億ドルを上限に買い入れる、③新規消費者ローンと小規模企業向けローンを裏付けとしたトリプルA格付けの資産担保証券(ABS)の保有者に対し、最大2,000億ドルのノンリコース融資を実施する。

20 信金中金月報 2009.3
きっかけに、米景気は09年半ばに底入れす
る可能性がある。
08年12月15、16日に開催されたFOMC(連
邦公開市場委員会)で、FedはFFレートの誘
導目標を1.00%から0.00~0.25%に引き下げ
ることを決定した(図表24)。Fedが、FF
レートの誘導目標に幅を持たせたのは今回が
初めてとなる。同時に、FRBは公定歩合を
0.75%引き下げて0.50%にすることを全会一
致で承認したほか、準備預金に0.25%付利す
ることも決定した。また、前述したMBSの
買取りが09年1月から開始されたほか、長期
国債の買入れ検討を表明するなど、事実上の
量的緩和政策に踏み込んだ。今後、MBSの
購入拡大などで量的緩和政策が一段と推し進
められる可能性もある。
コア消費者物価の前年比上昇率(08年12月、
1.8%)を差し引いた実質FFレートは過去最大
のマイナス金利の状態にあり、今後、徐々に
利下げ効果が浸透しよう。
(備考)米商務省資料より作成
図表22 企業収益と設備投資の前年比
(年)
(%) (%)
88 90 92 94 96 98 00 02 04 06 08
30
20
10
0
-10
-20
-30
15
10
5
0
-5
-10
-15
設備投資(右目盛)
税引き前利益(左目盛)
(備考)1.シャドー部分は景気後退期2.米商務省資料より作成
図表23 設備投資の名目GDP比
(年)
(%)
70 75 80 85 90 95 00 05
14
13
12
11
10
9
70年以降の平均(11.2%)
(備考)FRB、米労働省資料より作成
図表24 FFレートの誘導目標と消費者物価の前年比
91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09(年)
(%)7
6
5
4
3
2
1
0
コア消費者物価(食品・エネルギーを除く) (0.0~0.25)
FFレートの誘導目標

研 究 21
景気対策による下支え効果も期待される。
09年1月15日に民主党は、大型減税や公共事
業を柱とする総額8,250億ドル(2年間)の景
気対策を発表した。2,750億ドルの減税(1人
当たり年500ドル、夫婦で1,000ドルの戻し
税)のほか、高速道路建設などインフラ整備
に900億ドル、燃費効率の高い自動車開発な
どに320億ドル、雇用対策として失業給付と
職業訓練の拡充に430億ドルを投じる。米政
府は、2年間の景気対策によって、対策を実
施しなかった場合に比べGDPを3.7%押し上
げ、365万人の雇用を増やすと試算してい
る。なお、この対策は、2月中旬までの成立
を目指して審議に入ったが、その過程で1兆
ドル程度まで膨らむ可能性もある。
(4 )今後5年間の年平均実質成長率は1.4%に
とどまると予測
もっとも、こうした金融・財政政策の速や
かな実行を前提にしても、家計の過剰債務調
整が下押し圧力となり、米国経済が従来の回
復力を取り戻すことは難しいと考えられる。
今後5年間の年平均実質成長率は1.4%と、IT
バブル崩壊後の不況期(注)6を挟んだ00~04年
度(2.4%)を1%程度下回る緩慢な回復にと
どまると予測した(図表25)。
09年前半も厳しい後退局面が続くと予想
される。住宅価格の一段の下落や景気の悪化
で、金融機関の損失がさらに拡大し、金融機
関の貸し渋りによる信用収縮が実体経済を下
押しする悪循環から脱しきれないと考えられ
る。4~6月頃には景気対策に盛り込まれた
戻し減税が始まることで、個人消費の悪化に
歯止めがかかるとみられるが、住宅投資や設
備投資の減少が続くためマイナス成長が続く
と予想される。年後半にはインフラ整備を中
心とした財政政策の効果が徐々に顕在化しよ
う。住宅価格の調整がほぼ一巡し、信用収縮
にも歯止めがかかると予想される。年後半に
は実質成長率が前期比年率でプラスに転じる
(注)6 .ITバブルの崩壊をきっかけに、米国経済は01年3月をピークに01年11月まで8か月の景気後退が続いた。
(備考)1.図表中の計数は5年平均成長率。ただし、直近の05~08年は4年間2.米商務省資料、予測は信金中金総合研究所
図表25 米実質成長率の推移と予測
(年)
(%)
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0
-1.0
-2.0
予測期間09~13年(1.4%)
90~94年(2.3%)
95~99年(3.9%)
00~04年(2.4%)
05~08年(2.2%)

22 信金中金月報 2009.3
と予測した。
10年は、住宅価格の調整一巡など資産デフ
レに歯止めがかかり、金融システムが正常化
に向けて動き出そう。景気対策の効果や住
宅、自動車の反動増もあって、四半期ベース
の実質成長率は、前期比年率で2%台に回復
すると予想される。もっとも、家計の過剰債
務の調整が続くため、通常の回復局面の初期
に比べて回復力は弱く、10年の実質成長率は
1.8%、年間成長率(10~12月の前年比)は
2.2%と緩やかな回復にとどまると予測した。
11年には景気対策の効果が一巡するもの
の、住宅投資と設備投資がそろってプラスに
転じるなど、景気は自律回復メカニズムを取
り戻すと予想される。11年から12年にかけ
て主要国のテレビ放送の全面デジタル化(米
国は09年の予定)が予定されていることに
加え12年にはロンドン五輪が控えており、
世界的なIT需要の盛り上がりが、IT産業に
強みを持つ米国産業にとって追い風になろ
う。11年以降も家計の過剰債務問題は尾を
引くが、民需主導の安定成長軌道に復帰する
と予測した。
米国経済は、安定した人口の増加や健全な
企業部門、迅速な金融・財政政策の実行など
によって、日本経済が金融危機後に見舞われ
た厳しいデフレには陥らないと想定してい
る。しかし、資産価格の予想以上の下落に
よって金融機関の不良債権問題がより深刻な
ものとなった場合には、本格的なデフレ経済
に突入するリスクシナリオが現実味を帯びて
くる。利下げ余地のなくなった状況でデフレ
に陥ると、実質金利の上昇によって過剰債務
問題はより深刻な危機を招き、景気対策の効
果が一時的な押上げに終わる可能性がある。
デフレ経済からの脱却は容易なことではな
く、長期にわたって経済活動が低迷する恐れ
がある。これまでの一連の金融危機対応や景
気対策によって財政赤字は急増しているが、
デフレの悪循環に陥る前に、米政府と中央銀
行は可能な政策を総動員して景気浮揚に取り
組むことが求められる。
図表26 今後5年間の米国GDP成長率の予測 (単位:%)
項 目 07年 08年 09年 10年 11年 12年 13年 09-13年実績 実績 <予測> <予測> <予測> <予測> <予測> 年平均
実質GDP 2.0 1.3 △1.7 1.8 2.0 2.6 2.5 1.4個人消費 2.8 0.3 △1.5 1.4 2.1 2.5 2.4 1.4住宅投資 △17.9 △20.8 △20.4 △1.9 4.4 5.6 6.9 △1.7設備投資 4.9 1.8 △9.0 △1.1 7.9 5.1 5.8 1.6在庫投資 △0.4 △0.2 0.1 0.2 0.1 0.2 0.0 -政府支出 2.1 2.9 3.5 4.6 1.5 0.1 1.0 2.1純 輸 出 0.6 1.4 0.4 0.0 0.2 △0.0 △0.3 -
輸 出 8.4 6.5 △5.2 3.5 6.1 6.8 4.9 3.1輸 入 2.2 △3.3 △6.6 2.7 3.9 5.8 6.0 2.3
名目GDP 4.8 3.4 △0.6 3.6 4.6 4.9 5.1 3.5
(備考 )米商務省資料、予測は信金中金総合研究所

研 究 23
(キーワード) 経営改善支援、取組先率、ランクアップ率、外部環境分析、事業改善提案、人材育成
(視 点) 2007年度から各地域金融機関が恒久的、自主的に実施することとなった地域密着型金融への取組みであるが、社会的な関心は低下したとの印象も受ける。いったい、地域密着型金融の取組みは本当に浸透し、恒久化後も着実に進んでいるのであろうか。また、それらの取組みは、計数面ばかりではなく内容面も進展しているのであろうか。本稿では、地域密着型金融にかかる経緯を確認した上で、地域密着型金融への取組状況に関し、その中核業務である経営改善支援とその他の主な個別の取組項目について、金融庁が公表した03~07年度のデータをもとに検討する。さらに、複数の信用金庫の地域密着型金融関連業務の担当者に聞取り調査を実施し、現場の考え方も参考にしつつ、恒久化後の取組みの意義や残された課題等を明らかにしたい。
(要 旨)● 経営改善支援業務について、信用金庫は03年度こそ他業態に比べて要注意先以下の全先に対するランクアップ率が低めであったが、近年は上位で推移している。
● ただし、経営改善支援業務の中身をみると、進んで要管理先、破綻懸念先に取り組む信用金庫もある一方、ランクアップを見込みやすいその他要注意先に注力する場合もみられる。
● 信用金庫が策定する経営改善計画の内容は様々である。取引先企業の同業他社への聞取り調査による外部環境分析や、事業コンサルティング会社と提携した事業改善提案を実施する信用金庫もある。一方、財務改善提案を中心に取り組むケース、内部・外部環境分析を取引先経営者への聞取り調査等をベースに行っているケースもある。
● 今後の景況悪化の局面では、経営改善支援の経験を積み、組織内にノウハウを蓄積して共有する体制を整えることが、信用金庫の将来のために必要である。経営改善支援業務の最大の課題は人材育成であり、そのためには経営者の本腰を入れた取組みが必須である。
● 創業・新事業支援融資など個別の取組項目についても、件数・金額が順調に伸びている施策もあるが、必ずしも実態が伴っていない場合や、課題が多く利用しにくい場合もあり、制度改善などの一層のインフラ整備が期待される。
研 究
恒久化後も取組み進む信用金庫の地域密着型金融-経営改善支援には事業への助言を、一部個別取組項目は制度の改善を-
信金中央金庫 総合研究所主任研究員
間下 聡

24 信金中金月報 2009.3
はじめに
07年4月5日に金融審議会WGの「地域密着
型金融の取組みについての評価と今後の対応
について」(以下「報告書」という。)が公表
され、今後の地域密着型金融への取組みは、
各地域金融機関が恒久的、自主的に実施する
ものとなった。これにより、これまでの時限
プログラム方式が抱える総花的取組みなどの
問題が改善され、各地域金融機関の取組み
が、地域のニーズに応じてより選択と集中の
効いた、ノウハウ的にも成熟したものとな
り、地に足をつけた日常業務として金融機関
に浸透することが期待された。
しかし、一方で、恒久化後、地域密着型金
融やリレーションシップバンキングに対する
社会的関心がやや低下したとの印象も否めな
い。そうした言葉のマスコミ等への露出度は
低下し、近年の不良債権比率の低下と相まっ
て、地域密着型金融の課題が解消したかのご
とき印象が社会に広がっている感がある。
いったい、地域密着型金融の取組みは本当
に金融機関に浸透し、恒久化後も着実に進ん
でいるのであろうか。また、それらの取組み
は、名目的な件数、金額面ばかりではなく、
内容的にも進展しているのであろうか。今
後、景気後退懸念が強まる中において、地域
密着型金融への取組みの真価が問われること
になろう。
そこで本稿ではまず、地域密着型金融の恒
久化の経緯を確認した上で、地域密着型金融
の取組状況について、その中心である経営改
善支援とその他の主な個別の取組項目を、金
融庁から公表された03~07年度のデータを
もとに検討することとしたい。さらに、複数
の信用金庫の地域密着型金融関連業務の担当
者に聞取り調査を行い、恒久化後の地域密着
型金融への取組みの意義や残された課題等を
明らかにすることとしたい。
1.地域密着型金融恒久化の経緯
「報告書」は、07年度以降の地域金融機関
による地域密着型金融への取組みを、緊急時
の時限的取組みから平時の恒久的取組みへ転
換する必要があるとした。
03年度に第1次アクションプログラム(注)1が
始まった頃は(図表1)、まだ金融再生プロ
グラムの発表から約半年が経過したばかりで
あり、日本の金融システムは脆弱な状態から
抜け出しておらず、地域密着型金融も緊急時
の2年単位の時限的取組みとされ、その内容
も多岐にわたるものであった。そのため、独
立したプログラムが作成され、その取組計画
と半期の進捗状況の当局への報告が義務付け
られていた。
しかし、大手行に続き、07年3月までに地
域金融機関の財務健全化も進み、景気も回復
基調が続く中で、平時における恒久的な取組
態勢への移行が図られることになった。06
年度まで行われてきた当局への半期ごとの行
政報告が、短期に成果のあがる取組みへの偏
りを助長してきたとの指摘もあり、恒久化後
(注)1 .図表1の中の「リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム」のことを指す。

研 究 25
は、時限のアクションプログラムは作成され
ず、監督指針に必要な事項が盛り込まれるこ
とになった。これまで以上に地域金融機関が
中長期的に取り組めるよう、各金融機関が自
主的に策定する経営計画の中に地域密着型金
融への取組みも含められ、その内容および進
捗状況の行政当局によるフォローアップも、
通常の監督の中の定期的なヒアリングを通じ
て行われることとなったのである。
金融機関の地域密着型金融への取組みは、
引き続き、主に地域の利用者の目を通じて
チェックされることとなった。各金融機関
は、具体的な取組みの重点事項を自主的に設
定し、それを具体的目標と共に経営の中期計
画等において明示し、年1回程度、各決算期
などにおいて、その達成状況や具体的事例を
公表し、併せて行政当局に報告することと
なった。行政当局からも実績が継続的に公表
されることになった。
地域密着型金融への取組みは、通常の業務
や監督活動の一環として継続されることと
なったのである。
2 .地域金融機関の経営改善支援への取組状況
(1)07年度までの5年間の業態別取組状況
それでは、まず、地域密着型金融の取組み
の中心的内容である経営改善支援への取組み
について、第1次アクションプログラムの始
まった03年度以降、恒久化後1年目の07年度
までの活動を年度ごとに業態別にみることと
する。
(備考)信金中金総合研究所作成
図表1 地域密着型金融の機能強化推進の経緯と恒久化後の方向
集中改善期間2002.10.30 2003.4.1 2005.4.1 2007.3.31
重点強化期間
主要行の不良債権早期処理を最優先課題に
5つの視点の1つが「地域経済への貢献」
金融再生プログラム
中小・地域金融機関
金融改革プログラム
金融審WGの議論の整理
金融審WGによる報告
新たな課題 平時恒久的枠組みに移行
新局面で転換
継続・発展
示唆
緊急時対応 平時対応へ
性急な不良債権処理を行わず、借り手企業の経営改善支援と事業再生により、地域経済への連鎖的悪影響を避けるとともに、金融機関の健全化を目指す。
不良債権問題は一段落。金融サービス立国を目指す新局面入り。金融行政は金融システムの安定重視から活力重視に!
<地域密着型金融の本質 3大項目>①ライフサイクルに応じた取引先企業の支援強化②事業価値を見極める融資をはじめ中小企業に適した資金供給手法の徹底
③地域の情報集積を活用した持続可能な地域経済への貢献
収益管理、ITの活用等は各金融機関の経営判断
経営管理、財務の健全性、ガバナンス、リスク管理、顧客への説明態勢、相談苦情処理機能等はすでに監督指針の規定が定着・充実しているため、通常の監督で対応
リレーションシップバンキングの機能強化に関するアクションプログラム
地域密着型金融の機能強化の推進に関するアクションプログラム
監督指針に3大項目を追加して盛込み
不良債権問題への対処についての考え方において相反している。

26 信金中金月報 2009.3
図表2は、要注意先以下経営改善支援取組
先率(注)2(以下「取組先率」という。)をX軸
に、取組先ランクアップ率(注)3(以下「ラン
クアップ率」という。)をY軸に取り、地域
金融機関の03~07年度までの5年間の歩みを
業態別にプロットしたものである。これによ
ると、信用金庫は、03年度は信用組合と並
んで取組先率が低く、ランクアップ率は地方
銀行と並び、第二地銀よりは高いものの信用
組合よりは大幅に低かった。04年度には両
比率とも大きく改善し、05年度には取組先
率、ランクアップ率とも4業態中最高となっ
た。その後、ランクアップ率は低下したもの
の、取組先率は最高水準を維持している。
地方銀行は、04年度に取組先率が突出し
て高くなり、ランクアップ率もほぼ最高水準
となったが、その後は07年度まで取組先率、
ランクアップ率とも毎年低下している。
第二地銀は、04年度には取組先率、ラン
クアップ率とも向上し、その後も06年度ま
で取組先率は上昇したものの、ランクアップ
率は低下を続けた。さらに、恒久化1年目の
07年度は、取組先率、ランクアップ率とも
大きく低下した。
信用組合は、03年度はランクアップ率が
突出して高かったが、その後は急速に低下
し、取組先率のピークも他業態ほどには高ま
らなかった。
取組先率は、自主的に設定できるため、そ
の高さが取組意欲を反映しているという見方
もできる。ただ、経営改善支援の取組み内容
について特に定義はないため、取組先率が高
水準である場合、量が優先され内容が深いも
のとならない恐れがある。一方、取組先をラ
ンクアップさせやすい先に絞ることでランク
アップ率を高めることも可能であり、一概に
(注)2 .要注意先以下経営改善支援取組先率=要注意先以下経営改善支援取組先数/要注意先以下全先数3 .取組先ランクアップ率=取組先ランクアップ先数/要注意先以下経営改善支援取組先数
(備考)1.要注意先以下全先数=α、要注意先以下の経営改善支援取組先数=β、取組先ランクアップ先数=γとすると、要注意先以下経営改善支援取組先率=β/α取組先ランクアップ先率=γ/β
2.03、07の数字は年度3.金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表2 地域金融機関の業態別の要注意先以下経営改善支援取組先率と取組先ランクアップ率
24
22
20
18
16
14
12
10
(%)
5 6 7 8 9
24
22
20
18
16
14
12
10
(%)
(%) 5 6 7 8 9(%)
地方銀行第二地銀
信用金庫
取組先ランクアップ率
要注意先以下経営改善支援取組先率 要注意先以下経営改善支援取組先率
取組先ランクアップ率
信用組合
03
0303
03
070707
07

研 究 27
評価できないところがある。例えば、要注意
先以下のうち、一般的にランクアップの難し
いとされる破綻懸念先や要管理先よりも、
もっぱらその他要注意先に取り組むといった
形で表れる場合もあるようだ。
なお、今回の取組先率には、正常先に対す
る取組みを含んでいない。これは、正常先の
場合、ランクダウンを防いでもランクアップ
の実績には表れず、また、ランクダウン防止
の効果も定量的に測り難いからである。
結局、取組先率×ランクアップ率で求めら
れる、要注意先以下全先数に対する取組先ラ
ンクアップ率でみることが、経営改善支援の
取組みの度合いをより的確に捉るものと考え
る。そこで図表3では、07年度までの5年間
の当該比率の業態別の推移をみてみた。信用
金庫は、03年度は4業態中最低であったが、
04・05年度と2年続けて改善し、05年度以降
はおおむね他業態より高い水準で推移して
いる。
地方銀行は、04年度に突出して高水準を
示した後は07年度まで一直線に急低下し、4
業態中最低となった。
第二地銀も、03年度に低位でスタートし
たのちは改善し、信用金庫と似たような展開
となった。
信用組合は03年度に最上位でスタートした
が、05年度以降は3番手での推移となった。
いずれにしても、05年度以降、4業態とも
低下傾向にあり、恒久化後(07年度)も同様
である。その背景には、第1次アクションプ
ログラム開始前(02年度)に高水準にあった
不良債権比率が、4業態ともレベルの相違は
あるものの05年度まで急速に低下したこと
があろう(図表4)。不良債権比率の低下と
ともに、件数面での取組み意欲が低下したと
見られる。とりわけ、不良債権比率の絶対水
準が低下した地方銀行にそれが鮮明に表れた
のかもしれない。
データでみる限り、信用金庫の場合、03
年度は初動ないしは準備段階として取組みの
効果(取組先ランクアップ率)は低めであっ
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表3 地域金融機関の業態別の要注意先以下全先数に対する取組先ランクアップ率
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
(%)
03 04 05 06 07 (年度)
地方銀行
信用金庫
第二地銀
信用組合
(備考)1.データは金融再生法開示債権ベース2.金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表4 業態別不良債権比率の推移
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
(%)
07060504030201009998 (年度)
地方銀行信用金庫
第二地銀
信用組合

28 信金中金月報 2009.3
たものの、体制が整うに連れて業務遂行も円
滑となり、他業態を上回る効果が表れ始めた
といえよう。
(2 )経営改善支援への取組みにおける今後
の課題
これまで、データ面から経営改善支援の取
組状況をみてきたが、データだけでは取組み
の質の面を必ずしも完璧に補足しているとは
言えず、それだけに頼って評価を下すことは
なかなか難しい。そこで、先にみた要注意先
以下全先数に対する取組先ランクアップ率
(=取組先率×ランクアップ率)の07年度実
績が業界の中でも高水準に位置する首都圏の
複数の信用金庫(注)4に対して聞取り調査を実
施し、経営改善支援への取組みの方法、体制
の違い等を概観したうえで、今後の課題等に
ついて考えてみたい。
イ.取組対象
(イ )その他要注意先に重点的に取り組む
ケース
聞取り先信用金庫のうち、要注意先以下
全先数に対する取組先ランクアップ率が最
も高かった金庫は、対象先の範囲を広く設
定し、取組先率が全国でも高水準に位置し
ている。これは、事前に対象先を絞りすぎ
ると、ランクアップ先の絶対数も少なく
なってしまうと考えたからである。当該金
庫はランクアップ率も高いが、その内訳は
その他要注意先の正常先へのランクアップ
数が多いという。この場合の営業店評価上
の配点は、要管理先や破綻懸念先のランク
アップの場合の半分としているが、営業店
で半期のランクアップ目標と取組先を決め
て取り組んでいるためもあってか、ランク
アップの期待が高いその他要注意先への取
組みが多くなる傾向がある。
(ロ)要管理先・破綻懸念先を重視するケース
一方、支援対象先の選定基準を「経営者
が意欲的であること」のみとし、債権金
額、債務者区分、業種等に基準を設けてい
ない信用金庫もある。当該金庫は、1先で
も多くの取引先の支援を目指しており、営
業店評価1,000点満点の内、計画書作成1件
当たり10点(最大80点)とし、ランク
アップを加味すると評価上の上限は200点
となる。
また、別の信用金庫も貸倒引当金戻入益
を確保するため、要管理先や破綻懸念先の
ランクアップに取り組むべきとしている。
当該金庫は、取組先数の目標を設定すると
計画書の質が低下する、また、営業店がラ
ンクアップが容易な先しか取り組まなくな
るなどの理由で、数値目標を課していない。
ロ.営業店と本部専担部署との役割分担
(イ)本部専担部署主導のケース
ある信用金庫では、取引先に零細企業が
(注)4 .要注意先以下全先数に対する取組先ランクアップ率(=取組先率×ランクアップ率、全国平均は0.9%)が2%超(業界上位50位以内)の信用金庫のうちの3金庫と1%台(ほぼ業界上位100位以内)の信用金庫のうちの1金庫の計4金庫

研 究 29
多いので営業店では計画書を作成せず、本
部の専担チームが重点先を選定し計画書を
作成している。チームは専担者8名、兼任
者2名の大所帯であるが、大半が支店長経
験者であり、中小企業診断士も2名配され
ている。営業店が日常多忙なことから、計
画書作成先に対する3か月に1度の進捗管
理も本部担当者が行っている。
(ロ)営業店主導のケース
別の信用金庫は、取組みの当初より営業
店主導で経営改善支援業務を実施し、本部
はそのサポートに徹しているという。この
金庫の場合、90年代後半に定期積金の集
金を廃止した替わりに、顧客との関係維
持・強化のために当該業務を開始したとい
う経緯がある。本部担当者は、週の半分以
上、営業店を訪問してアドバイスを行い、
特に重点先(顧客)については営業店担当
者に同行訪問するなど積極的に関与してい
る。また、毎月、営業店が記入するフォ
ローカードに対しフィードバックを行って
いる。当該金庫は、全職員が経営改善支援
業務に関するスキル・ノウハウを身につけ
るべきと考えている。
(ハ )重点先等は本部、他は営業店で役割分
担するケース
全職員が当該業務をできるようになるこ
とを理想とする他の信用金庫では、大口分
類先や期待損失額(EL)の値が大きい重
点先を本部が担当し、それ以外の先は営業
店が担当して計画書を作成している。当該
金庫は08年度に入り、支援体制の確立、
計画を上回る取組実績、多額の貸倒引当金
戻入益の発生などを理由に、専担者を6名
から4名に減員した。しかし、営業店でも
計画策定の体制は整ったが、計画の評価や
進捗のフォローアップ体制の構築は今後の
課題であると考えていたため、最近の景況
悪化から、再び本部の担当者を増員する必
要性を感じている。
もう1つの信用金庫でも、基本的に営業
店が当該業務に取り組むが、要管理先以下
の取組案件については審査部の専担者2名
が営業店を介さずに直接支援している。し
かし、この場合、ノウハウの蓄積が進むの
はもっぱら専担者の2名であるという。
ハ.計画書の内容
(イ )ヒアリングを中心に主にコスト削減策
を提案しているケース
ある信用金庫では、本部専担者が企業経
営者と金庫営業店にヒアリングを実施して
計画書を作成している。企業の外部環境調
査は簡単には行い難いため、売上改善策等
には踏み込まず、ヒアリング調査をベース
に主にコスト削減策を提案している。売上
改善策を提案した場合、企業が提案内容に
従ったものの失敗した場合の責任問題、提
案内容の実施を理由とした融資申込みへの
対処の問題が発生するかもしれないという
懸念があることも、理由であるという。ま
た、大方の企業においてB/S目標の作成

30 信金中金月報 2009.3
が難しく、当金庫側の改善サポートも難し
いことから、P/Lのみの数値計画として
いる。
(ロ)環境調査を簡略的に実施しているケース
他の信用金庫では、環境分析、数値分
析、数値計画を盛り込んだ計画書を作成し
ている。ただし、内部環境調査は経営者へ
のヒアリングに基き、外部環境調査は新聞
等の報道や貸出審査辞典等の情報収集によ
ることとし、手間のかかる同業他社への調
査は行っていない。
(ハ )外部環境の聞取り調査や外部の事業コン
サルティング会社との連携を図るケース
また、別の信用金庫では、計画書策定に
あたって、財務分析、SWOT(注)5による現
状分析と課題抽出、改善計画書の骨子、予
想財務諸表を作成している。同金庫は、外
部環境についても同業他社へのヒアリング
調査等を実施し、年商100億円以上の先向
けに経営改善計画策定支援ソフトも導入し
ている。金融機関が顧客の事業分析を行う
ことは容易ではないが、SWOT分析を行
えば何らかの方向性などを見出すことも可
能であり、そのような認識の下、当金庫の
専担者は、外部環境が厳しい先に対しては
業種転換やアウトソーシングの提案も行う
必要があると考えている。当金庫は取引先
企業の問題解決を支援するため、企業から
悩みや問題点を聞きだし、必要に応じて外
部の事業コンサルティング会社と連携し
て、具体的な提案を行っている。金庫とし
ては、顧客が喜ぶレベルの提案ができてい
ると評価している。
ニ.経営改善支援業務への考え方
(イ )取引先や地域社会とのリレーション強
化のツール
信用金庫にとって、顧客への融資もさる
ことながら、取引先の経営状況を改善する
ことも、地域や顧客から求められる重要な
役割であろう。信用金庫は、経営改善支援
業務で相応の実績を上げてきており、今後
とも継続して取り組むべきものと考える。
確かに、金融機関にとって、顧客の業種
を理解することは容易ではないが、顧客が
何でどのように儲けているのかを知り、顧
客事業の把握を進めることで、事業の実態
に即した効果的な融資が可能になる。自分
たちで計画書を作ることができてはじめて
「顧客の事業を理解した」と言えるのではな
いだろうか。経営改善支援業務は、取引先
の業況悪化に伴う信用金庫自身の資産劣化
への対策であるだけでなく、取引先とのリ
レーションを強固にする重要なツールでも
ある。さらに、営業地域が限定された信用
金庫にとって当該業務は、地域貢献の観点
からも、地元との良好な関係維持の方策で
あると考えることもできる。
(注)5 .SWOTとは、Strength(強み:自社の)、Weakness(弱み:自社の)、Opportunity(機会:外部環境にあるチャンス)、Threat(脅威:外部環境の自社に不利な要因)の頭文字

研 究 31
(ロ )信用金庫のサポートを必要とする中小
企業経営者
実際、中小企業の経営者には、外部環境
の状況もその対処策もよく理解していない
場合も多い。自らの業況の良し悪しや、良
いときの理由すらも分かっていない場合も
ある。また、近年は、企業側も経営改善支
援を受けることへの抵抗感が薄れてきてい
る。各々の事情に応じて、各金庫が実施で
きる経営改善支援業務の内容は異なろう
が、本業務に取り組む余地はまだまだ残さ
れていると言えよう。加えて、こうした中
小企業経営者への支援は、協同組織金融機
関の使命とも親和性が高いといえるのでは
ないであろうか。
(ハ )時間のかかる人材育成に求められる経
営者の決意
本業務を実施していくうえでの課題は、
人材の確保である。支援先企業の計画書の
作成は、本部に専担チームを設けている信
用金庫においても営業店で作成する場合が
少なくない。取材をした複数の信用金庫に
おいて、経営改善支援業務は全職員がノウ
ハウを共有すべき業務であると位置付けら
れており、そのための人材育成の仕組みの
整備が重要であると考えられていた。
しかし、短期間での育成は難しく、人材
育成という息の長い取組みを成功に導くた
めには、経営改善支援業務に本腰を入れ
て取り組むという経営者の決意が必要と
なる。
ホ.経営改善支援に関する人材育成への取組み
ある信用金庫では、営業店向けにケース
スタディによるディスカッション形式の研
修を年1回実施し、事例企業の経営戦略・
方針等をレクチャーしている。また、若手
職員に対しては、企業経営診断に不慣れな
ことも多いため、資金繰り表の理解等を求
めている。
別の信用金庫では、経営改善支援の実務
自体がOJTとして人材育成に有効(注)6であ
ると捉えている。また、製品等の理解が難
しい製造業の経営診断については、外部の
事業コンサルティング会社と提携し、提携
先の企業訪問に自金庫職員を同行させるこ
とで、職員の企業を見る目の育成を図って
いる。工場がきれいなのか、汚いのかの見
分けがつくようになれば、書類上の数字と
実態の差にも気付くようになるのである。
加えて、この信用金庫は経営相談ノウハウ
の組織内での共有化を進めるため、過去の
経営改善支援事例を100ケース蓄積してい
る。これだけの蓄積があれば、どのような
案件に対しても、何かしら有用な事例が見
つかるという。
ヘ.まとめ
以上、複数の信用金庫の経営改善支援業務
(注)6 .この信用金庫は、製造業の取引先のない営業店に、他店の製造業の事例で研修をしても、研修生のイメージがわきにくく、深い理解は得られないため、各店での事例で研修した方がよいと考えている。

32 信金中金月報 2009.3
への取組事例を見てきた。方法や内容はそれ
ぞれに異なるが、この業務は地域密着型金融
のコア業務であるとも言え、財務面はもちろ
ん、事業改善面にも踏み込んでノウハウを組
織的に蓄積し、共有化する体制整備を進める
ことが、信用金庫の将来のために必要なので
はないだろうか。顧客の事業面にも関与し顧
客事業への理解を深めることは、不良債権へ
の対処はもちろん、審査力の向上にも有用で
ある。再び訪れつつある景気後退期において
こそ、本業務への取組みの真価が問われるも
のと考える。
3.個別取組項目の実施状況
ここでは、金融庁が07年度分まで公表を
続けている地域密着型金融の主な個別の取組
項目について、07年度までの5年間の取組実
績の推移や複数の信用金庫担当者への聞取り
調査を踏まえ、実施状況を検討していく。
(1)創業・新事業支援融資
創業・新事業支援融資は、07年度の件数・
金額に専用の融資商品の実績だけでなく、通
常の融資による支援実績も含めて計上してい
ることもあって、地域金融機関全体(地域銀
行、信用金庫、信用組合の合計)、信用金
庫、地域銀行の件数・金額とも急進してい
る。信用金庫は、貸出残高規模が地域銀行の
約3分の1であるが、件数・金額とも地域銀
行と遜色のない実績を残している(図表5)。
しかし、実績の大半は信用保証協会の制度
融資によるものとみられる。信用金庫への聞
取り調査によれば、創業時の融資は信用リス
クが非常に高いため、旧国民生活金融公庫
(現日本政策金融公庫)を顧客に紹介する
ケースもあるという。逆に、旧国民生活金融
公庫に融資を断られた先にプロパーの専用商
品を融資したという事例もあった。
いずれにしろ、地域金融機関と公的部門と
の役割分担が必要である。また、実施案件の
中には、創業や新事業の実態が伴わないケー
スも多いと見込まれる点も問題である。
(2)企業育成ファンドへの出資金額
近年、地域銀行の出資金額が減少する中
で信用金庫が伸びているのは、ファンド運営
(備考)1.07年度の件数、金額には専用の融資商品の実績だけでなく、通常の融資による支援実績も含めて計上2.金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表5 創業・新事業支援融資 業態別件数 業態別金額(百万円)200,000180,000160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000
0
(百万円)100,00090,00080,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00010,000
0
20,00018,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000
(件)8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
(件)
03 04 05 06 07 (年度) 03 04 05 06 07 (年度) 03 04 05 06 07(年度)
地域金融機関全体(件数)
地域金融機関全体(金額)
信用金庫
信用金庫
地域銀行
地域銀行

研 究 33
会社の営業努力によるものとの見方がある
(図表6)。確かに、地場産業など地元で注目
を浴びる投資対象があれば資金が集まる可能
性があるが、一方で、よい投資先がなかなか
見つからないという声もある。だからといっ
て、投資先を地域外に求めれば、地域内の取
引先を育成するという意義が希薄化してしま
う。今回のサブプライム問題に端を発した金
融市場の混乱から、ファンド出資の出口であ
るIPO(新規公開株式)市場の機能は大きく
低下している。そのため、今後は下火になる
可能性が高い。
(3)ビジネスマッチングの成約案件
ビジネスマッチングは、取引先中小企業に
別の取引先を紹介するサービスであり、金融
機関が蓄積してきた地域の企業情報を取引先
のビジネスチャンス拡大に活用するものであ
る。 地域金融機関全体でも、また地域銀行、
信用金庫とも年々成約実績を伸ばしてきてい
る(図表7)。
ビジネスマッチングを商談会やビジネス
フェアの形式で行う場合、「参加者は開始30
分くらいの間しか集まらず、後は食品ブース
ばかりに人が集まってしまい、会場はまばら
となる。一般人も入りやすいようでないと、
盛り上げるのは難しく、自金庫も取引先も費
用ばかりかかる。」という声もある。しか
し、実績を積み上げている信用金庫に話を聞
くと、周到に事前準備をすることが成功の鍵
であると言う。当該金庫は開催日の4か月前
には出展企業を固め、参加企業のプロフィー
ル(A4用紙1枚)を営業店に配り、参加者を
募っている。早い段階で参加者に働き掛け、
特定の出展企業を見るために来場するという
目的意識を持ってもらうことが、参加者の増
加や成約率の向上につながる。
一方、フェア形式は人手と費用がかかり、
ノウハウ習得のために時間(何回かの実施経
験)も要することから、個別マッチングの形
式を採っている信用金庫もある。当該金庫
は、営業店がリストアップした40数社にア
プローチして商品のセラーとバイヤーを特定
し、数社同士の見合いの形で個別マッチング
を行っている。今後の課題として、1金庫単
独の実施では早期に需要が飽和してしまうた
め、より広域の連携を模索していく必要があ
ろう。
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表6 企業育成ファンドへの出資金額(百万円)30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
003 04 05 06 07 (年度)
地域金融機関全体
地域銀行
信用金庫
(備考)図表6の備考に同じ。
図表7 ビジネスマッチングの成約案件(件)35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
003 04 05 06 07 (年度)
地域金融機関全体
地域銀行
信用金庫

34 信金中金月報 2009.3
(4 )中小企業再生支援協議会の再生計画策
定先
中小企業再生支援協議会を利用した再生計
画策定については、費用と取扱決定までに時
間がかかることが問題となっている。第1段
階の中小企業診断士の参画にかかる費用は
20~30万円だが、計画策定においては会計
士、税理士、弁護士などが参画し、半年程度
の時間と300~400万円の費用がかかってし
まう。一般的に、これだけの費用を負担でき
る企業の規模は年商5億円以上と見られるの
で、年商1億円未満の企業が多い信用金庫の
取引先には、同協議会の対象となる先も少な
い。また、計画策定に半年も時間がかかる
と、その間に対象企業の状態が大きく変化
し、場合によっては倒産してしまうケースも
あるため、3か月ぐらいを目処として自ら取
り組むという金庫もある。
実施状況をみると、地域金融機関は、件数
は06年度から減少し、金額も07年度に減少
しているが、その原因はもっぱら地域銀行の
近年の件数・金額の減少による(図表8)。
信用金庫については、件数・金額とも水準は
低いながら安定的に推移している。
07年6月に設置された中小企業再生支援全
国本部の推進の効果もあり、08年度は協議
会の活動は多忙のようである。新たに10月
から導入された協議会が策定支援する再生計
画における「資本的借入金」制度を利用した
DDSの活用を期待する向きもある。
(5)企業再生ファンドへの出資金額
企業再生ファンドへの出資金額について
は、近年、信用金庫も地域銀行も減少傾向に
ある(図表9)。地域銀行の不良債権処理が
活発だった04~06年度が天井圏となってい
る。企業育成ファンドと同様、適した投資案
件の減少や出資の出口問題などが背景にある
と思われる。
(6)M&A支援実績
M&A支援実績は、信用金庫が07年度に横ば
いながら、地域銀行が堅調なことから全体で
も件数は増加している(図表10)。信用金庫に
ついても、事業承継案件のニーズが今後は出
てこようし、顧客の関心もあると思われる。
ある信用金庫によると、M&Aの相談は売り
も買いも増えており、以前は週1件程度であっ
450400350300250200150100500
450,000400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000
0
(件)300
250
200
150
100
50
0
(件)(百万円) (百万円)
03 04 05 06 07 (年度) 05 06 07 (年度)
350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000
005 06 07 (年度)
地域金融機関全体(件数)
地域金融機関全体(金額)信用金庫
信用金庫
地域銀行 地域銀行
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表8 中小企業再生支援協議会の再生計画策定先 業態別件数 業態別金額

研 究 35
た相談案件が、08年11月は8件に上ったとの
ことである。事業承継案件は売りが9割であり、
買いサイドは一般のM&Aを目的としている。
今年度に入って、事前に相手も決まっている相
談が7、8件持ち込まれ、また、企業規模も関
係なくM&Aの話が持ち上がっているという。
しかし、別の信用金庫では、地域力連携拠
点として67件の相談を受け、うち1割は事業
承継案件だったものの、全件とも企業規模が
小さ過ぎてM&Aのディールには乗りにく
かったとのことであった。現段階で実施に至
るのは限られたケースである。
(7 )財務制限条項(コベナンツ)を活用し
た商品による融資
財務制限条項(コベナンツ)を活用した商
品による融資は、地域金融機関全体で件数は
頭打ちだが、金額は伸び続けている(図表
11)。うち、地域銀行は件数、金額とも増加
しており、信用金庫も件数は伸び悩んでいる
が、金額は順調に伸びている。件数が全体で
頭打ちなのは、当初は件数の多かった信用組
合の影響があろう。
しかし、この融資は、不芳先に対する融資
よりも優良の貸出先に対して優遇条件を付け
るために利用する傾向が強いという見方があ
る。利益が上がっており、借入れを増やした
いが担保余力がない取引先に、財務制限条項
を付し担保に依存せずに融資するということ
であり、景気の天井圏で貸出を増やしたい金
融機関が勧誘しているという。不芳先の金融
支援という当初の推進目的どおりに活用され
ているとは限らない恐れがある点、注意が必
要である。
(備考)図表8の備考に同じ。
図表9 企業再生ファンドへの出資金額(百万円)18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000
03 04 05 06 07 (年度)
地域金融機関全体
地域銀行
信用金庫
(備考)図表8の備考に同じ。
図表10 M&A支援実績(件)350
300
250
200
150
100
50
0070605 (年度)
地域金融機関全体
地域銀行
信用金庫
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表11 財務制限条項を活用した商品による融資 業態別件数 業態別金額
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
(件) (百万円)
03 04 05 06 07 (年度)
地域金融機関全体(金額)
地域金融機関全体(件数)3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
(件)
03 04 05 06 07 (年度)
信用金庫
地域銀行
(百万円)450,000400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000
003 04 05 06 07 (年度)
信用金庫
地域銀行

36 信金中金月報 2009.3
(8)動産担保融資
動産担保融資については、金融庁が07年2
月に金融検査マニュアルを改訂し、動産・債
権担保にかかる自己査定上の取扱いを明確化
したことなどもあり、07年度に地域金融機
関全体での件数・金額とも急伸している(図
表12)。同年度には、地域銀行が件数・金額
とも急伸したほか、信用金庫も件数は急伸し
た。そもそも当該融資は、金融機関貸付が不
動産担保に過度に依拠していたとの反省か
ら、それに替わる企業への資金供給ルートと
して期待された手法であり、インフラ整備も
進められている。畜産物やワインなどの動産
担保融資が、金融機関の農業分野への融資拡
大の話題と相まって注目を集めた。
しかし、動産は所在も移動するし、評価額
も変動する。多くの信用金庫において、動産
担保融資は、担保管理や評価が難しいと見て
いる。担保評価については、まずは専門機関
との連携が必要であろう。もともと旧中小企
業金融公庫、商工組合中央金庫、政策投資銀
行など、もっぱら政府系金融機関が取り扱っ
てきた融資というイメージが強く、現在研究
中といった信用金庫が多いのではなかろうか。
また、「当金庫はこれまでも十分に債務者
を目利きし、返済原資を明確にして無担保融
資を行ってきており、動産担保融資を積極的
に取り組む必要性は少ないと考える。」とい
う声もある。もう一段、利用しやすくならな
いとあえて取り扱う気にはなれないという意
見も多く、一層のインフラ整備等に期待がか
かる。顧客サイドに動産担保融資のニーズが
あればそれに応じるため、信用金庫も実施に
向けた情報収集を進めておく必要があろう。
(9)債権譲渡担保融資
債権譲渡担保融資の大半は売掛債権担保融
資である。地域金融機関全体でみて、05年
度をピークに件数は減少傾向、金額は弱含み
となっている(図表13)。ただし、信用金庫
の融資金額は、05年度以降も増加傾向を示
している。
売掛債権担保融資は、確かに制度の使い勝
手は改善したが、まだまだ充分ではないとい
う意見もある。手続きに手間がかかること、
何かあった場合は売掛先との個別交渉が必要
となることなどが難点であると指摘されてい
る。対象顧客は多いものの、需要自体は以前
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表12 動産担保融資 業態別件数 業態別金額
8007006005004003002001000
160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000
0
(件) (百万円)
05 06 07 (年度)
地域金融機関全体(件数)
地域金融機関全体(金額)
400350300250200150100500
(件)
05 06 07 (年度) 05 06 07 (年度)
信用金庫
信用金庫
地域銀行
地域銀行
(百万円)160,000140,000120,000100,00080,00060,00040,00020,000
0

研 究 37
ほどではないという意見もある。
(10)ノンリコースローン
地域金融機関全体のノンリコースローンの
件数は07年度に持ち直したが、金額は05年
度以降、減少傾向にある(図表14)。その内
訳はほとんどが地域銀行であり、信用金庫は
件数・金額ともわずかである。
実際、ノンリコースローンは、不動産ファ
ンドがレバレッジを取る際の融資や都市部の
大型プロジェクト案件の資金調達に利用され
ていたと推測され、不動産市況の悪化から、
今後は下火になるとみられる。モノにお金を
貸すアメリカ的な融資であり、日本には向い
ていないとの見方もあり、こうした商品性を
考えると、信用金庫におけるニーズは必ずし
も高くないと思われる。
(11 )財務諸表の精度が相対的に高い中小企
業向け融資商品
財務諸表の精度が相対的に高い中小企業に
対する融資商品については、地域金融機関全
体としては、04年度以降は件数・金額とも
おおむね横ばいで推移している(図表15)。
うち、地域銀行は06年度まで増加した後、
07年度は一服したかにもみえる一方、信用
金庫は件数・金額とも04年度をピークに減
少した後、底堅い推移となっている。
こうした商品による融資は、上場企業に比
べて低いと見られる中小企業の財務諸表の精
度を改善し、その情報の非対称性を軽減する
ために、金利等の優遇を通じて、中小企業会
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表13 債権譲渡担保融資 業態別件数 業態別金額
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
(件)14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
(件)
03 04 05 06 07 (年度) 03 04 05 06 07 (年度) 03 04 05 06 07 (年度)
地域金融機関全体(件数)
地域金融機関全体(金額)
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
(百万円)
信用金庫 信用金庫
地域銀行 地域銀行
(百万円)140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表14 ノンリコースローン 業態別件数 業態別金額
600
500
400
300
200
100
005 06 07
(件)
(年度) 070605 (年度) 070605 (年度)
地域金融機関全体(件数)
地域金融機関全体(金額)600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
(百万円)600
500
400
300
200
100
0
(件)
信用金庫
地域銀行
信用金庫
地域銀行
(百万円)600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

38 信金中金月報 2009.3
計指針や会計参与制度導入のインセンティブ
を与える狙いもあったと考えられる。しか
し、信用金庫によってはそのような商品を取
り扱っていないケースもあり、また、「金融
機関は資金の貸し手であり、金融機関が中小
企業に中小企業会計指針や会計参与制度の普
及を促すのには限界がある。やはり、商工会
議所などが推進すべきではないか。」という
意見もあった。さらに、いくらB/SやP/L
の精度が高く粉飾の心配がないとしても、商
品在庫の時価評価いかんで財務内容は大きく
変わるため、そもそも論として簿価ベースの
財務諸表自体の限界を指摘する声もあった。
ただし、中小企業の財務諸表は、リスク測
定のための基礎データとなることはもちろ
ん、本来、企業経営者自身の経営判断材料と
して参照されるべきものであり、その精度向
上自体の意義は大きい。
(12)PFIへの融資
PFIへの融資は、地域金融機関全体で件
数・金額とも07年度は前年度比減少したも
のの、長期的には増加傾向にある(図表
16)。07年度の動きは地域銀行によるもの
で、信用金庫は水準は高くないものの、件
数・金額とも堅調に推移している。
PFIは案件次第であり、地域内の案件につ
いては入札に参加していきたいという意見が
多く、多くの信用金庫が前向きであった。あ
る信用金庫はこれまでに4件の入札に参加
し、3件落札したという。しかし、PFIのア
レンジャー業務に参入するには、膨大な契約
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表15 財務諸表の精度が相対的に高い中小企業向け融資商品 業態別件数 業態別金額
40,00035,00030,00025,00020,00015,00010,0005,000003 04 05 06 07
(件)18,00016,00014,00012,00010,0008,0006,0004,0002,0000
(件)
(年度) 03 04 05 06 07 (年度) 03 04 05 06 07 (年度)
地域金融機関全体(件数)
地域金融機関全体(金額)400,000350,000300,000250,000200,000150,000100,00050,000
0
(百万円) (百万円)300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
0
信用金庫信用金庫
地域銀行地域銀行
(備考)金融庁資料より信金中金総合研究所作成
図表16 PFIへの融資 業態別件数 業態別金額
140
120
100
80
60
40
20
003 04 05 06 07
(件)
(年度)
1009080706050403020100
05 06 07
(件)
(年度)
地域金融機関全体(件数)
地域金融機関全体(金額)
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
(百万円)
信用金庫
地域銀行
05 06 07 (年度)
(百万円)60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
信用金庫
地域銀行

研 究 39
書のチェックが必要でマンパワーもかかるた
め、案件全体の数が少ない中で、専担者を配
置してノウハウを蓄積していくことは難し
い。このため、信金中央金庫の主幹事案件に
参加するのが一般的な事例のようである。
自治体の要請が強く、中には事業の先行き
を読みにくい案件もあるとの指摘もある。
「地元の建設会社でSPC(注)7を結成してPFIを
行いたいが、やはり大手ゼネコンの提案が
通ってしまうのが現状だ。しかし、ノウハウ
を蓄積していけば地元建設会社の提案が採用
されるかもしれないのでその際は対応した
い。」と期待を寄せる声もあった。
(13)まとめ
以上、12の個別取組項目についてみてき
た。一部を除き、アクションプログラムが終
了した後の07年度に実績が急低下するよう
な状況はみられず、恒久化により地域密着型
金融の個別項目への取組みが急激に後退する
ことはなかったようである。
しかし、創業・新事業支援融資、企業育成
ファンドへの出資、ビジネスマッチング、動
産担保融資などは、件数・金額が順調に推移
しているものの、まだまだ課題が残されてい
る。また、財務制限条項(コベナンツ)を活
用した商品による融資は、実態はシンジケー
トローンの計数が反映されている恐れがあ
る。他の多くの項目についても、課題が残さ
れているため件数や金額が伸びないというの
が実情であろう。各個別項目の使い勝手の向
上のために、制度改善などの一層のインフラ
整備が望まれるところである。
もちろん、個別の取組項目については、実
需に応じて対応すればよいし、ニーズが乏し
いものに無理に取り組み続ける必要はない。
ただし、それは取り組んでみたからこそ分
かったことであろうし、取り組むことで新た
な問題点を発見する場合もあろう。03年度
からの5年間で、多くの地域金融機関が地域
密着型金融への取組みを通じて様々な施策を
経験したこと自体は、決して無駄なことでは
あるまい。個別の取組項目については、今後
も恒久的取組みとして、必要な課題解決方法
の改善や取組項目の取捨選択を続けていけば
よいと考える。
おわりに
以上に見たように、信用金庫の経営改善支
援業務は、財務状況の改善提案が中心となっ
ている。人的資源等の制約もあり、一気に組
織的能力を高めることが難しく、可能な範囲
で経験を蓄積していくしかない場合もあろ
う。それでも、信用金庫に寄せられる中小零
細企業の期待は小さくなく、我々としては、
地域金融機関として、また中小企業金融機関
として、精一杯その期待に応える責務がある
のではないだろうか。
愛知県産業労働部が中小企業向けに行った
アンケート調査(注)8によると、調査対象中小
(注)7 .Special Purpose Company(特別目的会社)の略。ここではPFI事業を行う目的で設立されるもののこと。8 .2006年8月に実施された「愛知県に求められる中小企業金融施策の方向に関する調査」のこと。なお、詳細は参考文献にある家森信善名古屋大学教授と近藤万峰愛知学院大学准教授の論文を参照

40 信金中金月報 2009.3
企業のうち信用金庫・信用組合をメインバン
クとするところは、その16.8%が「経営につ
いてアドバイスを受ける専門家」として「金
融機関(≒信用金庫・信用組合)」を挙げて
いる。政府系金融機関(21.1%)をメインバ
ンクとする企業よりは回答割合が低いもの
の、地方銀行・第二地方銀行(12.2%)や都
市銀行(10.9%)をメインバンクとする企業
よりは回答割合が高くなっている。民間金融
機関の中でも信用金庫や信用組合は、顧客か
ら経営アドバイザーとして期待されており、
顧客からの経営改善支援ニーズも十分にある
と思われる。実際、中小企業の経営者は、と
もすれば経営に関する相談相手が少なく孤独
な状況にある。だからこそ、信用金庫は、今
後も当該業務を本業と位置付けて継続して取
り組み、財務面はもちろん、できる限り事業
改善に踏み込んだアドバイスを行っていく必
要があるのではないだろうか。
〈参考文献〉金融庁「平成19年度における地域密着型金融の取組み状況について」(平成20年7月1日)
家森信善・近藤万峰「地域密着型金融推進計画の展開とリレーションシップバンキングの現実-愛知県アンケート調査に基づく中小企業と銀行のリレーションシップの分析-」金融構造研究 第29号

研 究 41
(キーワード) バイオマス・ニッポン、バイオマスタウン、地域バイオマス利活用交付金
(視 点) 02年に「バイオマス・ニッポン総合戦略」を発表した政府は、「バイオマスタウン」、すなわち「バイオマスの発生から利用までが効率的なプロセスで結ばれた総合的な利活用システムを有する市町村」を、10年までに全国300の市町村に構築する目標を掲げている。これには、地球温暖化防止や、循環型社会の形成のみならず、地域の産業を活性化させ雇用を増やす効果も期待されている。そこで、本稿では、「バイオマスタウン構想」の目指すものや、交付金の利活用状況などの全般的特徴を述べるとともに、先進的と評される4市町村の事例を紹介したい。
(要 旨)● バイオマスは、カーボンニュートラルな再生可能資源であり、地球温暖化防止に役立つと期待されているが、廃棄物系バイオマスの中では食品廃棄物、未利用バイオマスの中では林地残材の利活用が遅れており、「バイオマスタウン」構築における当面の焦点になっている。
● バイオマス資源は、かさばるなど収集・運搬に手間とコストがかかるので、できる限り生産と消費を近接化させる「地産地消」が望ましく、それぞれの地域が、その特性に応じ実情に即した「バイオマスタウン」を構築していくことが求められている。
● 市町村が中心になって、地域の幅広い関係者とともに作成した「バイオマスタウン構想書」は、「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議」から公表される。これに基づき、市町村や民間事業者は、「地域バイオマス利活用交付金」を活用し、例えば、メタン発酵施設、木質ペレット製造施設などのバイオマス変換施設や、バイオマスの貯蔵施設、バイオマス・ボイラなどの利用施設等の一体的な整備を図ることができる。
● 岐阜県白川町は、木くず発電所の電力を利用し、林地残材や、製材くずなどからの木質ペレット生産を本格化しようとしており、岡山県真庭市では、チップや、ペレットといった木質バイオマス資源をボイラ燃料として地域内で循環させる仕組みを構築しつつある。
● 新潟県上越市は、生ゴミや下水汚泥を、生ゴミ自体のメタン発酵によって得られるバイオガスと木質バイオマスを燃焼させて得られる熱風によって乾燥させる効率的なバイオマス変換施設を導入したほか、木材や古々米などからバイオプラスチックを製造する設備を建設した。千葉県旭市では、食品工場やコンビニなどから排出される食品残さを活用して、養豚用の液状飼料を製造する工場が稼働している。
研 究
全国に広がる「バイオマスタウン」構築への取組み-林地残材などの木質バイオマスと食品廃棄物の利活用が当面の焦点に-
信金中央金庫 総合研究所主任研究員
澤山 弘

42 信金中金月報 2009.3
はじめに
08年7月の洞爺湖サミットを踏まえ、京都
議定書が定めた二酸化炭素排出量削減を実現
するため、様々な努力が本格化してきた。省
エネはもとより、太陽光発電や風力発電と
いった自然エネルギーの導入促進に加え、バ
イオマス資源の利活用による石油など化石由
来資源削減への期待が高まっている。
02年に、「バイオマス・ニッポン」、すなわ
ち、「製品やエネルギーとしてバイオマスを
総合的に最大限活用し、持続的に発展可能な
社会」(注)1を目指す「バイオマス・ニッポン総
合戦略」を策定したわが国政府は、ここへ来
て、「バイオマスタウン」の構築に本腰を入
れてきている。これは、「バイオマス・ニッ
ポン」の実現に向け、地域にそれぞれの実情
に即したバイオマス利活用システムの自主的
な構築を促していこうというもので、10年
度までに全国300の市町村における「バイオ
マスタウン」構築を目標としている。09年1
月末現在、中山間地や農村地域のみならず、
大都市近郊も含め、すでに全国163の市町村
が「バイオマスタウン構想」を公表するに
至っている。
その目的としては、地球温暖化防止や、循
環型社会の形成に加え、地域の活性化や、新
たな産業の創出が挙げられている。「地産地
消」をめざすこの取組みは、市町村が主導す
るものではあるが、民間事業者やNPO団体
等地域の様々な関係者も加わることにより、
地域の産業を活性化させ雇用を増やす効果も
期待されている。新たな融資機会の拡大も見
込まれるので、地域金融機関としても、注視
していくべき取組みといえよう。
そこで、本稿では、まず第1章で、バイオ
マス資源の特徴、利活用の現況などを見た後
に、第2章で、なぜ今バイオマスタウンの構
築が求められているのかを確認する。つい
で、第3章では、バイオマスタウン構想公表
へのプロセスや、どのようなバイオマス資源
を中心に取組みが進められようとしているの
かといった全般的特徴を述べ、さらに、その
実現を支援する「地域バイオマス利活用交付
金」の仕組みについても説明する。そして、
最後の第4章で、林地残材や食品廃棄物の利
活用を中心とした先進的事例として、岐阜県
白川町、岡山県真庭市、新潟県上越市、千葉
県旭市の4例を紹介したい。
1.利活用が期待されるバイオマス資源
(1 )再生可能でカーボンニュートラルなエ
ネルギー資源
初めに、バイオマス資源の重要性について
確認しておこう。バイオマスとは、バイオ
(bio:生物資源)とマス(mass:量)を組み
合わせた言葉であり、「再生可能な、生物由来
の有機性資源で化石燃料を除いたもの」(注)2
と定義されている。
バイオマスエネルギーは、生命と太陽があ
(注)1 .「バイオマス・ニッポン総合戦略」(2006)p.2参照2.「バイオマス・ニッポン総合戦略」(2006)p.1参照

研 究 43
る限り枯渇せず、再生可能であるので、サス
テナブル(持続可能)エネルギーと言える。
植物は、大気中の二酸化炭素を吸収し、水
と太陽光エネルギーにより有機物を合成(光
合成)することによって、二酸化炭素を固定
させている。草食動物は、植物を食べること
によって生存しており、その体内には炭素が
取り込まれている。他の動物等を食べること
によって生存している肉食動物も同様にし
て、炭素を取り込んでいる。
この炭素は、植物からでも動物(から出さ
れる排せつ物)からでも、燃やされたり微生
物によって分解されれば、二酸化炭素として
大気中に放出されてしまう。しかし、それは、
植物が成長する過程で光合成により大気から
吸収したものなので、大気中の二酸化炭素を
増加させることにはならない。再び、光合成
によって植物に固定され得るからであり、こ
れを「カーボンニュートラル」という。
したがって、石油や石炭など、化石資源に
由来するエネルギーやマテリアルを、バイオ
マスで代替していくことができれば、温室効
果ガスのひとつである二酸化炭素の排出量削
減を図ることができる。バイオマス資源に期
待が集まるのはこのためである。
(2)バイオマス資源の利活用状況
バイオマス資源にはどのようなものがある
のだろうか。「バイオマス・ニッポン総合戦
略」(以下、「総合戦略」という。)では、現
状および将来における利活用状況という視点
から以下の3つに分類している(注)3。
第1は、廃棄物系バイオマスである。その
代表的なものとしては、家畜排せつ物、製材
所端材、建設発生木材、食品残さ、下水汚泥
などがある。これらは、廃棄物として処理す
る以上、一般に、排出者側が費用を支払わな
ければならない(いわゆる「逆有償」)ので、
利活用する側から言えば、生産コストが比較
的安価で済むという特徴がある。
このため、廃棄物系バイオマスの利活用は、
現状でもある程度進んできている(図表1)。
特に、製紙工程におけるパルプ廃液である黒
液は100%利活用されているし、建設発生木
(注)3 .この点については、小宮山宏、迫田章義、松村幸彦[2003]が詳しく解説している。
図表1 わが国のバイオマス賦存量と利活用状況(2007年) (単位:万トン、%)
対象バイオマス 年間発生量 バイオマスの利活用状況 未利用率
廃棄物系バイオマス
家畜排せつ物 8,700 たい肥等への利用 約90% 10下水汚泥 8,000 建築資材・たい肥等への利用 約70% 30黒液 7,000 エネルギーへの利用 約100% 0廃棄紙 3,700 素材原料、エネルギー等への利用 約60% 40食品廃棄物 2,000 肥飼料等への利用 約25% 75製材工場等残材 440 製紙原料・エネルギー等への利用 約95% 5建設発生木材 470 製紙原料、家畜敷料等への利用 約70% 30
未利用バイオマス
農作物非食用部 1,400 たい肥、飼料、家畜敷料等への利用 約30% 70林地残材 350 製紙原料等への利用 約2% 98
(備考 )㈳日本有機資源協会資料「あなたのまちも バイオマスタウンに!」 より作成

44 信金中金月報 2009.3
材の未利用率は、従来約6割に達していた
が、02年に「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律」が完全施行された結果、
約3割まで大きく低下した。
ただし、年間約2,000万トン発生している
食品廃棄物の未利用率は依然として75%と極
めて高い水準にある。01年に「食品循環資源
の再生利用等の促進に関する法律」が施行さ
れてからは、肥料や飼料等への利用により、
それまでの未利用率90%からは改善されてき
たものの、今日でも、4分の3は焼却ないし埋
立て処理されているのが現状である。
第2は、未利用バイオマスである。主なも
のとしては、農作物の非食用部(稲ワラ、モ
ミ殻、麦ワラ、イネなどの茎、葉など)と、
間伐材や台風などによる被害木等の林地残材
がある。農作物非食用部は、年間1,400万ト
ン発生しており、現状では、約3割がたい
肥、飼料、畜舎敷料等として利用されている
ものの、7割が未利用で、そのまま農地にす
き込まれている。また、年間350万トン発生
している林地残材も、ほとんどすべて未利用
のまま山林に放置されている。
したがって、必要とされているのは、食品
廃棄物の利活用と並び、これら未利用バイオ
マスの利活用の拡大であると言える。「総合
戦略」では、これらを効率的に収集するシス
テムを整備したり、製品やエネルギーとして
の利用を拡大していくことを、今後の重点課
題としている。
第3は、資源作物と呼ばれるものである。こ
れは、糖質資源(サトウキビ、テンサイなど)、
でんぷん質資源(トウモロコシ、コメ、イモな
ど)、油脂資源(ナタネ、ダイズ、ラッカセイ
など)に分けられるが、食料と競合しない形
で、主としてエネルギー利用を目的として、
今後栽培されようとしている作物群を言う。
現状では、サトウキビやテンサイ、多収穫イ
ネ、規格外小麦などからバイオエタノールを製
造する試みが始まっているが、いずれもまだ
実験・実証段階にあり、「総合戦略」 でも、
本格的な拡大は、エネルギー変換効率の大幅
な向上が見込まれる20年頃と想定している。
なお、資源作物のひとつとして新作物を区
別して言うこともある。新作物とは、品種改
良や遺伝子組換えなどにより生産性を飛躍的
に高めた資源作物を指す。「総合戦略」 では、
50年頃の実用化を想定している。
2 .「バイオマス・ニッポン総合戦略」と「バイオマスタウン」
(1)「バイオマス・ニッポン」を目指す理由
「総合戦略」は、30年頃を見据えた 「バイ
オマス・ニッポン」 の姿を提示し、それへの
道筋を示すものとして、02年12月末に策定
されたものである。
同戦略は、「化石資源使い捨てニッポン」
から脱却し、「製品やエネルギーとしてバイ
オマスを総合的に最大限利活用し、持続的に
発展可能な社会」である「『バイオマス・
ニッポン』をできる限り早期に実現すること
が、強く求められている」(注)4としているが、
(注)4 .注1に同じ。

研 究 45
その理由として、以下の4点を挙げている。
①地球温暖化の防止
京都議定書発効を踏まえ、温室効果ガス削
減対策として、カーボンニュートラルという
特性を持つバイオマスの利活用を促進し、適
切な森林経営による二酸化炭素吸収量の上限
値(注)5を確保するために、森林吸収源対策を
進めること。
②循環型社会の形成
これまでの資源使い捨て社会から、廃棄物
の発生を抑制し、限りある資源を有効活用す
る循環型社会への移行を加速化していくこ
と。これは、00年の「循環型社会形成推進
基本法」に掲げられた理念の実現を目指すも
のである。
③競争力ある新たな戦略的産業の育成
バイオマスを使った製品やエネルギーへの
利活用において、革新的な技術や新製品を開
発したり、ノウハウを蓄積し、先進的なビジ
ネスモデルを創出していくことによって、新
たな「環境調和型産業」を生み出し、合わせ
て雇用の創出を図っていくこと。これは、日本
発の戦略的産業として、わが国産業の国際競争
力の再生にもつながるものと期待されている。
④農林漁業、農山漁村の活性化
わが国は温暖で多雨な気候に恵まれ、バイ
オマスは豊富にある。それらの多くは、農山
漁村に存在しているので、農林漁業には、従
来からの食糧や木材の供給に加え、エネル
ギーや素材・工業製品の供給という役割が生
まれ、地域の活性化をもたらすと考えられる。
以上のとおり、「バイオマス・ニッポン」
の構築は、地球温暖化防止、循環型社会形成
という21世紀の大きな課題に応えていくと
同時に、世界的にも最先端にあるわが国環境
技術をいっそう発展させ、併せて疲弊が著し
い地域経済を活性化させていくという、極め
て意欲的な国家プロジェクトなのである。
(2)なぜ「バイオマスタウン」なのか
バイオマスには、石油や石炭などの化石資
源と異なり、広く薄くではあるが、日本全国
どこにでも分布しているというメリットがあ
る。ただし、一般に、水分含有量が多かった
り、かさばったりするので扱いづらく、収
集・運搬には手間とコストがかかる。
このため、バイオマスは、できる限り発生
するバイオマスの近くで利活用するのがよ
い。生産と消費を近接化、一体化させ、可能
な限り複合的に循環利用していく「地産地
消」(小規模分散型の生産・消費)が望まれ
るのである。
とはいえ、あまりに小規模であるとバイオ
マスのエネルギー等への変換設備が割高とな
り、変換効率は低くなってしまう。他方、大
(注)5 .08年から12年までの第1約束期間における森林による二酸化炭素吸収量として、わが国は1,300万炭素トン(90年総排出量比3.8%)の上限値が認められている。

46 信金中金月報 2009.3
規模設備の稼動のために広域からバイオマス
を収集するとなると、今度は輸送コストやそ
のためのエネルギー消費(すなわち二酸化炭
素の排出量)が増大してしまう。このため、
この両面から、自ずとそれぞれの最適な地産
地消の規模が決まることになる。
また、発生するバイオマスの種類や量は地
域によってさまざまである。農村部ではコメ
や野菜などの農作物残さや家畜排せつ物、中
山間地では間伐材などの木質系バイオマスが
主となるが、都市部では大量に発生する食品
廃棄物や建築廃材、下水汚泥などが主なバイ
オマス資源となろう。
したがって、「バイオマス・ニッポン」を
早期に実現するためには、それぞれの地域が
その特性に応じて創意工夫に溢れた取組みを
推進していくべきであり、地域ごとにその実
情に即したシステムを構築することが求めら
れる。ここに、「市町村が中心となって、広
く地域の関係者の連携の下、総合的なバイオ
マス利活用システムを構築する『バイオマス
タウン』構想の取組を広げていくこと」(注)6
の意義がある。
これまでも、バイオマスの利活用は、収集
した生ゴミをメタン発酵させてメタンガス発
電を行うとか、商店街で集めた生ゴミをたい
肥にして近郊農家で使ってもらい、そこで作
られた有機野菜を商店街で売り出すといった
試みなど、個別には取り組まれてきている(注)7。
バイオマスタウン構想は、そうした「点」と
しての取組みを「面」としての地域全体の取
組みの中に取り込み、複合的な相互のつなが
りを持った取組みにしていこうとしているこ
とに大きな意義があるといえよう。
3 .本格化する「バイオマスタウン」への取組み
(1 )163市町村に達した「バイオマスタウン」
への取組み
バイオマスタウン構想は、具体的には、04
年8月に発表された「バイオマスタウン構想
基本方針」に基づいて募集が始められた。05
年2月の第1回公表を皮切りとして、04年度末
までに13の市町村から公表されている(注)8。
そして、06年3月、バイオマスタウン構築
の加速化を主なポイントとした「総合戦略」
の見直しが行われたことを受け、06年度に
は、一挙に50市町村がバイオマスタウン構
想を公表するなど、取組みは全国的に広がっ
た(図表2参照。例年、下半期に公表が増え
(注)6 .「バイオマス・ニッポン総合戦略」(2006)p.14参照7.詳しくは、澤山[2006b]および、澤山[2007]参照8 .当初、04年4月に閣議決定した 「京都議定書目標達成計画」 においては、10年までに全国で500市町村程度での構築を図ることとされていたが、06年3月の「総合戦略」見直しでは、「平成の市町村大合併」の進捗(従前、約3,000あった市町村数が、10年には半減)を踏まえ、300地域程度と改められている。
(備考)「バイオマスタウン情報ヘッドクォーター」 (http://www.biomass-hq.jp/)より作成
図表2 バイオマスタウン構想の年次別公表件数の推移
40
30
20
10
0
(件数)
05.3 05.9 06.3 06.9 07.3 07.9 08.3 08.9(半年度)

研 究 47
る傾向があるようである)。09年1月末まで
に31回にわたって公表が行われてきており、
バイオマスタウン構想を公表した市町村は、
163までになっている。
(2 )「バイオマスタウン」構想公表までのプ
ロセス
ここで、バイオマスタウン構想は、どのよ
うにして計画が練られ公表に至るのか、まと
めておこう。
この策定に当たっては、実施主体となる市
町村が中心になって、バイオマスの総合的な
利活用に向けた全体プランを作成し、NPO、
農協、事業者団体、地方大学等、地域の幅広
い関係者で検討する。そして、バイオマス利
活用の基本的構想や中期的な目標を掲げた
「バイオマスタウン構想書」を、都道府県、農
政局に提出する(具体的な記載項目について
は図表3参照)。
構想書は、農林水産省が事務局を務める
「バイオマス・ニッポン総合戦略推進会議」(注)9
で検討され、図表4に示したような基準に合
致したものが、インターネット上の「バイオ
マス情報ヘッドクォーター」(注)10において順
次公表されるという段取りである。
「バイオマスタウン構想書」のエッセンス
とも言える「取組工程」の一例として、岐阜
県白川町のケースを図表5に示しておこう。
おおむね、各構想書とも、5年度程度にわ
たって主な取組みの工程が示されている。
(3)利活用方法の全般的特徴
それでは、全国的に見ると、どのようなバ
イオマス利活用の取組みが多いのだろうか。
(注)9 .内閣府、総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省から構成される。10 .「バイオマス情報ヘッドクォーター」ホームページ(http://www.biomass-hq.jp/)参照
図表3 バイオマスタウン構想書に求められる記載項目対象となる地域 市町村が基本だが、複数市町村による連携や、逆に、市町村内の一部でも可構想の実施主体 市町村のほか、NPO法人、大学、農協その他が加わることもできる。地域の現状 地域の経済的、社会的、地理的特色など地域のバイオマス賦存量 地域のバイオマスの種類と年間発生量バイオマス利活用状況 これまでの取組みや既存の利活用施設の状況など基本的な構想 バイオマスの収集・輸送・変換方法、利活用方法など、中長期的な工程も含めたもの期待される効果及び利活用目標 環境面、および地域活性化での効果など、種類ごと、および全体の利活用目標検討状況 これまでの取り組み経過や改善内容等
(備考)「バイオマスタウン構想基本方針」(2004)より抽出
図表4 バイオマスタウン構想の公表基準炭素量換算で、廃棄物系バイオマスの90%以上、または未利用バイオマスの40%以上の活用に向け、総合的に進めるものであること。地域住民、関係団体、地域産業等の意見を配慮し、関係者が協力して安定的かつ適正なバイオマス利活用が進むものであること。関係する法制度を順守したものであること。バイオマスの利活用において、安全が確保されていること。
(備考)図表3に同じ。

48 信金中金月報 2009.3
㈳日本有機資源協会の取りまとめ(08年2月
現在)(注)11に従って概観しておこう。
イ.利活用の対象とされるバイオマスの種類
前掲図表1で見たように、林地残材と食品
廃棄物の未利用率は極めて高い(それぞれ、
98%と75%)。これを受けて、未利用バイオ
マスである間伐材や被害木等の林地残材を利
活用の対象として取り上げている市町村は、
08年2月現在でバイオマスタウン構想を公表
した市町村の65.6%(以下同じ)に及び、廃
棄物系バイオマスである食品廃棄物の利活用
も63.2%の市町村で取り上げられている(図
表6)。家畜排せつ物も、ほぼ同様の62.7%の
市町村が対象としており、次いで、廃食油
(38.9%)、下水汚泥(34.4%)、稲ワラ、麦ワ
ラ、モミ殻(34.4%)、製材工場端材(28.9%)
の順で取り上げられている。
ロ.バイオマスの利活用の方法
次に、これらの利活用方法を、モノとし
て利用するマテリアル利用と、熱源として
利用するエネルギー利用とに分けてみてみ
よう。
(注)11 .ただし、集計市町村数には項目によって差異がある。㈳日本有機資源協会事務局嶋本浩治参与に取材した。
図表5 白川町バイオマスタウン構想の取組工程平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度
バイオマスタウン構想 構想提出 実施
農と林のマイスター ・モニター体験実施・体験参加者募集
リピーター確保 参加者拡大
間伐材からのペレット製造
・現状の運用試験 大型製造機の導入検討
・大型機導入・利用販売
ペレット機器(冷暖房)普及拡大
冷暖房機器の共同開発
・開発選考・ 公共的な施設への導入(道の駅ピアチェーレ)
ペレット機器(家庭用)普及拡大
・ストーブ普及策・補助制度の検討
補助制度の検討 普及拡大
BDF 精製・利用 ・事業主体の確立・素案まとめ
・法手続、事業開始・試験的運用
スクールバス等への利用
有機物発酵・焼却灰等混合による肥料高度利用
試験製造 試験的施肥 製造開始
木材成分の高度利用 研究開発 試作 製造設備導入 商品販売
(備考)「白川町バイオマスタウン構想」(http://www.biomass-hq.jp/biomasstown/pdf18/18_16.pdf p.6)より作成
(備考)1 .バイオマスタウン構想90市町村の集計(08年2月末現在)2.㈳日本有機資源協会[2008]p.56より作成
図表6 利活用の対象とされるバイオマスの種類
油糧作物糖質系作物
林地残材(間伐材、被害木など)稲ワラ、麦ワラ、モミ殻
し尿汚泥農業廃水汚泥
下水汚泥廃食油
黒液(パルプ工場廃液)廃菌床
廃おが粉製材工場残材建設発生木材農産物残さ
水産系廃棄物食品廃棄物
家畜排せつ物家庭生ごみ
事業系紙ごみ
0 10 20 30 40 50 60 70(%)

研 究 49
①マテリアル利用
マテリアル利用として最も多い取組みはた
い肥化(注)12であり、8割強の市町村で取り組
まれている(図表7)。これは、原料となる
バイオマスが、食品廃棄物から家畜排せつ
物、モミ殻等幅広く存在し、たい肥への変換
も比較的容易であり、さらに、需要も安定し
ているためであろう。最も基本的な利活用方
法と言える。
次いで多いのは炭化である。これは、活性
炭など、炭として様々な利活用を目指そうと
するものである。一方、飼料化は現状では2
割にとどまっている。このほか、バイオプラ
スチック化なども挙げられているが、数は少
ない。
②エネルギー利用
次にエネルギー利用についてみると、6割
の地域でバイオディーゼル燃料(BDF)化
が取り組まれている。これは、全体としてみ
ても、たい肥化の8割に次ぐ。
原料となる廃食油は、家庭、食品関連事業
所と幅広く存在し、比較的簡便な装置で製造
が容易なこと、さらに、環境意識の高揚策と
して、住民にアピールしやすいことなども、
取組みが進み出した背景として挙げられよう。
木質バイオマス系では、チップ化による直
接燃焼に加え、ペレット・固形燃料化が4割と
かなり多い。すでに利活用が進んでいる製材
所端材に加え、今後は、間伐材など未利用の
林地残材の活用が考えられているようである。
また、メタン発酵も約4割と比較的取組み
が目立つ利活用策である。この取組みは、家
畜排せつ物のほか、生ゴミなどの食品廃棄物
や下水汚泥なども加え、メタン発酵によって
得られるバイオガスを燃焼させて発電し、同
時に熱利用も図るというケースが多く、期待
が高いようだ。
このほか、加熱ガス化発電(注)13も約2割の
市町村で取り組まれようとしている。なお、
バイオエタノール化を取り上げたのは、現状
では2割を下回っている。
(4)「地域バイオマス利活用交付金」の利用
バイオマスタウン構想を実現していくため
に、市町村等の創意工夫を凝らした主体的な
事業を、資金面から支援する「地域バイオマ
ス利活用交付金」制度が設けられている。
これは、各種の施設整備や技術開発など、
地域における取組みを進めていくための支援
措置として、国が07年度より11年度までを
(注)12 .㈳日本有機資源協会 [2008]では「コンポスト化」という用語を使っているが、本稿では一般に使われている「たい肥化」で統一した。
13.詳しくは、前掲澤山[2006b]参照
(備考)1 .バイオマスタウン構想105市町村の集計(08年2月末現在)2.㈳日本有機資源協会[2008]p.58より作成
図表7 バイオマスの利活用の方法
飼料化
たい肥化
炭化
プラスチック化
直接燃焼
ペレット・固形燃料化
加熱ガス化
メタン発酵
ディーゼル燃料化
エタノール化
0 20 40 60 80 100(%)

50 信金中金月報 2009.3
目途に実施しているものである(注)14。バイオ
マスタウン構想を進めようとする事業実施主
体は、その実現に向け、市町村を通じて地方
農政局等に「事業実施計画書」を提出し、こ
の交付金を申請することができる。
これには、ソフト面から支援する「バイオ
マス利活用推進交付金」と、ハード面を支援
する「バイオマス利活用整備交付金」がある。
前者は、①バイオマスタウン構想の策定と、
②バイオマスタウン構想実現のための総合的な
利活用システムの構築を対象として交付される。
市町村は、①により、バイオマスタウン構想を
策定するためのバイオマス存在量の調査といっ
たソフト支援が受けられるほか、すでにバイオ
マスタウン構想を公表している場合は、②によ
り、生ごみ処理機や、菜種搾油機、ペレット
ストーブ、土壌分析機器、液肥散布機械といっ
た簡単な機器を導入することも可能になる。
後者の「バイオマス利活用整備交付金」は、
以下の3つを対象として交付される。
①地域モデル実証タイプ
地域における効果的なバイオマス利活用を図
るために必要なバイオマス変換施設(メタン発
酵施設、炭化施設、たい肥化施設、木質ペレッ
ト製造施設など)、およびバイオマス発生施設
(畜舎、農産物の集出荷・貯蔵施設など)、バ
イオマス利用施設(畜舎、栽培温室、共同育
苗施設など)等の一体的な整備を図るもの。
ただし、地域で発生し、利用可能なバイオ
マスのうち1種類以上のバイオマスについ
て、所定割合以上の利活用を実現することが
採択要件である。
②新技術等の実証タイプ
新技術等を活用したバイオマス変換施設の
モデル的な整備を図るもの。
③家畜排泄物利活用施設の整備
たい肥化施設等の共同利用施設等の整備を
図るもの。
これらの事業実施主体は、市町村に限らず、
PFI事業者、農林漁業者等の団体、消費生活協
同組合、事業協同組合、NPO法人、食品事業
者、廃棄物処理業者等でも可能である(注)15。市
町村が作成する事業実施計画に位置づけられれ
ば、民間事業者も実施主体となることができる。
事業が採択された場合、交付金の補助率は
2分の1以内、ただし、民間事業者単独の場
合は原則として3分の1以内となる。
以上のとおり、ソフト、ハードの両面にわ
たって、バイオマスの円滑な利活用に関連す
る各種施設の一体的整備に向け、交付金によ
る支援が行われている。交付金の実施状況を
(注)14 .ただし、支援事業の内容は、それまでの「バイオマスの環づくり交付金」と基本的に同じである。それ以前には、「バイオマス利活用フロンティア整備事業」等の補助事業があったが、交付金化されたことにより、事前審査が簡素化され、地方が自ら考え使える幅が広がった。できるところから施設整備を始めたり、民間活力を導入できたり、畜舎、園芸ハウスといったバイオマスエネルギーや製品等の利活用施設など、バイオマス変換に関連する施設の整備も可能となった。
15 .農林水産省大臣官房環境バイオマス政策課バイオマス推進室松尾佳典課長補佐に取材した。なお、ソフト事業のうちバイオマスタウン構想策定の事業実施主体は市町村のみ。そのほか、業種別に多少異なるので、詳細は、「バイオマス情報ヘッドクォーター」ホームページ(http://www.biomass-hq.jp/)ほかを参照されたい。

研 究 51
見ると、たい肥化、メタン発酵、飼料化など
が多い(図表8)。
また、事業の実施主体としては、複数の主
体が連携している場合が多く、その際は、民
間団体、民間企業等が中心となることが多い。
4.バイオマスタウン構想の先進事例
以上のような全般的な取組み状況を踏まえ、
本章では、特に利活用が求められる林地残材
等の木質バイオマスおよび食品廃棄物を中心
に、バイオマスタウン構想に先進的に取組ん
でいる事例として、①木くず発電の活用を図
る岐阜県白川町、②木質バイオマスの地域内
循環システムの実験事業を進める岡山県真庭
市、③バイオガス化(メタン発酵)施設やバ
イオプラスチックの製造設備を立ち上げた新
潟県上越市、④液状飼料製造工場をバック
アップする千葉県旭市を取り上げてみよう。
(1 )岐阜県白川町:木くず発電所の電力で
木質ペレット生産へ
銘柄材産地「東濃檜(ひのき)の里・美濃
白川」として知られる岐阜県白川町は、町の
面積の9割弱を森林が占める典型的な中山間地
であり、木材産業が基幹産業となっている。
しかし、銘柄材産地として高級材への依存
が高かっただけに、新しい木材ニーズへの対
応が遅れ気味であるという(注)16。通し柱に使
われるヒノキの中でも最も高価な丸太は、バ
ブル期までは50~60万円/m3もしていたが、近
年は、住宅需要の減少に押され、12~13万円/
m3まで低下してしまった。並材は1.5~3万円/
m3程度にしかならず、材木の切出し意欲が湧
かなくなったという。森林は、計画的な間伐
などによる維持管理が必要とされるが、山林
所有者の世代交代や林業従事者の高齢化が重
なって、これすらも困難になってきている。
したがって、同町のバイオマスタウン構想
の柱は、木材産業の立て直しを通じた地域の
活性化に置かれた。現在、500ha/年の間伐
(伐採量は8,500トン/年)を行っているが、
搬出利用しているのは、その10%にとどまっ
ているという。そこで、白川町では、07年9
月から「林地残材利用促進助成制度」を始め
図表8 地域バイオマス利活用交付金の実施状況事業実施主体
バイオマス変換 総計 地方公共団体 民間団体 民間企業等 協同組合 農業法人ディーゼル燃料化 9 5 4 2 1 1メタン発酵 13 5 8 5 2 1たい肥化 24 8 16 11 4 1飼料化 12 0 12 7 5 0マテリアル 3 0 3 2 1 0木質ペレット等燃料化 5 1 4 1 3 0その他 13 5 8 4 4 0小計 79 24 55 32 20 3
(備考 )1.平成17年度から同19年度6月までの集計。バイオマスの環づくり交付金を含む。2.事業実施主体、バイオマス変換とも、複数実施があるので、小計と総計は一致しない。3.農林水産省資料「地域バイオマス利活用交付金」平成20年10月より作成
(注)16 .白川町森林組合玉置雅野業務課長への取材による。

52 信金中金月報 2009.3
た。これは、林地残材搬出に最大10,000円/
トンの補助金を支給するものである。そし
て、同町では、既設の木くず発電所の電力を
利用して、この未利用間伐材などの林地残材
や、製材くずなどを原料とした木質ペレット
の生産を本格化しようとしている(バイオマ
スタウン構想の全体については、前掲図表5
参照)。
イ .製材所端材の処理施設として木くず発電
所を建設
同町には、従来、町内の製材所に端材処理
用として合計約120基の焼却炉があった。し
かし、これらは、02年の「廃棄物の処理及
び清掃に関する法律」の改正により、廃棄物
焼却炉としての構造基準や維持管理基準を満
たせなくなり、使用できなくなってしまった。
このため、新たな廃棄物処理施設の建設が必
要となり、同年、「森林資源活用センター」
内に、木くず燃焼による発電を行う「森の発
電所」を建設した(注)17(図表9)。
東濃ひのき製品流通協同組合が事業主体と
なり、町内各所の製材所から産業廃棄物とし
て、製材端材や樹皮などの木くずを2,500~
4,500円/トンで受け入れるほか、近隣の建築
廃材なども受け入れている。06年度の木く
ず処理量は約7,600トンに上った。
同発電所では、こうした木くずをボイラで
毎時2.5トン燃焼させ、7.5トン/時の蒸気を
発生させている。このうち、6トン/時の蒸
気で発電タービンを回転させ、600kWhの電
力に変換させている。
残りの蒸気は大型木材乾燥施設(30m3×3
基)の熱源として利用している。自家消費し
ている電力は400kWhであり、隣接するプレ
カット工場(土木、公園用杭加工施設)等で
使われている。電力使用量が低下する夜間な
どを中心に、余剰となる200kWh程度は、中
部電力に売電している。
さらに、自家消費分についても、「グリーン
電力証書」をソニー㈱に発売している。これ
は、年間300万kWhに達する自家消費発電総
量のうち、約100万kWh分の「環境価値」(注)18
分を、同社が08年6月から13年12月まで約5年
間購入することで、環境に配慮した電力を使っ
たとみなすという発電委託契約である。同社
は、これを美濃加茂市の「ソニーイーエムシー
エス美濃加茂テック工場」の年間使用電力の
4%分に充当しており(注)19、この結果、年3,381
トンの二酸化炭素の削減に貢献している。(備考)白川町森林組合提供
図表9 木くず燃焼による「森の発電所」
(注)17 .林野庁の「木質バイオマスエネルギー利用促進事業」補助金を活用したもので、総工費は5.6億円。国と県が合わせて60%、町が約30%を負担している。
18.「グリーン電力証書」の仕組み、特に「環境価値」について詳しくは、澤山[2006a]p.10参照19.中日新聞08年6月13日付、および岐阜新聞08年6月14日付参照

研 究 53
ロ.木質ペレットの製造と利用
東濃ひのき製品流通協同組合では、この電
力をさらに活用しようと考え、04年から小
型の木質ペレット製造機を導入し、木質ペ
レットの試験的生産を開始した。
木質ペレットとは、微粉化された木くずに
熱を加えると溶け出すリグニンという成分が微
粉を固める性質を利用して圧縮した固形燃料で
ある。直径6ミリ(注)20、長さ数センチ程度であ
るが、発熱量は灯油の約半分の約4,700kcal/kg
(樹皮などを含まない「ホワイトペレット」の
場合)と、木質としてはエネルギー密度が高
く、自動供給が可能になるため、ボイラやス
トーブを連続運転できる特長がある。
同組合の場合、原料は隣接するプレカット
工場から排出される上質なヒノキとスギの削り
くずを使う。同工場では、材木をかんな盤で
研磨し丸棒に加工していくが、その際、体積
比で3割は木くずになってしまう。しかし、こ
れは、乾燥しすでに微粉になっているので、
改めて破砕機や乾燥機などによる前処理をす
る必要がなく、低コストで木質ペレットを生産
できる。今後は、1,000トン/年の生産能力を持
つペレット製造設備を建設し、町内の公共施設
などを対象に、岐阜県内をも視野に入れて、
ペレットボイラの普及を目指す計画である。
さらに、矢崎総業㈱が開発した木質ペレッ
ト炊きの吸収式冷暖房機(図表10)も、需
要増加を後押しそうである。吸収式冷暖房機
自体は、古くから商業ビルなどの空調に一般
的に用いられているが、これまで熱源には、
都市ガスや重油、LPG、灯油などが用いら
れてきた。これに対して、同社は、木質ペ
レット焚きも加えたのである。これにより、
二酸化炭素の排出を大きく削減できるほか、
LPG等と木質ペレットとの価格差次第では
あるが、ランニングコストも大きく引き下げ
ることができるようになる(注)21。
(2 )岡山県真庭市:木質ペレットを核にバ
イオマスボイラの普及に尽力
岡山県北部、中国山地に囲まれた盆地に位
置する真庭市も、約8割が森林(うちヒノキ
が7割、スギが2.5割)で占められており、
「美作(みまさか)材」として知られる西日
本有数の製材業地域である。同市がバイオマ
(注)20 .このほか、12ミリ、18ミリなどのものがあるが、家庭用ストーブには6ミリが最適とされている。なお、木質ペレットの詳細については、前掲澤山[2006b]を参照されたい。
21 .木質ペレット炊きの分は、「カーボンニュートラル」により、二酸化炭素排出はゼロとカウントされるが、ペレットの着火時に灯油バーナーまたは都市ガスバーナーが必要なため、同社では、使用ピーク時には灯油炊きも併用することを推奨している。それでも、二酸化炭素排出量は、210kwクラスで、ほぼ3分の2に低減される。同社環境エネルギー機器本部環境システム事業部事業企画部川下晴之氏に取材した。
(備考)矢崎総業㈱提供
図表10 木質ペレット焚き吸収式冷暖房機

54 信金中金月報 2009.3
スタウン構想を公表したのは06年4月である
が、同市における「木をとことん活用するま
ちづくり」の歴史は古く、木質バイオマスの
利活用という点では最も進んでいる地域のひ
とつとされている(注)22。
真庭市のバイオマスタウン構想の特質とし
ては、①銘建工業㈱という地元の製材企業大
手が中核となっていること、②90年代に始
まる 「21世紀の真庭塾」 という有志の集ま
りがバイオマス資源の利活用の研究を早くか
ら進めてきたこと、③NEDO(独立行政法人
新エネルギー・産業技術総合開発機構)か
ら受託した「地域エネルギー循環システム化
実験事業」を当面の中心に据えていることが
挙げられる。
イ .わが国最大規模の木質ペレット生産を行
う銘建工業㈱
銘建工業㈱は、大正時代に創業した老舗の
製材企業で、集成材の全国シェア20%を誇る
大企業である。
同社は、97年12月に大型木くず焚きボイ
ラによる発電設備を完成させた。樹皮8,000
トン/年、製材端材2,000トン/年、プレナー
くず30,000トン/年を燃焼させ、20トン/時の
蒸気を発生させ、1,950kwhを発電している。
これで、本社工場全体の電力を賄うととも
に、03年4月からは売電も始めている。
さらに、同社では、この加工工程から出
てくる100トン/日もの膨大なプレナーくず
を活用しようと、04年8月、木くず発電用か
ら一部転用して、木質ペレット生産を開始
した。
現在、1トン/時の生産能力を持つペレッ
ト製造設備を計3基有しており、年間1.5万ト
ンもの木質ペレットを生産している。08年
度の全国木質ペレット生産量は約50社合計
で3~4万トンと見込まれているので、当社
だけで約半分を生産していることになる。こ
のうち、外販しているのは1.2万トン/年であ
るが、約1万トンは、北海道から九州まで、
全国に広く出荷されている。
ロ .木質ペレットの販売を担当する真庭バイ
オエネルギー㈱
木質ペレットの販売を担っているのが、
04年9月に設立された真庭バイオエネルギー
㈱である。同社は、木質バイオマスエネル
ギーの生産販売、燃焼機器の販売・賃貸、コ
ンサルティング等、幅広い活動を通じて木質
バイオマスの流通システムを確立することを
目指している。
同社設立の母体となったのは、92年に始
まった「21世紀の真庭塾」である。同塾は、
20人ほどの有志が集まって始まったもので、
かねてからゼロエミッション活動などに取
り組んできた。真庭市の場合、こうした長
い積み重ねが今日の原動力となっているとい
える。
(注)22 .実際、海外からも含め、他地域から年間15,000人もの視察者を集めている。同市観光連盟に委託した有料のバイオマス視察ツアーは、ひとつの観光資源にまでなってきている。真庭市産業観光部森田学主事の紹介により、銘建工業㈱長田正之取締役総務部長をはじめとする数社に取材にした。

研 究 55
ハ .05年度から「地域エネルギー循環シス
テム化実験事業」を開始
こうした動きを踏まえて、真庭市は、05
年度から09年度にわたる「木質バイオマス
活用地域エネルギー循環システム化実験事
業」をNEDOから受託した。これが、06年4
月公表のバイオマスタウン構想の中核になっ
ている。
当実験事業の目的は、地産地消・地域循
環型のエネルギーシステムが成立すること
を実証することにある。すなわち、林地残
材や製材所端材などの木質バイオマス資源
を地域内で効率的に収集・運搬するシステ
ムを構築するとともに、様々な事業用重油
焚きボイラからバイオマスボイラへの転換を
促進し、チップや樹皮、ペレットといった木
質バイオマス資源をボイラ燃料として地域内
で循環させる仕組みを構築しようというので
ある。
同市のバイオマスタウン構想では、①利活
用されていない木質系廃材の大半を占める樹
皮について、3,400トン/年の活用を図ると
し、バイオマスボイラの補助燃料(注)23として
使用することを目指す、②57,000トン/年発
生している未利用木材(間伐材、林地残材)
のうち、当面、1,800トン/年について燃料と
しての活用を目指し、流通システムを構築す
るとの目標を掲げた。このため、06年度中
に、木質バイオマスを利用した冷暖房システ
ムや、園芸ハウス用の温水・温風ボイラ、工
場用の蒸気ボイラなどを導入し、07年度か
ら実験事業を開始している。以下に、その導
入事例をふたつほど紹介しよう。
① 温室用ペレットボイラを設置した「いち
ごっ娘農園」
イチゴのハウス栽培を行っている「いち
ごっ娘農園」は、NEDOの実験施設として、
新たに、木質ペレット炊き温水ボイラを導入
した(図表11)。木質ペレットは9m3のサイロ
に蓄えられ、半月で4トンは使用している。
計5棟、14aのビニールハウス内に、イチゴ栽
培のプランターが並び、その横に温水パイプ
が張り巡らされている。直接温水を循環させ
ることで、個々のプランターを温める方式で
ある。燃焼時のボイラ内温水の温度は50℃だ
が、30℃まで下がると自動的に再点火するよ
う設定してあり、ハウス内の気温は常時16~
17℃に保たれている。
(注)23 .樹皮は、熱量が相対的に低く、焼却灰が多いため、小規模なチップボイラなどには向かない。このため、大規模な木くず炊きボイラに投入し、補助燃料として燃焼させるのがよいとされている。
(備考)真庭市提供
図表11 「いちごっ娘農園」の温水ボイラ

56 信金中金月報 2009.3
②チップボイラを導入したランデス㈱
水路などのコンクリート製品を生産している
ランデス㈱では、コンクリートの養生(乾燥)
に使う2.5トン/時の蒸気ボイラの熱源として、
新たに木質チップを使用することとした(図
表12)。チップの保管サイロが必要となるた
め、従来使用していた6トン/時の重油焚きボ
イラに比べて、数倍のスペースが必要となっ
たが、燃料費は3割も削減できたという(注)24。
③健康増進施設:温水プール「水夢」
このほか、実験事業の対象にはなっていな
いが、木質ペレットを活用している公共施設
として、06年4月にオープンした市営温水
プール「水夢」がある。同プールには、2基
の給湯ボイラ(各20万kcal)があり、これで
水温31℃を常時保っている。木質ペレットの
保管サイロの容量は6m3で、年間150トンを使
用しており、週2~3回、フレコン袋(600㎏
入りの大きな麻袋)を6袋程度、手作業で投
入している。ホワイトペレットなので、焼却
灰は0.3%(一袋あたり1.8kg)に過ぎないが、
毎朝掻き出し、週に1度まとめて、職員が肥
料として持ち帰っているという。
ニ .08年度中に「真庭バイオマス集積基地」
を建設
こうした実験施設の稼動を踏まえ、真庭市
は、「真庭産業団地」の一角に10,000m2の土
地を確保し、08年度中に乾燥機能を有する
「真庭バイオマス集積基地」 を建設すること
とした。域内の林業者や製材所が持ち込んで
くる間伐材等の未利用材や端材をここに集積
させ、チッパーで破砕してチップ化し、乾燥
保管したあと、販売していく予定である(注)25。
この輸送・保管システムの構築により、真
庭市では、燃料チップの生産・販売が本格化
し、先行している木質ペレットの生産・販売
と合わせ、地域内バイオマス循環のシステム
作りがさらに進むことになる。
(3 )新潟県上越市:バイオマス変換施設と
バイオプラスチック製造設備を導入
上越市は、全国の自治体の中で最初に環境
に関するISO14001を取得するなど、もとも
と環境意識が高いことで知られているが、
08年度中に、「地域バイオマス利活用交付
金」等を活用し、複合型のバイオマス変換施
(注)24 .ランデス㈱生産技術部稲岡克敏部長に取材した。なお、同社は、「木片コンクリート」を開発したことでも知られている。これは、価格は通常より高価だが、軽く、保水性、透水性に優れるという特質を持つ。歩道などに使うと、水溜りができず、表面温度が低くなるので、ヒートアイランド対策に良い。また軽いので、ガーデニング用として好評を博している。
25.総工費3億円だが、「地域バイオマス利活用交付金」を利用し、国が1.5億円、県、市がそれぞれ0.5億円を負担する。
(備考)真庭市提供
図表12 コンクリート乾燥用蒸気ボイラ

研 究 57
設を完成させる予定である(注)26。これは、生
ゴミや下水汚泥を、生ゴミ自体のメタン発酵
によって得られるバイオガスと木質バイオマ
スを燃焼させて得られる熱風によって乾燥さ
せる効率的なシステムである。また、同市は、
木材や古々米などからバイオプラスチックの
生産を始めたベンチャー企業も支援している。
イ.複合型のバイオマス変換施設を建設
このバイオマス変換施設は、09年1月末に
操業を開始したもので、以下の諸システムを
一つの敷地内に集約し、効率的な熱利用を実
現しようとしている。
① 生ゴミをメタン発酵させるバイオガス化設
備(生ゴミ処理能力:50トン/日)
バイオガス化設備では、一般家庭等から回
収されてくる生ゴミ等を、まず、ホッパに投
入し、ゴミ袋ごと破砕した後、遠心分離の原
理を使って、プラスチック分を取り除く。そ
の後、可容化槽で3日かけて液状化させる
(図表13)。夾雑物をスクリュープレス(脱
水機)によって除去した後、メタン発酵槽に
約20日間とどめ、37℃程度の中温発酵を続
ける。ここで生成されるバイオガス(注)27か
ら、ボイラを傷める硫化物を除いた後、ガス
ホルダに貯留する。
このバイオガスをバイオガスボイラで燃焼
させて蒸気を発生させ、可容化槽やメタン発
酵槽を適温に保つために利用し、残りは次に
述べる汚泥乾燥設備の熱源や脱臭機の燃料と
して使う。バイオガスは、当施設全体の必要
熱エネルギーの3~4割を賄っている。
② 汚泥乾燥設備(下水汚泥処理能力:36.5
m3/日)
当施設では、市内の下水処理センターから、
85%の含水率まで濃縮されて湿った土のよう
な状態になった下水汚泥を、トラックで引取
り搬入する。この下水汚泥と上記バイオガス
化設備で生じる生ゴミの発酵残さを、熱風で
乾燥させるのが汚泥乾燥設備であるが、この
熱風は、上記のバイオガスと、木質チップ
を、熱風発生炉で燃焼させることで得られる。
従来、生ゴミや下水汚泥は、重油焚きボイ
ラを使って熱風乾燥させてからセメント工場
等に搬出していたので、多大な燃料費を要し
ていた上に、二酸化炭素の排出につながって
いた。これに対し、新たなバイオマス変換施
設では、生ゴミ自体のメタン発酵によって得
られるバイオガスを、自らの発酵のための熱
源に利用するとともに、下水汚泥の熱風乾燥
(注)26 .当総工費は27億円。ただし、投資額の半分を交付金で賄っている。組合は、廃棄物処理業者である上越マテリアル㈱、アグリフューチャーじょうえつ㈱、食品スーパーなどで構成。上越市産業観光部平原謙一主任の紹介により、各社に取材した。
27.バイオガスは、メタンが約6割で、残りのほとんどは二酸化炭素で占められており、約3,000m3/日発生する。
(備考)上越バイオマス循環事業協同組合提供
図表13 バイオガス化設備

58 信金中金月報 2009.3
にも利用する。その結果、乾燥処理が求めら
れる含水廃棄物の処理過程での化石燃料使用
を削減することが可能となったのである(注)28。
③ ペレット製造設備(製造能力:7.5トン/
日)とBDF設備(処理能力:115ℓ/日)
同市のくびき野森林組合では、スギの樹皮付
き丸太材や製材所端材をチッパーにより粉砕し、
循環事業協同組合の当施設に搬入している。
同協同組合は、これを原材料として購入
し、さらに細かく破砕し、乾燥した後に微粉
にさせてから、成型機にかけて、年1,800ト
ンのペレットを製造する計画だ。
当協同組合の場合、原料手当てや、販売先
の確保はまだ不十分というのが現状だが、当
協同組合の有力メンバーである上越マテリア
ル㈱の新社屋では、08年秋から、吸収式冷暖
房機への木質ペレット使用が始まっている。
また、当変換施設には、食品工場やレストラ
ンなどから回収した廃食油から、バイオディー
ゼル燃料を精製するBDF設備も併設してある。
ロ .バイオプラスチックを生産するアグリ
フューチャーじょうえつ㈱
さらに、同市は、古々米や、間伐材からバ
イオプラスチックを製造するベンチャー企業、
アグリフューチャーじょうえつ㈱を支援して
いる。これは、04年度に、「バイオマス利活
用フロンティア整備事業」により、国と県、
市が支援して、バイオプラスチック製造設備
を整備し、同社に貸与したものである(注)29。
世界的には、バイオプラスチックの原料と
してはトウモロコシが主流だが、コメからで
もポリ乳酸は作れる。ただし、これはまずで
んぷんを抽出したうえで、化学分解させるた
めコストが高いという問題がある。
これに対して、当社では、米粒等を、プラス
チック樹脂(ポリ乳酸やポリオレフィン)と混
練して複合化させる方式を開発した。要する
に、米なら粒のままで、もみ殻は粉砕したうえ
で、そのままプラスチック原料に混入していく
というものである。この方式であれば、原料を
加工しないので安く生産できるメリットがあ
る。化学プラントメーカーにあるような大型設
備は不要であり、既存の設備を利用して小ロッ
トでもプラスチックを作れる。汎用ポリ袋は、
現在250円/kgが相場だが、当社では200円/kg
で生産できるという。これらは、バイオマス
マーク認定商品(注)30となっている(図表14)。
(注)28 .これらの一般廃棄物の収集は行政の責任であるから、行政から適正な処理費用が委託費として支払われる。なお、この乾燥汚泥には、重金属などの有害物質を含んでいる可能性があるため、セメント焼成炉の燃料として搬出される。
29 .総投資額3.8億円。うち半分は国および県、10%を市が負担、当社は4割負担し、分担金として初年度に支払い、その後貸与を受けている形になっている。500kg/時、年間1,000トンの製造能力を持つ。同社大野孝代表取締役社長に取材した。
30 .これは、06年8月より本格運用が開始されたバイオマス利活用商品の識別表示制度であり、08年10月10日現在、188の商品が認定されている。
(備考)アグリフューチャーじょうえつ㈱提供
図表14 バイオプラスチック製品

研 究 59
(4 )千葉県旭市:液状飼料で先駆ける㈲ブ
ライトピック千葉
千葉県の北東部に位置する旭市は、都心か
ら2時間圏内にある典型的な近郊農業地帯で
ある。「首都圏の台所」として、米や野菜の
みならず養豚や養鶏などの畜産も盛んであ
り、農業産出高は全国第7位となっている。
同市では、バイオマスタウン構想において、
バイオマス利活用方法の筆頭に、食品加工残さ
および野菜非食部の利活用を掲げており、これ
らを原料として養豚用の液状飼料の生産を開
始した㈲ブライトピック千葉を支援している。
畜産飼料といえば、加熱乾燥されたものが
一般的であるが、オランダや、ドイツ、ベル
ギーなどの欧州では、30年以上も前から液
状飼料が普及している。
そのメリットは、第1に、飼料の原料は、食
品工場やコンビニ、スーパー等にとって基本的
に廃棄物であり、処理費を受け取ることがで
きること、第2に、乾燥が不要となることだ。
ただし、液状であるため雑菌の繁殖を防ぐ
ことが不可欠になるが、この点は、ギ酸を投
入して、Ph4.5以下と酸性に維持すれば、サ
ルモネラ菌や大腸菌は発生しないので食中毒
を防ぐことができる(注)31。
これを廃棄物処理・リサイクルの観点から見
ると、現在でも焼却後に埋立て処理することが
圧倒的な食品廃棄物を有効に利活用できるとい
う点で、循環型社会形成上、有意義であるし、
乾燥や焼却処理不要という点で、二酸化炭素
排出量削減につながることも言うまでもない。
㈲ブライトピック千葉(注)32は、こうした観
点に立って、「バイオマスの環づくり交付金」
を活用し、食品廃棄物から養豚用液状飼料を
製造する「溝原飼料工場」を建設した(注)33。
これまで、千葉県内の同社4農場がリキッド
フィーディング(液状飼料による給餌システ
ム)を利用してきたが、09年より社外販売
も開始する。
運び込まれる原料は、パン屑、ドーナツな
どの菓子屑や、チーズなどの乳製品、チョコ
レート、オカラ、ビール粕、醤油粕、弁当
と、実に様々である。ただし、生の肉や魚、
さらに人の口に触れた残飯類も、雑菌混入の
恐れがあるので引き取らない。これらの多く
は、加工作業に入るまでの間、低温倉庫で一
時保管される(注)34。
同社工場には3つのラインがある(図表15)。
(注)31 .ただし、農場側でも、給餌用の塩ビパイプ管や、ステンレス製の容器を導入し、定期的な洗浄によって衛生管理に努めるほか、コンピュータによる給餌コントロールシステムを整備するなど、それなりの初期投資が必要になる。
32 .同社は、1965年、神奈川県で志澤社長が一人で養豚業を立ちあげたものであるが、01年に千葉県内に第1農場を建設後、千葉県を中心に8農場を有し、今日では畜産業界のリーディングカンパニーにまで成長している。旭市役所農水産課吉田陽平氏の紹介により、㈲ブライトピック千葉石井俊裕取締役部長に取材した。
33.総工費5.5億円の半分弱の補助金を国から得て、06年度に着工し、07年夏から稼働させている。34 .とはいえ、通常、翌日の午前中までには飼料として消費される。なお、パンの耳などは、有価物であり、工場側が購入している。
(備考)㈲ブライトピック千葉提供
図表15 原料が搬入されるAライン

60 信金中金月報 2009.3
Aラインは、パン類、米類の加工処理を中心
としたもので、07年からは、形が悪い規格
外のサツマイモ、さらには飼料米も農家から
購入し、投入するようになった。Bラインで
処理されるのは、コンビニ等から搬入された
パンや弁当、惣菜、おにぎり、デザート類な
どである。賞味期限切れの弁当やおにぎり
が、毎日、山のように入ってくる。
これらは、まずベルトコンベアに流され、
仕分けされると同時に、焼き鳥の串のような
異物があれば除去される。次に、プラスチッ
ク包装を分別するために、高速粉砕機にか
けて細かく破砕したあと、比重の違いを利
用して遠心分離機でプラスチック類を回収
する(注)35。
それでも混入したものは、後述するスト
レージ槽に入る前に、網を通すことによって
除去される。A、Bラインの処理能力は、合
わせて、約60トン/日である。
Cラインには、食品加工工場やセントラル
キッチンなどから搬入されてきたバラの原料
が、建屋の外側に取り付けたホッパに投入さ
れ、そのままベルトコンベアでラインに運ば
れてくる。これらは、未包装の加工残さで、
コメ、麺類、野菜くず、うずらの卵といった
調理くずや余剰生産品である。食品工場等か
らの原料は、成分内容が一定しており、ほぼ
同量が毎日入ってくるので、そのまま投入で
きる。このラインの処理能力は約30トン/日
となっている。
このほか、牛乳、ジュースなどの液体原料
が約150トン/日搬入される。以上の各種原
料は、それぞれ処理後いったんストレージ槽
に貯められるが、逐次、ミキシング槽に送ら
れる(図表16)。ミキシング槽では、それぞ
れの主成分の状況を見ながら、適宜、固体原
料と液体原料を混ぜ合わせて、最適な液体飼
料になるように配合している。
現在の製造能力は、約240トン/日であり、
10~12トン積み専用運搬車で各農場に輸送
している。4農場では、合計約37,000頭の豚
が肥育されており、1日30~40トンの液状肥
料を各農場に供給している。
なお、それぞれの農場では、搬入されてく
る液体飼料の成分構成に合わせて、飼料メー
カーから購入してあるアミノ酸系などが入っ
たサプリメントを30~40%程度適宜配合して
いる。
おわりに
以上、バイオマスタウン構想の中で、先進
的とされる4地域の事例を述べてきた。すで
(注)35 .プリンの容器のような固いものは、ベルトコンベアに流した段階で除いておく。
(備考)㈲ブライトピック千葉提供
図表16 ミキシング槽

研 究 61
に述べたとおり、バイオマスの賦存状況はそ
れぞれの地域によって異なるので、バイオマ
スの利活用方法もその特性に応じ多様なもの
となっていることが理解されよう。
これまでに公表されたバイオマスタウン構
想としては、農山村地域が先行しているよう
である。中でも、未利用バイオマスとしての
林地残材の利活用が意欲的に取り組まれよう
としている。適正な間伐による森林保全は、
水源涵養機能の向上や、河川流量の安定化、
土砂崩れの抑制など、災害に強い国土作りの
基礎となるものであるし、クマなどによる鳥
獣被害の抑制にもつながる。加えて、二酸化
炭素の吸収に役立つと同時に、新たな安定し
たエネルギーの供給源として、地域のエネル
ギー自給にも資するものだ。
ただし、現状では、木質ペレットやチップ
を燃料とする温水ボイラや冷暖房機の普及は
遅れている。人口500万人のスウェーデンで
120万トン/年もの木質ペレットが消費され
ていることを考えれば、大きめの事業所や商
業施設の冷暖房、工場等の熱源として、わが
国でももっと普及しておかしくないだろう。
石油資源由来のボイラから、バイオマスボイ
ラへの転換を促進することが望まれる。
また、バイオマスタウン構想は、決して農
山村にだけふさわしいものではないことは、
上越市や旭市における生ゴミや下水汚泥、食
品廃棄物の利活用の事例を見れば明らかだろ
う。これらの乾燥・焼却処理には、現在、全
国各地の自治体で、多大なエネルギーとコス
トが費やされている。上越市のメタン発酵を
利用した自己乾燥のシステムは優れた解決策
のひとつと言えようし、旭市のように、未利
用の食品残さをそのまま養豚飼料に利用でき
れば、トウモロコシを主体とした輸入飼料を
多少なりとも削減でき、ひいてはわが国食料
自給率の向上にもつながろう。食品廃棄物の
利活用率が25%にとどまっている現状を考え
れば、今後は、都市部においても、近郊の畜
産業者や農家と連携した利活用のシステム作
りが進むことが考えられよう。
「総合戦略」は、「みんなでつくる バイオ
マスタウン」を強調している。「バイオマス
タウン」構築を行政任せにせず、地域金融機
関としても、地域の様々な民間事業者と連携
して、構想作りの段階から積極的に知恵を提
供していくとともに、事業実施計画の具体化
の一翼をも担っていってもよいのではないだ
ろうか。特に、各種のバイオマス変換施設の
建設やバイオマスボイラの導入には、「地域
バイオマス交付金」等を活用するにしても、
相応の自己資金も必要となる。資金面から見
ても、地域金融機関への期待は大きいといえ
よう。

62 信金中金月報 2009.3
〈参考文献〉小宮山宏、迫田章義、松村幸彦『バイオマス・ニッポン 日本再生に向けて』日刊工業新聞社(2003)
澤山弘「テイクオフした風力発電事業 -期待される地域金融機関の融資参加-」信金中金総合研究所『産業企業情報』18-2(2006a)
澤山弘「脚光浴び始めたバイオマス(生物資源)エネルギー-事業化進む木質バイオマスやメタン発酵による発電・熱利用-」信金中金総合研究所『産業企業情報』18-11(2006b)
澤山弘「成長続く廃棄物処理・リサイクル産業-環境負荷低減を目指す『循環型社会』形成に向けた 「静脈産業」 として-」信金中金総合研究所『産業企業情報』19-3(2007)
㈳日本有機資源協会『みんなでつくる バイオマスタウン』(2008)
中村良平・柴田浩喜・渡里 司「資源循環型社会における地域経済活性化の効果 -岡山県真庭市におけるバイオマス事業-」(2008)
農林水産省農村振興局「地域バイオマス利活用交付金 -あなたの市町村でもバイオマス利活用事業を進めてみませんか-」(平成19年6月20日)(2007)
「バイオマスタウン構想基本方針」平成16年8月閣議決定(2004)
「バイオマス・ニッポン総合戦略」平成18年3月31日閣議決定(2006)

調 査 63
(要 旨) アジア業務室では、08年9月9日、10日と山東省青島市を訪問し、北京オリンピック後の同市の様子を視察した。今回は、訪問後の世界的不況の影響を踏まえつつ、山東省沿岸部の中心都市として、発展を続ける青島市の様子や日本企業にとっての投資環境について報告する。1.青島市の現況(1 )青島市は7区5市からなり、07年末の市全体の戸籍人口は758万人、流動人口は840万人と言われている。市の中心部は高新技術開発区がある 山区に拡大しており、最近ではヨットのオリンピック会場の北東側の海岸地域の開発が進んでいる。
(2 )07年の青島市のGDPは3,786億元となり、成長率16.0%を達成し、中国全体の成長率13.0%を大きく上回った。第3次産業のウエイトは、05年を底に再び増加傾向にある。
(3 )07年の青島市への外国投資は契約件数1,068件(前年比23.6%減)、契約金額38.25億ドル(前年比22.7%増)、実行金額38.07億ドル(前年比4.1%増)となり、実行金額では過去最高を記録した。うち独資(100%外資)企業への投資は、8割を超えている。
(4 )青島市では、ホテル建設、道路整備等社会インフラの整備により生活環境の改善が見られ、前回調査時(06年7月)に比べて、市内中心部の道路は渋滞が緩和され走りやすくなっている。
(5 )日本人学校は青島日本人会の支援を受けて自前の校舎が完成し、8月に入り新校舎に移転した。校舎は、一般教室のほか、様々な特別教室、体育館、校庭、プールと充実した施設を備えている。また、日本人学校と並んで、青島日本人会の長年の懸案事項だった、在青島日本国総領事館が仮事務所ではあるが、09年1月5日(月)から業務を開始した。
2.投資環境(1 )青島市には、経済技術開発区、保税区、高新技術開発区、輸出加工区といった4つの国家級開発区が用意されている。保税区は経済技術開発区の中にあり、保税区の中には物流園区が設置され空港物流園区とともに、山東省の物流拠点となりつつある。
(2 )08年1月1日から労働契約法が施行されたが、日系企業においては、後日トラブルとならないよう対策がとられており、訪問先においては大きな問題は生じていなかった。
(3 )青島市でも、他の都市同様に1~2年で最低賃金が改定されるため、賃金上昇は避けられない状況にある。また、労働契約法の施行に伴い、退職時の経済補償金支払が義務化されたこと等により、毎年20%程度の人件費上昇を見込む企業が多かった。
調 査
中国山東省の投資環境について-青島市の現況-
信金中央金庫 総合研究所アジア業務室長
篠崎 幸弘

64 信金中金月報 2009.3
Ⅰ.青島市の現況
1.位置、気候
青島市は、北緯35度35分~37度09分、東経
119度30分~121度00分と山東半島南端に位
置し、東側が黄海に面している(図表1、2)。
気候は北温帯モンスーン気候区域に属し、
四季がはっきりしている。市区(市中心部)
および膠南市は海洋性気候の影響を受け、温
暖湿潤である。一方、内陸地にある膠州市、
即墨市、平度市および莱西市は市区および膠
南市に比較して寒暖の差が大きくなってい
る。市区の07年の最高気温は31.9℃、最低気
温がマイナス4.3℃で、年間の平均気温が
13.8℃、総雨量が1,353.2ミリであった。6~
9月が雨季にあたり、年間降水量の約8割が
集中している(図表3)。
2.行政区画および人口
青島市は7区5市からなり、07年末の青島
市全体の戸籍人口は758万人、流動人口は
840万人と言われている。行政区画別では、
市区に276万人が居住し、5つの県級市には
482万人が居住している(図表4)。
旧市街地と膠州湾を挟んだ黄島区には経済
技術開発区、保税区があり、近年港湾整備の
進展および電機・電子産業の大型プロジェク
トの進出が盛んである。黄島区は、ここ5年
で50%を超えて人口が増加しており、青島市
でもっとも人口増加が顕著な地域である。黄
島区に次いで、市南区、 山区、そして空港
図表3 07年市区の月別平均気温と降水量 (単位:℃、mm)
年間 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月平均気温 13.8 0.9 5.0 7.0 12.3 18.5 20.6 24.0 25.6 22.3 16.1 9.5 3.6降水量 1,353.2 5.9 10.6 65.8 47.5 75.9 201.4 161.7 482.2 258.3 13.1 0.0 30.8
(備考 )青島統計年鑑にもとづき作成
青島市
平度市
莱西市
即墨市
膠州市膠州湾
膠南市
黄島区
(市区)市南区、市北区四方区、 山区李滄区、城陽区
図表2 青島市概略図表1 市区別気候 (単位:℃、mm)
平均気温 最高気温 最低気温 降水量市 区 13.8 31.9 -4.8 1,353.2膠州市 14.0 36.9 -8.4 911.0即墨市 14.1 36.6 -9.1 947.6平度市 13.5 36.4 -9.3 773.8膠南市 14.1 35.5 -7.0 1,457.2莱西市 13.0 36.6 -11.0 857.3
(備考 )青島統計年鑑にもとづき作成

調 査 65
があり陸上交通の要所でもある城陽区の順で
増加率が高くなっている。
また、市の中心部は旧市街地(市南区、市北
区、四方区、李滄区)から青島市人民政府およ
び高新技術開発区がある 山区に拡大してお
り、最近ではヨット・オリンピック会場の北
東側海岸地域の開発が進んでいる(図表5)。
3.経済動向
(1)GDPの推移
07年の青島市のGDPは3,786億元となり、
成長率16.0%を達成し、中国全体の成長率
13.0%を大きく上回った。97年以降、GDP成
長率は2桁成長率を維持し、最近では16%前
後の高い成長となっている(図表6)。
青島市の産業構造は、他の沿海部の都市同
様に、第1次産業のウエイトが低下し、第2
次および第3次産業のウエイトが高まってい
る(図表7)。
そのうち、第2次産業は90年以降、全市
GDPに占める割合が40%台に低下していたが、
04年以降生産が好調であり再び50%台をキー
プしている。第3次産業のウエイトは、05年
を底に再び増加傾向にあり、市区での観光、
商業、物流といった分野の発展が著しい。
青島市の第1次産業は、市南区、市北区、
四方区では衰退しており、他の区も減少傾向
にある。一方、各市の産業別GDP(第1次産
業)のウエイトは、低下傾向にあるものの、
金額ベースでは増加している。第2次産業は、
図表4 青島市の人口
①02年末総人口(万人)
05年末総人口(万人)
07年末②総人口(万人)
面積(km2)
人口密度(人/km2)
②/①02年比総人口増加率
市区 241.6 265.4 275.5 1,159 2,377 14.0市南区 45.6 50.6 54.0 - - 18.4市北区 46.7 47.3 47.8 - - 2.4四方区 37.1 38.9 39.3 - - 5.9李滄区 27.8 29.1 30.0 - - 7.9黄島区 21.2 30.0 32.7 - - 54.2山区 19.6 21.5 22.4 - - 14.3
城陽区 43.6 48.0 49.3 - - 13.1膠州市 76.3 77.8 79.2 1,210 655 3.8即墨市 107.5 109.1 111.2 1,727 644 3.4平度市 134.0 135.4 136.5 3,166 431 1.9膠南市 83.7 81.1 82.7 1,870 442 -1.2莱西市 72.3 72.2 72.8 1,522 478 0.7合計 715.7 740.9 758.0 10,654 711 5.9
(備考 )青島統計年鑑にもとづき作成図表5 ヨット・オリンピック会場の北東側
海岸地域の様子

66 信金中金月報 2009.3
青島経済技術開発区がある黄島区、青島国際
空港がある城陽区、その周辺地域である膠州
市および即墨市の順に多い。物流もしくは人
の往来が便利な地域が伸びている。第3次産
業は、住居およびオフィス地域である市南区
と市北区において、第3次産業が第2次産業
を大きく上回っており、金額ベースでは、物
流拠点がある市南区(青島港)、黄島区(青
島・黄島港)、城陽区(青島国際空港)の順
で続いている(図表8)。
図表6 GDP成長率推移 (単位:%)
95 00 01 02 03 04 05 06 07青島市 12.0 15.2 13.7 14.5 16.3 16.7 16.9 15.7 16.0中国全体 10.9 8.4 8.3 9.1 10.0 10.1 10.2 10.7 13.0
(備考 )中国統計年鑑、青島統計年鑑等にもとづき作成
図表7 産業構造の推移 (単位:千人、億元、%)
総人口 労働者 GDP構成比 構成比
第1次産業 第2次産業 第3次産業 第1次産業 第2次産業 第3次産業80 5,961 2,701 56.9 30.4 16.0 48.65 21.0 54.0 25.090 6,666 3,528 44.4 34.9 20.7 180.77 21.7 48.0 30.300 7,066 3,976 36.4 33.9 29.7 1,191.25 11.8 46.6 41.601 7,105 4,005 33.4 35.5 31.0 1,368.55 10.6 47.0 42.402 7,157 4.133 29.4 37.2 33.4 1,583.51 9.3 47.9 42.803 7,207 4,390 27.3 37.3 35.3 1,869.44 8.0 49.4 42.604 7,311 4,588 24.8 39.4 35.8 2,270.16 7.2 50.7 42.105 7,409 4,710 22.2 41.8 36.0 2,695.82 6.6 51.8 41.606 7,494 4,901 21.0 42.8 36.2 3,206.58 5.7 52.3 42.007 7,580 5,058 20.2 43.1 36.7 3,786.52 5.4 51.6 43.0
(備考 )青島統計年鑑にもとづき作成
図表8 GDPの産業別ウエイト(区・市別)率 (単位:億元)
07(今回調査) 05(前回調査)GDP GDP
内訳 内訳第1次産業 第2次産業 第3次産業 第1次産業 第2次産業 第3次産業
市区 2,138.51 20.61 1,132.82 985.1 1,472.37 23.78 789.62 658.97市南区 333.01 - 46.30 286.71 229.01 - 34.42 194.59市北区 184.77 - 41.34 143.44 153.48 - 54.17 99.31四方区 120.32 - 61.32 59.00 86.92 - 46.23 40.69李滄区 178.67 0.09 114.23 64.35 141.25 0.16 95.09 46.00黄島区 590.08 3.32 410.29 176.48 358.64 3.97 244.66 110.01山区 251.60 4.67 150.25 96.68 197.03 5.70 120.74 70.59城陽区 480.06 12.53 309.09 158.44 306.04 13.95 194.31 97.78膠州市 418.56 28.92 245.77 143.87 292.11 24.17 166.19 101.75即墨市 433.80 37.41 242.93 153.46 300.94 29.84 158.22 112.88平度市 360.28 54.36 183.22 122.70 272.75 45.31 138.15 89.29膠南市 390.12 31.50 236.16 122.46 288.65 29.86 170.98 87.81莱西市 277.47 30.80 139.02 107.65 198.79 25.36 88.13 85.30
(備考 )青島統計年鑑にもとづき作成

調 査 67
(2)投資動向
07年の青島市への外国投資は契約件数
1,068件(前年比23.6%減)、契約金額38.25億
ドル(前年比22.7%増)、実行金額38.07億ド
ル(前年比4.1%増)となり、実行金額では
過去最高を記録した。うち独資(100%外資)
企業への投資は、件数が892件(投資契約総
数の83.5%)、契約金額が31.62億ドル(投資
契約総額の82.7%)、実行金額が31.86億ドル
(投資実行総額の83.7%)と総投資の80%以上
を占めている(図表9)。
第3次産業(サービス業)に対する投資
は、前回調査時(06年7月)、件数、契約金
額、実行金額とも投資全体の15%以下にとど
まっていたが、実行金額ベースで20%を超
え、契約金額ベースでは40%を超えることと
なった(図表10)。今後も、第3次産業への
投資は拡大すると思われ、青島市が山東省の
物流、商業の中心地となりつつある。
日系企業の進出は06年ぐらいから鈍化し、
07年、08年は横ばいであった。最近、合弁
解消や撤退が出始めている。繊維、食品と
いった産業は地場でも成熟産業となってお
り、コストの上昇を日本への輸出価格に上乗
せしきれないようである。食品は、一連の中
国産食品の問題で日本からの受注が減ってお
り、中国国内販売に転換する動きがでてい
る。中国の市場に受け入れられるものと受け
入られないものとに選別されており、中国国
内販売ができないところには撤退の動きが出
始めている。中国国内販売は上海、北京、広
州といった大都市圏向けが多く、広州からの
引合いが多いようである。青島でも実験的に
販売したいというところがある。新規投資で
図表9 投資実績の推移 (単位:件、万米ドル)
契約件数 契約金額 実行金額独資企業 合弁企業 合作企業 その他
90 64 6,900 4,839 659 4,161 19 -95 718 73,913 70,310 44,999 22,640 2,671 -00 1,128 266,221 126,132 82,992 39,224 3,886 3001 1,254 358,887 158,094 111,028 44,550 2,240 27602 1,832 552,428 231,214 186,254 37,340 7,054 56603 2,248 528,362 281,480 221,824 52,897 5,012 1,74704 2,423 671,723 379,917 317,088 54,798 7,319 71205 2,530 954,486 365,625 280,130 77,636 5,654 2,20506 1,397 311,697 365,815 309,452 49,240 7,123 -07 1,068 382,500 380,652 318,578 46,370 15,490 214
(備考 )青島統計年鑑にもとづき作成
図表10 07年産業別投資実績 (単位:件、万米ドル)
契約件数 契約金額 実行金額比率 比率 比率
第1次産業 8 0.75 6,717 1.76 9,700 2.55第2次産業 686 64.23 206,674 54.03 288,752 75.86第3次産業 374 35.02 169,109 44.21 82,200 21.59計 1,068 100 382,500 100 380,652 100
(備考 )青島統計年鑑にもとづき作成

68 信金中金月報 2009.3
はサービス分野での伸び率方が高まってお
り、済南、青島のITのソフトウェアへの進
出が目立っている。
山東省は広東省に台湾企業の進出が多いよ
うに、韓国企業の進出が多いが、外資優遇税
制の廃止や労働契約法の施行等に伴い07年
ごろから撤退する韓国企業が増えた。08年
中頃までこの傾向は続いていたようで、青島
市政府も撤退支援センターを設置して正規の
手続きによる撤退を指導している。
4.生活環境
青島に居住する日本人は、大使館への届出
ベースで07年10月末現在3,276人であり、山
東省全体(約4,000人)の8割が青島にいる。
届けていない人、短期出張を繰り返す人や留
学生もおり、そういう人たちを含めれば、常
時3,500人ぐらいは青島市にいると見られる。
前回調査時点からはあまり増加していないよ
うである。
青島市は、オリンピックのヨット競技が行
われ、オリンピックの会場整備や選手村に加
えて、ホテル建設、道路整備等が進められ、
生活環境の改善が見られる。前回調査時に比
べて、市内中心部の道路は渋滞が緩和され走
りやすくなっており、移動時間も2割程度短
縮されたように感じた。
日本との直行便は、2年前週22便であった
ものが、現在は週36便(東京・成田14便、名
古屋7便、大阪・関西11便、福岡4便)と大幅
に増加し、利便性はますます向上している。
日本人派遣者は、ジャスコとカルフールが
ある生活に便利な地域に集中しているようで
ある。当該地域は安全性が高く買い物・外食
に便利な地域であり、日本食店も多い。
一方、青島経済技術開発区がある黄島区
は、旧市街地から船で約30分であるものの、
車では2時間弱と通勤は難しい状況にある。
フェリーは4月から7月までよく霧がでるた
め、欠航することが多く、高速道路経由で膠
州湾を回って遅れるということは、結構ある
ようである。膠州湾を潜る海底トンネルが完
成するまではこの状況は続くものと思われる。
04年4月に日本人学校が開校し(図表11、
12)、現地調査時点(08年9月17日)では、
教職員13名に対して、児童・生徒が84名在
図表11 日本人学校全景 図表12 日本人学校体育館等

調 査 69
籍している。小学部、中学部があり、文部科
学省の学習指導要領に則り教育課程を編成し
ている。帰国後を考えて日本語教育に力を入
れる一方、小学部1年生より英語と中国語の
授業を実施し、視野の広い国際人を育てる努
力もしている。中国語の先生は、市内の中学
を退職された方で中国の国語の高級教師免許
を持つ人に委嘱している。修学旅行は、過去
上海、広州・深圳、北京を訪問した。
また、中学部では昨年初めて日本国内への
進学者を出した。今年も、中学部3年生がお
り、帰国して日本の高校に進学するか、イン
ターナショナル・ハイスクールに編入学する
ことになる。日本の高校を受験する生徒につ
いては、受験が予定される県の教育委員会と
の打合せ実施や帰国予定者に対する全カリ
キュラムの2学期中終了等きめ細やかな対応
がなされている。
さらに、青島日本人会の支援を受けて自前
の校舎が完成し、8月に入り新校舎に移転し
た(図表13~15)。新校舎は、木々の生い茂
る山の中腹より上にあり、閑静な環境にあ
る。校舎は、きれいな教室、家庭科実習、理
科実験、工作等様々な特別教室、体育館、校
庭、プールと充実した施設を備えている。新
校舎で児童、生徒はのびのびと勉学に励むこ
とができる。訪問時は、まだ工事中の部分も
あったが、今はそれも終り周囲を高さ約2m
の柵で囲まれ、赤外線警報装置が設置されて
いる。学校側は安全に配慮し、玄関門扉に日
中3名、夜間2名の警備員を配置しているほ
か、登下校は、学校玄関における引き受け引
き渡しを原則とし、警備員を添乗させたス
クールバスも運行されている。
日本人学校と並んで、青島日本人会の長年
の懸案事項だった、在青島日本国総領事館が
09年1月1日に開設され、仮事務所で1月5日
図表13 日本人学校音楽室
図表14 日本人学校コンピュータルーム
図表15 日本人学校舞台付体育館

70 信金中金月報 2009.3
(月)から業務を開始した。仮事務所では当
分の間、邦人援護、在留届の受理、在外選挙
人登録の申請受理だけの業務となり、パス
ポートの発給申請や証明事務およびビザの申
請は、従来どおり北京の大使館領事部への申
請となる。まだ、仮事務所ではあるが、山東
省に進出する企業にとっては、心強い味方と
なるはずである。
Ⅱ.青島市の開発区
1.開発区の現況
青島市には、経済技術開発区、保税区、高
新技術開発区、輸出加工区といった4つの国
家級開発区が用意されている(図表17、18)。
保税区は経済技術開発区の中にあり、保税区
の中には物流園区が設置され空港物流園区と
ともに、山東省の物流拠点となりつつある。
青島市には国家級開発区のほか6つの省級
開発区があり、各開発区とも標準的なインフ
ラが整備されている。各開発区へのアプロー
チは、開発区の中には、日本語が話せる人が
少ないところがあるので、青島市外商投資服
務中心(TEL+86-532-8197-8615)を利用す
ると良い。
日系企業は市街地4区、特に市南区に駐在
員事務所、商社が集中し、工場は黄島区の青
島経済技術開発区、城陽区の環海経済開発
区、即墨経済開発区、膠州経済開発区、膠南
経済開発区等に進出している。空港周辺は土
地に余裕がなく、城陽区西側の開発が進めら
れている。空港の北側にある即墨市も、城陽
区と並んで日系企業には人気があり、進出企
業が増えている。一方、労働集約型投資案件
図表16 在青島日本国総領事館仮事務所住所 青島市香港中路76号 クラウンプラザ・ホテル6階電話 0532-8576-3311、8576-3322開館時間 9:00~11:30、12:30~18:00休館日 土曜日、日曜日および中国の祝日(暫定的なもの。)
図表18 青島市の開発区開発区名 クラス 規制面積(km2)
青島経済技術開発区※ 国家級 220.0青島保税区 国家級 3.8青島高新技術開発区 国家級 67.0青島輸出加工区 国家級 2.8環海経済開発区 省級 6.7膠州経済開発区 省級 9.7即墨経済開発区 省級 27.2平度経済開発区 省級 10.2膠南経済開発区※ 省級 41.0莱西経済開発区※ 省級 20.3
(備考 )1 .国際経済情報ネット・経済園H.P.( http://www. qingdaochina.com/ch/jjyq/)より作成。2.「※」は、総面積。
図表17 青島市の主な開発区
平度経済開発区莱西経済開発区
即墨経済開発区
膠州経済開発区
膠南経済開発区
膠州湾
青島輸出加工区青島空港物流園区環海経済開発区
青島経済技術開発区青島保税区
青島高新技術開発区

調 査 71
は、市区部から即墨市、膠州市、膠南市、莱
西市といった衛星都市にシフトしている。
標準(賃貸)工場、ワンステップサービス
は、訪問した環海経済開発区、即墨経済開発
区には用意されていた(図表19)。即墨経済
開発区の賃貸工場は、1m2当たり年間70元、
空き地は1m2当たり年間1ドル(約7元)であ
る。工場スペースとは別に空き地の使用料が
徴収されるのが山東省の特徴である。
08年、山東省は北京五輪の影響で電力危
機となった。05年までの電力危機は発電所
の発電能力の不足によったが、08年は石炭
不足であり、これまでと様相が違っている。
石炭価格の高騰により、発電しても採算が
とれないことから、発電量を絞っていたと見
られる。突然の停電による精密機器の破損や
食品産業における冷凍冷蔵庫の停止による原
材料や冷凍食品(製品)の品質低下等の被害
が出た模様である。時期的には5~7月であ
り、特に7月が酷かったが、現在は改善して
いるようである。
2.雇用状況
青島市では、韓国企業の撤退が増加してい
るが、08年1月1日から労働契約法が施行さ
れ企業運営が難しくなったことが大きく影響
しているようである。一方、日系企業におい
ては①退職願の徴求、②退職時における引継
の実施、③パート労働者との契約書作成等後
日トラブルとならないよう対策がとられてお
り、訪問先においては大きな問題は生じてい
なかった。
そうは言っても、日系企業の賃金は、最低
賃金プラスαという構図ができており、青島
市でも、他の都市同様に1~2年で最低賃金
が改定されるため、賃金上昇は避けられない
状況にある(図表20)。また、労働契約法の
施行に伴い、退職時の経済補償金支払が義務
化されたこと等により、毎年20%程度の人件
費上昇を見込む企業が多かった。
さらに、地元政府からは工会(法令に定め
られたいわゆる労働組合)の設置について指
導があり、工会もしくは従業員会を設置する
企業が増えている状況にある。
韓国企業の撤退のほか、調査後、世界的不
図表19 即墨経済開発区外商投資企業服務中心(ワンステップサービスセンター)
図表20 青島市の最低賃金対象地域 02.10.1 05.1.1 06.10.1 08.1.1
青島市7区(市南区、市北区、四方区、李滄区、山区、黄島区、城陽区) 410元 530元 610元 760元
青島市5市(膠州市、即墨市、平度市、膠南市、莱西市) 380元 470元 540元 620元
(備考 )社会保障行政管理部門資料にもとづき作成

72 信金中金月報 2009.3
況の影響がさらに大きくなっており、雇用の
需給関係は改善していると見られ、ワーカー
の求人は比較的容易と見られる。一般的に、
不況下においては、離職率が低下する傾向に
あり、景気が上向くにつれて離職率が上昇し
てくることとなる。このような雇用側が有利
な状況において、優秀な人材を抱え込み、自
社に定着させることが、今後の発展の鍵にな
ると思われる。

信金中金だより 73
信金中金だより
平尾光司総合研究所長が専修大学で最終講義を行う
信金中央金庫
総合研究所
2009年1月8日(木)に、専修大学経済学部教授の平尾光司総合研究所長(非常勤)が同大学を定年退官する
ことに伴い、最終講義を行った。
平尾所長は、1961年3月に一橋大学社会学部を卒業、同年4月に日本長期信用銀行に入行、調査部やニュー
ヨーク支店等の勤務を経て、同行副頭取、長銀総合研究所社長を歴任し、2002年4月に専修大学経済学部教授、
2008年6月に本中金総合研究所長に就任した。
専修大学経済学部では、中堅企業論を専門分野に研究・教育に携わってきたが、今般、定年退官することに
伴い、同大学生田校舎において、「ベンチャー・中小・中堅企業の研究軌跡-イノベーション・企業成長・地
域・金融システム-」と題して最終講義を行い、多数の聴講生が出席した。
最終講義では、中小企業論への関心の契機、日本長期信用銀行入行時に配属された調査部時代の思い出、調
査部で担当した自動車部品産業、アメリカ留学時の産業組織論の研究、ベンチャー・ビジネスの研究、中堅企
業の成長要因分析調査、川崎市の地域イノベーション戦略提言など、研究の軌跡が語られた。
最後に、今後の研究活動について、「信金中金総合研究所所長として、また、神奈川県川崎市を拠点に、ライ
フワークであるベンチャー・中堅・中小企業および地域経済活性化の研究を続けたい」と、抱負が述べられた。
なお、平尾所長は、2009年4月以降、常勤で本中金総合研究所長として勤務することとなっている。

74 信金中金月報 2009.3
日本中小企業学会全国大会国際交流セッション講演抄録信金中央金庫
総合研究所
共通演題「地域再生と中小企業、大学」 2008年9月13日(土)から14日(日)にかけて、
日本中小企業学会第28回全国大会が北海道大学 札
幌キャンパスにて開催された。大会の統一論題と
して「中小企業と地域再生」が掲げられる一方、
13日午後には「地域再生と中小企業、大学」とい
う共通演題のものとで、国際交流セッション(信
金中央金庫協賛)が行われた。同セッションでは、
横浜国立大学 三井逸友教授がコーディネーターと
なり、海外ゲストスピーカーとして英国バーミン
ガム大学都市地域研究センター教授のスティーブ
ン ホール氏、北海道中小企業家同友会代表理事の
守和彦氏、北海道大学教授の濱田康行氏、の3氏に
よる講演が行われた。以下、講演内容について紹
介する。
本講演では、英国(イギリス)中部のウェスト
ミッドランズ(WM)地域における宝飾品産業と自
動車産業という2つの産業における、中小企業と政
策当局が抱える課題や問題点などについてのケース
スタディを提供したい。
1.ウエストミッドランズ(WM)地域について
イギリスのイングランド中央部に位置するWM地
域は、総人口230万人を擁する大都市圏で、その中
心に位置するバーミンガム市は、首都ロンドンの北
西200kmに位置する人口100万人の都市である。バー
ミンガムを中心とするWMは、19世紀の産業革命の
講演1:「中小企業と地域再生 -英国ウェストミッドランズにおける宝飾品業と自動車産業の事例研究-」
バーミンガム大学ビジネススクール 都市地域研究センター教授
Stephen HALL(スティーブン・ホール)氏

信金中金だより 75
中心地域としても栄え、熟練労働者による小企業中
心の産業構造が形成されてきた地域である。
1960年代初頭のWM地域の雇用の65%は、自動車
産業を中心とした製造業で占められ、イギリス全体
のなかでも相対的に高い就業率と賃金率を謳歌して
いた。1人当たりGDPはイギリス平均を10%上回り、
ロンドン南東部に次ぐものとなっていた。
しかし、1960年代後半以降のバーミンガムおよび
WMの各経済指標は停滞局面を迎えた。これは、①
ひとつの成熟産業(自動車産業)に依存し過ぎてい
たこと、②イノベーションに対する投資が少なかっ
たこと、③生産性向上に対する投資が低調だったこ
と、などが主因で、循環的な要因というよりは、構
造的長期的な衰退であった。1971年から1981年の10
年間で自動車産業の雇用の40%が失われ、1人当たり
GDPも1981年の時点でイギリス平均を10%下回るな
ど、WMは相対的に貧しい地域となってしまった。
しかし、その後20年間のバーミンガムは、都市ガ
バナンスの世界的な変化を反映した“起業家的”経
済発展モデルを実践し、いまや起業家的「ルネッサ
ンス(復興)」を遂げた都市の模範例(a paradigm
example of an entrepreneurial ‘renaissance’ city)と
して世界的にも知られるようになっている。バーミ
ンガムは、近年の都市中心部の旧自動車工場跡地へ
の再開発投資の結果、多様なタイプの企業の入居な
どで経済的多様化を実現し、近年の製造業の挫折と
いう嵐を乗り越えて(‘weather the storm’)、強固な
地位を確保したとされている。実際、1990年代以降
のバーミンガムでは、金融・専門サービス業や、小
売業・ホスピタリティ・レジャーを含む観光関連産
業(the ‘visitor’ economy)などの新しいサービスセ
クターが、雇用拡大をけん引しているのである。
このように、バーミンガムおよびWMは、今日に
至るまでに地域再生を遂げてきたとされているもの
の、経済状況には多くの課題も残されている。例え
ば、現在のWM地域の雇用に占める製造業の比率
(15%)は、イギリス全体の平均(11%)をわずかに
上回る程度にまで低下しており、脱工業化への転換
が成功したようにもみえる。しかし、バーミンガム
の製造業基盤は、依然として自動車産業や宝飾品産
業などの低成長部門が多くを占めており、強力で多
様化したサービス経済に基盤を置く脱工業化都市と
呼ぶにはまだ程遠いのが実情といえる。また、2007
年12月のバーミンガムの失業率(8.1%)は、主要な
イングランド都市の中で2番目に高いなど、経済状
況にはまだまだ多くの課題も残されているのが実情
といえる。
2.WMの宝飾品産業について
WMの宝飾品産業は、バーミンガム・ジュエリー・ク
オーター(BJQ:the Birmingham Jewellery Quarter)
と呼ばれる歴史のある地域に集中して立地している。
17世紀に飾り箱やアクセサリーの生産から始まった
BJQの宝飾品産業は、ビクトリア期(19世紀)を通
じて急速な発展を遂げてきた。これは、イングラン
ド富裕層の需要が拡大する一方で、英国と植民地の
独占的な関係により安価な素材の調達や製品の輸出
市場が確保されていたためである。BJQで宝飾品産
業に従事する人の数は、1825年には3,700人余に過
ぎなかったが、その後1800年までに1万4,000人、
1911年までには3万2,000人へと急拡大している。
BJQは、歴史的に中小企業が支配的な地域であ
る。1947年時点のBJQにおける全生産の60%が従業
員数10人未満の小企業によって生み出されており、
BJQはマーシャル的産業地域の古典的な典型例とさ
れてきた。垂直的に統合された生産工程は、バーミ
ンガム分析試験所(1774年)、バーミンガム造幣所
(1880年)、バーミンガムスクールオブジュエリー
(1887年)など、制度的な外部インフラにも支えら
れていた。
しかし、戦後の貴金属不足や海外の低コストの競
争相手の出現などで、BJQは衰退に直面、宝飾品産
業の熟練労働力は、自動車組立てなど賃金条件の良
い産業に吸収されていった。

76 信金中金月報 2009.3
こうしたBJQの衰退は、20世紀後半へかけて政策
当局者の関心の的となり、1997年には市場調査、ト
レンド分析、技能支援、技術移転などで宝飾品製造
業者を支援する目的で、宝飾産業イノベーションセ
ンター(JIIC)が設立された。JIICでは、宝飾品製
造業者のデザイン投資を促進するため、欧州地域開
発基金(ERDF)の補助金も受けながら、2007年ま
でに新製品デザイン(NPD)プロジェクトで1,275
社の宝飾品製造業者を支援してきた。一方、1990年
にイギリス政府によって始められた知識移転パート
ナーシップ(KTP)では、研究組織や高等教育機関
などの「知識ベース(‘knowledge base’)」と中小企
業の連携構築が図られていった。
近年のBJQでは、昔ながらの伝統的な宝飾品製造
業者が海外の低価格品との競争などで衰退する一方
で、バーミンガムスクールオブジュエリーの若い卒
業生たちから成るデザイナーメーカー(‘designer
makers’)と呼ばれるサブセクターが唯一成長してい
る。BJQには100社以上のデザイナーメーカーがあ
り、デザイン力主導で少量生産に特化、低価格攻勢
をかけてくる外国企業との棲み分けを実現している。
デザイナーメーカーに対しては、宝飾品産業の高
付加価値化を進めたい政策当局も注目している。た
とえば、バーミンガム市当局、バーミンガム市立大
学、欧州地域開発基金(ERDF)の支援を受けて
1993年に始められたデザインエクセレンスフェロー
シップ(DEF)は、小規模で資金調達を一般銀行か
らの融資に依存していることの多いBJQのデザイ
ナーメーカーの発展を期したものであった。
ところで、デザイナーメーカーがBJQに立地する
理由としては、①サプライヤとの近接性(92%が地
域内の外業労働者を相互にサプライヤとして活用)、
②市当局所有の建物のテナント料の安さ(半分以上
を市当局が所有)、③デザイナーメーカー同士の
「コミュニティ」の存在(60%のデザイナーメーカー
が他社と設備等を共有)、などがあげられる。ちな
みに、BJQのデザイナーメーカーのうち、本業で十
分な収入を得ているのは80%にとどまり、残りの
20%は、人に教えたり他社の外業労働者として働く
ことで収入を補っている。デザイナーメーカーの
67%は将来的に人を雇用したいという意向を有して
いるが、現実には事業計画に則った成長戦略などが
あるわけではない。
BJQは、ユニークな歴史的景観を有すると同時
に、立地条件が都市中心部ということもあり、近年
では宝飾品産業とは無関係な商業関連あるいは住宅
関連の投資先として多大な再開発ポテンシャルを有
する魅力的な存在でもある。しかし、こうした状況
は地価高騰を招きかねないことに加え、宝飾品産業
と両立し得ないような用途が近隣に広がっていって
しまうという点で、内生的な宝飾品産業にとっては
重大な問題といえる。
BJQは、高密度で多様な用途発展を遂げてきた地域
として、1998年には「都市ビレッジ(‘urban village’)」
に指定され、地域のポテンシャル活用に焦点を当て
た地域計画が提起された。しかし、この地域計画
は、宝飾品産業に対して何らかの優先権を与えるよ
うなものではなく、住宅開発規制の緩和などによっ
て居住人口を10倍化して5,000人とするなどの内容
を提起するものであった。こうしたなかで、2002年
に入りBJQは保存地区(‘Conservation Area’)に指
定された。これは、表面上は近隣の歴史的景観を保
護するというものであったが、実際は、投機的な住
宅開発投資を阻止することで、宝飾品産業を地価高
騰から守るものでもあった。なお、最近において
は、地域ビジョンとしてBJQを宝飾品生産の中心地
として確立していくことが明示されるに至ってお
り、2010年へ向けてBJQは地域の創造的ビレッジ
(the region’s creative village)となっていくものと
考えられる。
なお、以下では、BJQの直面している課題につい
て、伝統的な宝飾品製造業者、デザイナーメー
カー、地域の3者それぞれの立場から検討してみた。
まず、伝統的な宝飾品製造業者が今後も生き残っ

信金中金だより 77
ていくためには、高付加価値化のための投資をして
いく以外の選択肢はないと思われる。共同的集団的
な行動ではもはや衰退を食い止められないというこ
とは彼ら自身も認識しており、BJQの伝統的な宝飾
品製造業は「成熟した」クラスターともいえる。
次に、デザイナーメーカーは、地域政策当局の強
力な支援を受けているものの、低賃金でキャッシュ
不足という問題は残されている。デザイナーメー
カーの多くは、事業よりも芸術家的な部分に関心が
あり、人に教えたり人の外業労働者として働くこと
で収入不足を補うなど、事業的には不安定な存在で
ある。今後のデザイナーメーカーは、地域再生の第
1次的な原動力になっていくというよりは、ゆっく
りとした合同化が進展していくものと思われる。
最後に、地域としてのBJQの再活性化という面か
らいえば、宝飾品産業の繁栄を持続させていくこと
が中心であると考えるのが標準的な見方であろう。
BJQを再活性化させるために、商業地あるいは住宅
地として開発していく動きもあるが、こうした動き
を通じた資産価値高騰は、地域に根ざす宝飾品製造
業者の存続を脅かす危険もはらんでいる。宝飾品製
造業者にとっては、地域内に新しくできる小売業ア
ウトレットに関心はなく、むしろ地域内の中小企業
間の希少材料流通に何らかのリスクをもたらすもの
と認識するかもしれない。一方、新しい住民からす
れば、既存の宝飾品製造業者による騒音や汚染に被
害を感じるようなことがあるかもしれないのである。
3.WMの自動車産業について
次に、WMの自動車産業について、サプライ
チェーンを構成する中小企業に対する政策当局の課
題と併せて示したい。
イギリスの自動車産業の経済規模は、GDPの0.8%、
製造業GDPに限れば6.2%、製造品輸出に占める割合
は11%に及んでいる。2006年の生産規模は乗用車で
約140万台(うち輸出用が77%)、商用車で約20万台
(同66%)であるが、イギリス全体としての自動車分
野は輸入超となっている。なお、イギリスの自動車
産業は、およそ3,300社の企業群で構成され、2005
年時点でも21万人を雇用する一大産業である。
現在のWM地域の自動車製造業は、生産台数ベー
スでイギリス全体の18%を占める。雇用規模では、
1971年当時で約14万6,000人にも達していたが、近
年の大規模な工場閉鎖(2005年のMGローバー、
2006年のプジョー)などにより、現在では約5万
3,000人程度にまで減少している。これら大規模工
場閉鎖の動きは、100年以上に及ぶWMの量産型自
動車生産の終末を告げるものであった。
現在のWMの自動車産業は、地域経済に依存する
中小企業が多くを占め、スポーツカーやタクシーな
どのニッチな自動車分野への専門特化などを通じ
て、いまや少量・高付加価値型の生産を指向する産
業へと変貌している。
一般に、自動車産業は成熟産業としてイノベー
ティブではない業界というレッテルを貼られること
もあるが、EU全体で見てもR&I投資の水準は相応
に高く、多様な技術分野の統合などを指向したイノ
ベーションが図られている。こうしたなかで、WM
の自動車産業は、全世界へ向けて付加価値の高いエ
ンジニアリングデザインを提供する国際的プレイ
ヤー(Zytek、MIRA、Pro-Driveなど)を中心に活
況を呈している面もあるが、強い立場にある1次サ
プライヤーが、概してイノベーション不足にあるサ
プライチェーンの下位に位置する中小企業に対して
もイノベーションを求めており、こうしたプレッ
シャーへの対応が、WMの中小自動車製造業者の重
要課題となっている。
なお、WMの自動車産業クラスターは、3つのタイ
プに類型化できるといわれている。すなわち、①小
規模企業中心でイノベーションの力も限られる「純
粋集積型(pure agglomeration、全体の約30%)」、②
サプライチェーンの中流あたりに位置する「産業コ
ンプレックス型(industrial complex、同45%)」、③
ネットワーク力でイノベーションへも高度に取り組

78 信金中金月報 2009.3
みながらポジティブな未来像を抱いている「社会的
ネットワークモデル型(social network model、同
25%)」、の3つである。
自動車産業のサプライチェーンを構成する中小企
業を支援する政策として、1996年に創設された「ア
クセルレイト(‘ACCELERATE’)」という政策ツー
ルがある。「アクセルレイト」では、企業間の連携
を推進する「ネットワークフォーチェンジ(NfC)」
や、製造工程改善やリーン生産方式を目指す「ビジ
ネスデベロップメント助成金(BDG)」など7つの政
策支援ツールが用意されていた。
バーミンガム大学都市地域研究センター(CURS)
では、この「アクセルレイト」の評価を受託し、
フォローアップ調査を実施した。「アクセルレイト」
による地域経済全般へのマクロ的、全体的なインパ
クトの評価は困難であるが、MGローバー、プ
ジョーと大規模工場閉鎖が続いたなかで、閉鎖に追
い込まれた中小企業が少なかったという事実もあ
り、「アクセルレイト」には相応の成果もみられた
といえる。
イギリスの自動車産業は、新自由主義的な、いわ
ゆる「アングロサクソンモデル」に影響を受け、長
期的な投資や雇用よりも、短期的な株主価値を重視
していたといわれることが多い。こうしたなかで、
WMの自動車産業を構成するサプライチェーン内の
中小企業は、依然として大量かつ低付加価値な生産
のパターンへ依存したままであるケースが多く、価
格競争力は非常に弱い。このように、WMの中小企
業におけるイノベーションへの取組みが十分な成果
を残せていない原因のひとつは、投資資金の不足に
あると思われる。
4.結論
これまで示してきたWMの宝飾品産業と自動車産
業が直面しているさまざまな問題は、イギリスの中
小企業全般が直面している問題とも共通するもので
ある。
WMの伝統的な宝飾品産業と自動車サプライ
チェーンの多くは、海外企業との低価格競争激化へ
の対応として、高付加価値生産へのイノベーション
と投資が必要という、いわば教科書的な実例
(‘textbook examples’)といえる。
一方、WMの宝飾品産業におけるデザイナーメー
カーは、地域の経済と雇用の成長の原動力になって
いくという展望には乏しく、商業的な活性化策を進
めたい政策当局者たちの思惑と、芸術家的部分が動
機付けとなるデザイナーメーカーの関心とのギャッ
プは依然として大きいという問題を残している。ま
た、世界レベルにある自動車デザインエンジニアリ
ング部門においても、その競争力向上の局面で、
WM地域のサプライチェーンにおけるイノベーショ
ンのポテンシャルが十分に活用されていないことも
問題であろう。
これらの事例から見出すことのできる政策当局の
責務と課題としては、WMにおいて何世代にもわ
たって蓄積されてきた宝飾品産業および自動車産業
の能力と専門性の確固たる源泉をどのように活かし
ていけばよいのか、という点にあると考えられる。

信金中金だより 79
本講演では、厳しさを増す北海道経済の現状と、
北海道中小企業家同友会の活動などについて紹介し
たい。
中小企業家同友会とは、中小企業経営者が自主的
に参加して運営していく任意団体である。さらに、
全国47都道府県の同友会による協議体として、中小
企業家同友会全国協議会(中同協)が組織されてい
る。1969年設立当時に5同友会、640社で結成された
中同協は、現在では全国47都道府県の同友会で4万
1,000社が加盟する全国的な組織となっている。
1969年に設立された北海道中小企業家同友会(以
下、「北海道同友会」という。)も、設立当時は会員
数30社に過ぎなかったものが、現在では道内12支部
で会員総数5,078社(全国シェアで約7%)を擁する
組織となっている。
北海道同友会では、経営力を養うため、①良い会
社を作る、②良い経営者になる、③良い経営環境を
作る、という3つの目的を掲げ、中小企業の頼みに
なるブレーンとなるべく、合同企業説明会、新入社
員研修、営業マンのパワーアップ講座などのさまざ
まな経営支援活動を、補助金なしの手弁当で、随
時、開催している。
北海道経済の現状を、日銀札幌支店作成の調査レ
ポート「最近10年間の動きからみた北海道経済」
(2007年11月)から概観すると、2000年代半ばの全
国的な景気回復傾向に対し、2003年あたりを契機と
して北海道経済が相対的に大きく後れをとっている
傾向を見て取ることができる。なお、観光関連の指
標については唯一、比較的健闘している状況がみら
れ、北海道経済にとっての数少ない明るい材料と
なっている。
こうしたなかで、北海道同友会では、昨今の原
油・原材料価格の高騰が中小企業の経営を圧迫して
いる状況を探るため、2008年夏に緊急アンケート調
査を実施した。わずか10日間で1,313社の会員企業
より回答を得ることができ、この調査結果を踏まえ
た北海道同友会としての緊急要望を公表した。短期
間でこうした貴重なデータを集めることができるの
は、同友会の強みのひとつといえる。
地域活性化に取り組む会員企業の最近の具体的な
取組みのひとつとして、農商工連携の動きをあげる
ことができる。2008年春に公表された経済産業省と
農林水産省の「農商工連携88選」では、北海道から
は「ITを活用した酪農用自動給餌システムの開発」
や「建設業のハーブビジネス事業参入」など7件が
採択されたが、うち6件は北海道同友会の会員が中
心となった事例である。北海道の中小企業にとって
の農商工連携は、ある意味すでにあたりまえのこと
ともいえる。
最後に、中小企業憲章と中小企業振興基本条例制
定運動の展開についても紹介したい。中小企業憲章
とは、経済・社会・文化や国民生活における中小企
業・自営業の役割を正当に評価し、豊かな国づくり
の柱に据えることを国として決議し、憲章の精神を
実現するために、諸法令を整備・充実させる道筋を
示すものである。EUではすでに、2000年に「ヨー
ロッパ小企業憲章」を制定し、EU経済の中核に中
小企業を位置付けている状況があることから、同友
会では、日本版の中小企業憲章の制定を広く国民に
呼びかけるとともに、併せて地域経済活性化を促す
「中小企業振興基本条例」の制定を全国の自治体に
呼びかけているところである。
こうしたなかで、北海道帯広市では、北海道同友
講演2:「北海道の地域再生と同友会」
北海道中小企業家同友会 代表理事
守 和彦氏

80 信金中金月報 2009.3
会の帯広支部が中心となりこの振興条例を制定する
動きが具体的に進展し、2007年3月には「帯広市中
小企業振興基本条例」が帯広市議会で決議するに
至った。この振興条例制定後のエンジンとして設置
された「帯広市中小企業振興協議会」は、2008年8
月、帯広市長に対して中小企業振興に関する提言書
を提出した。このように、同友会では中小企業の経
営環境作りと地域経済活性化へ向けての活動を精力
的かつ継続的に実施していることを、この機会にぜ
ひともご理解願いたい。

信金中金だより 81
本講演では、国際交流セッションの共通演題であ
る「地域再生と中小企業、大学」に関連して、開催
校の大会準備委員長の立場も踏まえつつ、大学発ベ
ンチャーの動きを中心に総括させていただきたい。
2001年に発表された通称・平沼プラン「大学発ベ
ンチャー1,000社計画」を受けて誕生した、いわゆる
大学発ベンチャーは、直近の経済産業省発表(2008
年8月)によれば、07年度末でバイオ系やIT系を中
心に1,700社を超えたと伝えられている。一見、政
策目標を順調にクリアしてきているようにも見える
わけであるが、その内実には厳しいものがあるのが
実態だ。すなわち、1社当たりの平均赤字額は5,000
万円を超え、IPOも極めて少なく(2008年に至って
はゼロ)、人材確保、資金調達、販路開拓などが依
然として大きな問題点であると挙げられている。
大学サイドとしては、平沼プランに“悪乗り”し
てきたような面があることが反省点として挙げられ
る。すなわち、多くの大学発ベンチャーが、文部科
学省(旧・科学技術庁)からの補助金獲得を意図し
て設立されてきた面があった一方で、実は経営者が
いなかった(大学の教員は経営が不得手だった)、
という点が見落とされていた、と指摘できよう。
その一方で、前向きに評価できる点もある。たと
えば、地方圏における大学発ベンチャーの数は2007
年度末で909社と、2001年度末の261社に比べ約3.5
倍に増加するなど、地方大学の努力等によって大学
発ベンチャーの動きが着実に地方圏にも広がってい
る点は評価できよう。
また、大学発ベンチャーを巡る新しい流れとして
は、大学の同窓会やOB会などがそのネットワーク
力を活かして当該大学発のベンチャーを応援する
(例えば大企業役員もしくはその経験者である大学
OBが大学発ベンチャーの販路開拓を支援するな
ど)、といった動きもある。
なお、これまでの大学発ベンチャーは、“大学発”
にこだわりすぎていた面があったのではないだろう
か。大学の教員は経営が不得手、という現実も踏ま
えれば、今後は中小企業経営者に対して大学が技術
協力していくようなスタイル、いわば“中小企業
発”の大学発ベンチャーという方向についても、
もっと視野に入れていった方がよいと思われる。大
学が出資機能を持ち少数株主として経営参加できる
ようにしていくことも検討に値しよう。また、大学
発ベンチャーは、イメージ的に“理系の話”として
捉えられがちであるが、ビジネススクールなども含
めてもっと文系学部が参加するケースもあってよい
ものと思われる。
ちなみに、北海道における大学発ベンチャーの件
数は75社で全国第6位、このうち、わが北海道大学
発のベンチャーは43社で、全国の大学の中で第11位
となっている。北海道大学では、北海道経済産業局
や読売新聞社とともに、「イノベーション集結」と
題して全国の大学発ベンチャーを対象としたフォー
ラム(ビジネスモデルコンテストやセミナーなど)
をここ北海道大学で開催するなど、経済情勢厳しい
なかでも、大学発ベンチャーの振興等へ継続的に取
り組んでいるところである。
講演3:「地域再生と中小企業、大学」
北海道大学大学院経済学研究科 教授
濱田 康行氏

82 信金中金月報 2009.3
東京都北区商業活性化支援事業調印式の開催について
信金中央金庫
総合研究所
2008年12月18日(木)に、東京都北区の城北信用金庫本部会館4階会議室にて、北区商業活性化支援事業開
始に当たっての覚書の調印式が行われた。本事業は、今後、城北信用金庫が北区商店街連合会、東京商工会議
所北支部、信金中央金庫とともに、北区内の中小商店等を支援することで北区全体の商業活性化を図ることを
目的としたものである。
調印式には、事業主体である城北信用金庫、北区商店街連合会、東京商工会議所北支部、信金中央金庫東京
営業部および総合研究所が顔を揃え、総勢12名が出席した。
式では、北区商店街連合会三浦会長(写真左から2人目)、城北信用金庫田中副理事長(写真左から3人目)、
本中金坂下東京営業部長、本中金松崎総合研究所副所長、東京商工会議所北支部加藤会長(写真右から3人
目)の順に挨拶した。その後、覚書の調印・取り交わしを行い、引き続き、東京商工会議所北支部サービス・
情報産業分科会田村会長(写真右端)よりキックオフイベントの説明がなされた。
新聞社等10社程度の取材もあり、翌日以降の新聞等に記事が掲載され、城北信用金庫の取組みが北区内や都
内に広く広報された。
2009年1月から調査をスタートし、同年9月に最終報告を行う予定としている。

信金中金だより 83
和倉温泉活性化への提言キックオフミーティング開催について
信金中央金庫
総合研究所
2009年1月19日(月)に、石川県七尾市和倉温泉の和倉温泉観光協会会議室にて、和倉温泉活性化のための
コンサルティング事業開始にあたってキックオフミーティングが行われた。本事業は、今後、のと共栄信用金
庫が地元和倉温泉観光協会、和倉温泉旅館協同組合、信金中央金庫とともに、和倉温泉の活性化支援を通じて
七尾市・能登地域の地域振興を図ることを目的としたものである。
キックオフミーティングには、本事業のために組織された和倉温泉活性化委員会メンバーと信金中央金庫北
陸支店および総合研究所等の関係者総勢24名が出席した。活性化委員会には、事業主体である和倉温泉観光協
会、和倉温泉旅館協同組合、のと共栄信用金庫だけでなく、 七尾市や七尾商工会議所も参画し、同委員会は15
名の委員で構成される。委員長には和倉温泉観光協会小田会長(写真中央)が、副委員長にはのと共栄信用金
庫大林理事長(写真右)と和倉温泉旅館協同組合大井理事長が就任した。
キックオフミーティングでは、冒頭、小田会長、大林理事長、本中金千坂北陸支店長(写真左)の挨拶が行
われた。その後、のと共栄信用金庫企業支援部芝垣次長、本中金総合研究所松崎副所長が和倉温泉活性化の支
援方法および七尾市の現状、今後の予定等を説明し、引き続き、覚書の締結・取り交わしが行われた。
新聞社、テレビ局等7社程度の取材もあり、当日のテレビ番組で放送された。さらに、翌日以降の新聞数紙
にも記事が掲載され、のと共栄信用金庫の取組みが七尾市内や石川県内に広く報じられた。
今後調査を進め、4月に中間報告、6月には最終報告を行う予定である。

84 信金中金月報 2009.3
信金中央金庫総合研究所活動状況(1月)
1.レポート等の発行
発行日 レポート分類 通巻 タ イ ト ル 執 筆 者09.1.5 内外金利・為替見通し 20-10 - 斎藤大紀09.1.7 産業企業情報 20-6 新時代の金型産業に求められる“マーケティング力”
-日本にモノ作りの現場を残すために“マーケティング力”で難局を乗り切れ-
矢澤謙一
09.1.13 貿易投資相談ニュース 165 - -09.1.14 産業企業情報 20-7 全国に広がる「バイオマスタウン」構築への取組み
-林地残材などの木質バイオマスと食品廃棄物の利活用が当面の焦点に-
澤山弘
09.1.15 中小企業景況レポート 134 10~12月期業況は急速に悪化(特別調査:平成21年の経営見通しについて)
-
09.1.15 上海通信 17 - -09.1.21 金融調査情報 20-10 恒久化後も取組み進む信用金庫の地域密着型金融
-経営改善支援には事業への助言を、一部個別取組項目は制度の改善を-
間下聡
2.講座・講演・放送等の実施
実施日 種類 タ イ ト ル 講座・講演会・番組名称 主催 講 師 等09.1.9 講演 2009年の経済見通し 職員向け勉強会 東京三協信用金庫
総合企画部斎藤大紀
09.1.15 講演 今年の経済展望 新春経済講演会 西尾信用金庫 斎藤大紀09.1.15 講演 期待高まる地域ブランド 信和会(新年会) 埼玉縣信用金庫
(岩槻支店)谷地向ゆかり
09.1.16 講演 日本経済の現状と今年度の展望 新年講演会 SEC徳丸支部(事務局:西京信用金庫徳丸支店)
斎藤大紀
09.1.16 講演 2009年(平成21年)の景況見通し-中小企業経営者の予想を中心に-
足利ロータリークラブ例会
足利ロータリークラブ(足利小山信用金庫)
藤津勝一
09.1.19 講演 保険窓販の現状と将来動向 保険窓販セミナー 共栄火災海上保険㈱ 藁品和寿09.1.20 講演 ゆうちょ銀行の営業力 業務推進委員会 但馬信用金庫 品田雄志09.1.21 講演 日本経済の現状と展望 金信会 島田信用金庫
金谷支店斎藤大紀
09.1.23 講演 日本経済の現状と金利・為替見通し 四国地区信用金庫専務・常務理事情報連絡協議会
信金中央金庫四国支店四国地区信用金庫協会
斎藤大紀
09.1.27 講演 新年の経済見通しについて 新春講演会 下野市国分寺事業所協会(足利小山信用金庫)
斎藤大紀
09.1.27 講演 保険窓販の現状と将来動向 保険窓販セミナー 共栄火災海上保険㈱ 藁品和寿09.1.29 講演 今後の日本経済の行方 工業団体合同新春交流会 熊谷市工業団体連
合会(埼玉縣信用金庫)
斎藤大紀
09.1.31 講演 経済金融・経済指標の見方(金利・為替相場・株式相場の動向から想定される事象)
若手職員向け研修 東京信用金庫 角田匠

統 計 85
1.信用金庫統計(1)信用金庫の主要勘定概況 …………85(2)信用金庫の店舗数、合併等 ………87(3)信用金庫の預金種類別預金、地区別預金 ……88(4)信用金庫の預金者別預金 …………89(5)信用金庫の科目別貸出金、地区別貸出金 ……90(6)信用金庫の貸出先別貸出金 ………91(7)信用金庫の余裕資金運用状況 ……92
2.金融機関業態別統計(1)業態別預貯金等 ……………………93(2)業態別貸出金 ………………………94
統 計
統計資料の照会先:信金中央金庫総合研究所Tel 03-5202-7671 Fax 03-3278-7048
(凡 例)1.金額は、単位未満切捨てとした。2.比率は、原則として小数点以下第1位までとし第2位以下切捨てとした。3.記号・符号表示は次のとおり。 〔 0〕ゼロまたは単位未満の計数 〔̶〕該当計数なし 〔△〕減少または負 〔…〕不詳または算出不能 〔*〕1,000%以上の増加率 〔p〕速報数字 〔r〕訂正数字 〔b〕b印までの数字と次期以降との数字は不連続4.地区別統計における地区のうち、関東には山梨、長野、新潟を含む。東海は静岡、愛知、岐阜、三重の4県、九州北部は福岡、佐賀、長崎の3県、南九州は熊本、大分、宮崎、鹿児島の4県である。
※ 信金中金総合研究所のホームページ(http://www.scbri.jp/)よりExcel形式の統計資料をダウンロードすることができます。
1.(1)信用金庫の主要勘定概況○預 金 12月の全国信用金庫の預金は、月中1兆4,739億円、1.2%増と、前年同月(1兆9,355億円、1.7%増)と同様に増加した。① 要求払預金は、年金振込金の滞留やボーナス預金の受入れ、月末休日による残高高どまり等から、月中1兆256億円、2.6%増と、前年同月(1兆1,803億円、3.0%増)と同様に増加した。
② 定期性預金は、満期到来の増加や公金預金の流出等がみられたものの、ボーナス預金の受入れや預金増強キャンペーンの実施等から、月中4,456億円、0.5%増と、前年同月(7,989億円、1.0%増)と同様に増加した。
③ 外貨預金等は、月中25億円、0.7%増加した。 なお、2008年12月末の預金の前年同月比増減率は、1.4%増となった。
○貸出金 貸出金は、月中1兆260億円、1.6%増と、前年同月(8,818億円、1.4%増)と同様に増加した。① 割引手形は、季節的要因による持込手形の増加や月末休日による商手決済の翌月へのズレ込み等から、月中540億円、3.2%増と、前年同月(2,956億円、17.9%増)と同様に増加した。
② 貸付金は、ボーナス支払資金等季節的な資金需要および経常運転資金の増加、月末休日による回収分の翌月へのズレ込みや特別融資の実施等から、月中9,720億円、1.5%増と、前年同月(5,861億円、0.9%増)と同様に増加した。
なお、2008年12月末の貸出金の前年同月比増減率は、1.6%増となった。
○余資運用資産 余資運用資産は、月中4,322億円、0.7%増と、前年同月(1兆817億円、1.9%増)と同様に増加した。 主な内訳をみると、預け金は、月中5,758億円、2.6%増となった。 コールローンは、月中1,297億円、15.3%減となった。 有価証券は、社債(813億円増)、短期社債(590億円増)、株式(113億円増)等が増加したものの、国債(3,377億円減)、外国証券(162億円減)等が減少したことから、月中2,199億円、0.6%減となった。

86 信金中金月報 2009.3
信用金庫の主要勘定増減状況(2008年12月末) (単位:百万円、%)
区 分 残 高前月比増減 前年同月比
増 減 率
前 年 同 月
増 減 額 増 減 率 月中増減額 月中増減率前年同月比増 減 率
資
産
項
目
現 金 1,768,093 182,562 11.5 7.3 118,943 7.7 △ 1.9(小 切 手 ・ 手 形) ( 221,422 )( 9,503 )( 4.4 )(△ 21.7 )( 140,739 )( 98.9 )(△ 1.6 )
預 け 金 22,166,055 575,804 2.6 0.0 721,301 3.3 7.9(信 金 中 金 預 け 金) ( 19,412,256 )( 415,747 )( 2.1 )(△ 1.4 )( 567,836 )( 2.9 )( 6.5 )(譲 渡 性 預 け 金) ( 167,481 )( 6,500 )( 4.0 )( 81.0 )( 10,000 )( 12.1 )( 77.8 )
買 入 手 形 0 0 ― ― 0 ― ―コ ー ル ロ ー ン 714,830 △ 129,730 △ 15.3 △ 33.8 168,794 18.5 34.8買 現 先 勘 定 0 0 ― ― 0 ― ―債券貸借取引支払保証金 30,561 14,839 94.3 1.8 0 0.0 9.0買 入 金 銭 債 権 303,656 17,779 6.2 △ 0.8 21,216 7.4 △ 5.8金 銭 の 信 託 241,595 △ 8,508 △ 3.4 △ 22.5 △ 1,502 △ 0.4 △ 3.5商 品 有 価 証 券 4,171 △ 593 △ 12.4 △ 3.6 △ 650 △ 13.0 △ 35.5有 価 証 券 33,006,866 △ 219,903 △ 0.6 2.5 53,651 0.1 4.3国 債 9,147,289 △ 337,709 △ 3.5 △ 1.8 △ 35,038 △ 0.3 3.6地 方 債 3,729,782 △ 9,997 △ 0.2 5.4 23,328 0.6 2.4短 期 社 債 154,675 59,002 61.6 77.8 35,968 70.5 60.6社 債 12,984,054 81,375 0.6 7.2 37,018 0.3 2.9株 式 878,762 11,332 1.3 1.5 4,606 0.5 17.5貸 付 信 託 3 0 0.0 0.0 0 0.0 △ 88.4投 資 信 託 996,090 △ 7,863 △ 0.7 △ 7.0 6,410 0.6 20.1外 国 証 券 4,975,394 △ 16,224 △ 0.3 △ 1.4 △ 19,715 △ 0.3 5.1そ の 他 の 証 券 140,813 181 0.1 7.0 1,075 0.8 △ 0.3
小 計 58,235,832 432,250 0.7 0.9 1,081,752 1.9 5.8貸 出 金 64,901,864 1,026,020 1.6 1.6 881,824 1.4 0.1(月 中 平 残) ( 63,925,819 )( 483,626 )( 0.7 )( 1.3 )( 359,408 )( 0.5 )( 0.1 )(うち金融機関貸付金) 694,598 16,007 2.3 52.2 2,307 0.5 36.7割 引 手 形 1,732,277 54,001 3.2 △ 10.7 295,634 17.9 △ 7.3貸 付 金 63,169,586 972,019 1.5 2.0 586,189 0.9 0.3手 形 貸 付 5,709,607 107,950 1.9 △ 6.4 177,955 3.0 △ 4.7証 書 貸 付 54,433,070 846,336 1.5 3.1 393,931 0.7 0.9当 座 貸 越 3,026,908 17,733 0.5 0.3 14,304 0.4 0.4
負
債
項
目
預 金 ・ 積 金 116,484,545 1,473,918 1.2 1.4 1,935,538 1.7 2.6(月 中 平 残) ( 114,947,949 )( 640,692 )( 0.5 )( 1.3 )( 898,330 )( 0.7 )( 2.6 )要 求 払 預 金 39,394,349 1,025,698 2.6 0.2 1,180,325 3.0 0.5当 座 預 金 2,775,821 219,634 8.5 △ 2.5 421,689 17.3 △ 5.1普 通 預 金 34,547,242 822,061 2.4 0.8 878,247 2.6 0.9貯 蓄 預 金 1,121,639 △ 716 △ 0.0 △ 4.5 716 0.0 △ 3.7通 知 預 金 229,312 22,757 11.0 12.6 36,656 21.9 △ 9.1別 段 預 金 684,279 △ 35,740 △ 4.9 △ 10.8 △ 157,434 △ 17.0 12.8納 税 準 備 預 金 36,054 △ 2,297 △ 5.9 △ 1.8 451 1.2 △ 2.7定 期 性 預 金 76,722,189 445,643 0.5 2.1 798,933 1.0 3.8定 期 預 金 71,069,628 542,462 0.7 2.3 900,112 1.3 4.5定 期 積 金 5,652,559 △ 96,821 △ 1.6 △ 0.7 △ 101,179 △ 1.7 △ 3.8外 貨 預 金 等 368,006 2,578 0.7 △ 23.1 △ 43,720 △ 8.3 0.2実 質 預 金 116,263,122 1,464,414 1.2 1.4 1,794,799 1.5 2.6譲 渡 性 預 金 95,363 △ 10,572 △ 9.9 1.5 △ 6,852 △ 6.7 △ 22.8借 用 金 284,416 △ 13,047 △ 4.3 20.8 15,427 7.0 42.1
預 貸 率 55.6
純
資
産
項
目
純 資 産 6,424,691 297 0.0 1.1 278 0.0 4.1出 資 金 712,087 516 0.0 2.8 253 0.0 1.9普 通 出 資 金 619,772 516 0.0 1.4 253 0.0 0.7優 先 出 資 金 92,315 0 0.0 13.4 0 0.0 11.8優 先出資申込証拠金 0 0 ― ― 0 ― ―資 本 剰 余 金 49,334 0 0.0 19.5 0 0.0 22.1資 本 準 備 金 49,334 0 0.0 19.5 0 0.0 22.1そ の 他 資 本 剰 余 金 0 0 ― ― 0 ― ―利 益 剰 余 金 5,508,073 2 0.0 1.0 0 0.0 4.5利 益 準 備 金 418,821 0 0.0 2.5 0 0.0 4.8そ の 他 利 益 剰 余 金 5,089,251 2 0.0 0.8 0 0.0 4.5特 別 積 立 金 4,916,941 0 0.0 0.8 0 0.0 4.4前 期 繰 越 金 171,673 0 0.0 1.5 0 0.0 6.9未 処 分 剰 余 金 636 2 0.3 △ 0.6 0 0.0 79.7
処 分 未 済 持 分 △ 684 28 ― ― 24 ― ―自 己 優 先 出 資 0 0 ― ― 0 ― ―自己優先出資申込証拠金 0 0 ― ― 0 ― ―その他有価証券評価差額金 △ 245 △ 245 ― ― 0 ― ―繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △ 1,729 0 ― △ 351.6 0 0.0 △ 75.1土 地 再 評 価 差 額 金 157,854 △ 4 △ 0.0 △ 2.5 0 0.0 △ 2.3
(備考)預貸率=貸出金/預金・積金×100(預金には譲渡性預金を含む。)

統 計 87
1.(2)信用金庫の店舗数、合併等
(単位:店、人)
年 月 末店 舗 数
会 員 数常 勤 役 職 員 数
本 店(信用金庫数) 支 店 出張所 合 計 常勤役員 職 員 合 計男 子 女 子 計
2004. 3 306 7,471 282 8,059 9,091,805 2,396 84,345 35,051 119,396 121,79205. 3 298 7,312 269 7,879 9,134,192 2,342 81,431 33,342 114,773 117,11506. 3 292 7,195 290 7,777 9,191,407 2,272 79,286 32,080 111,366 113,63807. 3 287 7,172 275 7,734 9,256,033 2,292 77,908 32,165 110,073 112,3656 287 7,170 273 7,730 9,274,473 2,315 79,863 35,166 115,029 117,3449 287 7,160 272 7,719 9,275,967 2,324 79,093 34,435 113,528 115,852
07. 12 284 7,136 273 7,693 9,278,117 2,315 78,496 33,984 112,480 114,79508. 1 282 7,140 276 7,698 9,286,820 2,307 78,254 33,845 112,099 114,4062 282 7,131 278 7,691 9,288,786 2,307 78,056 33,701 111,757 114,0643 281 7,128 278 7,687 9,278,994 2,298 77,110 33,065 110,175 112,4734 281 7,127 273 7,681 9,282,133 2,297 80,055 36,933 116,988 119,2855 280 7,127 273 7,680 9,286,428 2,289 79,907 36,873 116,780 119,0696 280 7,130 273 7,683 9,290,161 2,307 79,405 36,589 115,994 118,3017 279 7,131 275 7,685 9,289,874 2,304 79,206 36,386 115,592 117,8968 279 7,131 275 7,685 9,290,604 2,304 79,009 36,200 115,209 117,5139 279 7,126 274 7,679 9,295,402 2,303 78,680 35,931 114,611 116,91410 279 7,123 273 7,675 9,297,746 2,303 78,531 35,863 114,394 116,69711 279 7,121 274 7,674 9,299,347 2,300 78,416 35,835 114,251 116,55112 279 7,125 274 7,678 9,301,992 2,297 78,198 35,565 113,763 116,060
信用金庫の店舗数、会員数、常勤役職員数の推移
年 月 日 異 動 金 庫 名 新金庫名 金庫数 異動の種類2004年7月12日 下関 豊浦 下関 305 合併2004年7月20日 彦根 近江八幡 滋賀中央 304 合併2004年10月12日 大阪 南大阪 大阪 303 合併2004年11月15日 大牟田 柳川 大牟田柳川 302 合併2004年11月22日 足利 小山 足利小山 301 合併2005年1月4日 伊勢崎太田 アイオー 301 名称変更2005年2月14日 北海 古平 北海 300 合併2005年2月14日 阪奈 八光 大阪東 299 合併2005年3月14日 (大分県信組) 杵築 (大分県信組) 298 合併・解散2005年7月19日 仙台 塩竈 杜の都 297 合併2005年10月17日 高鍋 西諸 高鍋 296 合併2005年11月21日 新川水橋 滑川 にいかわ 295 合併2005年11月21日 広島 大竹 広島 294 合併2006年1月10日 多摩中央 八王子 太平 多摩 292 合併2006年10月16日 三島 伊豆 三島 291 合併2006年10月16日 愛媛 三津浜 愛媛 290 合併2006年11月6日 島根中央 (出雲信組) 島根中央 290 合併2007年1月9日 下関 津和野 宇部 吉南 西中国 287 合併2007年10月9日 名寄 士別 北星 286 合併2007年11月26日 かんら ぐんま 多野 しののめ 284 合併2008年1月15日 沼津 駿河 沼津 283 合併2008年1月15日 きのくに 湯浅 きのくに 282 合併2008年1月21日 伊達 (室蘭商工信組) 伊達 282 合併2008年3月17日 鶴岡 酒田 鶴岡 281 合併2008年5月19日 八戸 十和田 八戸 280 合併2008年7月7日 盛岡 二戸 盛岡 279 合併
信用金庫の合併等

88 信金中金月報 2009.3
1.(3)信用金庫の預金種類別預金、地区別預金
(単位:億円、%)
年 月 末預金計 実質預金 譲渡性預金要求払 定期性 外貨預金等前年同月比
増 減 率前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 1,055,175 1.8 328,610 5.0 720,951 0.6 5,614 △ 13.6 1,052,971 1.9 789 223.105. 3 1,074,324 1.8 350,807 6.7 717,300 △ 0.4 6,216 10.7 1,072,219 1.8 999 26.606. 3 1,092,212 1.6 377,476 7.6 709,409 △ 1.1 5,326 △ 14.3 1,089,623 1.6 1,181 18.107. 3 1,113,772 1.9 386,576 2.4 721,712 1.7 5,483 2.9 1,110,316 1.8 998 △ 15.46 1,132,280 2.7 392,918 2.1 734,503 3.0 4,858 1.8 1,129,872 2.6 1,102 △ 29.09 1,134,180 2.5 388,420 1.0 740,559 3.2 5,200 4.1 1,131,409 2.5 1,167 △ 9.7
07. 12 1,148,722 2.6 392,923 0.5 751,013 3.8 4,785 0.2 1,145,892 2.6 939 △ 22.808. 1 1,136,221 2.7 377,900 0.3 753,610 4.0 4,711 0.9 1,134,970 2.7 816 △ 39.62 1,139,995 2.5 382,502 △ 0.1 753,199 4.1 4,293 △ 7.6 1,138,732 2.6 851 △ 23.53 1,137,275 2.1 382,240 △ 1.1 749,326 3.8 5,707 4.0 1,134,949 2.2 911 △ 8.74 1,148,256 2.0 391,112 △ 0.9 752,462 3.7 4,681 3.1 1,146,960 2.2 1,071 △ 15.35 1,144,768 2.4 384,603 0.1 755,021 3.6 5,143 2.5 1,142,596 2.3 1,067 △ 0.66 1,155,357 2.0 389,905 △ 0.7 760,497 3.5 4,954 1.9 1,154,100 2.1 1,054 △ 4.37 1,149,391 2.1 379,619 △ 0.4 765,042 3.5 4,729 △ 8.7 1,148,229 2.1 996 △ 1.48 1,156,253 2.5 385,489 0.8 766,229 3.5 4,534 △ 9.9 1,153,992 2.4 1,062 △ 0.59 1,154,026 1.7 383,904 △ 1.1 765,437 3.3 4,684 △ 9.9 1,152,387 1.8 1,027 △ 11.910 1,148,778 1.6 381,901 △ 0.6 762,741 2.8 4,136 △ 15.5 1,147,532 1.5 1,000 △ 4.511 1,150,106 1.8 383,686 0.6 762,765 2.6 3,654 △ 30.0 1,147,987 1.7 1,059 5.112 1,164,845 1.4 393,943 0.2 767,221 2.1 3,680 △ 23.1 1,162,631 1.4 953 1.5
(備考)1 .沖縄地区は全国に含めた。 2.東京・関東地区の2003年3月の増減率は、地区間の事業譲渡を調整して算出 3.南九州地区・全国の2005年3月から2006年2月までの増減率は、旧杵築信用金庫を調整して算出
預金種類別預金
(備考)1.預金計には譲渡性預金を含まない。 2.実質預金は預金計から小切手・手形を差引いたもの。 3.2005年3月から2006年2月までの増減率は、旧杵築信用金庫を調整して算出
(単位:億円、%)
年 月 末 北海道 東 北 東 京 関 東 北 陸 東 海前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 56,194 1.6 39,896 1.0 196,903 1.8 201,888 2.0 32,710 1.2 209,402 2.505. 3 57,186 1.7 40,036 0.3 200,759 1.9 205,375 1.7 33,050 1.0 213,983 2.106. 3 57,985 1.3 40,213 0.4 205,069 2.1 208,477 1.5 33,344 0.8 217,087 1.407. 3 59,138 1.9 40,258 0.1 207,952 1.4 211,889 1.6 33,765 1.2 221,464 2.06 59,911 2.1 41,131 0.8 210,840 2.4 215,468 2.4 34,319 2.0 224,034 2.49 59,917 1.9 40,999 0.5 211,311 2.1 215,626 2.2 34,207 1.8 224,847 2.5
07. 12 61,435 2.0 41,489 1.4 213,546 2.6 218,792 2.5 34,486 2.0 227,468 2.708. 1 60,289 3.2 41,047 1.3 211,477 2.7 216,184 2.5 34,097 2.0 225,288 2.92 60,330 3.1 41,182 1.3 212,091 2.5 217,190 2.4 34,219 2.0 225,971 2.63 59,718 0.9 40,772 1.2 211,882 1.8 216,685 2.2 34,270 1.4 226,859 2.44 61,197 2.6 41,530 1.1 213,228 1.8 218,739 2.2 34,540 1.4 228,277 2.45 60,629 2.8 41,097 1.2 213,328 2.3 217,908 2.5 34,494 2.0 227,529 2.76 61,509 2.6 41,571 1.0 214,157 1.5 220,259 2.2 34,796 1.3 229,875 2.67 60,822 2.3 41,323 1.3 212,866 1.5 219,065 2.3 34,645 1.5 229,171 2.88 61,268 2.9 41,649 1.8 213,844 1.7 220,610 2.7 35,045 2.3 230,276 3.19 61,043 1.8 41,437 1.0 213,266 0.9 220,044 2.0 34,910 2.0 230,484 2.510 60,804 2.0 41,570 1.2 212,401 0.6 219,167 1.7 34,718 2.0 228,935 2.311 61,458 2.4 41,583 1.5 212,829 0.8 219,272 2.0 34,710 2.2 229,053 2.512 62,558 1.8 41,996 1.2 215,009 0.6 222,430 1.6 35,145 1.9 231,986 1.9
地区別預金
年 月 末 近 畿 中 国 四 国 九州北部 南九州 全国計前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 205,213 1.7 50,456 0.5 18,625 2.3 18,298 1.7 24,219 1.9 1,055,175 1.805. 3 209,461 2.0 51,044 1.1 19,286 3.5 18,597 1.6 24,085 1.0 1,074,324 1.806. 3 214,393 2.3 51,229 0.3 19,914 3.2 18,916 1.7 24,078 △ 0.0 1,092,212 1.607. 3 220,845 3.0 52,842 3.1 20,731 4.1 19,220 1.6 24,173 0.3 1,113,772 1.96 225,850 3.9 53,830 4.3 21,082 3.9 19,672 1.6 24,612 0.5 1,132,280 2.79 226,859 3.3 53,539 3.9 21,255 4.1 19,697 2.3 24,506 0.8 1,134,180 2.5
07. 12 229,545 3.5 54,017 1.8 21,728 4.8 19,923 1.5 24,871 1.0 1,148,722 2.608. 1 227,414 3.3 53,294 1.2 21,655 5.4 19,650 2.2 24,427 0.8 1,136,221 2.72 227,961 3.1 53,698 1.1 21,734 5.2 19,781 1.9 24,450 1.3 1,139,995 2.53 226,819 2.7 53,292 0.8 21,775 5.0 19,492 1.4 24,313 0.5 1,137,275 2.14 228,851 2.3 53,897 0.7 21,899 5.0 19,987 1.4 24,721 0.9 1,148,256 2.05 228,527 2.5 53,515 0.9 21,879 5.0 19,884 2.4 24,599 1.4 1,144,768 2.46 230,609 2.1 54,130 0.5 22,152 5.0 20,067 2.0 24,729 0.4 1,155,357 2.07 229,912 2.2 53,641 0.6 22,069 5.0 19,909 1.7 24,535 0.8 1,149,391 2.18 231,047 2.7 54,109 1.1 22,205 4.9 20,085 2.5 24,703 1.2 1,156,253 2.59 230,832 1.7 53,927 0.7 22,179 4.3 19,939 1.2 24,550 0.1 1,154,026 1.710 229,777 1.7 53,577 0.5 22,186 4.3 19,849 1.3 24,403 △ 0.0 1,148,778 1.611 229,573 1.6 53,679 1.1 22,265 4.7 19,871 1.7 24,429 0.3 1,150,106 1.812 232,514 1.2 54,294 0.5 22,515 3.6 20,204 1.4 24,820 △ 0.2 1,164,845 1.4

統 計 89
1.(4)信用金庫の預金者別預金
(単位:億円、%)
年 月 末預金計
個人預金 要求払 定期性 外貨預金等前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 1,054,774 1.8 842,751 2.7 226,091 7.0 616,073 1.2 576 110.905. 3 1,074,223 1.8 861,039 2.2 243,198 7.5 616,915 0.1 915 58.706. 3 1,092,110 1.6 873,926 1.4 263,269 8.2 610,130 △ 1.0 515 △ 43.607. 3 1,113,482 1.9 893,616 2.2 270,825 2.8 622,333 2.0 446 △ 13.36 1,132,279 2.7 906,631 2.9 278,151 2.4 628,069 3.2 401 △ 27.99 1,134,178 2.5 906,248 3.1 271,257 1.9 634,502 3.7 479 △ 12.6
07. 12 1,148,721 2.6 924,211 3.4 277,245 1.6 646,459 4.1 497 △ 0.308. 1 1,136,220 2.7 919,757 3.4 271,034 1.5 648,167 4.2 546 21.92 1,139,993 2.5 926,594 3.4 276,754 1.0 649,300 4.4 529 22.23 1,136,980 2.1 923,693 3.3 273,708 1.0 649,352 4.3 623 39.44 1,148,254 2.0 929,928 3.2 278,512 0.7 650,771 4.3 634 44.45 1,144,766 2.4 926,450 3.5 274,004 1.7 651,779 4.2 657 53.96 1,155,355 2.0 936,139 3.2 280,480 0.8 654,992 4.2 657 63.67 1,149,390 2.1 933,028 3.3 273,339 1.2 659,018 4.2 661 60.18 1,156,251 2.5 940,314 3.6 278,917 2.0 660,733 4.2 653 41.39 1,154,025 1.7 935,618 3.2 274,030 1.0 660,905 4.1 672 40.310 1,148,777 1.6 938,376 2.9 277,498 0.8 660,126 3.8 741 56.611 1,150,104 1.8 935,763 3.0 273,835 1.5 661,201 3.6 717 36.412 1,164,844 1.4 946,838 2.4 279,208 0.7 666,857 3.1 762 53.4
(備考)1 .日本銀行 「預金現金貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(3)預金種類別・地区別預金の預金計とは一致しない。
2.2005年3月から2006年2月までの増減率は、旧杵築信用金庫を調整して算出
年 月 末 一般法人預金 公的預金要求払 定期性 外貨預金等前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 175,652 1.1 88,396 4.8 86,899 △ 2.2 349 △ 7.3 20,785 △ 6.705. 3 178,067 1.4 93,657 5.9 84,078 △ 3.1 323 △ 7.4 20,055 △ 3.406. 3 181,849 2.1 99,317 6.0 82,264 △ 2.1 259 △ 19.8 21,534 7.307. 3 186,590 2.6 102,909 3.6 83,430 1.4 242 △ 6.4 21,517 △ 0.06 185,745 3.5 102,040 4.5 83,464 2.3 233 △ 17.2 27,926 △ 1.99 188,799 0.4 104,504 △ 0.5 84,022 1.5 264 △ 0.6 26,664 4.6
07. 12 187,169 △ 0.3 103,317 △ 1.9 83,563 1.4 280 15.3 25,306 1.608. 1 177,264 △ 0.4 92,694 △ 2.1 84,250 1.3 312 34.1 27,134 3.82 175,472 △ 1.0 91,319 △ 2.8 83,836 1.0 309 31.3 26,185 2.83 180,120 △ 3.4 96,086 △ 6.6 83,703 0.3 323 33.3 21,462 △ 0.24 182,765 △ 3.3 98,417 △ 6.2 84,025 0.1 315 34.8 23,776 4.25 182,705 0.7 98,610 1.3 83,774 △ 0.0 312 36.2 24,326 △ 13.56 178,644 △ 3.8 95,012 △ 6.8 83,309 △ 0.1 314 34.8 28,649 2.57 175,931 △ 2.0 92,148 △ 3.7 83,470 △ 0.2 305 22.4 28,941 △ 5.18 178,980 0.8 95,683 2.3 82,995 △ 0.8 293 13.7 26,606 △ 10.69 179,495 △ 4.9 95,944 △ 8.1 83,232 △ 0.9 311 17.6 26,992 1.210 174,714 △ 3.2 91,771 △ 4.3 82,704 △ 2.0 230 △ 13.0 25,595 △ 3.411 179,699 0.0 98,234 2.4 81,228 △ 2.6 229 △ 24.2 25,544 △ 10.012 184,107 △ 1.6 103,301 △ 0.0 80,561 △ 3.5 236 △ 15.5 24,379 △ 3.6
年 月 末 譲渡性預金金融機関預金 政府関係預 り 金要求払 定期性 外貨預金等前年同月比
増 減 率前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 9,929 △ 15.8 10,554 1.8 298 152.7 15,579 △ 18.9 0 78905. 3 10,292 3.7 9,410 △ 10.8 349 17.2 15,055 △ 3.3 0 99906. 3 11,146 8.3 9,939 5.6 444 27.0 14,797 △ 1.7 0 1,18107. 3 10,088 △ 9.4 10,864 9.3 562 26.4 11,753 △ 20.5 0 9686 10,800 △ 15.6 17,031 9.1 91 29.1 11,970 △ 16.0 0 1,1029 10,041 △ 2.8 16,210 7.9 409 235.5 12,461 △ 13.5 0 1,167
07. 12 9,918 △ 5.2 15,174 5.5 210 250.0 12,029 △ 2.9 0 93908. 1 11,648 △ 4.2 15,435 11.1 47 △ 37.8 12,060 △ 3.0 0 8162 11,814 △ 5.1 14,341 11.1 26 △ 69.5 11,737 △ 6.2 0 8513 9,087 △ 9.9 11,620 6.9 752 33.8 11,700 △ 0.4 0 9114 11,285 4.6 12,449 4.0 38 △ 28.6 11,780 △ 1.8 0 1,0715 10,064 △ 28.3 14,113 1.6 145 △ 30.4 11,280 △ 14.6 0 1,0676 11,641 7.7 16,813 △ 1.2 190 108.6 11,918 △ 0.4 0 1,0547 11,564 △ 10.4 17,132 △ 0.7 240 △ 25.8 11,484 △ 10.4 0 9968 9,244 △ 27.2 17,114 1.6 244 14.6 10,346 △ 18.4 0 1,0629 10,798 7.5 15,991 △ 1.3 199 △ 51.2 11,913 △ 4.3 0 1,02710 10,261 △ 6.8 15,229 △ 1.5 101 157.8 10,086 △ 17.7 0 1,00011 9,538 △ 24.0 15,601 △ 0.6 402 196.9 9,092 △ 30.0 0 1,05912 9,253 △ 6.7 15,062 △ 0.7 61 △ 70.6 9,514 △ 20.9 0 953

90 信金中金月報 2009.3
1.(5)信用金庫の科目別貸出金、地区別貸出金
(単位:億円、%)
年 月 末貸出金計 割引手形 貸付金 手形貸付 証書貸付 当座貸越前年同月比
増 減 率前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 622,364 △ 0.6 22,388 △ 6.9 599,975 △ 0.3 77,758 △ 8.2 490,499 1.3 31,717 △ 5.305. 3 620,948 △ 0.1 20,555 △ 8.1 600,393 0.1 71,918 △ 7.4 498,000 1.5 30,473 △ 3.806. 3 626,702 0.9 18,931 △ 7.8 607,770 1.2 67,172 △ 6.5 510,693 2.5 29,904 △ 1.807. 3 634,953 1.3 20,168 6.5 614,784 1.1 62,626 △ 6.7 522,186 2.2 29,971 0.26 629,111 1.0 19,026 4.6 610,085 0.9 58,126 △ 5.7 523,089 1.7 28,870 0.19 635,458 0.4 18,496 △ 6.2 616,962 0.6 60,102 △ 5.0 526,214 1.2 30,645 1.5
07. 12 638,374 0.1 19,403 △ 7.3 618,970 0.3 61,044 △ 4.7 527,751 0.9 30,174 0.408. 1 630,614 0.1 16,967 △ 7.3 613,646 0.4 59,595 △ 4.7 524,205 1.0 29,844 0.22 629,771 0.2 16,590 △ 6.6 613,180 0.4 59,615 △ 4.7 523,733 1.0 29,832 0.03 635,433 0.0 16,753 △ 16.9 618,680 0.6 60,234 △ 3.8 527,985 1.1 30,459 1.64 629,236 △ 0.0 15,950 △ 17.4 613,285 0.4 56,992 △ 4.8 526,896 1.0 29,396 1.45 631,662 0.9 17,672 3.2 613,990 0.9 55,238 △ 4.7 529,639 1.6 29,112 △ 0.66 630,412 0.2 15,746 △ 17.2 614,666 0.7 55,184 △ 5.0 530,132 1.3 29,349 1.67 631,570 0.6 15,563 △ 7.8 616,007 0.8 55,490 △ 5.0 531,021 1.5 29,494 0.58 633,796 0.9 16,974 3.1 616,822 0.8 55,787 △ 5.0 531,646 1.6 29,387 △ 0.59 638,492 0.4 15,285 △ 17.3 623,207 1.0 56,819 △ 5.4 535,160 1.7 31,226 1.810 635,822 1.0 15,141 △ 6.9 620,681 1.2 56,148 △ 5.0 534,485 1.9 30,047 0.911 638,758 1.4 16,782 2.0 621,975 1.4 56,016 △ 5.4 535,867 2.3 30,091 0.212 649,018 1.6 17,322 △ 10.7 631,695 2.0 57,096 △ 6.4 544,330 3.1 30,269 0.3
(備考)1 .沖縄地区は全国に含めた。 2.東京・関東地区の2003年3月の増減率は、地区間の事業譲渡を調整して算出 3.南九州地区・全国の2005年3月から2006年2月までの増減率は、旧杵築信用金庫を調整して算出
科目別貸出金
(備考)2005年3月から2006年2月までの増減率は、旧杵築信用金庫を調整して算出
(単位:億円、%)
年 月 末 北海道 東 北 東 京 関 東 北 陸 東 海前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 29,855 0.7 23,865 △ 2.2 123,525 △ 0.7 116,513 △ 0.2 18,768 △ 1.5 118,715 0.105. 3 29,999 0.4 23,463 △ 1.6 123,026 △ 0.4 117,256 0.6 18,633 △ 0.7 118,485 △ 0.106. 3 30,652 2.1 23,277 △ 0.7 123,508 0.3 118,550 1.1 18,546 △ 0.4 119,924 1.207. 3 31,012 1.1 22,849 △ 1.8 124,506 0.8 119,227 0.5 18,384 △ 0.8 122,722 2.36 29,524 △ 0.0 22,545 △ 1.1 123,681 0.1 118,264 0.6 18,253 △ 0.4 121,612 2.09 29,870 △ 0.9 22,648 △ 1.7 124,845 △ 0.1 119,466 0.2 18,362 △ 0.6 123,172 0.9
07. 12 30,215 △ 1.2 22,642 △ 1.5 125,526 △ 0.0 119,800 △ 0.0 18,418 △ 0.7 123,776 0.508. 1 29,676 △ 0.6 22,376 △ 1.7 123,983 0.0 118,522 △ 0.0 18,180 △ 0.9 122,146 0.52 29,791 △ 0.8 22,344 △ 1.8 123,680 0.0 118,430 0.0 18,128 △ 0.6 121,761 0.43 31,109 0.3 22,672 △ 0.7 123,881 △ 0.5 119,536 0.2 18,316 △ 0.3 123,155 0.34 30,241 0.6 22,258 △ 1.3 123,060 △ 0.6 118,395 0.0 18,109 △ 0.6 122,010 0.45 29,924 1.7 22,233 △ 1.2 123,406 0.5 118,701 0.6 18,213 0.1 122,748 1.56 29,723 0.6 22,273 △ 1.2 122,963 △ 0.5 118,659 0.3 18,208 △ 0.2 122,752 0.97 29,806 1.1 22,284 △ 0.8 123,091 △ 0.3 118,835 0.6 18,254 0.0 123,057 1.48 29,992 1.4 22,318 △ 0.6 123,271 △ 0.1 119,144 0.9 18,377 0.6 123,637 1.89 30,540 2.2 22,470 △ 0.7 123,303 △ 1.2 120,300 0.6 18,510 0.8 125,327 1.710 30,629 3.2 22,478 △ 0.0 122,879 △ 0.7 119,670 1.1 18,358 0.9 124,547 2.311 30,636 3.9 22,528 0.2 123,453 △ 0.3 120,061 1.5 18,434 1.4 125,318 2.812 31,384 3.8 22,715 0.3 125,809 0.2 121,719 1.6 18,652 1.2 127,407 2.9
地区別貸出金
年 月 末 近 畿 中 国 四 国 九州北部 南九州 全国計前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 122,626 △ 1.4 29,815 △ 1.0 10,800 △ 0.2 11,406 △ 1.4 15,470 △ 0.1 622,364 △ 0.605. 3 121,978 △ 0.5 29,537 △ 0.9 10,753 △ 0.4 11,364 △ 0.3 15,362 0.6 620,948 △ 0.106. 3 124,456 2.0 29,238 △ 1.0 10,631 △ 1.1 11,523 1.3 15,260 △ 0.6 626,702 0.907. 3 127,784 2.6 30,232 3.3 10,608 △ 0.2 11,566 0.3 14,963 △ 1.9 634,953 1.36 127,308 1.8 30,022 3.9 10,547 0.7 11,508 0.6 14,826 △ 1.8 629,111 1.09 128,589 1.1 30,247 3.1 10,675 1.0 11,663 △ 0.1 14,910 △ 2.0 635,458 0.4
07. 12 129,111 0.8 30,348 0.8 10,690 1.3 11,754 0.1 15,080 △ 2.3 638,374 0.108. 1 127,567 0.9 30,025 0.7 10,614 1.4 11,612 0.3 14,905 △ 2.0 630,614 0.12 127,484 1.0 30,085 1.0 10,613 1.1 11,598 0.5 14,851 △ 2.3 629,771 0.23 128,502 0.5 30,194 △ 0.1 10,684 0.7 11,709 1.2 14,652 △ 2.0 635,433 0.04 127,557 0.2 29,795 △ 0.2 10,619 0.8 11,613 0.6 14,584 △ 2.1 629,236 △ 0.05 128,406 1.7 30,014 0.5 10,692 1.4 11,696 2.4 14,616 △ 1.6 631,662 0.96 127,855 0.4 29,993 △ 0.0 10,665 1.1 11,751 2.1 14,554 △ 1.8 630,412 0.27 128,090 0.9 30,104 0.5 10,678 1.2 11,774 2.5 14,575 △ 1.2 631,570 0.68 128,577 1.2 30,275 1.1 10,712 1.4 11,851 2.9 14,620 △ 0.8 633,796 0.99 128,996 0.3 30,493 0.8 10,862 1.7 11,903 2.0 14,759 △ 1.0 638,492 0.410 128,459 1.0 30,298 1.3 10,848 2.3 11,865 2.7 14,768 △ 0.7 635,822 1.011 129,203 1.5 30,447 1.5 10,887 2.3 11,949 3.2 14,817 △ 0.4 638,758 1.412 131,111 1.5 30,900 1.8 10,976 2.6 12,245 4.1 15,070 △ 0.0 649,018 1.6

統 計 91
1.(6)信用金庫の貸出先別貸出金
(単位:億円、%)
年 月 末貸出金計 企業向け計
製造業 建設業前年同月比増 減 率 構成比 前年同月比
増 減 率 構成比 前年同月比増 減 率 構成比 前年同月比
増 減 率 構成比
2004. 3 622,363 △ 0.6 100.0 405,336 △ 2.3 65.1 82,022 △ 4.7 13.1 61,786 △ 5.3 9.905. 3 620,947 △ 0.1 100.0 404,453 △ 0.1 65.1 79,376 △ 3.2 12.7 59,463 △ 3.7 9.506. 3 626,700 0.9 100.0 407,728 0.8 65.0 78,118 △ 1.5 12.4 58,229 △ 2.0 9.206. 12 637,673 0.9 100.0 420,612 1.3 65.9 80,702 △ 0.8 12.6 58,732 △ 1.4 9.207. 3 634,953 1.3 100.0 416,942 2.2 65.6 79,103 1.2 12.4 57,780 △ 0.7 9.06 629,110 1.0 100.0 412,731 1.9 65.6 77,987 0.6 12.3 55,304 △ 1.1 8.79 635,457 0.4 100.0 419,293 1.0 65.9 79,015 △ 1.2 12.4 57,078 △ 1.2 8.912 638,372 0.1 100.0 422,707 0.4 66.2 79,589 △ 1.3 12.4 57,807 △ 1.5 9.0
08. 3 635,431 0.0 100.0 416,464 △ 0.1 65.5 76,511 △ 3.2 12.0 56,640 △ 1.9 8.96 630,411 0.2 100.0 412,777 0.0 65.4 75,326 △ 3.4 11.9 54,347 △ 1.7 8.6 9 638,490 0.4 100.0 419,868 0.1 65.7 76,210 △ 3.5 11.9 55,597 △ 2.5 8.7
(備考)1 .日本銀行「業種別貸出金調査表」より作成。このため、「日計表」による(5)科目別・地区別貸出金の貸出金計とは一致しない。
2.企業向け計には、海外円借款、 国内店名義現地貸を含む。 3 .2003年3月の業種分類の見直しに伴い、製造業の対象業種から「出版業」が除かれ、従来の「出版・印刷業」に代えて「印
刷業」のみが対象となったことから、増減率の算出においては、出版業・印刷業とも除いて算出した。また 「サービス業」は 「各種サービス」 となり飲食店等を含む。
4.2005年3月から2005年12月までの増減率は、旧杵築信用金庫を調整して算出
年 月 末 卸売業 小売業 飲食店 不動産業前年同月比増 減 率 構成比 前年同月比
増 減 率 構成比 前年同月比増 減 率 構成比 前年同月比
増 減 率 構成比
2004. 3 33,039 △ 3.5 5.3 37,328 △ 5.7 5.9 12,684 △ 6.8 2.0 82,312 5.3 13.205. 3 32,326 △ 2.1 5.2 34,509 △ 7.4 5.5 11,812 △ 6.8 1.9 92,948 12.9 14.906. 3 32,103 △ 0.6 5.1 33,303 △ 3.4 5.3 11,116 △ 5.8 1.7 100,316 7.9 16.006. 12 33,772 0.6 5.2 33,374 △ 2.6 5.2 11,092 △ 2.8 1.7 105,814 7.6 16.507. 3 32,828 2.2 5.1 32,640 △ 1.9 5.1 10,780 △ 3.0 1.6 108,200 7.8 17.06 32,388 1.8 5.1 32,194 △ 2.4 5.1 10,634 △ 3.6 1.6 108,838 7.7 17.39 33,208 0.4 5.2 32,534 △ 2.0 5.1 10,613 △ 4.3 1.6 110,446 6.8 17.312 33,599 △ 0.5 5.2 32,469 △ 2.7 5.0 10,524 △ 5.1 1.6 111,794 5.6 17.5
08. 3 32,332 △ 1.5 5.0 31,544 △ 3.3 4.9 10,304 △ 4.4 1.6 114,045 5.4 17.96 31,818 △ 1.7 5.0 31,194 △ 3.1 4.9 10,238 △ 3.7 1.6 114,712 5.3 18.19 32,376 △ 2.5 5.0 31,367 △ 3.5 4.9 10,209 △ 3.8 1.5 115,802 4.8 18.1
年 月 末地方公共団体 個 人
サービス業(各種サービス)
住宅ローン前年同月比増 減 率 構成比 前年同月比
増 減 率 構成比 前年同月比増 減 率 構成比 前年同月比
増 減 率 構成比
2004. 3 83,956 △ 2.4 13.4 16,932 7.9 2.7 200,095 2.4 32.1 143,110 6.2 22.905. 3 80,908 △ 3.6 13.0 18,529 9.4 2.9 197,965 △ 1.0 31.8 143,781 0.4 23.106. 3 80,075 △ 1.0 12.7 21,043 13.5 3.3 197,929 △ 0.0 31.5 147,901 2.8 23.506. 12 81,435 △ 0.4 12.7 20,454 13.1 3.2 196,607 △ 1.0 30.8 149,595 1.4 23.407. 3 79,987 △ 0.1 12.5 23,294 10.6 3.6 194,717 △ 1.6 30.6 149,058 0.7 23.46 79,688 △ 0.3 12.6 22,882 14.2 3.6 193,497 △ 2.1 30.7 148,815 0.2 23.69 80,135 △ 1.1 12.6 22,937 13.9 3.6 193,227 △ 2.3 30.4 149,066 △ 0.2 23.412 80,261 △ 1.4 12.5 23,125 13.0 3.6 192,540 △ 2.0 30.1 149,830 0.1 23.4
08. 3 78,660 △ 1.6 12.3 27,845 19.5 4.3 191,122 △ 1.8 30.0 148,973 △ 0.0 23.46 78,580 △ 1.3 12.4 27,759 21.3 4.4 189,875 △ 1.8 30.1 149,203 0.2 23.69 79,080 △ 1.3 12.3 28,171 22.8 4.4 190,451 △ 1.4 29.8 149,835 0.5 23.4

92 信金中金月報 2009.3
1.(7)信用金庫の余裕資金運用状況
(単位:億円、%)
年 月 末 現 金 預 け 金 金融機関貸 付 等 買入手形 コール
ローン 買現先勘定 債券貸借取引支払保証金
買入金銭債 権 金銭の信託うち信金中金預け金
2004. 3 16,040 196,398 ( 1.1) 154,855 (△ 2.6) 2,175 600 1,575 0 0 3,095 2,72905. 3 19,162 199,157 ( 1.4) 150,939 (△ 2.4) 2,472 907 1,555 0 0 3,142 2,67806. 3 16,963 194,245 (△ 2.4) 151,668 ( 0.4) 1,949 0 1,949 0 0 2,825 2,66807. 3 17,490 193,753 (△ 0.2) 168,470 ( 11.0) ― 0 7,517 0 1,303 2,641 2,6376 15,554 213,170 ( 3.9) 190,595 ( 1.6) ― 0 9,618 5 310 3,273 3,1269 15,710 211,465 ( 7.0) 185,892 ( 8.0) ― 350 9,189 0 300 2,789 3,135
07. 12 16,475 221,515 ( 7.9) 196,885 ( 6.5) ― 0 10,804 0 300 3,062 3,12008. 1 15,019 219,326 ( 9.6) 193,505 ( 7.2) ― 0 9,389 0 718 2,945 3,1052 13,832 217,857 ( 6.6) 191,805 ( 4.1) ― 0 10,362 0 910 2,955 3,0113 16,670 208,064 ( 7.3) 176,971 ( 5.0) ― 500 8,918 0 1,299 2,452 2,2054 15,703 225,261 ( 7.4) 197,877 ( 4.5) ― 0 8,509 0 334 2,926 2,3795 16,116 215,488 ( 4.8) 189,399 ( 2.8) ― 0 8,031 0 0 2,855 2,4376 16,023 225,683 ( 5.8) 198,084 ( 3.9) ― 0 9,649 0 194 2,792 2,4717 14,319 221,148 ( 7.4) 194,145 ( 5.0) ― 0 9,371 0 10 2,693 2,5278 14,447 226,230 ( 5.8) 199,290 ( 3.5) ― 0 10,138 0 53 2,770 2,5529 14,998 217,379 ( 2.7) 188,006 ( 1.1) ― 300 7,979 0 757 2,603 2,57210 13,565 217,118 (△ 0.1) 191,205 (△ 1.7) ― 0 8,547 0 114 2,813 2,57611 15,855 215,902 ( 0.7) 189,965 (△ 0.6) ― 0 8,445 0 157 2,858 2,50112 17,680 221,660 ( 0.0) 194,122 (△ 1.4) ― 0 7,148 0 305 3,036 2,415
(備考)1 .( )内は前年同月比増減率 2.預貸率=貸出金/預金×100(%)、預証率=有価証券/預金×100(%)(預金には譲渡性預金を含む。) 3.2005年3月から2006年2月までの増減率は、旧杵築信用金庫を調整して算出 4 .2006年8月末までの余資運用資産計は、現金、預け金、金融機関貸付等、買入金銭債権、金銭の信託、商品有価証券、
有価証券の合計 5 .2006年9月末以降の余資運用資産計は、現金、預け金、買入手形、コールローン、買現先勘定、債券貸借取引支払保証金、
買入金銭債権、金銭の信託、商品有価証券、有価証券の合計
年 月 末 商 品有価証券 有価証券 国 債 地方債 短期社債 社 債 公社公団債 金融債 その他
2004. 3 159 268,761 ( 8.3) 73,655 ( 17.4) 26,755 0 110,483 ( 1.7) 33,875 34,274 42,334 05. 3 78 287,574 ( 7.0) 82,465 ( 11.9) 31,460 3 111,680 ( 1.1) 39,070 32,452 40,158 06. 3 69 306,055 ( 6.4) 89,127 ( 8.0) 34,696 80 115,196 ( 3.1) 42,609 33,464 39,122 07. 3 59 318,110 ( 3.9) 98,728 ( 10.7) 33,976 169 116,636 ( 1.2) 44,265 33,925 38,445 6 63 322,004 ( 3.5) 99,556 ( 8.1) 35,476 599 120,667 ( 2.6) 45,785 35,038 39,843 9 52 321,595 ( 3.7) 96,477 ( 4.5) 35,234 369 119,654 ( 2.5) 44,564 34,865 40,224
07. 12 43 321,737 ( 4.3) 93,225 ( 3.6) 35,379 869 121,114 ( 2.9) 44,469 35,620 41,025 08. 1 41 321,625 ( 4.0) 93,694 ( 2.5) 34,964 870 120,514 ( 2.0) 43,769 35,437 41,307 2 41 328,362 ( 5.3) 97,852 ( 3.4) 35,815 926 122,137 ( 3.4) 44,674 35,811 41,650 3 45 323,482 ( 1.6) 101,608 ( 2.9) 34,602 320 120,431 ( 3.2) 42,898 35,774 41,758 4 45 329,108 ( 3.6) 100,630 ( 2.6) 35,175 493 123,040 ( 3.4) 43,285 36,286 43,467 5 55 333,719 ( 4.5) 101,264 ( 3.6) 36,206 857 125,044 ( 4.2) 44,275 36,595 44,173 6 54 332,248 ( 3.1) 98,842 (△ 0.7) 36,664 810 125,838 ( 4.2) 44,347 36,797 44,6937 52 332,901 ( 2.8) 98,354 (△ 1.1) 36,944 889 126,821 ( 4.7) 44,441 36,978 45,4018 50 332,879 ( 4.3) 97,489 ( 4.0) 37,183 952 126,825 ( 5.7) 44,393 37,124 45,3079 50 334,654 ( 4.0) 99,929 ( 3.5) 37,067 352 127,142 ( 6.2) 43,807 37,178 46,15610 48 333,885 ( 4.5) 97,467 ( 4.3) 37,393 623 128,408 ( 6.7) 44,331 37,524 46,55111 47 332,267 ( 3.4) 94,849 ( 1.3) 37,397 956 129,026 ( 6.8) 44,555 37,727 46,74412 41 330,068 ( 2.5) 91,472 (△ 1.8) 37,297 1,546 129,840 ( 7.2) 43,609 38,064 48,167
年 月 末余資運用資 産 計(A)
信金中金利 用 額(B)
預貸率 (A)/預金 預証率 (B)/預金(B)/(A)株 式 貸付信託 投資信託 外国証券 その他の証 券
2004. 3 5,449 2 5,650 46,121 643 489,360 154,855 58.9 46.3 25.4 14.6 31.605. 3 6,131 0 6,745 47,983 1,102 514,265 150,939 57.7 47.8 26.7 14.0 29.306. 3 9,236 0 8,911 47,338 1,466 524,777 151,668 57.3 47.9 27.9 13.8 28.907. 3 10,514 0 9,518 47,161 1,404 543,515 168,470 56.9 48.7 28.5 15.1 30.96 7,937 0 9,056 47,431 1,279 567,128 190,595 55.5 50.0 28.4 16.8 33.69 8,427 0 10,250 49,916 1,264 564,589 185,892 55.9 49.7 28.3 16.3 32.9
07. 12 8,654 0 10,716 50,461 1,315 577,058 196,885 55.5 50.1 27.9 17.1 34.108. 1 8,712 0 10,754 50,790 1,323 572,171 193,505 55.4 50.3 28.2 17.0 33.82 8,735 0 10,753 50,821 1,320 577,334 191,805 55.2 50.6 28.7 16.8 33.23 8,284 0 9,129 47,488 1,616 563,638 176,971 55.8 49.5 28.4 15.5 31.34 8,636 0 10,460 49,152 1,520 584,270 197,877 54.7 50.8 28.6 17.2 33.85 8,768 0 10,425 49,692 1,460 578,704 189,399 55.1 50.5 29.1 16.5 32.76 8,819 0 10,332 49,488 1,451 589,117 198,084 54.5 50.9 28.7 17.1 33.67 8,789 0 10,303 49,350 1,448 583,025 194,145 54.9 50.6 28.9 16.8 33.28 8,798 0 10,240 49,950 1,438 589,122 199,290 54.7 50.9 28.7 17.2 33.89 8,687 0 10,222 49,830 1,422 581,294 188,006 55.2 50.3 28.9 16.2 32.310 8,654 0 10,032 49,896 1,410 578,669 191,205 55.2 50.3 29.0 16.6 33.011 8,674 0 10,039 49,916 1,406 578,035 189,965 55.4 50.2 28.8 16.5 32.812 8,787 0 9,960 49,753 1,408 582,358 194,122 55.6 49.9 28.3 16.6 33.3

統 計 93
2.(1)業態別預貯金等
(単位:億円、%)
年 月 末信用金庫 国内銀行
(債券、信託を含む。)
大手銀行(債券、信託を含む。)
地方銀行うち預金 うち都市銀行前年同月比
増 減 率前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 1,055,175 1.8 6,798,238 △ 0.0 4,420,297 △ 0.0 2,842,197 2.9 2,456,008 3.2 1,825,541 0.605. 3 1,074,324 1.8 6,902,096 1.5 4,483,596 1.4 2,862,150 0.7 2,470,227 0.5 1,878,876 2.906. 3 1,092,212 1.6 7,428,778 7.6 4,998,602 11.4 2,911,320 1.7 2,507,624 1.5 1,888,910 0.507. 3 1,113,772 1.9 7,674,949 3.3 5,191,912 3.8 2,916,384 0.1 2,487,565 △ 0.7 1,936,818 2.56 1,132,280 2.7 7,745,803 3.0 5,236,067 3.1 2,917,118 1.3 2,484,873 0.5 1,955,473 3.09 1,134,180 2.5 7,715,888 3.1 5,231,028 3.6 2,927,602 2.2 2,443,278 △ 0.0 1,932,727 2.3
07. 12 1,148,722 2.6 7,720,436 2.2 5,206,699 2.3 2,957,695 3.7 2,459,477 1.3 1,955,718 2.408. 1 1,136,221 2.7 7,711,550 2.0 5,231,462 1.9 2,984,217 3.7 2,479,673 1.3 1,930,379 2.42 1,139,995 2.5 7,737,257 1.9 5,251,149 1.9 2,994,622 4.0 2,490,036 1.6 1,934,135 2.03 1,137,275 2.1 7,780,686 1.3 5,268,076 1.4 3,032,690 3.9 2,525,751 1.5 1,956,991 1.04 1,148,256 2.0 7,769,906 0.7 5,246,034 0.4 3,030,574 3.3 2,517,167 0.5 1,967,121 1.35 1,144,768 2.4 7,750,715 △ 0.1 5,231,118 △ 0.9 3,024,294 1.7 2,513,056 △ 1.1 1,964,189 1.66 1,155,357 2.0 7,798,134 0.6 5,243,945 0.1 3,039,528 4.1 2,522,926 1.5 1,992,541 1.87 1,149,391 2.1 7,693,165 △ 0.6 5,173,010 △ 1.8 3,020,502 2.4 2,494,784 1.1 1,964,304 1.98 1,156,253 2.5 7,595,482 △ 1.5 5,063,627 △ 3.4 2,995,131 2.3 2,467,667 0.9 1,973,805 2.69 1,154,026 1.7 7,529,496 △ 2.4 5,014,192 △ 4.1 3,026,582 3.3 2,492,534 2.0 1,959,024 1.310 1,148,778 1.6 7,554,806 △ 2.2 5,061,978 △ 3.9 3,009,513 2.5 2,479,419 1.2 1,941,852 1.511 1,150,106 1.8 7,613,800 △ 1.3 5,096,231 △ 2.8 3,049,355 1.6 2,515,687 0.3 1,962,888 1.912 1,164,845 1.4 7,625,566 △ 1.2 5,076,807 △ 2.4 3,038,382 2.7 2,490,156 1.2 1,986,613 1.5
(備考)1.日本銀行『金融経済統計月報』、ゆうちょ銀行ホームページ等より作成 2.大手銀行は、国内銀行-(地方銀行+第二地銀)の計数 3.国内銀行・大手銀行には、全国内銀行の債券および信託勘定の金銭信託・貸付信託・年金信託・財産形成給付信託を含めた。 4 .信用組合、労働金庫、農業協同組合の計数については、日本銀行がデータの掲載を中止したことを受けて、更新を停止
した。 5.2007年10月移行の郵便貯金は、振替貯金を含む。また、郵便貯金は2008年4月より四半期ベースで公表 6 .預貯金等合計は、単位(億円)未満を切り捨てた各業態の預貯金残高の合計により算出した。なお、2006年4月以降に
ついては、信用組合、労働金庫、農業協同組合を除いたベースで算出した。
年 月 末 信用組合 労働金庫 農業協同組合 郵便貯金 預貯金等合計第二地銀 前年同月比
増 減 率前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 552,400 △ 1.6 152,526 2.8 135,713 3.1 759,764 2.0 2,273,820 △ 2.5 11,175,236 △ 0.105. 3 539,624 △ 2.3 156,095 2.3 138,604 2.1 776,685 2.2 2,141,490 △ 5.8 11,189,294 0.106. 3 541,266 0.3 159,430 2.1 141,803 2.3 788,653 1.5 2,000,023 △ 6.6 11,610,899 3.707. 3 546,219 0.9 ― ― ― ― ― ― 1,869,692 △ 6.5 10,658,413 1.36 554,263 1.8 ― ― ― ― ― ― 1,848,812 △ 6.5 10,726,895 1.29 552,133 1.1 ― ― ― ― ― ― 1,808,431 △ 6.4 10,658,499 1.2
07. 12 558,019 1.6 ― ― ― ― ― ― 1,856,301 ― 10,725,459 ―08. 1 549,709 1.8 ― ― ― ― ― ― 1,836,810 ― 10,684,581 ―2 551,973 1.9 ― ― ― ― ― ― 1,833,621 ― 10,710,873 ―3 555,619 1.7 ― ― ― ― ― ― 1,817,438 ― 10,735,399 ―4 556,751 1.1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―5 555,408 1.7 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―6 561,648 1.3 ― ― ― ― ― ― p 1,811,385 ― p 10,764,876 ―7 555,851 1.4 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―8 558,050 1.9 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―9 556,280 0.7 ― ― ― ― ― ― 1,785,613 ― 10,469,135 ―10 550,976 0.6 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―11 554,681 1.0 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―12 562,146 0.7 ― ― ― ― ― ― p 1,791,005 ― p 10,581,416 ―

94 信金中金月報 2009.3
2.(2)業態別貸出金
(単位:億円、%)
年 月 末信用金庫 大手銀行 地方銀行 第二地銀 信用組合
都市銀行前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 622,364 △ 0.6 2,344,621 △ 4.3 1,958,921 △ 5.4 1,352,081 △ 0.0 420,236 △ 2.0 91,234 △ 0.305. 3 620,948 △ 0.2 2,243,788 △ 4.3 1,869,540 △ 4.5 1,372,381 1.5 403,403 △ 4.0 91,836 0.606. 3 626,702 0.9 2,291,469 2.1 1,896,885 1.4 1,403,556 2.2 412,564 2.2 93,078 1.307. 3 634,953 1.3 2,270,176 △ 0.9 1,860,370 △ 1.9 1,445,409 2.9 419,377 1.6 ― ―6 629,111 1.0 2,257,345 △ 0.8 1,849,285 △ 1.4 1,434,045 2.7 417,219 1.0 ― ―9 635,458 0.4 2,250,915 △ 1.9 1,834,185 △ 2.7 1,453,735 2.8 422,248 1.1 ― ―
07. 12 638,374 0.1 2,276,097 △ 1.1 1,861,640 △ 1.8 1,471,741 2.7 428,556 1.9 ― ―08. 1 630,614 0.1 2,271,161 △ 0.4 1,861,501 △ 1.0 1,459,824 2.6 423,834 2.0 ― ―2 629,771 0.2 2,271,821 0.4 1,859,440 △ 0.2 1,466,141 3.1 424,092 2.2 ― ―3 635,433 0.0 2,281,304 0.4 1,854,662 △ 0.3 1,483,586 2.6 429,309 2.3 ― ―4 629,236 △ 0.0 2,264,393 0.5 1,846,901 0.0 1,472,571 2.7 425,991 2.0 ― ―5 631,662 0.9 2,265,049 1.0 1,848,591 0.6 1,478,055 3.7 427,400 2.9 ― ―6 630,412 0.2 2,284,825 1.2 1,862,142 0.6 1,478,736 3.1 426,408 2.2 ― ―7 631,570 0.6 2,275,650 1.4 1,855,276 1.1 1,483,538 3.3 426,828 2.4 ― ―8 633,796 0.9 2,272,970 0.8 1,853,191 0.5 1,488,046 3.5 427,655 2.6 ̶ ̶9 638,492 0.4 2,280,702 1.3 1,849,717 0.8 1,495,911 2.9 430,585 1.9 ̶ ̶10 635,822 1.0 2,310,735 3.7 1,886,720 3.6 1,498,556 3.7 428,806 2.3 ̶ ̶11 638,758 1.4 2,341,065 4.6 1,916,932 4.7 1,512,185 4.4 430,860 2.5 ̶ ̶12 649,018 1.6 2,391,819 5.0 1,957,331 5.1 1,540,064 4.6 436,608 1.8 ̶ ̶
(備考)1.日本銀行『金融経済統計月報』より作成 2.大手銀行は、国内銀行-(地方銀行+第二地銀)の計数 3 .公的金融機関は、日本政策投資銀行、国際協力銀行、国民生活金融公庫、住宅金融公庫、農林漁業金融公庫、中小企業
金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、商工組合中央金庫の合計 4.公的金融機関のうち中小企業向けは、国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫の合計 5 .信用組合、労働金庫、農業協同組合、公的金融機関の計数については、日本銀行がデータの掲載を中止したことを受
けて、更新を停止した。 6 .合計は、単位(億円)未満を切り捨てた各業態の貸出金残高の合計により算出した。なお、2006年3月以降については、
信用組合、労働金庫、農業協同組合、公的金融機関を除いたベースで算出した。
年 月 末労働金庫 農業協同組合 公的金融機関 合 計うち中小
企業向けうち住宅金融公庫
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
前年同月比増 減 率
2004. 3 92,664 6.1 214,871 △ 0.1 1,531,569 △ 5.2 274,726 △ 1.7 605,947 △ 9.8 6,669,640 △ 2.905. 3 94,887 2.3 212,986 △ 0.8 1,457,114 △ 4.8 270,971 △ 1.3 550,993 △ 9.0 6,497,343 △ 2.506. 3 97,095 2.3 213,185 0.0 ― ― ― ― ― ― 4,734,291 2.007. 3 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,769,915 0.76 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,737,720 0.69 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,762,356 0.0
07. 12 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,814,768 0.408. 1 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,785,433 0.72 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,791,825 1.33 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,829,632 1.24 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,792,191 1.25 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,802,166 2.06 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,820,381 1.77 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,817,586 2.08 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 4,822,467 1.89 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 4,845,690 1.710 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 4,873,919 3.211 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 4,922,868 3.912 ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ ̶ 5,017,509 4.2

ISSN 1346-9479
2009年(平成21年)3月1日 発行
2009年3月号 第8巻 第3号(通巻435号)
発 行 信金中央金庫
編 集 信金中央金庫 総合研究所
〒103-0028 東京都中央区八重洲1-3-7
TEL 03(5202)7671 FAX 03(3278)7048
<本誌の無断転用、転載を禁じます>
当研究所のホームページでは、当研究所の調査研究成果である各種レポート、信金中金月報のほか、統計データ等を掲示し、広く一般の方のご利用に供しておりますのでご活用下さい。 また、「ご意見・ご要望窓口」を設置しておりますので、当研究所の調査研究や活動等に関しまして広くご意見等をお寄せいただきますよう宜しくお願い申し上げます。
【ホームページの主なコンテンツ】○当研究所の概要、活動状況、組織○各種レポート 内外経済、中小企業金融、地域金融、 協同組織金融、産業・企業動向等○刊行物 信金中金月報、全国信用金庫概況等○信用金庫統計 日本語/英語○アジア主要国との貿易・投資に関する各種情報 アジア業務室ページ○論文募集
【URL】 http://www.scbri.jp/
ホームページのご案内





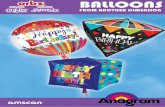
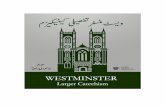





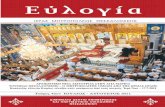

![INDEX []ROCKER ARM ASSY 9 KV74008BA ロツカ- プレ-ト 1 PLATE,ROCKER 10 KV72012AA ロツカア-ム 1 ARM,ROCKER 11 KV72013AA ロツカア-ム 1 ARM,ROCKER 12 KU23013AA ナツト](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5fde9bd37e867c36f63083d2/index-rocker-arm-assy-9-kv74008ba-iii-ioeii-i-1-platerocker-10.jpg)





