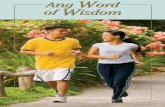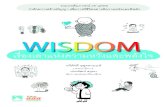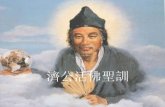Beyond data collection, sentiment analysis for crowds and stakeholders
集合知 創発する場のデザイ ン A Design for the Wisdom Crowds …
Transcript of 集合知 創発する場のデザイ ン A Design for the Wisdom Crowds …

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
集合知を創発する場のデザイン一
理論的再検討とオンライン ・ コミュ ニ ティの事例分析から
A Design for the Emergent ‘“Wisdom of Crowds ”
:
Theoretical reconsideration and analysis of the online communities
濱 崎雅弘
産 業 技 術総 合 研 究所
HAMASAKI Masahiro
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology(AIS丁1
要旨
本稿で は 集合知を創 発 す る場、特 に ウ ェ ブ上 にお け る場 の デ ザ
イ ン に 関 し て 議論す る。ウ ェ ブ上 に生 ま れ た 創造 活 動 の 場 は、
膨 大 な 参加 者 と、デ ジ タル 空 間 で あ る た め 場 (プラ ッ ト フ ォー
ム) を 自由 にデ ザ イ ン で き る とい う特 徴 を持 つ 。こ れ は 大 き な
可能 性 を秘 めて い る一方、そ の デ ザイ ン に は 多 く の 知 見 が 新た
に 必要 とな る と考え ら れる 。 本稿で は ウェ ブ上 に生まれ た創 造
活動の 中で も 多数の 人 々 の 参加に よ る創 造活 動、つ ま りは 集合
知 に着 目す る。本稿で は まず ウ ェ ブに限 定 しな い、集 合 知一般
に関 す る こ れ まで の 議論 を振 り返 り、集合 知 が 創 発 され る た め
の 要 件 と、そ の た め の 場 の デ ザ イ ン は どう あ る べ き か に つ い て
述 べ る。次 に ウ ェ ブ上 で 展 開 され る 様 々 な試 み を も と に、ウ コニ
ブ上 で の 場 の デ ザ イ ン の 可 能 性に つ い て 述 べ る 。 最後 に 知 識 や
道具 な どと は異 な る個人的主観性の 高い コ ン テ ン ツ を生み 出 す
集合知の 場 の デ ザ イ ン につ い て 実 デー
タ の分 析 を 交 えな が らそ
の可 能性を議論す る。
Abstract
This paper describes a web −based community design to facili−
tate the emergen ピ‘wisdom of crowds .”The World Wide Web
was first created as a publishing platform, but is now becom−
ing a platform for two−way communication , and thanks to its
flexibility, various types of communication have emerged . The
Web has various advantages over older systems , and enables
form of massively interactive collaboration that would not be
possible via real −world communicatiQn channels . This new
platform is powerful, but designing for communities in this
medium requires a high degree of new forms of knowledge . In
this paper, we survey requirements for the emergent wisdom
of crowds and use case studies to discuss the possibility of
designing a community on the Web to support such wisdom .
We also discuss the role of the wisdom of crowds for generat−
ing both objective content e .9., knowledge and software tools,
and subjective content , such as art and entertainment , based
on an analysis of an actual dataset from a video sharing web −
site.
1.は じめ に
情 報 技 術 の 発 展 に よ り、人 々 は こ れ まで に な い ほ ど多様な創造
活 動 が 可 能 に な っ た。特に ウ ェ ブが 大 規模 な 情報 共有 お よ び コ
ミ ュ ニ ケー
シ ョ ン を 広 く一
般 に 可能 な も の と す る こ と で 、新 し
い ス タイ ル の 創造活 動 が 生 まれ て い る。そ れ らは CGM (Con−
sumer Generated Media) や Web2 .0、集 合知 と い っ た言 葉 で
語 られ る。こ こ で 注 目す べ き は、創 造 され た もの を享受す る 人
が創 造 活動 に参加 す る とい う、社会 と直接 に 結び つ い た 創造 活
動 で あ る 点で あ る。そ し て そ れを支 え る の が、多 くの 人が 関わ
る 創 造 活動 を 実 現 す る プ ラ ッ ト フ ォー
ム で あ る。
ウ ェ ブ 上 に 生 まれ た 創 造 活動 の 場 は、膨大 な 参 加 者 と、デ ジ タ
ル 空 間 で あ るた め場 (プ ラ ッ トフ ォーム) を 自由 に デ ザ イ ン で
き る と い う 特 徴 を 持 つ 。こ れ は 大 きな 可 能性 を秘 め て い る一
方、そ の デ ザ イ ン に は多 くの 知 見が 新た に 必要 とな る と考え ら
れ る。本稿 で は ウ ェ ブ 上 に 生 まれ た 創造活動 の 中で も 多数 の
人々 の 参加 に よる 創造活動、つ ま りは 集合知 に 着目す る。集合
知 に 関す る こ れ ま で の 議論 を 振 り返 る と と も に、現在、ウ ェ ブ
上 で 展 開 され る様 々 な 試 み にっ い て 述 べ 、集 合 知 を創 発 す る た
めの 場 の デ ザ イ ン は どの よ う にな され る べ きか 考 察す る。
本 稿 の 構 成 は 以 下 の 通 り で あ る。ま ず 2 章 に て 集合 知 に 関 す る
既 存の 議論 に つ い て 振 り返 り、集合 知が創 発 され る ため の 要件
と、そ の た め の場 の デ ザ イ ン は ど うあ るべ き か に つ い て 述 べ
る。次 に 3 章 に て、ウ ェ ブにあ る 集 合 知 の 事 例 に つ い て 述 べ 、
ウ ェ ブの ど う い っ た特 徴 が集 合 知 を可 能 に した の か述 べ る 。4
章 に て 芸術 的 コ ン テ ン ツ と い う これ ま で と 毛 色 の 違 う 対 象 に お
い て 集合知 は 成 立 す る の か と い う点 に つ い て 議論 し、5 章に て
そ の 事 例 と し て ニ コ ニ コ 動 画 に お け る 集合 知 に つ い て 述 べ る 。
最 後 に 6章 にて 本稿 を ま とめ る。
2.集合知
複 数 の 人 々の 協 調 や協 働 が生 み 出 す創 造性 に関 して は、集団意
志 決 定 や グ ループ ワーク と い う観 点 か ら数 多 く議 論 され て き
た。そ こ で は、非専 門 家 も混 じえ た多 数 に よ る コ ラ ボレーシ ョ
ン に 関 し て は、集 団 浅 慮 や偏 向 化 に よる 衆 愚 化 の 可 能 性 が あ る
こ とが 指摘 され て い る。
しか し一方 で 、群衆 の 叡 智 と も言 え る 現 象 も多 く報告 され て い
る 。 James Surowiecki は 著書 に お い て 、様々 な事例 や既 存研
究を紹介 し集合知の 可能性を述べ て い る [SurowieckiO7]。 有
名な もの は牛 の 体重 を当て る話 で あ る。あ る見 本 市 で 雄牛 の 体
14デ ザ イ ン字研 究特集号
special issue otiapanese societyforthe science ot designVel.17−4 No.68 2011
_ 、_ レ

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
重 当 て コ ン テ ス トが 行 われ、牛 の 専 門 家か らま っ た くの 門外漢
ま で 多様 な 人 た ちが 参 加 した。さ て 当て た の は誰か とい う と、
専 門 家 で も門 外漢 で も な く参加 者 全 員 の 予 想 値の 平均 値で あ っ
た。集合 知 が個 人 の 知 を、さ らに は専門家の 知 を も越え た と い
う話 で あ る。こ の 話 を 聞 い て、そ う い う 問題 だ か ら う ま く い っ
ただ け で は な い か、と 思 わ れ る方 も 多い で あ ろ う。実 際、み ん
な が 集 ま っ て 意 見 を 出 し て 平 均 を 取 れ ば あ ら ゆ る 問題 が 解 け る
と い う こ と は あ り え な い 。Surowieckiは 数 多 くの 集 合 知 が効 果
的 に機能 した 事例 を 踏 ま え、集合 知 の 要件 と して 以下 の 4 つ を
挙 げて い る。
・独 立性 :各 自は独 立 して 意 見を 出す
・多様性 :色 々 な 人たち が参加する
・分散性 :各自そ れぞ れ 色 々 な情報 源 を 持 つ
・集 約 1 みん な の 意 見 を 集約 す る メ 力 ニ ズム が あ る
参加 者の 条件 と して 独立 性、多様性、分散性と幾つ か挙げら れ
て い る が、独 立 性も 分 散性も 多様性 を 担 保 す る た め の も の と 考
え る と、つ ま り は 「多様 な 意見が 適切 に 集 約 さ れ た な ら ば、集
団 浅 慮 や 偏向化 が 避 け ら れ 、集合 知 が 発 揮 さ れ る 」 と、捉 え る
こ と が で き る。実 際、複 数 人 に よ る協 調 作 業 に お い て 多様 性 の
重要 性 は あ ち こ ち で 指摘 さ れ て い る。Gerhard Fischerは ソ フ
トウ ェ ア開 発 の よ うな分 業 が 進 み全 専 門分 野 を把 握 して い る 人
が 誰 も な い よ う な現 場 に お い て 、個人 で はな くそ の 集団が 生 み
出 す 創 造 性 を Social Creativityと 呼 び、そ の よ う な 場 で は 相 手
の 専門分野 に 対す る 無知 が む し ろ 多様性 に 寄与 し て 良い と述 べ
て い る [FischerO l]。ま た 、 Scott Page は シ ミ ュ レーシ ョ ン
を 通 し て 集 合 知 に お い て 多様 性 が 有 効 と な る問題 の 条 件 を示 し
た [PageOl]。そ れ は 以下 の よ う な もの で あ る。
・条 件 1 :い ず れ の 参加 者 も個人 で 全 体最適 解 (グ ロー
バ ル ・
オ プ テ ィ マ ム )をみ つ け ら れる こ とは ない 。 すなわ ち、誰 も
一人 で は 解け な い 程度に 問題 が難 し い 。
・条件 2 :す べ て の 参 加 者 が 自身 の 局 所 最適 解 (ローカ ル・オ
プテ ィ マ ム ) を リス トに 書 き出 す こ とが で き る。す な わ ち、
す べ て の 参 加 者 が 自分 に と っ て 考 え ら れ る 最 高 の 答 え を 出せ
る だ け 賢い 。
・条件 3 :全体最適解以 外 の 全 て の解が、最 低一人 の 参 加 者 に
と っ て 局 所 最 適解 で はな い 。す な わ ち、全 員 が 正解 だ と思 っ
た回 答 が誤 りで あ る こ とは な い。
条件 4 :大 勢 の 参加 者候補 か ら か な りの 大 き さの 集団 を選
ぶ 。す な わ ち、た くさん の 中か ら選 んだ た くさん の 人 た ち が
参 加 す る。
さて 、多様 性 の あ る 参 加 者 が 確 保 で きれ ば 集合 知 は 発揮 さ れ
る の で あ ろ う か 。 Surowieckiは 問題 解決者の 特徴 と と も に、集
合 知 の 要件 と し て 群衆か ら 知識 を どの よ うに 集め る か と い う集
約も 重要 で あ る と述べ た 。 社会 心 理 学 に お い て も集 団 に よる ア
ウ トプ ッ トが必ず し も 効率よ くな い こ と は指摘 され て お り、こ
れ は 相互 作用 にお け る プ ロ セ ス の 損 失 と い われ る。こ の プ ロ セ
ス の 損失を 避 け る た め に は 適切 な 集約 の 手 段 が必 要 と な るが、
lvan Steinerは 集約の プ ロ セ ス を 以 下 の 三 つ に分 類 して い る
[Steiner72]。 こ れ ら は い ずれ か が 良 い と い う もの で は な く、
対象と なる 問題 に合わせ て 適切 に選 ばれ る べ き もの で ある 。
・加算 型 :各参 加 者 の 遂 行量 の 合 計値 が そ の ま ま グ ループ全体
の 遂 行 量 と な る。(例 :運 動 会 の 玉 入 れ )
・結合型 : 参加 者全 員 が 課題 を達 成 し て 初 め て グル ープ と して
の 課 題 が 完 了す る。(例 : 山登 り)
・分 離型 :結 合型 とは逆 に、少な く とも参加 者の一人 が課 題 に
成 功 すれ ば グループ 全体 と して の 遂行が 完了する 。
集団で ア イ デ ア を生 み 出す 手法 と して 有名な も の に ブレ イ ン ス
トーミ ン グ が あ る 。 ブ レ イ ン ス トー
ミ ン グは 比 較的少人 数 で 密
な コ ミ ュ ニ ケーシ ョ ン の も とで 行わ れる も の で ある た め、本稿が
意図 す る 集合知 と は や や 異 な るが、場 の デ ザ イ ン と い う点 で は
共 通 項が 多い た め、こ こ で 例 と して 用 い る。ブレイ ン ス トー
ミン
グ は メ ン バー
が 自由 に ア イ デ ア を 出 し合 うこ と で 、良 い ア イ デ
ア を 生み だ そ う とす る発 想法 の一つ で あ る。集 約方 法 として は、
メ ン バー
全 員 が 自由 に ア イ デ ア を ポ ス トイ ッ トに 書 き、それ を
壁に貼 りだ して、最 後 に全 員 で カテ ゴラ イ ズす る とい っ た方 法
が と られ る。自 由 に叩 き台 を 出す とい う点 で は加 算 型 の 集 約 方
法 とい え、カテ ゴ ライ ズ を通 して 最終的 に い くつ か の 良い ア イ
デ ア を見い だす とい う 点で は 分離型 の 集約方法 と も い え る 。
さ て 、多 様 な メ ン バー
が そ ろ い 、問題 に 対 して 適切 な集 約 方法
が 決 まれ ば、集 合 知 は 自 ら発揮 され る もの な の だ ろ うか。残 念
なが らそ の よ う には 上手 くい か な い 。こ れ は頻繁に 行わ れ て い
る ブ レイ ン ス トーミ ン グ も例 外で は な い 。 そ の 要 因 と し て (1)k産 性の 阻害 :他人 との や り と りの た め の コ ス トが 生 じ る、(2)社
会的抑制 ; 他者へ の 配慮 に よ りア イ デ ア が 出 しに く くなる、〔3)
社会的怠惰 : 責任感が薄れて 他人任せ にな る、とい っ た点が 指
摘 さ れ て い る。実 際 に や っ て み る と うま くい っ た と感 じる こ と
が 多 い か も しれ な い が、こ れ に つ い て は、実 際 に結 果 は 同 じ
だ っ た と して も、一人 で や っ た と きよ りもグ ループで や っ た と
き の 方 が生 産 性が 高か っ た と感 じて しま う 「グループ効果 の 幻
想 」 が あ る との 指 摘が あ る 。
も ち ろ ん ブレ イ ン ス トー
ミ ン グ が 常 に 失敗 す るわ けで は な い 。
こ れ らの 指摘は、逆 に 言 え ば問題 を回避 す る よ う に場 をデ ザ イ
ン す れ ば ブ レイ ン ス トーミ ン グ は う ま く行 く こ と を 示 唆 して い
る。事 実、創 造 性 の 高 い 企 業 と し て 名高 い IDEO に お い て は ブ
レ イ ン ス トーミ ン グが 頻繁に 用 い ら れ て お り、ま た 、そ の よ う
な ブレ イ ン ス トー
ミ ン グ に は ノ ウハ ウがあ る こ と を述 べ て い る
[Kelley2001]。 そ もそ も一
般に ブ レイ ン ス トーミ ン グ に は 「自
由に ア イデ アを 出 す」「他 人 の ア イ デ ア に 文 句 を言わ な い 」 と
い っ た 前述 の 問題 を回 避 す る よう なルー
ル が あ る。し か しな が
ら、そ うい っ た 素朴 な ルー
ル を 作る だ け で 場 が 正 し く デ ザ イ ン
さ れ、コ ラ ボ レー
シ ョ ン が 適 切 に 行 わ れ る 訳 で は な い 。
で は、場 の デ ザ イ ン と は ど うい っ た 方 法 で で き る の だ ろ うか 。
法 学者 の Lawrence Lessigは人 々 を制約す る もの と して 法、社会
毳鑽 :ご:∵:∵∴!
15

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
の 規範、市場、アー
キ テ ク チ ャ の 4 つ を挙 げて い る [LessigO7]。
例 え ば喫 煙 行為を制約す る も の と して 、飛 行 機 内 で 喫 煙 し て は
な ら な い の は 法 に よる 制約 で あ り、他 人 の 車 の 中で 確認 も な し
に 喫煙 して は な らな い の は社会 の 規 範 に よ る 制約で あ る 。タバ
コ の 値 段 が 上 が る こ とで 喫煙 しづ ら くな るの は 市場 によ る制 約
で あ る。に お い の 強い タバ ⊇ は吸 え る場所 を 限 定 す るが、こ れ
は タバ コ 自体 の 構造が持つ 制約、つ ま りアーキ テ クチ ャ に よ る
制約で ある 。 制約は こ れ ら 4 種 類 の 力が 相 互作 用 して 生 み 出す
も の で あ る が、レ ッ シ グ はデ ジ タル 空 間 に お い て は 特に アー
キ
テ クチ ャ が強 力 にな る と指摘 して い る (た だ し、法 が 他 の 3 つ
に対 して 大 き く影 響 を与 え る と も述 べ て い る )。
多様 性 を担 保 す る 大 勢の 参加 者 と、集 約 の デザ イ ン に お い て 大
き な 可 能性 を持 つ デ ジ タル空 間、こ の 2 点 を備 えた 世界最大 の
プ ラ ッ トフ ォー
ム がイ ン ターネ ッ トで あ り、ウ ェ ブで あ る 。 事
実、こ の プ ラ ッ トフ ォーム上 にて 多 くの 集合 知、そ れ も新 し い
形 の 集合知 が 生 ま れ て い る。次 章は ウ ェ ブ と 集合知 の 関係 に つ
い て 述 べ る。
3.ウ ェ ブ と集合知
イ ン ターネ ッ ト、そ し て 1986 年 に Tim B. Lee が 開発 した ウ ェ
ブ は、多様な 、そ して 何 よ り膨 大 な 人 々 が 集 ま るデ ジ タル 空 間
で ある。こ の 空 間 は集 合知 が 発 揮 され る 最適 な 場所で あ る とい
え、実 際、数 多 くの 様 々 な 事 例 が 生 み 出 され て い る。オ ン ラ
イ ン 百 科 事 典 で あ るWikipediaや Linuxに 代表 され る オープ ン
ソー
ス ソ フ トウ ェ ア は そ の 代表例 と い え る。Don Tapscottら
は こ れ を マ ス コ ラ ボ レー
シ ョ ン と 呼ん で 、次 世 代 の 開発 ・生産
手 法 と 評 し て い る [Tapscotto7]。マ ス コ ラ ボ レーシ ョ ン の 鍵
と な る の は 個人 に よ る 参加 と 協 調 (ピ ア リ ン グ) で あ り、こ れ
を実 現 す る条 件 と して (1)生 産 物 が情 報 や 文化 で あ る こ と (参加
が容 易 )、(2)他 の 部 分 とは 独 立 に個 人 が 少 しず つ 貢献で き る こ
と (貢 献 の 費 用 対 効果 の 高 さ)、 得 ら れ た 部品を 最終成果 物
に す る コ ス トが低 い こ と (管理 コ ス トの 抑 制 )、を挙 げ て い る。
実 際、Linuxの よ うな オープ ン ソー
ス ソ フ トウ ェ ア や、 Wikipe−
diaで は こ う い っ た 条 件 が 満 た され て い る。〔1)は ソ フ トウ ェ ア
や コ ン テ ン ツ を 対象 と し た 時点で 実現 さ れ るが、 や は そ の
よ う に は い か な い 。 タ ス ク内容 や 開発 プ ラ ッ トフ ォーム な どが
要 因 と して考え られ るが、特に 評価 指 標 の共 有 が 重要 で あ る と
考え られ る。評価 指標 が共 有 な され て い な い と、部分 の 貢 献が
全 体 へ の 貢 献 に つ なが らな か っ た り、最終成 果 物に す る コ ス ト
が 膨 大 に な っ た り して し ま う。速 く ・軽 く ・正 確に 動 く こ と が
求 め ら れ る ソ フ トウ ェ ア や、客観性が 求め ら れ る 百科事典な ど
は 条件を満た し て い る こ と が わ か る 。
Linuxや Wikipediaは た く さん の 人 々 の 間 で一
つ の 目標 が 共 有
され、そ こ へ 向 か っ て 集合 知 が 動 き 出 した ケース と い え る が、
た くさ んの 目標 (解決すべ き問題)に 対 して 集合知が 機能する
と い う ケー
ス も あ る。Yahoo Answers の よ うな QA サ イ トが ま
さ にそ れ に 当 た る。サ イ トに は 多 くの 質 問が 投 げ か け ら れ る
が、そ こ に い る 多く の 参加者の 誰か が そ の 答え を 知っ て い て回
答する 。 こ れ は い わ ば分離型の 集約 に よ る集合知で あ る。米国
16デザ イ ン 学 研 究特集号special issueofjapanesesocietytorthescienceetdesign
Vol.17−4 No.682011
Innocentive社 が 提供 す る サービス で は、研 究 開 発 案 件 を 持 つ
企 業 と、登 録 され た 10数 万 人 の 研 究 者 と の マ ッ チ ン グが 行わ
れ て い る。こ れ も分 離型 の 集合知 と い え よ う 。 こ う い っ た 多数
の 専 門家 に よる 問題解決は、コ レ クテ ィ ブ ・イ ン テ リジ ェ ン ス
とも 呼 ばれ る 。
JefF Howe は こ の よ うな 多 くの 人 々 に 問題 を投 げか け て 解決す
る方 法 を クラ ウ ドソー
シ ン グ と よ び、こ の よ う な解 決 方 法が 成
立 した背 景 に は 4 っ の 進 歩 :(1)ア マ チ ュ ア 層 の 増 加、 オープ
ン ソー
ス とい う 生 産 方 式 の 登 場、〔3澗 題 解 決 に必 要 な ツール の
コ モ デ ィ テ ィ 化、(4)オ ン ラ イ ン コ ミ ュ ニ テ ィ の 進 化、が あ る と
した [HoweO9 ]。こ れ ら は特定 の サービス 内 で 起 きて い る こ
とで は な く、ウ ェ ブ全 体 にお い て 起 きて い る こ とで あ る。最近
で は Web API (ウ ェ ブア プ リケーシ ョ ン プロ グ ラ ミ ン グ イ ン タ
フ ェー
ス ) を持 つ ウ ェ ブ ア プ リ ケーシ ョ ン が 多い が 、こ れ は
ユー
ザ に と っ て 適切 なイ ン タ フ ェー
ス を ク ラ ウ ド ソー
シ ン グ し
て い る とも い える 。例 えば Twitterは APIを 利用 した ク ラ イ ア ン
トア プ リケーシ ョ ン は 数 百 も あ り、多 くの ユ ーザ が 標準 の ウ ェ
ブ イ ン タ フ ェー
ス で は な く、専用 ク ラ イ ア ン トか らTwitterを
利用 し て い る 。
こ の ケース は、Twitterが 依頼者 と い う わ け で も な く、ユ
ーザ
が依 頼 者 とい うわ けで も な く、た だ API をオープ ン にす る こ と
で イ ン タ フ ェー
ス 構築 と い う 難 し い 課 題 を解 か れ て い る 点 が興
味 深 い。Donald Norman は 著書 「誰 の た め の デ ザ イ ン ?」 に
お い て 、人 工 物デ ザ イ ン に お け る 3 つ の メ ン タル モ デ ル :デ ザ
イ ナー
が も つ デ ザ イ ン モ デ ル、シ ス テ ム が持 つ シ ス テ ム イ メー
ジ、そ して ユー
ザ が 持 つ モ デル、を挙 げ、デ ザ イ ン モ デ ル が
ユ ーザ が 持 つ モ デ ル に近 づ くこ との 重 要性を 述 べ た [Norman
90]。しか し、様 々な 背景 を持つ ユーザ の メ ン タ ル モ デ ル を適
切 に 見 抜 くこ と は 容易 で は な い。
だ が こ こ で ウ ェ ブ と い う プ ラ ッ トフ ォーム を用 い る と、制 作
者 は 素 直 に 自分 が 描 くデ ザ イ ン モ デ ル に従 っ て シ ス テ ム を作
り、そ れ を公 開 す れ ばよ い。 そ れ に 合 っ た メ ン タル モ デ ル を持
つ ユ ーザが い れ ば利用 して も ら え、さらに クチ コ ミ や検索でそ
れが 広ま っ て い く 。 利用 者側か らす る と 自分 が 持 つ メ ン タ ル モ
デ ル に一番適 した シ ス テ ム を選 択 すれ ば よ い。こ の よ うな 振 る
舞 い が 可能 と な っ たの は、圧倒 的 多数 の 参加 者 が 自 ら の 動機 に
基 づ い て 自由 に 振 る舞 い 、検 索 や情 報 流通 に よ っ て 人 や 情報 の
マ ッ チ ン グが 行 わ れ る とい う ウ ェ ブ空 間 に 拠 る と こ ろ が 大 き い
と考え る 。
「誰の た め の デザ イ ン ?」 に 対 す る 回答 は、理 想 は 「私 の た め
の デ ザ イ ン 」 で あ ろ う。だ が 誰 もが DIYや オーダーメイ ドで き
るわ け で はな い 。しか しウ ェ ブとい うプ ラ ッ トフ ォーム の マ ッ
チ ン グ に よ り、同 じメ ン タル モ デ ル を 持 つ 作 者 と利用 者 と が出
会 え た の な ら ば、我 々 は「私 た ち の た め の デ ザ イ ン 」 を 手 に 入
れ ら れ る 。 こ れ は 集合 知 が イ ン タ フ ェース と い う難 問 を 解 い た
と も言 え な い だ ろ うか。Twitterの よ う に う ま くい くケース ば
か りで はな い だ ろ うが、こ れは集合知の ため の プ ラ ッ トフ ォー
ム デ ザ イ ン に 示 唆的な 事例 の一
つ で あ る と 考え ら れ る。
_ _ 紐

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
4 .市民 芸 術 と集合知
我 々 は 平 成 17年 よ りJST委託研究事業「情報デ ザ イ ン に よる
市 民 芸 術 創 出 プ ラ ッ トフ ォーム の 構築 (代表 : 多摩美術大 学
須 永 剛 司 )」 と い う プ ロ ジ ェ ク ト に 取 り 組 ん で い る 。 こ れ は
(表 現 活 動 にお い て プ ロ・セ ミ プ ロ で な い と い う意味 で )
一般
の 人 々 の 表 現 活動 を、こ れ まで そ う い っ た 活 動 を 行 っ て こ な
か っ た 方 々 も 含め て、encourage し enhance しよ う とい う プ ロ
ジェ ク トで あ る 。
前 節 に て 集合 知 プ ラ ッ トフ ォーム と し て 見 た と き の ウ ェ ブ が、
参加 者 の 多 様性 確 保 の み な らず 目 的の 多様性を も持っ こ と を 述
べ た。こ れ らは 多様 で は あ る も の の 目的指向型、問題 解決型 の
集 合知 で あ っ た。で は、芸術の よ う な 目的が ある の か な い の か
よ くわ か らな い、あ っ た と し て も極 め て 個人的な、そ の よ う な
創 作活動 にお い て 集合知 は どの よう に 発揮 され うる だ ろ うか。
そ もそ も 芸術 に お い て 集合 知的 な活 動 が 無 か っ た わ けで は な
い 。新 し い 作 品 や著 作 を つ くりだ す創 造 的活 勤 は個 人 に 帰 す る
場 合 も あ る が 、複 数 の 人 が 関与 して 協 調 的 に行 わ れ る こ とも 多
い 。こ の 集 合 知 的創 造 活 動 は、か つ て は物 理 的 に 集ま れ る 数人
か ら 数 十人 程 度 の 規 模 で しかな か っ たが、近 年の イ ン ターネ ッ
トの 発達、そ して ウ ェ ブに よ っ て 、非 常 に多 くの 人 が関与す る
大 規 模 な創 造 活 動が 出 現 す る よ うに な っ た 。 そ れ は単 に規模が
変 わ っ た だ けで は な い。創造 され る 作品や著作の 種類か ら、参
加 者 の 集 ま り方、創造 活 動 へ の 関 与 の や り 方、協 調 の や り方 に
至 る ま で、こ れ ま で に な い 新 し い ス タイ ル に な っ て い る。
こ の よ うな こ とが 可能 に な っ た要 因 を、特 に そ の よ う な 活 動 が
顕著 にみ られ る 日本 に限定 し、技術的要因 と社会的要因 の 点か
ら考察 し て み る 。 ま ず 技術的要 因 で あ るが、ウ ェ ブ上 に集 合 知
が生 まれ る プ ラ ッ トフ ォー
ム が で きつ つ あ る こ と は 前節 にて 述
べ た 。 し か し前節に て 挙げた 集合知は 目的 指 向で あ り、客 観 的
指標 を 持ち得た 創作活 動 で あ っ たが、芸 術 の よ う な 主観 的 評 価
が 重 視 され る生 産物、例 え ば文 芸 作 品 やエ ン ターテ イ メ ン ト性
の 高 い コ ン テ ン ツ な ど で は ど うで あ ろ う か。こ の 点 に つ い て 濱
野 は、マ ス コ ラボ レーシ ョ ン 的な 創造活動 に よ っ て 生み 出され
た エ ン ターテ イ メ ン ト性 の 高い コ ン テ ン ツ が 国 内に 多数存在す
る と い う現 状 か ら、主 観 的評価 が 十分 に 共有 さ れ る こ と で コ
ミュ ニ テ ィ に お ける 客観的評価 とな り、こ れ に よ りマ ス コ ラボ
レー
シ ョ ン が実現さ れ て い る の で は な い か と指摘 して い る [濱
野 08 ]。
次 に社 会 的 要因 に つ い て 考 察 す る。一般 に 文 芸的 作 品 に お い て
は個 々 の 作者 の 主観 性 や個別作品 の オ リ ジナ リ テ ィ が 重 視 され
る の で、集合知的創造 活 動 は 発 生 しづ ら い と考 え られ る。一
方、日本に お い て は連 歌 や 本歌 取 り とい っ た集 合 知 的作品が 古
来よ りあ り、日本の 文 化 は比 較的 許 容 さ れや す い 土 壌 で あ る と
い わ れ て い る [山田 02]。そ の 顕 著 な ケー
ス が 漫 画等 に お け る
同人文化で あ る。漫画 等 の 同 人誌 に お い て は、オ リジ ナ ル な 作
品 も あ るが 、二 次 創作、す な わ ち商 業作 品か ら キ ャ ラ ク ター
や
ス トーリーを と っ て そ れ を改変 した り、新た に 追加 した りした
創作 も大き な ウ エ イ トを 占め て い る。こ の同 人文 化 は現 在 大 変
興 隆 し て お り、毎年 2 回開 か れ る コ ミ ッ クマーケ ッ トと い うイ
ベ ン トに は 毎回50 万 人以 上 の 人 が 参加 して い る [霜 月08]。
こ れ は非 常 に特 異 な 人 々 の 現 象 で あ ろ うか。日本 に お け る コ ン
テ ン ツ創 作 に 関与 して い る 人 は 潜在 的 に は も っ と 多い こ とが 調
査 に よ り明 ら か に さ れ て い る 匚小 山 09 ]。 こ の 調 査 は 20 代 か
ら40 代 の 日 本 人 男 女 に お け る イ ラ ス ト、漫 画、小 説 と い っ た
創 作 活動 に 関 与 に 関 す る ア ン ケー
ト調 査 で あ る 。こ れ に よ る と
6,3 % の 人 が 現 在 定期 的 に イ ラ ス トを 描 い て お り、漫画 で は 同
2.6%、小説 で は 同4.7 % で あ る。こ れ を 人 口 比 で 考 え る と創
作人口 は か な り多い こ と が わか る。しか も作 品 を イベ ン トで 販
売 し た 経験 の あ る割 合、Web な ど で 公 開 した こ とが あ る 割 合
は そ れ ぞ れ 10% 程 度で 、コ ミ ッ クマーケ ッ トや Web と い っ た
と こ ろ で 顕 在 化 して い る 作者 だ け で な く潜 在 的 に 多数 の 作者が
い る こ とが わ か る。また オ リジナ ル 創 作 と二 次 創作 の 割合は 漫
画 で お お よそ 2 : 1 、小 説 で 3 : 1 で、二 次 創 作 が 無 視 で き な
い 量 で 存在 す る こ と もわ か る 。 こ の よ う に少な く と も 日本に お
い て は 二 次 創 作 と い う形 で の 集 合 知 的創造 活動 は 大規模か つ一
般 的な 現象 にな っ て い る 。
5 .事例 :集合知 とニ コニ コ 動画
前章 にて 、日本 に お け る集 合知 的 創造 活 動 の 技 術 的 ・社会 的 要
因 を述 べ た。本 章で はニ コ ニ コ 動 画 とい う ウ ェ ブサービス で 起
きて い る 集合 知 的創造 活動 に つ い て 述 べ る。
5.1,ニ コ ニ コ動 画
二 コ ニ コ 動 画 [NiwangoO6 ]は 国 内 に お い て も っ と も 有 名 な
動 画共 有 サ イ トの一
つ で あ る 。 2006 年 1 月 に サー
ビス 開始 し、
2009 年 1 月 の 時点 で ユー
ザ 数 は 1100 万 を 数 え、登 録 さ れ た
動画数 は 200 万 本を越 える。基 本 的 なサービス は世界 的 に有 名
な 動 画 共 有 サ イ トで あ る YouTubeとほ ぼ 同 じで あ る が、幾 つ
か の ユ ニ ーク な機 能 を持 ち、急速 に 多 くの ユーザ を 獲 得 し た。
も っ とも特徴 的 な の は動 画 の 上 に コ メ ン ト を重 畳 表 示 で き る機
能 で あ る。ユ ーザ は コ メ ン トを 動 画 再生 中の 任 意の 時 間 の (あ
る 程度 ) 任 意 の 場 所 に コ メ ン ト を 表 示 す る こ とが で き、ユ ーザ
はま る で 多 く の 人々 と 同時に 動画 を 見 て い るか の よう な感 覚 を
味わえ る 。
一方で 作者 に と っ て は、視聴 者 が どのポイ ン トに特
に 興 味を 持 っ て くれ た か を知 る こ とが で き る。
ニ コ ニ コ 動 画 に お い て、人 気 力テ ゴ 1丿の
一つ が MAD 動 画 と 呼
ば れ る もの で あ っ た。こ れ は オ リ ジナ ル の ア ニ メ 作 品 か ら動 画
や 音楽を 取 っ て き て つ な ぎ合 わせ る こ と で 新 しい 動 画 を作 成 す
る と い う も の で あ る。こ れ は 既 存 の 動 画や 音楽 や画像 を マ ッ
シ ュ ア ッ プ し て 動 画 を作 っ て い る とい え、マ ッ シ ュ ア ッ プ型の
動 画 作 成 と も い え る。ニ コ ニ コ 動画の 特徴に より、MAD 動画
の 作 者 は互 い に刺 激 しあ い な が ら 多 く の 動画 を再 び ニ コ ニ コ 動
画 に ア ッ プ ロードし た。
MAD 動画の 重要 なポイ ン トは、商用 ア ニ メ 番 組か ら 多 く の パー
ツ を 抽 出 し て 用 い て い る 点 で あ っ た。こ れ は 人 気 の 番組を 異
な っ た視 点 で 見 られ る と い う点 で 人 々 に と っ て メ リ ッ トが あ っ
た とい え る が、当然な が ら 著作権的 な 問題 が残 る。初音 ミ クの
デザイ ン 学研 究特集号
sPecLa )Issueotlapanese society forthescience ot designVoi 17・4 No、68 2el1
_ 叫17

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
登 場 は、こ の よ う な MAD 動 画 に 新 し い 方 向性 を 与 え た と い え
る。初 音 ミ ク動 画 で は、商用 コ ン テ ン ツ か ら 素 材 を と っ て くる
の で は な く、コ ミ ュ ニ テ ィ が 作 り 出 し た 動画 か ら 素 材 を 得 て 、
新 しい 動画が 作 ら れ て い る。
5.2 ,初 音 ミ ク
初音 ミ ク [CryptonO7 ]は合 成 音 声 に歌 を 歌 わせ る ソ フ トウ ェ
ア で ある 。 エ ン ジン 部分 は YAMAHA 株 式 会 社 に よ り開 発 され
た もの で あ り、ユ ーザ は コ ン ピ ュータ ミ ュ
ージ ッ ク の よ う に 曲
と歌詞 を入 力 して ソ フ トウ ェ ア をチ ュー
ニ ン グ す る こ と で 歌 唱
付 きの 合成 音 を 作 り出 す こ とが で き る。初 音 ミ ク は Vocaloid 2
と呼 ば れ る 合 成 音声 ソ フ ト ウ ェ ア の バージ ョ ン で あ る が、興 味
深 い の は そ こ に ア ニ メ キ ャ ラク ター
が 当て られ て お り擬 人 化 さ
れ て い る 点で ある 。 初期 に お い て は す で にあ る 曲 を初 音 ミ クに
歌わせ る と い う こ と が 行 われ たが、次第 にオ リジナ ル 曲が 歌 わ
れ るよ う に な っ た。
同 時 に、初 音 ミ クの マ ス コ ッ ト化も 進 ん で い っ た。最初 は た っ
た一っ の 企 業側 で 提 供 し た 初音ミ ク の イ ラ ス トだ け で あ っ た。
しか し人 々 が 新 し い 初音 ミ ク の イ ラ ス トを 作成 し投 稿 す る よう
に な り、さ ら に そ れ ら オ リ ジ ナ ル ソ ン グ や イ ラス トを用 い て、
ミ ュージ シ ャ ン の PV の よう な動画 の 作成 も行わ れ だ した 。
図 2 は 初音 ミ ク に お け る協調 的創造 活 動 の 例 で あ る。minato
氏が 「流星 」 と い う タイ トル の 動 画 を ア ッ プ ロ
ード して い る。
こ れ はオ リ ジナ ル ソ ン グ とオ リジナ ルの イ ラ ス トで 構 成 され た
もの で あ る。しか しminato 氏 が作 成 した の は オ リ ジ ナ ル ソ ン
グ と初 音 ミク の チ ューニ ン グ の み で、イ ラ ス ト に 関 し て は 他の
作者 の も の を借 りて き て い る 。 ussy 氏 は 初音 ミ ク の プ ロ モー
驫撫
シ ョ ン ムービーの よう な動 画 を作 成 し て い る。こ の 動 画 で は オ
リジナル ソ ン グ と初 音 ミ ク の 3D モ デ ル と 多く の イ ラ ス トが 利
用 さ れて お り、そ れ ら全 て が他 の 作者 に よる も の で あ る。こ の
協調的創作活動は こ こ で 留 ま らず、FEDis氏 は さ ら に新 しい 動
画 (ussy 氏 が作成 した 動 画 の 長 編 ) を作 成 して い る。こ れ ら
の 動画は MAD 動 画 の マ ナーに し た が っ て 作成 さ れ て い る 。多
くの 動 画 は一部 を借用 す る と 同 時 に新 しい コ ン テ ン ツ を 付 け 加
え る こ とで 、新 し い 作 品 と し て い る 。 ま た 、元 の コ ン テ ン ツ の
作 者が 極 力 わ か る よ う に し て い る。この た め 多く の 作 者 は他 の
作者 か ら 引用 さ れ る こ と を歓迎 して い るよ うで あ る。そ の 結果
と し て、多 くの 動画 が集合知的 創作 活 動 に よ る作 品 と して 公 開
さ れ る 。 初音 ミ ク に お け る集合 知 的 創 作 活 動 で 興 味 深 い の は、
異 な るタ イ プ の 創 造活 動 が 交わ っ て い る 点 で あ る 。例 え ば コ ン
ピ ュー
タ ミ ュー
ジッ ク分 野 の ク リ エ イ ター、同 人誌 やイ ラ ス ト
分 野 の ク リエ イ ター、さ ら に は CG ク リ エ イ ターな どで あ る.
大半 はア マ チ ュ ア で ある が、中 に は プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル の 人 も
い る。
我々 は分析 にあ た り、初 音 ミ ク に関す る創 作 活 動 を以 下 の よ う
に分 類 した。
〔a 〕作曲 : ア マ チ ュ ア 作曲者は 自身の 歌を プ ロ モー
シ ョ ン す る機
会 を望 ん で い る が、一般的に プ ロ の 歌手 に歌 っ て も ら うの
は 時 間 的 に も 金 銭 的 に も困 難 で あ る。しか し現 在 は、コ ン
ピ ュータ ミ ュ
ージ ッ ク の よ うな感 覚 で、自身 の 歌 を歌 唱 して
も ら う こ と が 可能 で あ る。こ れが ア マ チ ュ ア 作曲者が オ リ ジ
ナ ル ソ ン グ を初音 ミ ク に 歌わせ て 公 開す る の を 促 し た 。
(b鯛 整 ;初音 ミ クに 自然に聞 こ え るよ う な声で歌わ せ る の は容
易 で は な い 。 初音 ミ ク をチ ュー
ニ ン グす る確 か な技 術 が必 要
smby
sm1381337
by mikuru396
図 2 二ニ コ ニ コ動画に お ける 初音 ミ ク動画の 引用ネ ッ トワ ークの 例
各画像 は 動画 ま た は イ ラ ス トを 表 し て お り、矢印 が 引用 関 係を 示 して い る。始 点 の 動 画 や 画 像 が、終 点 の動 画 に て 引用 され て い る。矢印 の ラ ベ ル は どの 部分 を 引 用 し た か を示 し て い る。な お 、動 画 の 画 像 は い ずれ もニ コ ニ コ 動 画 よ り、イ ラ ス トの画像 は い ず れ も ク
リプ トン社が 運 営す る コ ン テ ン ツ共 有サ イ ト「ピア プ ロ 〔http:〃piapro.jp/)」 よ り転載 。
18デ ザ イ ン学研 究 特集号
special issue ofjapanese society terthescience of designVol.17−4 No.682Q11
_ _ レ

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
と な る。そ の た め、楽 譜 や歌 詞 を 入 れ て ボ ー力 ロ イ ド用 の
デー
タ に 変 換 した だ け で 投 稿 して い る ケース も ある 。 しか し
一方 で チ ュ
ーニ ン グ は よ り良 い 曲 を作 る と い う 楽 し み を 伴 う
作業 で もあ り、作 者 の 中 には 互 い にチ ュー
ニ ン グの 腕を競 い
合 うか の よ う に 作 品 を公 開 し て い る ケー
ス も あ る。「調 整 」
とい う言 葉 か ら は 主 に 後 者 が 想起 さ れ る が 、本研 究 で は既 存
の 楽 曲 をボーカ ロ イ ド用 コ ン テ ン ツ と し て 変 換 し た だ け の 前
者 の ケース も調 律 と い う カ テ ゴ リ に 入 れ る。こ れ は 前 者 も後
者 も、初 音 ミ ク に あ る 楽曲 を 歌 わ せ る こ と に 動画 の (コ ミ ュ
ニ テ ィ 内に お け る )オ リ ジナ リテ ィ が あ る とい う点 で 同一で
あ る と判断 し た ため で ある。
(c )作画 ;初 音ミ クの イ メージ図 は典 型 的 な ア ニ メ キ ャ ラ ク ター
で あ り、アニ メ フ ァ ン の 興 味 を惹 きつ けた。彼ら は 自分 自身
で お気 に入 りの キ ャ ラ ク ターを描 き、様々 な 情景 や 表 情 の 初
音 ミクイ ラ ス トを作 成 し、さ ら に は ア ニ メー
シ ョ ン を 投稿 す
る も の も現 れ た。
(d騙 集 :初 音 ミ ク 動 画 は 膨 大 に あ る。中 に はお 気 に入 りの も の
を 集 め た り サ マ ラ イ ズ し て ラ ン キ ン グ付 け した動 画を 投稿 し
た りす る 作者 も い る。本研 究 で は、こ の よ う な 他 の 作者 が
作 っ た 動 画 を、ある テーマ にも とつ い て ま とめ て 新 し い 動画
に して い るケー
スを 編集 と呼 ぶ。
5.3.初 音 ミク動 画の 分 析
初音 ミ ク動画に お ける 集合 知 的 創作 活 動 に 関す る 分 析 結 果 に つ
い て 述 べ る。な お 本 分 析 の 詳 細 は [濱 崎09 ] を参照 し て い た
だ く と し、本 稿 で は概 略 の み を述 べ る。初音 ミ ク 動 画 に お い て
は、前節で 述 べ た とお り、引用を通 して作品 が集合知的 に作 り
出 され て い る 。 そ こ で こ の 引用 関係 に着 目 し、分析 を行 っ た。
ニ コ ニ コ 動 画 に投 稿 され た動 画 に は投稿 者 が 付け た タイ トル と
説明文 が ある。他 の 動 画 か らデータ を引用 した 場合 に は 、そ の
元 デー
タ を持 つ 動 画 へ の 八 イ パー
リ ン ク が 説 明 文 に し ば し ば書
か れ て い る。こ れ を辿 る こ とで 引用 関係 の ネ ッ トワーク を作 成
す る こ とが で き る (図 3 )。動 画 A か ら 動 画 B に 引 用 が あ っ た
場 合、そ れ ぞ れ の 作 者 の 間 に も 引用 関係 が 成 立 す る と 考 え る
と、動 画間の リ ン クを 元 に し て 作者間 の リン ク を作 成 す る こ と
が で き る 。 以後 は こ の ネ ッ トワーク を作 者 の ソー
シ ャ ル ネ ッ ト
ワーク と し て 扱う 。
図 4 は各 力 テ ゴ リ問 の 関係で あ る 。 ノー
ドが カ テ ゴ リ、リン ク
が 各力 テ ゴ リ に 属 す る 作者間 で の 引用 関係 を示 して い る。ノ ー
ドの 大 き さが属 す る 作者 の 数、リ ン ク の 太 さが 作 者 間 の 引用 関
係 の 数 を 示 し て い る 。リ ン クの 横 の 数字 は各力 テ ゴ リ が持 つ 引
用 関係 に お け る 引用 元 の 割 合 を 示 した も の で ある 。 例え ば作画
力 テ ゴ リの 引 用 元 の 28% は作 曲 力 テ ゴ リ で あ る 。 な お、カ テ
ゴ リ間 の 引 用 関 係 の 数 が 50以 下 の 場合 は リ ン クを表示 して い
な い た め、全 て の リン ク の 数 字 を足 し て も 1.0に は な らな い 。
図 4 か ら作曲が 特 に 多 くの リン ク を集 め て い る こ と が わ か る。一方 で、作画 は 多 く の 作 者 が い る にも 関わ ら ず、被 リ ン ク 数 は
少な い こ と が わ か る。こ の こ とか ら、作曲 が創作活 動 を 誘 発 す
‘.
涙講;/111 裏、、 ♪
図 3 .ニ コ ニ コ 動 画 に おけ る 初 音 ミ ク動 画 の 引用 ネ ッ トワ ーク (一部)
( 急 ・(整
作 曲&作画
」v . ,・
図4 .創作力 テ ゴ リ間の 引用関係
1000 ・} 全 体 .
辷 !
、。。Ly ・93487 ,.・z・・ 1
4101
、
・
r 、
一茄 ド∴
1 ;
014 」
図 5 .作者の 被 リ ン ク数 の 分 布
作曲
y=13.891 ×.0731
作曲&厠 整 &作画
作 画1… y三130.28x.1.4Bi
r.一._一. し _、 1GOO i 、。 IQ 1000
∫
る の に 大 き く影 響 し た こ と が わ か る。同時 に、作画が参加 者の
裾野 を 広 げて い る こ と も伺 え る。
次 に創 作 力 テ ゴ リ単位 で は な く作者単位で 見 て み る。図 5 は横
軸 が被 リン ク数、縦軸が人数を 示す両 対数 グ ラ フ で あ る。左 が
全体、中央 が作曲力 テ ゴ リ に 属 す る作 者 の み 、右 が 作画 力 テ ゴ
リに属す る 作者の み の も の で あ る。創 発 的 な ネ ッ トワーク に お
い て 被 リ ン ク 数 は べ キ 分 布 とな る こ と が 多い が、こ の ネ ッ ト
ワ ーク も同 様 の 傾 向 が見 ら れ る。つ ま り、ご く一
部 の 人 が 大 多
数 の 引用 を 引 き受 け て い る とい う こ と を 示 し て い る。
集合 知 的な創作 活 動 に お い て 、中 心 的 な 人 物 が 生 じる こ と は
Wikipediaに お い て も見 られ る一般 的 なケース で あ る 。 し カ・ し
Wikipediaと異 な る点 は、中心 的 人物 と い う 組織的構造 と、創
作 にお ける 作 曲 作 画な どの 役割 と の 間 に 関 係 が あ る 点 で あ る。
初 音 ミク動 画 で は 作 曲 と い う 創 作 力 テ ゴ リ を 含 ん で い る 人 が、
静欝 1∵∴::∴ !

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
inspireされ る 人 を増 や す、つ ま り創 作 活 動 の 牽 引役 と な っ て
い る と考 え られ る。そ して そ れ に多 く呼 応 し て い る の が作画カ
テ ゴ リである。また、作画 カ テ ゴリ間で も 引用 関係が あ る。そ
こ で は作画を 中心 と し た コ ミ ュ ニ テ ィ が形成され て お り、キ ャ
ラ ク ター化や 3D モ デ ル 作成環境 の 充実化が な さ れ て い た。
5.4.集 合知 的 創作活 動 を促す 場の デ ザ イ ン
初音ミ ク動画を取 り巻 くコ ミュ ニ テ ィ の 構造は、誰か がデ ザイ
ン した訳 で は な く、ニ コ ニ コ 動 画 や初 音 ミク と い っ た特 色 あ る
ツールが 搆成 す る 場 か ら創発 され た もの で あ る。そ の よ う な場
は どの よ うな特徴を 持っ て い る の だ ろ う か 。 ま た、そ れ は どの
よ うに し て 作 り出し う る だ ろ う か 。
初音 ミク動画 にお け る 集合知的創作活 動 の基 本 は 引用 にあ る。
引 用 の 仕 方 は音楽 や イ ラ ス ト、3D ポ リゴン データ な どデータ
を そ の ま ま転 用 した 物 か ら、ア イデ ア だ けを 借 用 し た 物 ま で、
多 岐 にわ た る。初 音 ミク は著 作権 者 で あ る ク リ プ トン・
フ ユー
チ ャー・
メ デ ィ ア が 利用 を 許 可 し た た め、様 々 な 関 連 デー
タ が
イ ン ターネ ッ ト上 に て 流 通 し た。著作権問題 は 集合知 的 創作活
動 に と っ て 大 きな 問 題 で あ る 。 Lessigは イ ン ター
ネ ッ ト上 で の
作品流通 を進め るた め の仕組み として、再 利 用 を 許可す る意志
を作 者 が簡 単 に表明 で きる よう、Creative Commons とい うライ
セ ン ス を考 案 した。非 商 用 コ ン テ ン ツ にお い て は こ の よ うな 方
法 で 法 的問 題 を解決 で きる が、商 用 コ ン テ ン ツ とな る と難 し い。
ニ コ ニ コ 動 画 に お い て 初 音 ミ ク 動 画 同様 に 人気 の あ る コ ン テ ン
ツ と して 、ア イ ドル マ ス ター
動 画 が あ る。こ れ は ナ ム コ バ ン ダ
イ の 同 名 の ゲーム を も と に し た もの で あ り、作 中 の キ ャ ラ ク
ターを転 用 した様 々 な動 画 が投 稿 さ れて い る。しか し初 音 ミク
動 画 と異 な り著作権 的 に再配布が 禁 止 さ れ て い る た め、関連
デー
タの 再配布 は (少 な く とも大 っ ぴ ら に は )行 わ れて い な
い 。本来 は 動画 投 稿 も グ レー
で は あ る が 、こ う い っ た コ ミ ュ ニ
テ ィ 的 な盛 り上が りは著 作権 者 と して も商 品価 値 が 上 が る と い
う効用 が あ る た め、黙認 して い るの が現 状 で あ る。権 利 問 題 は
大 きな課題 で あ る が、こ の 例 が示 す よ う に、集 合 知 的創 作 活 動
は権利者 と対立す る も の で は な く、む しろ 共存共栄で き る も の
で あり、そ こ に 解決の 糸口 が あ る と 考え ら れる 。
初 音 ミ ク 動 画 に お い て 関 連 データ の 流 通 を促 した 要 因 と して、
法 的 問題 の ク リ ア に 加 え て、デ ジタ ル コ ン テ ン ツ の モ ジ ュ ラー
性の 高 さ が 挙げ ら れ る。そ れ が 部品単位 で の 流 通 を 可 能 に し、
マ ッ シ ュ ア ッ プ の 自由度 を 高 め た。こ れ は 先に 挙 げた Twitter
の Web APIの話 にも通 じる も のが あ る。コ ン テ ン ツに せ よサー
ビス にせ よ、完成 され たパ ッ ケージで の み 流通 させ る の で はな
く、部 品単 位 の オープ ン な流通 も許 す こ とで 、集 合 知 が創 発 さ
れ る 場 を 生 み 出 す こ と が で き る。初 音 ミ ク 動 画 に お い て 興 味 深
い の は 、そ の 場に お い て 作者 と ユーザ の 出会い だ け で な く、作
者 同 士 の 出会 い も 生 じ て い る 点で あ る 。 こ れ に は、動画 と い う
マ ル チ メデ ィ ア 性や、ニ コ ニ コ 動 画 とい う完 成 され た パ ッ ケー
ジ で な くて も発 表 で き る 舞台 が あ っ た こ と も 大 き い と思 わ れ
る 。 作者と ユー
ザと い う画一
的な役割関係で は な く、役割自体
が 創発 さ れ る よう な場、それ こ そ が 集合知的創作活動を 生み 出
20デ ザイ ン学研究特集号special issue ofjapanese soclety fOrthe SCie ∩Ce et deSignVol.17・4 NQ.682011
す 場 の 要件 の一
つ で あ る と考 え ら れ る。
6.おわ りに
本稿で は 、ウ ェ ブ と い う プ ラ ッ ト7 オーム に よ っ て 改 め て 注 目
を集め て い る集合知 につ い て、こ れ まで 蓄積 され て きた 知 見 を
振 り返 りつ つ 現 在 起 きて い る集 合 知 の 事 例 に つ い て 紹介 を行
い 、集 合知 が 創 発 され る 場 の デ ザ イ ン とそ の 可能性 につ い て 考
察 した 。
本 稿 で 紹介 した の は、様 々 な人 々が 語 る集 合 知 を創 発 す る た め
の 要 件 で あ っ た。コ ラム ニ ス ト、会 社 役員 か ら複 雑 系、認知 科
学、社 会心 理 学 の 研 究 者 ま で、あ ち こ ち か らの つ まみ 食い で 節
操 の な い もの とな っ て しま っ た が、こ れ も集合知 の 要件で あ る
多様性の ため と思 っ て ご 容赦 い た だ きた い 。 本来な ら ば 適切な
集 約 を 行 うべ きな の だ が、筆者の 力不 足 で そ こ ま で に は 至 っ て
い な い 。 皆様 との 議論に よ っ て た ど り着け れ ば と 思 う。
最 後に 紹介 した初 音 ミク 動画 に見 られ る 集 合 知 的創 作 活 動 は ま
だ まだ特 殊 な ケー
ス で あ る が、情 報 技 術 が可 能 に した新 しい 創
作 活 動 ス タイ ル と して 、多 くの 可能 性 を感 じ させ る 事 例 で あ る
と考え る。集合知 の 源は 多様な参加 者で あ る 。 初音 ミ ク動画 は
も ち ろ ん の こ と、ウ ェ ブ 上 の 多 く の サービス 、さ ら に は ウ ェ ブ
で す ら、確保で きて い る 人々 の 多様性は、人類全体か ら見 れ ば
ま だ まだ十分 と は言 えな い だ ろ う。小 学生、幼 稚 園児、お じい
ち ゃ ん、お ばあ ち ゃ ん、海外 の 人 々、特 に こ れ か らイ ン ター
ネ ッ トに接 続 され て い くで あ ろ う発 展 途上 国 の 人 々、こ れ ら が
参 加 し出 した とき、集 合 知的 創作 活 動 が ど の よ う な もの を生 み
出す の だ ろ う。
そ の た め に必 要 な の は、よ り多 くの 人 々 に参加 して も らう こ と
で あ る。Vbcaloidは 歌 えな い 人 に も歌 唱付 きの 楽 曲 を創 作 で き
る よ う に した。技 術 に よ っ て で き る こ とが 拡 大 して い く こ と
は、そ の一助 と な る だ ろ う。しか しで き る だ け で は な く、人 々
が実 際 に しな け れ ばな ら な い。よ り多 く の 人 が 「で き る 」 よ う
に な る た め の デ ザ イ ン (ユー
ザ 中心 デ ザ イ ン 、ユ ニ バー
サ ル デ
ザ イ ン 、な ど )は 行わ れ て い る が、多 く の 人 が 「す る 」 よ う に
な るた め の デ ザ イ ン は、ま だ まだ こ れ か らで あ ろう。そ して そ
の よ うな取 り組 み の 先 駆 者 た ちが本 特 集 号 の 他 の 執筆 者 の皆 様
で あ る。皆 様 の ご 活躍を 心 か ら期待 した い。
集合知は イ ン ター
ネ ッ ト、そ して ウ ェ ブ と 出会 う こ と で そ の 可
能性 を大 き く変 え た。万 里 の 長 城 が 何 人 の 労働 者 の 参 加 に よ っ
て 作 られ た か 寡 聞 に して 知 らな い が、1000万 人 は くだ らな い
だ ろ う (ち なみ に 日本最大の 古墳で あ る 仁徳天 皇 陵の 労 働者数
は 大林組 の 試算 に よ る と670 万 人 ら し い )。 強 制で は な く自 由
な参加 で、生存の ため で は な くただ 楽 し い か ら とい う 理由で 、
人類史上最大参加者数の 創作物が で き あ が っ た ら、こ れ ほ ど痛
快 な こ と は な い 。集合 知 の そ こ まで の 発 展 に 本稿が 少 しで も 貢
献 で きれ ば幸 い で あ る。
_ _ レ

Japanese Society for the Science of Design
NII-Electronic Library Service
Japanese Sooiety for the Soienoe of Design
参考文 献
[Surowiecki O6] James Surowiecki: 「み ん な の 意 見 」 は 案
外 正 し い (原 題 :The Wisdom of Crowds )、角 川 書 店
(2006),
[Page O9]Scott E, Page :「多様 な 意 見 」 は な ぜ 正 し い の
か 一衆愚が 集合知 に 変わ る と き (原 題 ;The Difference:
How the Power of Diversity Creates Better Groups, Firms, Schools, and Societies)、 (2009 ).
[Tapscott O7]Don Tapscott, and Anthony D. Williams: ウ ィ キ
ノ ミ ク ス マ ス コ ラ ボ レーシ ョ ン に よる 開発 ・生 産 の 世 紀
へ (原題 :Wikinomics)、日経 BP 社 (2007 ).
[Fischer OO ]Gerhard Fischer:Symmetry of lgnorance, SociaI
Crea±ivity, and Meta−Design, Knowledge −Based Systems
Jo凵rnal, Vbl.13, No,7−8, pp、527 −537 (2000 ).
[Steiner 72 ]lvan Dale Steiner:Group Process and Productiv−
ity, Academic Press (1972 ).
[Howe O9]Jeff Howe:ク ラ ウ ドソーシ ン グー
み ん な の パ ワー
が 世 界 を 動 か す (原 題 :Crowdsourcing−Why the Power
of the Crowd is Driving the Future of Business)、早 川 書房
(2009 ).
[Norman 90]Donald Norman : 誰 の た め の デ ザ イ ン ?一認 知
科 学 者 の デ ザ イ ン 原 論 (原 題 ;The Psychology of Every−
day Things)、新曜社 (1990 ).
[山田 02 ]山田 奨治 ;日本文 化の 模 倣 と創造、角川書 店 (2002).
[小 山09 ]小 山 友 介 :「作 品 『で 』 楽 し む 」 コ ン テ ン ツ 創 作 の
厚 み、KDDI総研 R&A (2009)、
http:〃www .kddi−ri.jp/pdf/KDDI −RA −200904 −02−PRT.pdf
[濱野 08]濱野 智史 : アー
キ テ ク チ ャ の 生 態 系 一情 報 環境 は い
か に 設計 され て き た か 、NTT 出 版 (2008).
[霜 月08 ] 霜 月た か なか : コ ミ ッ クマー
ケ ッ ト創世 記 (2008)、
http://www .comiket .co .jp/info−a/WhatlsJpnO80225 .pdf
[Niwango O6]株式会社ニ ワ ン ゴ :ニ コ ニ コ 動画 (2006)、
http://www .nicovideo .jp/
[Grypton O7] ク リ プ トン ・フ ユ
ーチ ャ
ー・メ デ ィ ア 株 式 会
社 : 初音 ミク (2007)、
http:”www ・crypton ・co ・jp/mp /pages〆prod/vocaloid /cvO l.jsp[Lessig O7]Lawrence Lessig:CODE Version 2.0、 翔 泳 社
(2007).
[濱 崎 10]濱崎雅弘、武 田 英 明、西 村拓一
; 動画共有サ イ トに
お ける 大規模な協調 的創 造 活 動 の 創 発 の ネ ッ トワー
ク 分析
一
ニ コ ニ コ 動画 にお ける初 音 ミク動 画 コ ミ ュ ニ テ ィ を対象
と し て 一、人 工 知 能 学 会論 文 誌、Vol.25 、 No.1、 pp.157 −
167 、 (2010 ),
糴秘∴濫 !