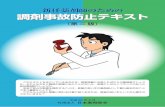特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧 …...2020/03/27 · 特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧【2020年3月27日版】
平成 25...
Transcript of 平成 25...
-
平成 25年度新潟薬科大学薬学部卒業研究Ⅱ
ウイルス性肝炎に関する研究
Studies on Viral hepatitis
臨床薬剤学研究室 6 年
08P083 八木 瞳
(指導教員:河野 健治)
-
要 旨
肝炎と言ったらまず何が思い浮かぶだろうか。
一口に肝炎と言ってもウイルス性や薬剤性、アルコール性など実に様々な種類がある。原
因によって治療法も大きく異なり、今回はその中でも日本に多いウイルス性肝炎を中心にま
とめた。
本邦のウイルス性肝炎患者数は、B型で約 7万人、C型で約 37 万人と推定されている。
また、患者数を含めたキャリア数はB型で 110~140万人、C型で約 190~230万人と言わ
れており、自分が肝炎ウイルスに感染していると気付いていないキャリアが多数存在してい
ると言える。
一般に肝臓は「沈黙の臓器」と言われており、肝炎は自覚症状が乏しい疾患である。その
ため気付いた頃には手遅れというケースも多く、早期診断が大切であると考えられる。
キーワード
1.薬害肝炎訴訟 2.劇症化 3.急性肝炎
4.慢性肝炎 5.ウイルス性肝炎 6.ラミブジン
7.インターフェロン 8.自殺企図 9.間質性肺炎
10.テラプレビル
-
目 次
1.はじめに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2.病因・病態 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
3.治療 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
4.主な使用薬剤 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
5.調査方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
6.結果 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
7.考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
9.おわりに ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
謝 辞 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
引用文献 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
-
1
1. はじめに
ウイルス性肝炎といえば薬害肝炎を連想するかもしれない。薬害肝炎の歴史は比較的
新しく、その事実が周知されるようになったのは 1987年 4月の青森県三沢市の産婦人
科病院での集団感染が新聞報道されてからである。
この時使用されていたミドリ十字の非加熱フィブリノゲン製剤の中に C 型肝炎ウイ
ルスが混入しており、当時入院していた産婦 8名が非 A非 B型肝炎(現在の C型肝炎)
に感染した。その後も患者は増え続け、2002 年 10 月 21 日、東京 13 名、大阪 3 名の
被害者が原告となり、東京地方裁判所および大阪地方裁判所において、損害賠償を求め
て提訴した。
C 型肝炎は感染すると少なくとも 75%が慢性化し、感染者の 20%は肝硬変を発症、
肝硬変から肝臓癌へと進行する重篤な病気である。
急性肝炎はわが国では届出伝染病に指定されていないため、正確な発生数は明らかで
ないが、年間約 40 万人と推定されている。また劇症肝炎の年間発生数は約 3,000 人と
推定されており、急性肝炎の約 0.75%に相当している。また、その 3分の 2の 2,000人
が死亡している(1)。
このような疾患に対して薬剤師として適切な薬物治療が行われているかどうかを評
価することも必要であるが、薬物療法の実態を把握することも大切であると考えた。そ
こで、本論文では新潟市の薬局の 1施設に協力を得て、ウイルス性肝炎患者に対する薬
物療法の実態と薬剤師としてどのように行動していくべきか調査・考察した。
年間 40万人 100万人 40万人
10% 数十年
年間 1,500人
死 亡
劇症肝炎
急性肝炎
自己免疫性
肝炎性 肝細胞癌
ウイルス性
年間 1,000人 年間 25,000人 年間 10,000人 慢性肝炎
肝硬変
アルコール性
-
2
2. 病因・病態
A) 急性肝炎
急性肝炎は肝炎ウイルス(現在までに発見されている肝炎ウイルスは A~E,G 型肝炎
ウイルスの 6 種類であるが、わが国では D 型・G 型急性肝炎はまれである。これらは
経口・水系感染と血液を介する感染に大別される)、アルコール多飲、薬剤服用などが
原因で発症する可能性がある。症状は感冒様症状(発熱、悪心・嘔吐、食欲不振、関節
痛、筋肉痛)、尿、皮膚の黄染。
B) 慢性肝炎
慢性肝炎の原因として、B型、C型肝炎ウイルスの持続感染、自己免疫性肝炎、アル
コール長期連用、ウイルソン病(銅代謝異常)、ヘモクロマトーシス(鉄代謝異常)な
どが存在する。急性肝炎や肝硬変と異なり自覚症状は少ない。
3. 治療
A) 急性肝炎
急性肝炎は C型肝炎を除き、本来自然治癒する傾向が強い疾患である。急性肝炎の
治療上、最も大切な点は極期を過ぎたか否かの見極めであり、重症化や劇症化への移
行の可能性を常に留意しながら注意深く観察し、対処することが重要である。
B) B型慢性肝炎の治療
・インターフェロン(IFN)療法
HBe型高原陽性または HBVDNAポリメラーゼ陽性活動性肝炎が対象となる。
B型慢性肝炎に対するガイドラインによると、35歳未満では IFN単独治療あるいは
核酸アナログ・IFNの sequential療法を基本とし、35歳以上ではエンテカビルを中心
に核酸アナログ製剤を投与することで、最終的にHBs抗原陰性化を目指すとある。
・核酸アナログ製剤
現在ではエンテカビル連日投与(経口)が標準的方法である。
以前は第一選択薬としてラミブジンが使われていたが、耐性の問題があるためその座
をエンテカビルに明け渡している。
ラミブジン及びエンテカビル耐性株に対しては、ラミブジン+アデホビル併用療法を
基本とする。しかし、ラミブジン+アデホビル併用療法を行って 3 年以上経過しても
HBV DNAが 4 log copies/mL以上でかつ ALT値≧31IU/Lの症例はエンテカビル+ア
デホビル併用療法も選択肢のひとつとなる。
ラミブジン、アデホビル、エンテカビルのいずれの薬剤にも耐性株が出現した症例に
対しては、エンテカビル+アデホビル併用療法あるいはテノフォビルも選択肢のひとつ
となる。
-
3
テノフォビル(ビリアード®)は海外で B 型肝炎に対して使用実績のある薬剤だが、
日本ではまだ未承認である。そのため、使用する際は個人輸入という形になる。
C) C型慢性肝炎の治療
C 型肝炎治療の目標は、HCV 持続感染によって惹起される慢性肝疾患の長期予後の
改善、即ち、肝発癌ならびに肝疾患関連死を抑止することにある。
ペグインターフェロンとリバビリンの併用が標準的な抗ウイルス療法となって著効
率は向上したが、難治性である HCV ゲノタイプ 1 型・高ウイルス量症例では同療法
においても SVR 率が 40~50%であり、約半数の症例では HCV が排除できない。
近年、治療効果の向上あるいは副作用軽減を目指して多くの新規抗ウイルス薬が開発
され、2011 年 11 月には、第 1 世代プロテアーゼ阻害剤であるテラプレビル(テラビ
ック®)がゲノタイプ 1 型高ウイルス量例に対して一般臨床で使用可能となった。テラ
-
4
プレビル+Peg-IFNα・2b+リバビリン 3 剤併用療法により、初回治療の SVR 率は約
70%と向上し抗ウイルス効果は増強したが、高度な貧血の進行、重篤な皮膚病変の出現
など副作用も増加した。
一方で、現在、わが国において第 2 世代プロテアーゼ阻害剤(TMC43514、 MK700915、
BI-201335)と Peg-IFN+リバビリンとの 3 剤併用療法、ならびに IFN free であるプロ
テアーゼ阻害剤/NS5A 阻害剤の内服剤による抗ウイルス療法などの臨床試験が進んで
いる。こうした次世代 DAAs (direct anti-viral agents)は、副作用が非常に少なく、ま
た初回治療の SVR 率 80%以上と更なる抗ウイルス効果の向上が報告されており、今後
期待がもたれる。
C 型肝炎の治療方針は、以上の現況を踏まえ、個々の症例における現時点での抗ウイ
ルス療法の適応を十分に考慮した上で決定する必要がある。
4. 主な使用薬剤
ペグインターフェロンα-2a
ペグインターフェロンα-2b
週 1 回の投与で C 型慢性肝炎のウイルス血症を改善する。血中濃度が 1 週間持続す
る PEG-IFN製剤である。重大な副作用として、間質性肺炎、肺浸潤、呼吸困難、うつ
病、自殺企図など。
小柴胡湯との併用で間質性肺炎が起こりやすいので併用は禁忌である。
インターフェロン製剤の副作用と発生率
投与例数 発生数(%)
1.精神症状(うつ病、分裂症など) 6,412 81例(1.26)
2.神経症状(意識喪失、知覚異常など) 6,412 18例(0.28)
3.間質性肺炎 6,912 14例(0.20)
4.甲状腺異常 6,312 67例(1.06)
5.自己免疫性疾患 6,912 15例(0.22)
6.糖尿病あるいはその悪化 6,312 23例(0.36)
7.腎・循環器系疾患 6,412 15例(0.23)
8.眼疾患 6,132 26例(0.42)
9.感染症誘発 6,412 10例(0.16)
10.皮膚症状(乾癬、発疹など) - 12例(-)
リバビリン(レベトール®、コペガス®)
IFNと併用することで、IFNの効果を増強させる。単剤投与は無効である。
催奇形性及び精巣・精子の形態変化等が報告されており、妊婦又は妊娠している可能の
-
5
ある婦人には投与しないこと。妊娠する可能性のある女性患者及びパートナーが妊娠する
可能性のある男性患者に投与する場合には、避妊をさせる。
テラプレビル(テラビック®)
IFN、リバビリンと併用することでその効果を増強させるプロテアーゼ阻害剤。
通常、成人は、テラプレビルとして 1回 750mgを 1日 3回食後経口服用し、服用期間は
12週間とする。
貧血や皮膚障害などの重い副作用が問題となっており、市販後調査で、重度の腎機能障
害も明らかになった。そのため副作用の出やすい 66歳以上は原則として使用を控える。
アデホビル(ヘプセラ®)
ラミブジン投与中に B 型肝炎ウイルスの持続的な再増殖を伴う肝機能の異常が指摘され
た、B 型慢性肝炎に適応する。1 日 1 回 10mg、ラミブジン 1日 1 回 100mgを併用する。
ただし、腎機能障害患者では、投与間隔の調節が必要である。
投与終了後のウイルス再増殖に伴い、肝機能もしくは肝炎の悪化が認められることがあ
る。そのため、本剤の投与終了をする場合は少なくとも 4 ヵ月間は原則として 2 週間ごと
に患者の臨床症状と臨床検査値の観察を行うこと。
エンテカビル(バラクルード®)
逆転写酵素を阻害し、B型慢性疾患における B型肝炎ウイルス増殖の抑制を行う。
0.5mgを 1日 1回空腹時に服用する。ラミブジン不応患者には、1mgを 1日 1回服用す
る。主な副作用は吐き気や下痢など胃腸症状、頭痛や倦怠感などである。
ラミブジン(ゼフィックス®)
B型慢性肝疾患における B型肝炎ウイルスの増殖抑制。
1日 1回、1錠(100mg)を経口投与する。
抗ウイルス活性としては、HBV の逆転写酵素活性阻害と DNA 伸長阻害である。投与後
速やかに血中HBVDNA量は低下し、これに伴い ALT値の正常化もみられる。
主な副作用は頭痛と倦怠感で、耐性変異出現に伴う肝炎の再燃を除くと重篤なものはま
れである。胎盤透過性があり、妊婦への投与は治療上の有益性が危険性を上回ると判断さ
れる場合のみとされている。
-
6
45歳 女性
Rp.1 バラクルード®錠 0.5mg 1錠
1日 1回 就寝前
5. 調査方法
新潟県内で薬局展開する市民調剤薬局からデータ提供の協力を得て、2012 年 11 月
(11/1~11/30)に来局した患者の処方せんからウイルス性肝炎と思われる患者を対象
とし、過去 1年間の処方せん、薬局薬歴より、年齢・性別・処方医薬品名・用量・用法・
投与日数のデータ収集・集計を行った。
6. 結果
A) 対象患者
処方せんよりウイルス性肝炎と思われる患者 15 名を対象に、過去 1 年間の処方を調
査した。処方せん 1 枚を 1 症例とし、93 例集めることができた。対象患者の平均年齢
は 52.9(40~80)歳で、そのうち男性が 7名、女性が 8名であった。
グラフを見ると、高齢になるにつれ女性患者の割合が多いように思える。しかし人数
が少数であるため、患者の性別や年齢に偏りが出ていると考えられる。
B) 代表的な処方例
処方例 1) エンテカビル単剤投与の B型肝炎患者
エンテカビルが単剤で出ている患者の処方例。今回の調査では最も多い処方だった。
エンテカビルは耐性化する確率が従来の抗ウイルス薬よりも少ない。そのため多数の患
者が処方変更なく継続服用していると考えられる。
0
1
2
3
4
5
6
7
40代 50代 60代 70代 80代
男性
女性
-
7
C) ケーススタディ
処方例 2) アデホビルとラミブジン併用の B型肝炎患者
アデホビルとラミブジンが併用されていることから、ラミブジンかエンテカビル耐性
の患者だと考えられる。アデホビルは 1 日おきに服用の指示があり、加えて 80 歳と高
齢であることから、腎機能に何らかの障害がある可能性が高い。
アデホビルは副作用に腎障害があり、腎機能障害のある患者には投与間隔の調節が必
要な薬剤である。
抗ウイルス剤の他に、へパンとラクツロースも併用されている。へパン ED内用剤は
肝不全患者用の栄養剤で、血漿や脳内の遊離アミノ酸のバランスを是正し、脳内モノア
ミン代謝異常を改善、また血漿アンモニア濃度を低下させ、肝性脳症の昏睡時間を短縮
する効果がある。通常、肝性脳症を伴う慢性肝不全患者の栄養状態の改善に用いられる。
ラクツロースは血中アンモニアを低下させ、肝性脳症を改善する薬剤である。
よって、この患者は B型肝炎発症後、肝不全まで病状が進んでいる可能性がある。
処方例 3) ウルソからエンテカビルへ処方変更された例
80歳 女性
Rp.1 ゼフィックス®錠 100mg 1錠
1日 1回 就寝前
Rp.2 ヘプセラ®錠 10mg 1錠
1日 1回 朝食後
○指 1日おき
Rp.3 ヘパン ED®配合内用剤 80g
1日 1回 就寝前
Rp.4 ラクツロース・シロップ 60%「コーワ」60ml
1日 3回 毎食後
48歳 男性
Rp.1 ウルソ®錠 100mg 3錠
1日 3回 毎食後
48歳 男性
Rp.1 ウルソ®錠 100mg 3錠
1日 3回 毎食後
Rp.2 バラクルード®錠 0.5mg 1錠
1日 1回 就寝前
-
8
この患者は長期に渡りウルソデオキシコール酸の単剤を処方されていたが、21 日分
のエンテカビルとの併用を経て、エンテカビル単剤に切り替えられた。
ウルソデオキシコール酸は肝臓の血流を増加させることで、肝細胞を保護する作用が
あり、AST(GOT)、ALT(GPT)値を低下させる。しかし抗ウイルス作用は有しておらず、
一般に効果は高くない。ウルソデオキシコール酸での肝庇護療法のみでは進行を抑えら
れず、抗ウイルス剤に変更された可能性がある。
処方例 4) リバビリンが処方されている C型肝炎患者
肝疾患用薬としてはリバビリンが単剤で処方されている。しかしリバビリンは単剤投
与は無効であるため、病院で IFNの投与が行われていると考えられる。
IFNは投与初期にインフルエンザ様症状(発熱、頭痛)の副作用があり、ロキソプロ
フェン(ロキソニン®)はこの症状の緩和を目的として処方されていると考えられる。
48歳 男性
Rp.1 バラクルード®錠 0.5mg 1錠
1日 1回 就寝前
42歳 男性
Rp.1 レベトール®カプセル 200mg 4錠
1日 2回 朝・夕食後
Rp.2 ロキソニン®錠 60mg 2錠
1日 2回 朝・夕食後
Rp.3 パリエット®錠 10mg 1錠
1日 1回 夕食後
42歳 男性
Rp.1 タリオン®錠 10mg 2錠
1日 2回 朝・夕食後
Rp.2 アンテベートクリーム 0.05% 30g
1日 2回 体幹部皮疹に塗布
※14日後、上の処方に追加
-
9
ラベプラゾール(パリエット®)は PPIであり、ロキソプロフェンの副作用である胃腸
障害を防ぐ目的だと思われる。
また、IFN投与中期(2~12週間)にはそう痒感が現れることがある。抗ヒスタミン
薬であるベポタスチンベシル酸塩(タリオン®)とステロイド外用薬のベタメタゾン(ア
ンテベート®クリーム)が痒みと炎症を抑える役割を果たしていると考えられる。
7. 考察
調査対象者が 2013 年 12 月時点で処方されていたウイルス性肝炎治療薬の種類の内
訳を図 1に示す。リバビリン(レべトール®)が単剤で処方された症例は 5例(5.4%)、
アデホビル(ヘプセラ®)とラミブジン(ゼフィックス®)の併用が 11例(11.8%)、エ
ンテカビル(バラクルード®)の単剤は 75例(80.6%)であり、他の肝炎治療薬との併
用例は 2例(2.2%)であった。
なお、今回の調査においてテラプレビル(テラビック®)が処方されていた症例は 0
件であった。臨床での使用期間が浅い(2011 年 9 月承認)こと、薬価が高いこと、前
述の副作用が影響していると考えられる。
また、今回は薬局での調査であるため、注射薬である IFN がエンテカビルと併用さ
れている割合は分からなかった。
調査期間中にウイルス性肝炎治療薬に関して何らかの処方変更があった症例は 2 例
(13.3%)であり、変更は肝庇護剤から抗ウイルス剤への切り替えが 1例、肝庇護剤と
抗ウイルス剤の併用から抗ウイルス剤の単剤への変更が 1例であった。(図 2)
75
11
5 2
エンテカビル単剤
アデホビル+ラミブジン
リバビリン単剤
エンテカビル+ウルソデオ
キシコール酸
ウイルス性肝炎治療薬処方数の割合
-
10
尚、今回はウイルス性肝炎の症例を集めたため、肝庇護剤単剤での処方は枚数から除
外した。
エンテカビル(バラクルード®)を服用している患者のうち、投与量は全て 0.5mg錠
が 1 日 1 回であった。添付文書によると、エンテカビルは成人で 1 日 1 回 0.5mg の服
用とある。今回の調査では、全てこれに沿った結果となった。
ちなみにラミブジン不応(ラミブジン服用中に B型肝炎ウイルス血症が認められる又
はラミブジン耐性変異ウイルスを有するなど)患者には、エンテカビルとして1mg を
1日1回経口服用することが推奨される。今回の調査でラミブジン不応患者と考えられ
る処方は見つからなかった。
エンテカビルの服用タイミングについては図 3に示した通り、就寝前が 39例(50.6%)、
食前か食後 2時間が 21例(27.8%)、起床時が 13例(16.9%)、空腹時が 3例(3.9%)、
朝食後が 1例(1.3%)であった。エンテカビルは空腹時服用であるので、各々の患者の
生活に合わせて服用タイミングが選択されているのだと考えられる。1例だけ朝食後の
指示があったが、起床後に変更されている。
91
2
なし
あり
図 2
ウイルス性疾患薬の処方変更の有無
-
11
8. おわりに
肝炎は現在も多くの新薬の開発が進められており、数年後にはさらなる治療法の発展
が予想されている。また、ここ数年では患者ごとに薬剤の効きやすさを事前に調べるオ
ーダーメイド医療も広がり始めており、高額でリスクの高い IFN 療法を始めるかどう
かや使用するタイミングを判断する有用な材料となっている。
日本は世界の中でも特に肝炎患者の高齢化が進んでおり、今後はより身体的負担の少
ない治療法が待ち望まれている。
謝 辞
本調査を行うにあたり処方せんデータの提供にご協力いただいた市民調
剤薬局の皆様、ご指導頂いた河野健治先生に深く感謝申し上げます。
39
21
13
3 1
就寝前
食前か食後2時間あけて
起床時
空腹時
朝食後
エンテカビルの服用タイミング
図 3
-
12
引 用 文 献
1. 肝炎―C 型肝炎の新展開 改訂第 3 版 1995 3 20
2. わかりやすい疾患と処方薬の解説 アークメディア.
3. 図説病態内科講座 第 6 巻肝・胆・膵 メジカルビュー社.
4. 肝胆膵特大号 特集 薬物治療学の進歩―この 30 年― アークメディア
5. FOCUS消化器①肝・胆・膵疾患の薬物療法 中山書店.
6. Zeyzem S, Welsch C, Herrmann E : Pharmacokinetics of peginterferons. Seminars
in Liver Disease 23 : 23-28,2003.
7. Dienstag JL, Perrillo RP, Schiff ER et al : A preliminary trial of lamivudine for
chronic hepatitis B infection. N Engl J Med 333 : 1657-1661,1995.
8. Hidehiro KAMEZAKI et al : Entecavir hydrate (Baraclude). 肝胆膵 61(6) :
997-1004, 2010.
9. 鈴木 宏, 太田康幸,滝野辰郎,他 : 協力ネオミノファーゲンCの慢性肝炎に対す
る治療効果について―二重盲検法による検討―.医学のあゆみ 102 : 562-578,
1977
10. Hiroshi YATSUHASHI : Pegasys / Copegus. 肝胆膵 61(6) : 941-949, 2010.
11. 独立行政法人国立国際医療研究センター
http://www.kanen.ncgm.go.jp/index.html
12. C 型肝炎治療ガイドライン 第 1 版 日本肝臓学会
http://www.kanen.ncgm.go.jp/index.html