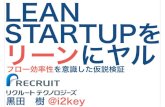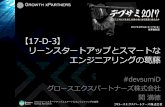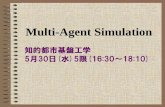「デジタルヘルスコネクト」 ワークショップ第1回...
Transcript of 「デジタルヘルスコネクト」 ワークショップ第1回...

ブレークスルーパートナーズ株式会社
マネージングディレクター 赤羽 雄二
http://www.b-t-partners.com
http://b-t-partners.com/akaba/
http://twitter.com/YujiAkaba
http://www.facebook.com/yuji.akaba
http://www.slideshare.net/yujiakaba/presentations
2 0 1 5 年 1 月 2 2 日
リーンスタートアップの考え方と具体的なアプローチ、顧客ニーズの把握方法
「デジタルヘルスコネクト」ワークショップ第1回

1 出典: http://www.dhconnect.jp/

2
内 容
1.リーンスタートアップの背景、環境
2.リーンスタートアップの本質とステップ
3.リーンスタートアップ時代の企画とサービス開発
4.企画力・思考力を大幅に強化するA4メモ書き
5.情報力の強化
6.今後の進め方
7.参考

1.リーンスタートアップの 背景、環境
3

リーンスタートアップが可能となった背景
安価で、非常に使いやすいクラウドの充実
開発環境、フレームワーク・ライブラリー等の整備 必見:「Unityを使い3次元メダル落としゲームを20分で開発」 http://d.hatena.ne.jp/umonist/20101209/p1
iPhone、Androidの普及、Facebook、Twitter等APIを公開するプラットフォームの発展
Facebook、Twitter等ソーシャルメディアの普及で、よいアプリ・サービスは一瞬で広まる
サービス拡大時の資金調達が非常に容易 4

2.リーンスタートアップの 本質とステップ
5

6
リーンスタートアップのステップ
ユーザー・顧客が泣いて喜ぶ「価値仮説」と
1人のユーザー・顧客が3人呼ぶ「成長仮説」をそれぞれ1000字で書き(14フォントでA4に1ページ)、
それぞれターゲットとするKPIを設定し(5~6個ずつ)
仮説を検証するMVP(Minimum Viable Product)を素早く構築し、
さっと検証。違ったら微妙にピボットし価値仮説、成長仮説、KPIを設定し直して、再チャレンジ
「超高速仮説構築・検証・修正型商品開発」

7
MVP(Minimum Viable Product)
リーンスタートアップでは、仮説検証のための必要最小限の製品=MVPを作り、そのMVPを使ってユーザーからのフィードバックを得て、そのデータに基づいて製品の改善を繰り返し行う
MVPは単なるプロトタイプ、デモ版ではなく、価値と成長に関して明確な仮説を持ち、それを検証するために必要な最低限のものだけを含む
製品のデザインや技術的なことだけを検証するのではなく、あくまでビジネスの仮説(=顧客が泣いて喜ぶか)をテストする
作り込みすぎたり約束しすぎたりという衝動をいかに抑えるかがポイント
出典: http://enterprisezine.jp/iti/detail/3932
http://leanstartupjapan.org/?p=490
http://www.techventurebusiness.com/archives/645

3.リーンスタートアップ時代の 企画とサービス開発
8

事業計画の意味合いが変わった
以前は、十分練った事業計画を作成することがほぼ必須だった
リーンスタートアップ的に動ける事業の場合は、事業計画を作ることに1~2ヶ月かけるくらいなら、価値仮説、成長仮説を作り、MVPを作って検証する重要性の方が高まった
最低限、デモを見せないと、投資家もこちらの力を信じてくれなくなった
つまり、パワーポイントでの事業計画よりも、企画力、開発力についての重要性が大きく高まった
9

企画上で多い問題点は . . .
誰が買ってくれるのか、よく見えない、考えてない
ユーザーが多くなるまで、サービスを使えない
どうスケールアップするのか、見えない
~できれば、~できるのだが、という他力本願
あればいいが、なくてもいいようなサービス案
気になる課題、懸念がいくつもあるサービス案
→ 本気で考え抜いていない 10

また、誤解で多いのは . . .
広告費があればユーザーを獲得できるという誤解
企画がよければ、資金調達ができるという誤解
ユーザーが集まるまで会社がもつという誤解・過信
マーケットリサーチをすると深い洞察が得られるという誤解、安易な姿勢
アイデアはいいのに、一緒にやってくれる人が集まらないという誤解、自己認識の甘さ
リーンスタートアップだから、さっさとやれば何とかなるという誤解、甘さ
11

ユーザーインタビューの方法(1/2)
ユーザーインタビューのポイント ①深刻な課題を持ち、代替案にトライしているユーザーに狙いをしぼる、②2人インタビューし、共通点、相違点からセグメント仮説を出す、③3人目で仮説検証、④ここまでで爆発的にヒットする予感がなければまずだめ。不可能ではないが、後で延々と苦労する。ユーザーに出会えていないのではなく、間違ったアイデアを追求していると思うべき
10人以上ユーザー(候補)インタビューをしようとすると、疲れるし、時間がかかるし、逆に感度が鈍る。そのプロセスで思考停止になりがち。最初の2~3人で結論を出す方がむしろ精度が高い。そこでユーザーが夢中になって話してくれれば、金脈は近い
12

ユーザーインタビューの方法(2/2)
ユーザーインタビュー時には、何で困っているかを徹底的に聞く。ひたすら聞く。全部聞く。もちろん、目を輝かせて、相づちを打ちながら。大事なポイントはすべて書き留める。その姿勢がユーザーをさらに元気づけ、もっと話してくれる
特に女性ターゲットの場合は、仲のよい友達2~3人集めてもらい、わいわい話してもらうのが一番。セグメントはあまり気にせず、まずは爆発的に盛り上がるガールズトークを聞く
ユーザーインタビューを効果的に行うには、普段からアンテナを高くし、感度を上げ、何事も深掘りする力をつけるような努力が必要。最も簡単かつ効果的なのは、毎日10枚以上メモを書くこと。感度が低いとユーザーの発言に惑わされる
13

14
自分がぜひ作ってみたい、欲しいアプリ・サービス・製品は?
多くの人が望む、喜ぶアプリ・サービス・製品は?
1人のユーザーが 3人連れてきてくれそうか?急速に成長するか?
他のアプリ・サー
ビス・製品との
違いが明確か?
企画アイデア立案ワークシート
儲ける手段が
はっきり見える
か?

企画アイデアの立案と評価
15
アプリ・サービス案
自分がぜひ作りたい
多くの人が望む
ユーザーが急増しそう
他のアプリとの差が明確
儲ける手段が見える
総合
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
◎:非常にそう思う(4点) ○:そう思う(2点) △:やや微妙(1点) ×:う~ん . . (0点)

企画アイデアの立案と評価
16
アプリ・サービス案
自分がぜひ作りたい
多くの人が望む
ユーザーが急増しそう
他のアプリとの差が明確
儲ける手段が見える
総合
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
◎:非常にそう思う(4点) ○:そう思う(2点) △:やや微妙(1点) ×:う~ん . . (0点)
①アプリ・サービス案を10~20個出し、概略を記入 ②記入後、◎○
△×で評価 ③総合点数
を計算する

アプリ・サービスを急速に立ち上げるためには?
そのアプリ・サービスを見た瞬間、ユーザーが「え? 何? すごい!」と即座に自分でも始める(見た瞬間、興味を引くこと)
すぐ使える(できるだけ、最初は余計な登録情報とかなしで、後で加える形)
その日夢中になってサイトを見続け、チェックしまくる。始めたら1時間やり続ける
使って感動し、はまり、その日以降も毎日使い続ける(習慣化する工夫、毎日ログインしていただく工夫、飽きない)
17

友達・同僚・知人に会うたびに、「これいいよ。すごいよ」とふれ回る、見せて回る(口コミ=バイラル化)
さらに、その驚き、感動をTwitter、Facebook、勉強会、交流会などで発言する(ネットでのバイラル化)
ファンとなって、改善項目をどんどん投稿してくれる(投稿ページ、Facebookページでの活発な書き込み)
ユーザーが数十人でも十分楽しく、はまってしまう。コンテンツが十分準備できたり、ユーザーが増えて初めて価値を生じるのでは、最初の谷間を越えられない。ニワトリと卵の関係を壊せない
18
アプリ・サービスを急速に立ち上げるためには?

4.企画力・思考力を大幅に強化 するA4メモ書き
19

頭がよくなり、考えが整理できるメモ書き
メモを書くねらい
–頭に浮かんだことをすべてメモに書き留めることにより、考えを整理する、頭がすっきりする
–自分が何を悩んでいるのか、はっきり見える。悩みが大幅に減る –メモが外部メモリになるため、頭の働きがよくなる –暗黙知を形式知化する
–インタビューメモ、人から聞いたお話、ミーティング議事録など、すべて一元管理できる
方法
–思いついたこと、気になること、疑問点、次にやるべきこと、自分の成長課題など、頭に浮かんだことはすべてメモに書きとめる
–メモはすべてA4コピーの裏紙に
–必ず、1件1葉で。必ず横置きで、左上にタイトル、右上に日付を書く
–頭に浮かんだことをすべて書く、ということで、毎日10ページ • 真剣に考えていれば、毎日10ページ程度にはなる
• 1枚1分で素早く書く。毎日10分程度
–夜まとめてではなく、思いついたその瞬間に書き留める、という習慣づけ 20

21
メモ見本

22
メモ見本 左に寄せて、下も少し空けて
↑
4~6行、各20~30字
A4横幅の2/3程度が目安

2013年末、「ゼロ秒思考」を出版(現在7万部超)
メモを毎日10ページ書くだけ
– A4の裏紙を横置きにして
– 4~6行、各20~30字
– 1ページ1分で
– 毎日10ページ
– 思いついた時にさっと書く
効果
– 迷いが大幅に解消する
– 自信が生まれる
– 頭がどんどん整理される
– 優先順位が明確になる
– アクションが早くなる
23 出典: http://goo.gl/xUznv6 Facebookグループ: https://www.facebook.com/groups/1493945480872832/

「ゼロ秒思考」は世界へ
24
中国版(簡体字) 台湾版(繁体字)
韓国版、タイ版が続きます http://www.knowledger.info/2014/12/30/the-power-of-real-time-thinking/

A4用紙に書く理由
ノートを使わないのは? – ノートだと、あっという間に何十冊にもなってしまう – 似たタイトルのメモがあっても整理できない – 他のA4資料等と一緒に整理できない
日記帳を使わないのは? – 似たタイトルでも整理できない – 怨念がたまる。なぜか頭の整理になりにくい
PCでない理由は? – 1分で1ページ書き出して、その場で並べてみることが全くできない – どこででも簡単に書く、ということがまだ現実的ではない – 図を素早く書けないので、文字だけで無理やり表現しようとする
スマートフォンでない理由は? – 1分で4~6行、各20~30字のスピードが出ない – 並べてみるなどが全くできない – 図を素早く書けない
25

メモを多面的に書く
重要な課題に関して、多面的にメモ書きすることが重要 例えば、「だめだと思っていることをずばっと言いきれないのは?」というタイトルのメモを書いたとすると、それに加えて
・なぜずばっと言いきれないのか?
・ずばっと言いきらないと何がまずいのか?
・ずばっと言われると相手はどう思うのか?
・ずばっと言わない自分を相手はどう思うのか?
・ずばっと言わないのは、具体的に何を指摘し、どう変えるべきかわからないからでは?
・○○さんにずばっと言うべきことは? (4~5人を具体的に)
・そもそもコーチングとは?
・ずばっと言いきるのがいい時とまずい時は? をそれぞれメモに書くと効果的 多面的に、こちら側からあちら側から、中から外から、上から下から書くことで
1.今まで見えなかった側面がはっきり見える
2.十分考えていなかったことをしっかり考えることができる
3.理解不能と思っていた相手の行動、絶対いやだと思っていた相手・自分の行動への
理解が深まる。別の見方ができる
4.全体としてもやもやが整理でき、新しい自分としての取り組みができる 26

メモ書きに対する質問
27
1分を超えたらストップすべきか? 15秒程度であれば延ばして書く。ただし、2~3分かけて書くのはよくない
同じトピックが何度も浮かぶが? 何度でも書く。気が済むまで書く
書いたメモは見返さなくてよいのか? 普段は必要ない。3,6ヶ月後に一度だけ
フォルダ分けが必要か? 初めて10日以内には7~10程度のフォルダに分ける。頭が整理される
1分で2行、10字くらいしか書けないが . . . 1分で4~6行、20~30字を絶対に書く、書けるようになるという信念で
メモは取っておくのか? せっかく書いたものであるし、取っておけば . . .

クリアフォルダによるメモ整理
28

クリアフォルダの重ね方
29

メモのタイトル例
自分の強みは?
自分の成長課題は?
今回のコンテストで自分は何をなし遂げたいか?
今回のビジネスプランの一番のポイントは?
今回のビジネスプランで強化すべきポイントは?
顧客・ユーザーが泣いて喜ぶ価値仮説は?
どうやって競合に勝つか?
30

5.情報力の強化
31

情報力を3倍増に ①
32
毎朝・毎晩、自宅で30分 ずつ記事を読む
毎朝・毎晩自宅で30分、ネットで記事を読むことをお勧めしている。日中は人に会ったり、会議があったり、必要な資料を作成したりで、何かと忙しい。ゆっくりネットで情報収集をする時間は中々取れない。取れたとしても取っている場合ではない
ネットからの情報収集は朝起きてすぐの歯磨き、夜寝る前の歯磨きのように、時間も含めて習慣化することをお勧めしたい
毎朝・毎晩自宅で30分と時間を決め、それ以上時間をかけない。時間を決めて対応することで、情報洪水の中で溺れない方法、特に優先順位のつけ方を身につけていく
特に、就寝前の30分は、タイムライン等からの記事に加え、あれと思ったり、ちょっと気になっていたり、今日わからなかったりした言葉をこまめにネットで検索し、次々に読む。これが頭と気持ちの整理に役立つ

情報力を3倍増に ②
33
PCおよび大型ディスプレイを使用
自宅では、PCの利用をお勧めしたい。なぜならば、画面が広い分、そのページ全体を見渡しやすく、過去の人気投稿等にも目がいきやすい。また、良記事のブックマークや保存・整理がスマートフォンよりも素早くできる。よい内容を投稿したりメールで友人・チームに知らせることもPCの方が早い。印刷も同様
読みやすさと総合的な生産性を考えると、スマートフォンよりPCの方が確実に早く、再利用もしやすくなる。再利用というのは、最重要記事はチーム内ですぐ共有するとか、触発された考えをパワーポイント1ページに作成するとか、最も重要な部分を印刷して書き込みをしメモと同様に保存しておくとか、PDFやパワーポイントなどの他の資料と一括管理するとかなど
PCは大型ディスプレイに接続する方が格段によい。生産性が数十パーセント違う上、疲れにくい
「スマートフォン、タブレットを使い出してからは自宅でもPCを使わなくなった、開かなくなった」という人が時々いるが、上記の理由で、お勧めできない。成長し、大きな成果をあげたいと思う人にとっては、当分、PCによる生産性の高さは捨てられない。リビングでくつろぎながらスマートフォンやタブレットで情報検索する、というのはたまにはよくても、日常的には色々な意味からお勧めできない

情報力を3倍増に ③
34
ブラウザを最適化する
ブラウザはGoogleのChromeの検索スピードが一番早くストレスがない。ブラウザを使いやすくするプラグインの種類も豊富で進化のスピードも早い
生産性を上げるには、表示件数を100にする。Chromeで検索すると、右上に歯車が出てくるので、これをクリックし「検索設定」をクリックする。「ページあたりの表示件数」がデフォルトでは10なので、これを100にする。10件のままだと、検索してもよい記事に出会わないことが多い。さらっと見て、「あんまり面白くないな」「役に立たないな」で終わってしまう。ページ下に「次へ」があるが、これをクリックし次のページまでわざわざ行くのは面倒なので、ついやらずじまいになってしまう
ところが、表示件数が100だと、クリックの必要なくよい記事に多数出会えるので、見逃すことが減り、興味がさらにかき立てられる
ちなみに、こうやってよいブログ記事に出会った時、私はその著者の過去記事をほぼ全部読むようにしている。よい記事を書く著者は、不思議なほどほぼ常によい記事を書く。宝物に出会ったようで、すごく得をした気分になる

情報力を3倍増に ③(続き)
35
ブラウザを最適化する
もう一つのお勧めは、同じく検索設定で、「結果ウィンドウ」の「選択された各結果を新しいブラウザ ウィンドウで開く」にチェックを入れ、保存することだ。
こうすれば、クリックした際に別のウィンドウが開くので、読み終えた後Ctrl+W(Windowsの場合)で閉じても他の検索結果を続けて見に行くことができる
ちょっとしたことだが、そうしないと、うっかり閉じた時、もう一度ブラウザを立ち上げ、検索ワードを改めて入力して検索しないといけないので、普通の人は続きを見るのをやめてしまう

情報力を3倍増に ④
36
何でも相談できる相手を確保
毎朝毎晩の30分ネットで情報収集するだけでは足りないものがある。それは生身の人間だ。知見と洞察力のある方からの刺激は、何ものにも代えがたい
何でも相談できる相手を同年齢、5歳年上、10歳年上、5歳年下で最低2名ずつ確保しておくと視点が大いに広がり、情報収集力、現場感、判断力が大いに強化される
私自身は、次のようにして相談相手を見つけた。各年代でそれぞれこれはという人6,7人ずつをピックアップし、アプローチする。同じ会社だけではなく、外部の方、なるべく違う立場の方も含める
こちらが普段まともに接している状況で、「一度食事しながらお話させてください」とお願いすれば、よほどのことがない限り、4,5人は受けてくれる。すぐには無理でも数ヶ月以内には実現する。(ほとんど受けてもらえない場合、自分の生き方、人への接し方、仕事のしかたを振り返る必要がある)
4,5人と個別に食事の機会ができれば、2,3人とは話が弾み、意気投合できる。相手が5年、10年先輩でも、こちらが熱心であれば、心配しなくてもそれなりに楽しく感じてくれる。ネットからの情報収集や、この本に書いてあるような活動をしていれば、こちらからも十分貢献できる

情報力を3倍増に ④(続き)
37
何でも相談できる相手を確保
そうやって見つけた相手には、半年に一度、最低でも1年に一度、食事か何らかのミーティングをして最新状況を説明しておく。助言に基づいて取り組んだ結果、こういう変化、成果があった、ということをお伝えすれば、喜んでくれる
それ以外に、数ヶ月に一度はメールで相談する。私は何か知りたいことがある場合、ほぼ同文で何人にも依頼することがある。もちろん失礼にならないように、ある程度はご挨拶や近況報告を書くが、本文はほぼ同文に近い。例えば、「電子書籍はどういうスピードで伸びていくと思いますか?」だったり、「HTML5はいつ頃本格的に普及すると思いますか?」だったりする
「何でも相談できる相手」には二つ条件がある。こちらとのやり取りを相手がある程度歓迎してくれることと、メールでの返信が早いことだ。こちらから相談するのになぜ歓迎してくれるかと言えば、こちらが真剣に何かを考えていたり、勉強しようとしたりしていることが伝わり、応援しようという気持ちになるからだ
元々、食事に誘った段階で、ある程度よい関係にある。食事をしながら盛り上がったということは、相手もこういうやり取りを喜んだことになる。その上で、時々近況報告をしたりしながら真剣なメールを送れば、十中八九真剣に答えてくれる。人は相談されることが嬉しいからだ。もちろん、こちらが真剣でなく、アイデアのただ盗りを意図していれば、すぐ見抜かれる。そもそもこういう関係が成立しない

6.今後の進め方
38

39
今後のスケジュール
第1回 1/22 リーンスタートアップの考え方と具体的なアプローチ、顧客ニーズの把握方法
第2回 1/27 価値仮説と成長仮説の確認
第3回 2/3 ビジネスモデルの検討、ビジネスプランの書き方・仕上げ方
第4回 2/10 アクションプランの検討
第5回 2/17 ビジネスプランの仕上げ(1)
第6回 2/24 ビジネスプランの仕上げ(2)
第7回 3/5 準決勝プレゼン大会
–全チーム3分でのプレゼンで審査(決勝プレゼン大会と同一の審査基準)
– 6チームが決勝プレゼン(7分+3分)、残りのチームはライトニングトーク(3分)
3/7まで6週間しかありません。3週間程度でプランをほぼ完成し、残りの3週間でさらに完成度を上げるつもりで進めるくらいがちょうどよいかと思います

40
支援体制
メンター
– 各チームにメンターが1名アサインされています
– メンターにはビジネスプランの検討に関して、色々相談してください
– 検討の主体は言うまでもなく各チームですが、メンターはできる限り知見を提供します
– メンターとのミーティングは、ワークショップの直前、直後などがスケジュールを調整しやすいと思いますが、それ以外もなるべく対応していただくようにします
事務局からの支援
– 各チームへの支援は主に赤羽から提供します。チームごとのメーリングリスト(各チームおよび事務局を含む)を使っていつでもご質問ください
– 必要に応じ、個別ミーティングも可能です
– スカイプ、電話ミーティングでも対応できます

7. 参 考
41

参考図書
42

事業計画作成: 想いを7日間でいったん形にする
頭に浮かぶものを全部メモに書き出す(50~100ページ)
それをざっとまとめる
手書きのまま、顧客候補にインタビューしてみる
新たな発見を入れ、パワーポイントに落とし込む
プレゼン練習もしてみる
そうすると課題が見え、アイデアが湧いてくる
7日で事業計画第一版ができ、次に何をすべきか見えてくる
社内の新事業でも、起業でも、SOHO・個人事業主でも
スキルアップ、情報力強化等について詳しく解説
43 Amazon: http://www.amazon.co.jp/dp/4756916902/ Facebookグループ: https://www.facebook.com/groups/1002910873057800/

44
より本格的には . . .
出典: http://www.slideshare.net/yujiakaba/ss-7021997

45 Version 1.4
目 次 1. はじめに 4
–総務省 ICTベンチャー向け事業計画作成支援コースの意義 5
–本マニュアルのねらい 6
–本マニュアルでのベンチャーの定義 7
–本マニュアルでの顧客、ユーザーの定義 8
–ベンチャーを成功させる社長の要件 9
–ベンチャーへの誤解、取り組みの甘さ 11
–急成長を目指すベンチャーの創業時に目指すべき水準 12
–創業準備から上場後の成長まで 13
–会社設立に向けての創業融資 16
– 1章終了後のチェックリスト 17
2. 事業計画作成のポイント 18
–事業計画に多く見られる問題点 19
– 「説得力ある合理的な事業計画」を作成するために 20
–事業計画作成チェックリスト 21
–エグゼクティブサマリー 22
–主要経営陣の略歴 23
–事業ビジョン 24
–製品・サービスの特長とビジネスモデル 26
–ターゲット市場と市場規模、成長性 27
–顧客・ユーザー特性 29
• 顧客の切実なニーズをしっかり把握したのか、
製品・サービスの市場性を徹底的に確認したのか 30
• 市場性確認のメリット 31
• 情報開示を抑えつつ、顧客候補の切実なニーズを探る 32
• フォーカスグループインタビューの実施 33
–勝ち続けるための独自の優位性 34
–戦略的提携 35
–事業戦略のまとめ 36
–全体スケジュール 37
–社内組織: 開発・調達・生産・営業体制 38
–実行計画 39
–数値計画: 売上・粗利シミュレーション 40
–数値計画: 損益計算書、資金繰り表、貸借対照表 41
2. 事業計画作成のポイント(続き) –事業リスクの整理と対応 42 –事業計画作成後のチェックリスト 43 – VCは何を求めているのか、事業計画作成への意味合いは 44 –事業計画をプレゼンする際に 45
3. 事業計画テンプレート例 46
– 3章終了後のチェックリスト 83 4. 会社設立 84
–創業メンバーの決定 85 –創業メンバーが前職から退社し、会社を設立する前に 86 –オフィスの決定、整備 87 –設立登記書類の作成と手続き 88 –顧問弁護士の決定 89 – 4章終了後のチェックリスト 90
5. 社内の方針決定=事業計画の議論、確定、確認、修正 91
–事業計画への合意形成、コミットメント確立 92 –経営会議での素早く、的確な意思決定 93 –週次の課題進捗会議での厳しいフォロー 101 –事業計画の確認、修正、抜本的見直し 102 –じり貧状況からの脱却 103 –取締役会の効果的な運営 105 –効果的な会議のやり方 106
• ホワイトボードの活用 107 • 事業アイデアのブレーンストーミング 108
– 5章終了後のチェックリスト 109
6. ベンチャーの経営=事業計画の日々の実行 110 –競争力ある商品・サービスを開発する 111 –顧客を開拓し、一刻も早い売上を実現する 112 –提携を積極的に推進する
• 戦略的提携の進め方 113 • 契約書の作成、修正、調印 115 • 開発費用の獲得 116 • NDA(秘密保持契約)の結び方 117 • 弁護士の使い方、活かし方 118

46
「速さは全てを解決する 」1/23にダイヤモンドから出版
Amazon: http://goo.gl/XclbkY Facebookグループ: https://www.facebook.com/groups/582229468576375/
仕事を限界まで速くするためのノウハウを徹底的に説明
目次
– 第1章:速さは全てを解決する
– 第2章:スピードを上げるための8つの原則
– 第3章:思考のスピードを上げる具体的な思考法
– 第4章:スピードと効率を極限まで上げるノウハウ

47
「頭を前向きにする習慣」を 幻冬舎から12/1に出版
Amazon: http://goo.gl/frE73R Facebookグループ: https://www.facebook.com/groups/725048367582553/
前向きになれずに困っている人が多い
– 前向きになる習慣を詳しく書いた
– 前向きになり、実行できるように
目次
– 序章:頭を前向きにするメモ書きの習慣
– 第1章:日本の危機
– 第2章:なぜ考えないのか
– 第3章:即断即決し、行動する習慣
– 第4章:人は誰でも前向きに考える力がある
– 第5章:実行できる人になる
– 終章:前向きに考え、生きてみる

考えの整理のしかた:
フレームワーク
48

物事を明確に整理する「フレームワーク」
フレームワークとは、物事を整理するための枠組み
フレームワークの種類は多種多様で、課題に応じて最適の枠組みを考え、整理する
–縦・横で整理する
–基本要素を押さえる
–各要素の相互の関係が見える、等々
次ページのテンプレートで毎日6個作成する
自社の競争力
市場の魅力
大
中
中 大
製品・市場の優先順位
・ 製品A
・ 製品B
・ 製品C
・ 製品D
フレームワークとは フレームワークの例
49

フレームワーク作成練習(毎日6個)
50
縦軸記入
横軸記入
XX
X
XX
X
XXX XXX
タイトル
・ XXX
・ XXX
・ XXX
縦軸記入
横軸記入 X
XX
X
XX
XXX XXX
タイトル
・ XXX
・ XXX
・ XXX
縦軸記入
横軸記入
XX
X
XX
X
XXX XXX
タイトル
・ XXX
・ XXX
・ XXX
縦軸記入
横軸記入
XX
X
XX
X
XXX XXX
タイトル
・ XXX
・ XXX
・ XXX
縦軸記入
横軸記入
XX
X
XX
X
XXX XXX
タイトル
・ XXX
・ XXX
・ XXX
縦軸記入
横軸記入 X
XX
X
XX
XXX XXX
タイトル
・ XXX
・ XXX
・ XXX
タイトルに合わせて、縦軸・横軸を決め、それぞれ上下・左右のラベルを記入。4つの箱には
適切な項目を1つずつ記入。一つのタイトルで複数個書くと、特に練習になる
・ XXX
・ XXX
・ XXX
・ XXX
・ XXX
・ XXX

フレームワーク作成練習(毎日6個)
51

ホワイトボード活用
52

ホワイトボードを活用したチームディスカッション
ホワイトボードを活用すると、チームの生産性が飛躍的に上がる
リーダーは、ディスカッションのテーマを決め、左上に書く
左側に問題点・課題、右側に解決策を書く
発言内容をできるだけそのまま、聞きながら書く
読みやすいよう、きれいに書く
時間は30分程度に区切り、ホワイトボード1ページを埋める
終了後、写真を撮って議事録とする
53

ホワイトボードの効果的な使い方
リーダーが書く(書記を使うことはあまり効果的でない) その時、何を話す時間なのかをはっきりさせる。すなわち、議事進行をきちんとおこなう。ブレーンストーミングであっても、結論を確認する時間を作る
最初はまとめようとせず、話を聞いて書く . . . わかりにくい時は躊躇せず、また恥ずかしがらず聞きなおし、簡潔に言い直してもらう
書いたものを指差して、言いたいことが表現されているか本人に確認する。他の人が話し始めていてもやんわり制止して確認し、積み上げていく方が効果的
論点がすれ違いの時は、それを整理し、どこにギャップがあるかできるだけ図示する(ここでフレームワーク、ロジックツリーが生きる)
誰が何をいつまでにやるか、明確に決め、確認し、書く。検討すべきリスク項目なども明確にする
ざわついた時は注意を促す。大きめの声で
左上に会議のタイトルと出席者、右上に日付を書く
複数の議題、トピックがあるときは、左上に小さく箇条書きしてから始める(場合によって時間配分も明記する)
印刷したときにはっきり読めるように、字の大きさ、読みやすさなど留意する
下半分は椅子にすわって書く方が早い、きれい、落ち着いて判断できる
最初は誰でもあがる。思っていることの半分も書けない。場数が必要(20回程度)
ホワイトボードの効果的な使い方
テーマによっては話がぶれやすい。それぞれが言いたいことを言って終わる
時間はかかるものの実際は何も決まらず、誰が何をいつまでに実行すべきかはっきりしない。決めたと思っても漏れがある
論点のすれ違いを明確にできず、平行線のまま議論が続く
報告はでき、結論は出せても、本質的な問題解決につながらない
リーダーはいいミーティングだったと思っても、チームメンバーは今ひとつ何が何だかわからない。情報共有したようでいてしていない、方針を出したようでいて、出していない
一般の会議・ミーティングで見られる問題点
ホワイトボードに書こうとしても、発言者の内容がよく理解できない(実際何を言いたいかわからないことが多い)
ホワイトボードの前に立つと、何をどう進めたらよいか、よくわからなくなってくる
議論が発散するのでまとめようとしても、皆がついてきてくれない。皆言いたいことを言う
ホワイトボードを使う時起きる現象、むずかしさ
54

コミュニケーション力強化
55

コミュニケーション力強化のポイント
コミュニケーションの大前提は、相手の話を最後まで聞くこと
それをするだけで、ほとんど「コミュニケーションの達人」になれる
コミュニケーションの本質は「相手への愛情、関心」+「平常心」
ものすごく嫌な相手とコミュニケーションする際は、相手の挙動、発言がなぜそうなのか、研究する。そうすると嫌悪感が減る → コミュニケーションできるようになる
こみいったことは何を言いたいのか、メモを数ページ書いておく
言うかどうか迷う時は、言うことのメリット・デメリットをメモに書く
バランス感覚を身につけるため、何でも相談できる相手を同年齢、5歳年上、10歳年上、5歳年下で数名ずつ確保しておく
56

ポジティブフィードバック
どんな小さなことでも褒める。その場で褒める
問題指摘、改善内容等は後で伝える。その場は褒めるだけ
結果が今ひとつだが努力・プロセスはよい場合、「頑張ったね!」
とねぎらう
結果が今ひとつでも努力に対してきちんと感謝する
だめな時、「今回はうまく行かなかったが、次はこうしよう」と励ます。
「このクソ野郎。地獄に堕ちろ」ふうのことを絶対に言わない
57
費用が全くかからず、成果は大。しかも即時。相手には感謝され、すべてが好循環であり、やらない理由がない

58
主な講演資料、ブログ スライドシェアでの講演資料アップ: http://www.slideshare.net/yujiakaba/presentations 事業計画作成とベンチャー経営の手引き: http://www.slideshare.net/yujiakaba/ss-7021997
ベンチャー人材確保ガイドライン: http://www.slideshare.net/yujiakaba/ss-8854374
経産省イノベーション環境整備研修 最新のベンチャー起業環境と課題: http://www.slideshare.net/yujiakaba/ss-32714627
リーンスタートアップ時代の事業計画作成、資金調達とサービス開発: http://www.slideshare.net/yujiakaba/ss-16717087 大企業の経営改革とベンチャーの活性化で日本を再び元気に: http://www.slideshare.net/yujiakaba/ss-16751751
ブレークスルーキャンプ決勝プレゼン大会: http://www.slideshare.net/yujiakaba/2011-9466238 全国VBLフォーラム第5回基調講演: http://www.slideshare.net/yujiakaba/5vbl
クリーンテックベンチャー: http://www.slideshare.net/yujiakaba/ss-8973633
現代ビジネス「ソーシャライズ!」でのブログ http://gendai.ismedia.jp/category/akaba – 日本が変わった: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31677
– 大企業が変われない理由: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/31888
– リーンスタートアップの最新事情: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32038
– SXSWが世界を動かす: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/32138
– 大企業の改革と新事業立ち上げへのヒント: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/33705
– 素早い仮説構築・検証・修正による商品開発 実践的リーンスタートアップ: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36828
– 経営改革を進めるには7つの鍵を同時に開けること: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/36859
– 経営改革を進める第1の鍵: ビジョンと戦略の変更、全社員への浸透 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41111
– 経営改革を進める第2の鍵: 既存事業の抜本的改善-詳細なターゲット設定と厳しい進捗管理 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41122
– 経営改革を進める第3の鍵: 複数の新規事業立ち上げ-リーンスタートアップ http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41205
– 経営改革を進める第4の鍵:高度な経営支援能力の構築-経営改革推進チームの設置と実践トレーニング
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/41230
– 40歳からのネクストチャレンジ! --セカンドキャリアのための戦闘力アップ講座第一期を終えて http://gendai.ismedia.jp/articles/-/40147
– 決定的に広がる日米製造大企業の競争力!: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39584
– 今後の技術・産業動向を占う10のキーワード【前編】: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39591
– 今後の技術・産業動向を占う10のキーワード【後編】: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39594
– 米国の優れた起業・イノベーション環境 と日本の挽回策を整理する: http://gendai.ismedia.jp/articles/-/39600
日経ビジネスオンラインでのインタビュー記事 – 日本の大企業が再び輝きを取り戻すには: http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20121112/239314/
– 日本企業を襲う「自分のアタマで考えない」病: http://business.nikkeibp.co.jp/article/interview/20140324/261629

略歴: 赤羽 雄二
東京大学工学部を1978年3月に卒業後、コマツで建設現場用の超大型ダンプトラックの設計・開発に従事 1983~1985年、スタンフォード大学 大学院に留学(機械工学修士) 1986年、マッキンゼー入社。経営戦略、組織設計、マーケティング、新事業立ち上げなどのプロジェクト多数を14年間にわたりリード。うち、1990~2000年の10年間、マッキンゼーソウルオフィスを立ち上げ、韓国のトップグループの経営改革を推進 シリコンバレーのベンチャーキャピタルをへて、2002年、創業前、創業当初からの非常にきめ細かな支援を特徴とするブレークスルーパートナーズ株式会社を森廣弘司と共同創業し、「日本発の世界的ベンチャー」を生み出すべく活動。スマートフォン、ソーシャルメディア、コンテンツマーケティングに注目し、B2C、B2B両方の分野でリーンスタートアップを推進中 中堅・大企業の経営改革、経営幹部育成、新事業創出にも深く関わっている 学生向けアプリ開発コンテスト、ブレークスルーキャンプ2011、2012 Summer 企画・運営 主要な学生向けビジネスプランコンテストでは、基調講演、審査員、メンター等を務める 米Fenox Venture Capitalアドバイザー 経済産業省「産業競争力と知的財産を考える研究会」、総務省「ITベンチャー研究会」委員、「ICTベンチャーの人材確保の在り方に関する研究会」委員、 「事業計画作成支援コース」の企画立案および講師、「事業計画作成とベンチャー経営の手引き」著者 東京大学工学部「産業総論」、電気通信大学「ベンチャービジネス特論」、北陸先端科学技術大学「ベンチャー創出論」講師 NEDO 技術委員、SUI(スタートアップイノベーター)事業カタライザー ベストセラー「ゼロ秒思考」、「7日で作る事業計画書」、「頭を前向きにする習慣」著者 ダイヤモンド社から1/23に「速さはすべてを解決する ゼロ秒思考の仕事術」を出版 KADOKAWA中経出版から2/25に「世界基準の上司」を出版
59

今日の感想、発見、質問等をぜひ、[email protected] までお送りください。 いつでも、何でもご相談ください。すぐお返事します。 別途、http://b-t-partners.com/akaba/ の方にメールアドレスを登録しておいていただければ、新刊情報、ブログ記事、講演会資料等お送りします。 Twitterで@yujiakabaのフォローをしていただければ、有用情報を流しています。
1. 今日の感想、発見
2. 今日のワークショップでわかりにくかったこと、質問内容
3. それ以外になんでも
60






![[AWS Summit 2012] ソリューションセッション#2 リーンクラウドでいこう! クラウドで実現するリーンスタートアップ](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/556157cfd8b42a780d8b54ac/aws-summit-2012-2-.jpg)