ã Ä éé éé » & / !¥ » & / !¥ +® 0 0 0 0 · 1 Very Preliminary Present External Net Assets...
Transcript of ã Ä éé éé » & / !¥ » & / !¥ +® 0 0 0 0 · 1 Very Preliminary Present External Net Assets...

DISCUSSION PAPER SERIES
July 2012
No. 2012-05
日本日本日本日本のののの対外純資産対外純資産対外純資産対外純資産 Present External Net Assets of JapanPresent External Net Assets of JapanPresent External Net Assets of JapanPresent External Net Assets of Japan
中藤中藤中藤中藤 泉泉泉泉
Izumi NAKATOIzumi NAKATOIzumi NAKATOIzumi NAKATO

1
Very Preliminary
Present External Net Assets of Japan
July 2012
Izumi NAKATO
Faculty of Economics
Nagasaki University
Abstract:
External net assets of Japan recorded 253 trillion yen. In this paper we deal with
external net assets of Japan.
In section 2 we will review draft of the current account balance and the transition
of foreign assets, foreign liabilities and net external assets in section3. Then we will
review profitability of foreign direct investment and foreign security investment.
Section 5 is review of regional breakdown of the income balance. Section 6 presents
challenges of the present and future.
JEL Classification: E00,F21
Key words: foreign net assets, Foreign Direct-Investment (FDI),
Returns of FDI and securities

2
1.はじめに
日本経済の現状をみると、ゆるやかなデフレが進行している中、個人消費をはじめ
として内需は伸び悩んでいる。輸出を巡る環境は、欧州危機の影響が世界経済、なかん
ずく中国やインドといった新興国の成長にも低下がみられるとともに、安全資産である
円資産への海外資金の流入もあって円高が進行するなど厳しい状況にある。
他方、日本経済の海外との結びつきは強まっている。2011年は貿易収支については
1.6兆円の赤字になったが、所得収支は 14.0兆円の黒字であり、経常収支は 9.6兆円の
黒字となった。貿易収支にとってかわり、今や所得収支が日本経済にとって大きな稼ぎ
手の役割を果たしている。いうまでもなく、所得収支は、対外資産からの受取から対外
負債への支払を差し引いたものである。
ところで、経常収支の黒字は海外への資本流出と一対の関係にある。長年にわたって
積み上がった資産・負債残高をみると、2011年末の日本の対外資産残高は 582兆円、
対外負債残高は 329兆円、対外純資産残高は 253兆円となった。日本の対外純資産残
高は、1991年以降 21年間に渡り世界一の座を占めている。2011年の対外純資産残高
は、第 2位の中国が約 138兆円、3位のドイツが約 94兆円である。他方、英国は約 24
兆円の債務超過、米国(2010年末)は約 201兆円の債務超過となっている。
本稿においては、これまで積み上がった日本の対外純資産に着目し、資産・負債残高
の推移、増減要因、資産(直接投資や証券投資)の収益性を概観するとともに、地域別
の所得収支の特徴をとらえ、今後における対外資産の活用の方向性を明らかにしたい。
2.経常収支の推移
(経常収支の推移)
はじめに、経常収支の動向をみる。図 1から分かるように、2007年にかけては増加し、
2008年以降減少傾向を示している。貿易収支については、2004年に 13.9兆円と直近
のピークを付け、2008年以降は資源価格の動向やリーマン・ショックなどの影響もあ
って減少傾向し、2010年には回復をみせたものの、ギリシャ危機や東日本大震災の影
響、原発に代わる火力発電にかかる原油輸入量の増大、さらには円高等により 2011年
には 1.6円の赤字となった。他方、所得収支については、2007年 16.5兆円と直近のピ
ークを付け、その後世界経済の影響もあり、2010年にかけて減少を示したが、2011年
には 14.0兆円の黒字となっている。所得収支の黒字額は 2005年に貿易収支の黒字額
を上回り、その後経常収支の黒字を支える大きな役割を果たしている。サービス収支に
ついては、赤字傾向が続いているが、図から明らかなように赤字幅が減少している。こ
れについては、後述する。なお、政府間の無償資金援助、国際機関への拠出金、労働者
送金などからなる経常移転収支は、概ね 1兆円程度の赤字となっている。

3
図 1
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
次に、地域別経常収支を概観する。図 2から分かるように、日本の場合、資源の輸入
国であることを反映し、中東及び大洋州との経常収支については赤字が持続している。
これら地域との貿易収支は赤字であり、なかんずく原油をはじめとした資源価格からの
影響を強く受ける。2005年から 2008年、2011年と原油価格の高騰などにより赤字幅
が拡大している。北米や欧州については、2008年 9月のリーマン・ショックの影響が
強く出た 2009年以降、ギリシャ危機の影響なども重なり、黒字幅は縮小している。他
方アジアについては、2009年以降北米を上回る規模となっている。中南米については、
増加傾向を示している。
前述したように、経常収支の中で、サービス収支については、赤字幅が縮小傾向を示
している。図 3から分かるように、サービス収支の赤字の縮小幅(2011年と 1999年
で 4.1兆円の縮小)のうち、旅行収支の縮小幅は 2.0兆円と概ね半分を占めている。地
域別にみると、アジアが 8235億円、北米が 5349億円、欧州が 3387億円の縮小とな
っている。特許権等使用料収支についてみると、1999年は 0.2兆円の赤字が 2011年に
は 0.8兆円の黒字と改善幅は 1兆円となっている。地域別にみると、アジアが 5188億
円、北米が 1703億円、欧州が 1928億円も改善を示している。輸送収支は赤字が続い
ている。通信、建設、保険、金融、情報、文化・興業、公的サービスを便宜的にまとめ
た「その他収支」は小幅の赤字傾向となっている。以上のサービスを除いた、「その他
営利業務サービス」(仲介貿易・その他貿易関連等)は 1.2兆円の改善を示している。
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
経常移転収支 -1.4 -1.1 -1.0 -0.6 -0.9 -0.9 -0.8 -1.2 -1.4 -1.4 -1.2 -1.1 -1.1
所得収支 6.6 6.5 8.4 8.3 8.3 9.3 11.4 13.8 16.5 16.1 12.8 12.4 14.0
サービス収支 -5.9 -4.9 -5.2 -5.1 -3.6 -3.7 -2.6 -2.1 -2.5 -2.1 -1.9 -1.4 -1.8
貿易収支 13.8 12.4 8.4 11.6 12.0 13.9 10.3 9.5 12.3 4.0 4.0 8.0 -1.6
経常収支 13.1 12.9 10.7 14.1 15.8 18.6 18.3 19.9 24.9 16.7 13.7 17.9 9.6
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
兆円 兆円 経常収支の推移
貿易収支 サービス収支 所得収支 経常移転収支 経常収支
経常収支は右目盛

4
サービス収支については、これまで赤字傾向が日本の特徴であったが、記述したよう
に、傾向的には縮小がみられる。また、縮小幅に貢献している地域は、いずれもアジア
地域である。
図 2
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
図 3
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
2.9 3.8 1.9 4.4 6.7 8.9 8.5 9.0 11.7 10.1 8.4 13.2 10.1 8.5 9.8 10.1
10.6 9.6 9.9 11.4 13.5
13.5 11.3
7.1 7.3
5.9
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
-20.0
-10.0
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
1,999 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011
兆円 経常収支の地域別推移
アジア 北米 中南米 大洋州 欧州 中東 経常収支
経常収支は右目盛
-3.3 -3.1 -2.8 -2.9 -2.3
-2.9 -2.8 -2.1 -2.0 -1.8 -1.4 -1.3 -1.3
-5.9
-4.9 -5.2 -5.1
-3.6 -3.7
-2.6 -2.1
-2.5 -2.1 -1.9
-1.4 -1.8
-7.0
-6.0
-5.0
-4.0
-3.0
-2.0
-1.0
0.0
1.0
2.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
兆円 兆円 サービス収支の推移
輸送収支 旅行収支 特許権等使用料収支
その他営利業務収支 その他収支 サービス収支

5
3.本邦対外資産負債残高の推移
(対外純資産残高の推移)
次に、対外資産残高、負債残高、純資産残高の推移をみたものが図4である。これら
残高の増減には3要因がある。すなわち、取引フローの増減、為替相場の変動による増
減、株価・債券価格等の変動に伴う増減(フロー統計である国際収支統計との作成方法
の相違による増減等を含む)である。以下、簡略化して、フロー要因、為替要因1、価
格要因と呼ぶことにする。
図 4
(出所)財務省・日本銀行『本邦対外資産負債残高』から作成
対外純資産残高の増減をみたものが、図 6である。図から明らかなように、円高は資産残
1 資産・負債には様々な通貨建てが含まれる。たとえば、2011年の建値通貨別・証券種類
残高(資産サイド)では、証券投資残高 262.3兆円のうち、米国ドル建て 112.3兆円 43%、
ユーロ建て 29.7兆円 11%、円建て 78.1兆円 30%、その他通貨建て 42.1兆円 16%の構成
となっている。以下の図では、参考までに円ドルを添付している。
336.8 303.6
341.2
379.8 365.9 385.5
433.9
506.2
558.1
610.5
519.2 554.8 563.5
582.0
203.5 218.9 208.2 200.5 190.6
212.7 248.1
325.5 343.0
360.3
293.7 288.6 312.0
329.0
133.3
84.7
133.0
179.3 175.3 172.8 185.8 180.7 215.1
250.2 225.5
266.2 251.5 253.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
兆円 日本対外純資産残高の推移
対外資産残高 対外負債残高 対外純資産残高

6
高の減少要因となる。リーマン・ショック後の 2008 年末は前年に比べて 24.7 兆円の純資
産減となったが、このうち為替要因は 88兆円の減額要因となった。なお、価格要因が、見
かけのうえでは増加要因となっているが、これは資産価格の上昇ではなく、資産価格の下
落によるものである。2008年末は価格要因による資産の減少額(21.8兆円)に対して、負
債の減少額(61.5 兆円)が資産の減少額を上回ったことにより、純資産残に対しては 39.7
兆円の増加要因となったためである。2009年末、2010年末については資産価格の上昇によ
り純資産は増加している。2011 年末には、資産価格は下落したが、負債の減少額が大きく
純資産については増加要因となった。このように価格要因については、資産額、負債額の
動向に留意することが肝要である。為替要因については、2010年末、2011年末では、減少
に寄与している。取引要因については、総じてみれば純資産の増加要因となっている。
図 5
(出所)財務省・日本銀行『本邦対外資産負債残高』から作成
(対外資産残高の推移)
対外資産残高の推移は、図 6のとおりである。2002年 1月の景気の谷から 2008年 2
月の景気の山まで、日本経済は 73 か月の景気上昇期間を経験した。IMF データでは、
世界輸入は 2003年から 2008年にかけては毎年 2桁の伸びを示し、また世界経済の成
長率も 2003年から 2007年にかけては堅調な伸びを示した。こうした時期には、対外
資産も堅調な増加を示している。
2011年末の対外資産の構成をみると、証券投資が全体の 45.1%(債券 36.2%、株式 8.
34.4 35.1
-24.7
40.7
-14.7
1.5
118.92
113.12
90.28 92.13
81.51
77.57
60
70
80
90
100
110
120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
80
2006 2007 2008 2009 2010 2011
円/ドル 兆円 対外純資産残高の増減要因
取引要因 為替要因 価格要因 純資産残高増減 円/ドル
為替レートは右目盛

7
1%)、直接投資が 12.9%、外貨準備が 17.3%、その他投資(貸付・貿易信用・現・預
金、雑投資)が 24.1%となっている。2また、資産サイドの長短比率(短期は現契約期
間が 1年以内、長期は現契約期間が 1年超)は、長期が 67.5%、短期が 32.5%となっ
ている。債券投資残高 210.5兆円でみると 208.6兆円が中長期債であり、短期債は 2
兆円となっている。
図 6
(出所)財務省・日本銀行『本邦対外資産負債残高』から作成
図 7で 2006年以降の増減要因をみると、2007年までは取引要因により堅調に推移
したが、2008年は為替要因が大きく減少に寄与し、また価格要因も現象に寄与してい
る。2009年には落ち込みから回復がみられたが、2010年、2011年は為替要因が減少
に寄与しており、増加額は小幅となっている。
2 このほかに、金融派生商品が 0.7%のウェイトを占めている。以下、図 6から図 9におい
て資産・負債残高総額・同増減額には金融派生商品を含めている。ただし、図 6、図 9にお
いては、ウェイトが低いため金融派生商品は割愛している。(2011年負債残高に占める金融
派生商品の構成比は 1.7%)
25.4 32.0 39.6 36.5 35.9 38.6 45.6 53.5 61.9 61.7 68.2 67.7 74.8
131.7 150.1
170.0 167.2 184.4 209.2
249.5 278.8
287.7
215.7 262.0 272.5 262.3 116.6
117.2 117.1 105.8 92.6
97.7
108.5
116.7
146.2
141.8
123.6 129.7 140.2
29.4 41.5
52.8 56.1 72.1
87.7
99.4
106.4
110.3
93.0
96.8 89.3 100.5
303.6
341.2
379.8 365.9
385.5
433.9
506.2
558.1
610.5
519.2
554.8 563.5 582.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
0.0
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
兆円 対外資産残高の推移
直接投資 証券投資 その他投資 外貨準備 資産残高

8
図 7
(出所)財務省・日本銀行『本邦対外資産負債残高』から作成
(対外負債残高の推移)
対外負債残高の動向をみたものが図 8、9 である。2003 年から 2007 年にかけては、
世界経済が堅調に推移したこともあり、証券投資の増加などもあり、負債残高は増加し
ている。2008 年には、リーマン・ショック後金融市場の混乱などもあり、証券投資残
高が急減した。要因別にみると、株式や中長期債の下落により価格要因がその大半を占
めている。証券投資残高は 2009 年ほぼ横ばい、2010 年以降緩やかに回復している。
残高の増減要因をみると、2010、2011 年には、取引要因が「その他投資」の借入の増
加を主因に増加に寄与している。2011 年には対内短期債投資の増加も残高増加に寄与
している。価格要因は本邦株価の下落などから減少に寄与している。為替要因は、2010
年には円高にともない残高の減少に寄与している。
2011 年末の負債残高の構成をみると、証券投資が全体の 47.9%(株式 20.0%、債券
27.9%)、その他の投資 45.0%(借入 29.9%、貿易信用・現・預金、雑投資計 15.2%)
直接投資 5.3%となっている。また、負債サイドの長短比率は、長期 44.6%、短期 55.4%
である。2011年末の債券投資残高は 91.6兆円と前年末の 71.9兆円から約 20兆円の増
加となったが、その主因は短期債投資が約 17兆円増加である。
51.9 52.4
-91.3
35.6
8.7 18.5
118.92
113.12
90.28 92.13
81.51
77.57
60
70
80
90
100
110
120
-150
-100
-50
0
50
100
2006 2007 2008 2009 2010 2011
円/ドル 兆円 対外資産残高の増減要因
取引要因 為替要因 価格要因 対外資産増減 円/ドル
為替レートは右目盛

9
図 8
(出所)財務省・日本銀行『本邦対外資産負債残高』から作成
図 9
(出所)財務省・日本銀行『本邦対外資産負債残高』から作成
4.7 5.8 6.6 9.4 9.6 10.1 11.9 12.8 15.1 18.5 18.4 17.5 17.4
118.4 101.6 87.8 73.2 92.9 120.1
182.0 209.7 221.5
140.3 141.9 152.5 158.2
95.5 100.4
105.7 107.6
109.5
116.8
127.7 116.9
118.7
127.1 123.1 136.8
148.8 218.9 208.2 200.5 190.6
212.7
248.1
325.5 343.0
360.3
293.7 288.6 312.0
324.1
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
兆円 対外負債残高の推移
直接投資 証券投資 その他投資 対外負債残高
17.5 17.2
-66.6
-5.1
23.4 17
118.92
113.12
90.28 92.13
81.51 77.57
60
70
80
90
100
110
120
-100
-80
-60
-40
-20
0
20
40
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011
円/ドル 兆円 対外負債残高の増減要因
取引要因 為替要因 価格要因 対外資産増減 円/ドル
為替レートは右目盛

10
4.対外資産・負債(対内投資)の収益率
以上、対外資産・負債残高の推移をみてきたが、ここでは積み上げられた対外資産(海
外への投資)と対外負債(海外からの投資)のうち、直接投資、証券投資の収益性3に
ついて概観する。
(対外資産の収益率の推移)
直接投資収益率は、フローベースの国際収支表から得られる当該年の直接投資収益を
ストックベースの当該年平均の直接投資残高(前年末残高と当該年末残高の平均)で除
して求める。証券投資収益率についても同様に算出する。このようにして得られたもの
が図 10である。
図 10
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』『本邦対外資産負債残高』から作成
3 本稿においては、「その他投資」(貸付・現・預金、雑投資、貿易信用)の収益率は割愛す
るが、2007年から 2011年 5年間の平均収益率は 1.4%である。
25.4 32.0
39.6 36.5 35.9 38.6 45.6
53.5 61.9 61.7
68.2 67.7 74.8
131.7 150.1
170.0 167.2 184.4
209.2
249.5 278.8 287.7
215.7
262.0 272.5 262.3
2.5
3.1
5.7 5.5
4.2
5.5
8.0 8.2
9.2
8.1
6.6
4.9
6.6
4.7 4.4 4.5 4.5
4.3 4.2 4.2
4.7
5.3
6.7
4.2 4.2 4.6
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% 兆円 対外投資の収益率の推移
直接投資残高 証券投資残高 直接投資収益率 証券投資収益率
収益率は右目盛

11
図から明らかなように、2001年以降、直接投資の収益率が証券投資の収益率を上待って推
移している。直接投資の収益率は、2005 年から 2008 年にかけては世界経済が堅調に推移
したこともあり収益率は 8~9%に高まったが、リーマン・ショックの影響や 2010 年のギ
リシャ危機などもあり 2010年にかけては 4.2%まで低下し、2011年には 6.6%に上昇した。
証券投資の収益率は 4%台で推移し、2007,8 年にかけて高まりを示したが、2009 年以降
4%台の動きとなっている。
次に、証券投資収益を株式配当と債券利子に分けて収益率をみたものが図 11 である。我
が国においては証券投資の大半を占めるのは中長期債を中心とした債券投資であり、2011
年末で証券投資残高 262.3 兆円のうち債券残高は 201.6 兆円と約 8 割を占めている。株式
残高は 51.8兆円と 2割を占めるに過ぎない。ただし収益率の推移をみると、2008年以降、
株式投資の収益率が債券投資の収益率を上回って推移している。このことは、証券投資に
おいて、株式の運用割合を高めることによって、収益を増加させる余地が残されているこ
とを示していると言える。株式の場合、一般的には債券に比べリスク性が高くなるが、資
産の活用という面から、株式での運用割合を高めていくことが、今後の課題として示唆さ
れる。
図 11
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』『本邦対外資産負債残高』から作成
209.2
249.5
278.8 287.7
215.7
262.0 272.5
262.3
38.0 48.2 60.7 65.4 35.8 54.7 55.3 51.8
171.3 201.3 218.0 222.3
179.9 207.3 217.3 210.6
4.4 4.8 5.0
5.3
6.5
5.1 5.7
8.2
4.5 4.5 4.9
5.4 5.6
4.5
3.9 3.7
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% 残高(兆円) 対外証券投資収益率の推移
証券投資 株式 債券
証券投資収益率 株式配当収益率 債券利子収益率
収益率は右目盛

12
次に、わが国対外直接投資の収益率を世界と比較したものが図 12 である。図から分かる
ように、わが国の直接投資収益率は、アメリカ、イギリス、スイスに比較してみると総じ
て低いが、フランス、ドイツ、オランダと比較すると遜色のない水準と言える。国内の投
資機会が縮小する中、対外直接投資を高めていくことが引き続き求められる。
図 12
(出所) (財)国際貿易投資研究所『国際比較統計』から作成
(対内投資の収益率の推移)
ここでは、対内投資(対内直接投資と対内証券投資)の収益率をみる。我が国への投資残
高をみると、2011年で対内証券投資残高が 157.5兆円、対内直接投資残高は 17.5兆円とな
っている。先にみたように、2008年には取引要因や価格要因によって大幅な減少となった。
その後取引要因は改善傾向を示しているが、回復はゆるやかなものとなっている。対内直
接投資の収益率は、2007年にかけては上昇傾向がみられるが、2008年以降は日本経済の低
迷を反映して収益率は急速に低下し、2011 年には若干の回復を示している。他方、証券投
資の収益率は 1%台で推移しており、2011年には 1.7%なっている。
世界の対内直接投資の収益率の推移をみたものが図 15である。対内投資の収益率は主要
国と比べ、総じて遜色のない水準である。ただし、直近の 2010年では収益は低迷している。
なお、中国であるが、対内直接投資残高は 2000 年の 1933 億ドルから 2010 年には 5788
億ドルへと急増し、2010年では世界 9位の水準である。他方、我が国の対内直接投資残高
5.6
7.6
1.6
3.1
11.4
6.6
3.0
8.1
12.0
4.3
6.6
14.2
7.8 7.9 8.2
6.5
3.4
5.7 5.9
3.6
6.1
8.9
7.5
4.8
6.1
7.6
5.6 4.6
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
アメリカ イギリス フランス ドイツ スイス オランダ 日本
% 世界の対外直接投資の収益率
2000 2005 2009 2010

13
は 2000年 503億ドルから増加を示しているが、2010年 2149億ドル、世界 20位の水準に
とどまっている。収益性のみならず、対内投資の一層の呼び込みが課題と言える。
図 13
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』『本邦対外資産負債残高』から作成
図 14
(出所) (財)国際貿易投資研究所『国際比較統計』から作成
5.地域別所得収支の推移
1.3 1.4 1.5 1.5 1.4 1.3 1.2 1.3 1.4 1.8 1.6 1.6 1.7
7.0
5.4
8.1 8.3
6.2 7.0
9.5 8.5
12.5
7.3
4.5
2.8
5.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
% 兆円 対内投資の収益率推移
対内直接投資残高
対内証券投資残高
対内証券投資収益率
収益率は右目盛
2.0
9.5
1.4
4.7
6.6
10.4
5.2
4.3
7.8
3.1
8.3
6.6
17.6
9.4
4.4 4.6
2.8
7.7
4.3
17.9
2.7 0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
アメリカ イギリス フランス ドイツ オランダ 中国 日本
% 世界の対内直接投資の収益率
2000 2005 2009 2010

14
以上、対外資産・負債残高の推移や収益性について概観した。ここでは、国際収支ベース
に戻り、地域別所得収支の構成の変遷をみる。図 16から明らかなように、北米や欧州の比
率が低下する中で、アジア、中南米、豪州の比率が高まっている。また、図 17の地域別所
得収支(受取)をみても同様の傾向がみてとれる。
図 15
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
そこで以下では、図 18から 23を用いて、地域別の所得収支(受取)を概観する。
まず、アジア地域については、直接投資収益が堅調に増加しており、2011年には全体
の 7割超を占めるに至っている。他方、証券投資収益は比率が低い。中南米(ケイマン
除く)をみると、直接投資収益、証券投資について堅調に増加している。ケイマンから
の所得は証券投資利子・配当が大部分である。北米や欧州については証券投資利子・配
当のウェイトが高い。大洋州について見ると、直接投資収益が増加しているとともに、
証券投資利子も相応のウェイトを占めている。
全体としてみると、先進地域では、証券投資利子や配当のウェイトが高く、アジア、
中南米(ケイマン除く)では直接投資収益のウェイトが高い。大洋州では直接投資収益
のみならず証券投資収益も相応の収益をあげている。
0.1 0.1 0.7 0.8 0.9 1.2 1.5 1.8 2.2 2.2 2.0 2.1 2.6
3.5 3.7 4.6 4.0 3.5 3.7 4.6 5.4 5.7 5.8 4.4
3.3 3.3
0.4 0.4
0.8 0.8
0.7 0.8 1.2 1.5
1.8 1.8 1.6 2.3 3.1
0.2 0.2
0.2 0.2
0.3 0.4 0.5 0.6
0.8 0.7 0.7 1.0 1.1
1.7 1.5 1.4 1.6 2.1 2.5
2.8 3.6 4.7 4.3 3.3 2.8 3.0
0.6 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1.0 1.2 1.3 0.9 0.9 0.9
6.6 6.5
8.4 8.3 8.3 9.3
11.4
13.8
16.5 16.1
12.8 12.4
14.0
0.0
2.0
4.0
6.0
8.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
地域別所得収支の推移
アジア 北米 中南米 大洋州 欧州 その他 所得収支
(数字の単位:兆円)

15
図 16
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
図 17
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
1.3 1.2 1.7 1.5 1.3 1.5 2.0 2.4 3.0 2.8 2.4 2.4 2.9
4.6 4.7 5.7 4.9 4.3 4.7 6.2 7.6 8.7 7.9 5.8 4.8 5.1
0.6 0.6 0.9
1.0 0.8 1.0
1.5 1.9 2.4 2.3 1.9 2.5 3.6
0.2 0.3 0.2 0.2
0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 0.8 0.7 1.0
1.1
3.3 3.2 3.4 3.3 3.6 4.0 4.7 5.9 7.6 7.2 5.2 4.5 4.7
0.5 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.8 1.1 1.2 0.8 0.8 0.8
10.5 10.5
12.5 11.5 11.1
12.3
15.6
19.3
23.6 22.3
16.9 16.0
18.1
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
所得収支(受取)の地域別推移
アジア 北米 中南米 大洋州 欧州 その他 受取総額
(数字の単位:兆円)
-2903 -1321
5633 6962 5717 7921
10895 13365
17195 16894 16768 16841 20966
12671 12420
17494
14718 13237
15308
19596
24374
30022 28439
23971 23573
28596
-5000
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
億円 アジアからの所得収支(受取)の推移
直接投資収益 証券投資配当 証券投資利子
その他投資収益 受取総額

16
図 18
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
図 19
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
470 -697
493 1,624 890 919
1,718 2,699 3,440 4,047 3,548 3,618 3,459
3,695
2,709
3,841 4,308
3,008 3,056
5,084 5,624
7,157 7,802
6,922
8,007
9,551
-2,000
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
億円 中南米(ケイマン除く)からの所得収支(受取)の推移
直接投資収益 証券投資配当 証券投資利子
その他投資収益 受取総額
861 1,115 2,174 3,033 3,034 4,259 7,320
10,009 11,722 10,826 7,873
14,719
23,917
2,026 3,437
5,530 5,240 5,220 6,735
9,717
13,713
16,539 15,541
12,120
17,297
26,263
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
兆円 ケイマンからの所得収支(受取)の推移
直接投資収益 証券投資配当 証券投資利子 その他投資収益 受取総額

17
図 20
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
図 21
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
27495 30452
37350 33843
32820 35022
42365
52685 60626
53609
40811
37791 35144
45891 46775
56575
49175 43324
46761
62360
76267
86800
78542
57976
47651 50618
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
億円 北米からの所得収支(受取)の推移
直接投資収益 証券投資配当 証券投資利子
その他投資収益 受取総額
22174 21331 22286 23406 26721
28978 31727
37662
43746 42822
34246
30680 27582
33244 32335 33796 33194 36366
40443
46754
59276
76331 72211
52195
44517 47360
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
億円 欧州からの所得収支(受取)の推移
直接投資収益
証券投資配当
証券投資利子
その他投資収益
受取総額

18
図 22
(出所)財務省・日本銀行『国際収支統計』から作成
6.結びにかえて
以上、日本の経常収支、対外純資産、所得収支の地域別構成の変遷をみてきた。ここ
では、その動向を整理するとともに、今後の課題を示す。
はじめに、フローベースの経常収支の動向をみると、これまで積みあがった資産から
の所得が今や貿易収支を凌駕している。今後については、所得収支の増加に向けて、海
外直接投資の増加が引き続き求められる。特に、アジア、中南米(ケイマン除く)、大
洋州をみると、直接投資収益が急増している。また、証券投資については、リスクを考
慮した中で、株式の運用割合を高めることにより、所得の増加を図っていくことも課題
の一つである。
次に、対外純資産残高は、対外資産残高、対外負債残高の双方向の動向によって影響
を受ける。残高の増減要因である取引要因、為替要因、価格要因は資産のみならず負債
にも影響を与える。円高は為替要因として円建て資産残高の減少に寄与するが、負債の
残高評価もまた減少する。価格要因についても、その内容を吟味することが求められる。
従って、対外純資産については、その増減のみならず、資産・負債の両面をみていくこ
とが肝要である。
318 324 609 814 1162 1194 1600 2149
4523 3595 3970
5848 6131 2433 2564 2031
2397 2995
3755
4901
5997
8796
7765 7428
10390
11280
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
億円 大洋州からの所得収支(受取)の推移
直接投資収益 証券投資配当 証券投資利子
その他投資収益 受取総額

19
最後に、 直接投資については、日本の場合、対外直接投資残高に比して対内直接投
資残高が極めて低い水準にある。また、絶対額だけでなく GDP比でみた水準も主要先
進国に比べて低位である。図 24は、経済産業省『平成 24年版通商白書』から転載し
たものであるが、主要国においては、対外・対内残高が額としてのみならず GDP比で
みても日本に比して高い水準にある。対外投資の一層の促進のみならず、対内投資の呼
び込みのための環境整備や方策が求められる。
図 23
(出所)経済産業省『平成 24年版通商白書』から転載

20
参考文献
経済産業省 『平成 24年版通商白書』(2012年 6月)
財務省・日本銀行 『国際収支統計』(各年版)
財務省・日本銀行 『本邦対外資産負債残高』(各年末版)
日本銀行 『2011年国際収支』(Reports & Research papers 2012 年 4月)
日本銀行 『2011年末の本邦対外資産負債残高』
(Reports & Research papers 2012年 5月)




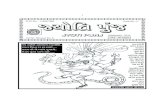
![Wð¯NÉ–É{Éɯ ]Ée·Éà ]Ée·Éà PÉÚ'ÉÒ{Éà lÉà{ÉÖ¯ »Én·É … book.pdf · ·ÉһɛíÉlÉÒ ·ÉÉ{ÉNÉÒ+Éà §ÉÖ–ÉÉ> NÉ«Éà–ÉÉ »·ÉÉqí](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5aef841e7f8b9a8b4c8c624d/wn-e-e-p-l-n-bookpdfl-n-n-q-a-h-yh-1-hce.jpg)








![g°ML$ y¨ r h°]$ Ad©[ ^pfp - Jainworld – Combining the ... Dhara.pdf+©ÉÞlÉ yÉÉùÉ +©ÉÞlÉ yÉÉùÉ »ÉÉiÉ»ÉÒoÉÒ H {ÉÉ + Å ÅSÉ©ÉÉ . ~É Å +É´«ÉÉ](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5b2643667f8b9aed7c8b5e2a/gml-y-r-h-ad-pfp-jainworld-combining-the-dharapdfeble.jpg)

![Iraq Guj Big - Amazon S3€¦ · 6 ( 7) ©Éq É+{à É W{ÉÉ¥É »É±É©ÉÉ{É £Éù»ÉÒ (+.»É.) W{ÉÉ¥É à ¾É]à «£É «É©ÉÉ{ÉÒ (ù¾à .). W{ÉÉ¥É à](https://static.fdocument.pub/doc/165x107/5f8174dfec440c628a1e15b8/iraq-guj-big-amazon-s3-6-7-q-w-.jpg)


